行政書士の難易度や合格率はどのくらい?他資格との比較から合格点まで徹底検証
更新日:2023年12月18日

行政書士試験の難易度は、難しいとも易しいとも言われます。
試験自体の難易度を偏差値で表現すると62程度。
誰に聞いても難関資格と呼ばれる資格の偏差値が65以上、多くの方が取得できるレベルの資格が偏差値60未満と考えると、ちょうどその中間の難易度の資格ということになりまAす。
そんな行政書士試験の難易度を、合格率の推移やほかの人気資格との比較から解説していきます。
さらに行政書士試験に短期間で合格するためのおすすめの勉強方法も紹介しましょう。
- 行政書士の仕事は、官公署などに提出する書類の作成を請け負うことが中心になります。
- 過去10年の平均合格率は約11%で、初学者には難易度の高い試験です。
- 行政書士に必要な勉強時間は、法律初学者であれば1,000時間程度。通信講座などを利用することにより、勉強時間を少なくすることができます。
- 合格を目指すには、「計画性」と「効率」に重きを置いた学習が不可欠です。
- 行政書士試験は「絶対評価」の試験です。合格率にバラつきがあるのが絶対評価の試験の特徴です。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
行政書士試験の難易度
行政書士の仕事は、官公署などに提出する書類の作成を請け負うことが中心になります。そのために必要となるのが他分野にわたる法律の知識です。
行政書士試験で問われるのがこの法律知識。かなり幅広い法律知識を問われる試験となりますので、特に初学者の方にとってはかなり難易度が高い試験となります。
そんな行政書士試験の難易度を、過去10年間の合格率から見ていきましょう。
行政書士とは
年齢、学歴、国籍等に関係なく受験可能な行政書士試験は、法律系資格の登竜門として人気の国家資格です。
試験範囲は幅広く、「行政書士の業務に関し必要な法令等」として憲法、民法、行政法、商法及び基礎法学、「行政書士の業務に関連する一般知識等」として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解が出題されます。
例年11月の第2日曜に実施されます。
関連記事:
行政書士の仕事内容の詳細はこちら
行政書士試験の合格率推移
まずは行政書士試験の、過去10年における合格率推移を確認しておきましょう。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2012年度 | 59,948名 | 5,508名 | 9.19% |
| 2013年度 | 55,436名 | 5,597名 | 10.10% |
| 2014年度 | 48,869名 | 4,043名 | 8.27% |
| 2015年度 | 44,366名 | 5,820名 | 13.12% |
| 2016年度 | 41,053名 | 4,084名 | 9.95% |
| 2017年度 | 40,449名 | 6,360名 | 15.72% |
| 2018年度 | 39,105名 | 4,968名 | 12.70% |
| 2019年度 | 39,821名 | 4,571名 | 11.48% |
| 2020年度 | 41,681名 | 4,470名 | 10.72% |
| 2021年度 | 47,870名 | 5,353名 | 11.18% |
| 過去10年合計 | 458,598名 | 50,774名 | 11.07% |
もっとも合格率が低かった2014年が8.3%、もっとも高かった2017年で15.7%とかなり幅のある結果となっています。
過去10年の平均合格率は約11%。この数値から考えれば、当然簡単な試験ではないということはご理解いただけるかと思います。
行政書士という資格を活用して業務を行うには、基本的に独立開業が条件となります。つまり行政書士試験を受験する方というのは、ある程度独立開業も視野に入れている方がほとんど。つまり受験者はしっかりと対策してきた方が中心と想像できます。
例えば企業に務めながらその企業内で活用できるような資格、また企業から資格手当が出るような資格、さらにその企業から取得を推奨されているような資格の場合、そこまで対策はできていなくても受験するという方が多くなります。
こういった資格の場合は、合格率は低くとも、受験者のレベルが低い可能性もあり、そこまで難易度は高くないということも考えられます。
行政書士試験はかなりハイレベルな受験者が集まっていることが予想されます。その中での11%ですから、特に初学者には難易度の高い試験と言っていいでしょう。
行政書士試験に合格するためにかかる時間とは
行政書士試験合格までに必要な勉強時間は、受験生によって様々ですが、法律初学者であれば1,000時間程度とも言われています。
仮に丸一年受験対策をする場合、1日3時間コンスタントに学習を積み重ねる必要があり、非常に長い道のりとなります。ただし、資格予備校や通信教育を活用することで、勉強時間を500~600時間に半減させることも可能です。
行政書士合格に向け、効率良く質の高い学習を心がけるのが得策です。
関連記事:
行政書士の勉強時間の詳細はこちら
行政書士試験の難易度を他の法律系の資格と比較
最初に触れたとおり、行政書士試験で出題される問題の中心は法律問題です。もちろん行政書士試験以外にも、法律知識が問われる資格試験はあります。
そこで行政書士試験の難易度を、ほかの法律系の資格試験と比較してみたいと思います。
宅地建物取引士試験と比較
不動産取引の場では必要不可欠な資格が宅地建物取引士、いわゆる宅建士です。
宅建士資格は人気が高く、例年20万人程の受験者を集める人気資格。問われるのは不動産取引や土地建物に関する法律知識が中心となります。
双方の試験の難易度を偏差値で表すと行政書士試験が62程度、宅建士試験が57程度と言われています。
実はこの2つの試験、合格率では大きな差はありません。宅建士試験が15%前後、行政書士試験が10~15%程度です。
資格の性格上、宅建士資格は資格手当の対象であったり、勤務先から取得を推奨されるタイプの資格。そう考えると試験の難易度としては行政書士試験の方が高いと断定していいでしょう。
関連記事:
宅建士の合格率の詳細はこちら
社会保険労務士試験と比較
労働者と雇用している企業の間に起こる諸問題の解決などのスペシャリストが社会保険労務士。独立開業はもちろん、企業に勤務しながらでも活用できる資格とあって、人気の高い資格になります。
社会保険労務士試験の偏差値は65程度。行政書士試験よりもやや難しいという評価になっています。
社会保険労務士試験の出題範囲は、労働法や社会保障法などが中心で、行政書士試験と比較すれば限定的な法律知識が問われます。ただし、こういった専門知識を、しっかり身に着け、さらに応用する力が求められるのが社会保険労務士試験の特徴。
例年の合格率も8%前後と行政書士試験よりも低く、さらに受験資格に大卒等の学歴が必要となることからも、社会保険労務士試験の方が少し難易度が高いといえるでしょう。
関連記事:
社労士の難易度の詳細はこちら
日商簿記2級試験と比較
直接法律とは関係のない資格ですが、難易度比較の参考に日商簿記2級試験との比較も紹介しておきましょう。
日商簿記2級の資格は、商業簿記はもちろん工業簿記の知識を持っていることが証明できる資格。2級を取得できるほどの知識があれば、企業の財務諸表を読み取れるようになります。
日商簿記2級の試験で問われるのは商業簿記と工業簿記の知識。これらの知識を身に着けるには、ある程度数学的な知識が必要となります。
人によってはこの数学的知識というだけで、難しいイメージを持つ方も多いかと思いますが、反対に言えばコツをつかめば案外あっさり身につくのが簿記の勉強です。
試験の難易度に関しては、学ぶ方向性は違うもののやはり行政書士試験の方が難易度高いというのが一般的な考え方です。
関連記事:
日商簿記2級の勉強時間の詳細はこちら
中小企業診断士試験と比較
中小企業の経営状態を見たり、その後の経営方針に関してアドバイスをしたりする中小企業診断士。中小企業診断士試験は、法律知識はもちろん、経営論や経済学の知識も必要になります。
中小企業診断士試験の偏差値は67程度。行政書士試験よりも高くなっており、この数字を見ても難易度の高さがうかがえます。
法律知識に加え、さらに経営学や経済学の知識も問われる中小企業診断士試験は、二次試験で実務的な出題があることもあり、身に着けた知識を活用できることが合格条件に。
この点を考えても行政書士試験よりも難易度は高いといえるでしょう。
関連記事:
中小企業診断士の合格率の詳細はこちら
司法書士試験と比較
行政書士と非常に近いイメージがあるのが司法書士。しかし試験の難易度は大きく違います。
司法書士は不動産や法人などの登記を代行する業務や、少額訴訟の代理人となることもできる資格ですので、問われる法律知識の範囲がかなり広くなります。民法や商法などはもちろん、登記関係の法令や民事訴訟に関する法律知識なども問われる難関資格です。
実際に司法書士試験を偏差値で表現すると76程度、例年の合格率も5%程度とかなり難易度は高く、行政書士試験よりも難しい難関資格となります。
関連記事:
司法書士試験の難易度の詳細はこちら
行政書士試験が「易しい」と言われる3つのポイント
行政書士試験は、「易しい」とも「難しい」とも言われる珍しい資格。
そこでまずは行政書士試験は易しいと言われる理由について3つ紹介しておきましょう。
ポイント① 受験資格がなく誰でも挑戦できる
まずは受験資格がないというのが大きなポイントとなります。学歴や職歴は問わず、さらに年齢も国籍も問わない資格ですので、誰でも挑戦できる資格となります。
誰でも挑戦できるということは、それだけ受験のハードルが低い資格ということ。試験問題の難易度という点とは関係なく、イメージとして易しい試験と感じる方も多いかと思います。
もうひとつ、受験資格がないということは、専門的に学んだ方意外でも挑戦できるということ。つまりそれだけ出題内容の難易度が高くないというイメージがつくことも考えられます。
ポイント② 他士業の試験と比較すると易しい
行政書士は「八士業」のひとつと言われています。
八士業とは、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、弁理士、税理士、土地家屋調査士、海事代理士を指して呼ぶ言葉。八士業の資格を持っている方は、職務上必要な場合、住民票や戸籍謄本などの請求ができます。
この八士業の中で、試験難易度がもっとも低いのが行政書士です。さらに行政書士と同じく独立開業を目指せる士業、公認会計士や中小企業診断士、不動産鑑定士などと比較しても、行政書士試験の難易度は低いとされています。
法律知識が問われるほかの士業と比較した場合、行政書士試験は易しいという結論になるわけです。
ポイント③ 絶対評価のため対策がしやすい
行政書士試験の難易度を易しいとする理由の一つに、「合格を目指しやすい」というポイントがあります。なぜ目指しやすいかと言われれば、それは行政書士試験が「絶対評価」の試験であることがポイントです。
絶対評価の試験とは、あらかじめ合格基準点が公表されており、この合格基準点をクリアした受験者は全員合格できる試験。最初に過去10年間の合格率を表にしましたが、8~15%と合格率にバラつきがあるのが絶対評価の試験の特徴です。
絶対評価とは反対に、あらかじめ合格率や合格者数が決まっており、その率や人数に合わせて合格基準点が変動する試験を「相対評価」の試験と呼びます。司法書士試験やマンション管理士試験がこの相対評価の試験に含まれます。
| 行政書士試験合格基準(全てを満たす必要あり) | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 必要な正答率 | 合格基準点 | |
| 法令等科目 | 50%以上 | 122点(244点満点) | |
| 一般知識等科目 | 43%以上 | 24点(56点満点) | |
| 試験全体 | 60%以上 | 180点(300点満点) | |
行政書士の合格基準点は上記の通り。この基準を満たせば合格です。
絶対評価の試験が易しいといわれる理由は、事前の対策に明確な目標設定ができるという点。相対評価の試験は受験者のレベルが高い年と低い年で合格ラインが大きく変わるため、どこまで勉強しても安心ということがありません。
ある程度のラインを目標に勉強できる行政書士試験は、対策がしやすい、つまり難易度としては易しい試験と呼ばれることになります。
行政書士試験が「難しい」と言われる3つのポイント
続いては行政書士試験が難しいと言われる3つのポイントを紹介していきます。これから行政書士試験を目指そうと考えている方、特に初学者の方はこちらのポイントを頭に入れておくといいでしょう。
ポイント① 法律の専門知識が問われる
この記事でも何度も紹介していますが、行政書士試験で出題される問題の多くは法律知識を問う問題です。
大学が法学部だった方や、すでにほかの資格試験に挑戦し、ある程度法知識がある方にとっては大きな問題ではありませんが、そうではない方にとってこの法律の専門知識を身に着けるのはかなり難易度が高い勉強となります。
法律には法文でしか目にしないような言い回しがあったり、ほかの法律と絡めて覚える必要があるものがあったりと、慣れていない方には難しいイメージがあるかと思います。
ポイント② 試験範囲が広い
法律問題に関するもうひとつのポイントは試験範囲が非常に幅広いという点。
行政書士の仕事は官公署に提出する書類の作成代行が中心。官公署に提出する書類にはあらゆる種類があり、それらの書類を作成するために必要な法知識をしっかりと身に着ける必要があります。
勉強を進めていく中で、いろいろな法律の内容が混ざってしまったりと、初学者の方にはなかなかハードルの高い試験ということができます。
ポイント③ 「易しい」と思い込んでいる方が多い
そもそものポイントとして、「行政書士試験は易しい」という論調が目立つという問題があります。
最初に書いた通り、行政書士試験の難易度を偏差値で表現すれば62程度。ほかの法律知識を必要とする資格試験と比較すればやや易しいレベルですので、行政書士試験を屋しいという方がいるのは間違いありません。
こうした「易しい」という論調を耳にして、気軽に挑戦しようとなると、実際に勉強を始めてからその難しさに驚くかと思います。
行政書士試験の難易度を冷静に把握しておくことで防げるポイントではありますが、なんとなくで目指し始めると非常に難しく感じるかと思います。
行政書士試験に合格するための勉強法
行政書士試験合格を目指す上では、「計画性」と「効率」に重きを置いた学習が不可欠です。
膨大な試験範囲を、ただやみくもに勉強していても、体系的な知識は身につきませんし、合格レベルに到達することも難しいでしょう。
試験予定日から逆算して、いつの段階でどこまでの学習をこなすのかを常に念頭に置くこと、さらに出題傾向を元に狙われるポイントのみを重点的に勉強することを意識できるのが理想的な行政書士試験対策です。
関連記事:
行政書士試験の勉強方法の詳細はこちら
行政書士試験は独学でも合格できるのか?
難しいとも易しいとも言われる行政書士試験。ではこの試験の対策は独学でも可能なのかを考えていきたいと思います。
ネットなどで探してみると分かるかと思いますが、行政書士試験に独学で挑戦して合格したという方は少なくありません。この事実だけをみれば、当然独学でも合格可能な試験ということになります。
ただし、これは相当厳しい方法であることも間違いありません。特に初学者の方にとってはあまりおすすめできる勉強方法とも言えません。
実際に行政書士試験に独学で合格したという方は、すでにほかの資格試験に独学で合格した経験がある方や、法律知識の基礎がある方、さらに何度か行政書士試験に挑戦したことがある方でしょう。
ほかの資格試験を独学でクリアしたことがある方は、そもそも資格試験の勉強に慣れている方。資格試験とはどのようなもので、どのように学ぶのが効率が良いかを知っている方でしょう。
法律知識のある方とは、業務上法律知識が必要な方や、大学などで法律の勉強をしたことがある方。すでに行政試験に挑戦したことがある方は、すでに予備校や通信講座を利用して受験をして失敗した方。つまりあと少し勉強すれば合格できるレベルにある方であり、初学者の方とは大きく状況が違います。
幅広い法律分野の知識を、ある程度の期間で身に着けようとする勉強は、よほど勉強が好きな方、得意な方を除けば独学では難しいでしょう。
そこで、より合格率を高めるための勉強方法を紹介していきましょう。
行政書士試験の合格率を上げるには通信講座がおすすめ
行政書士試験を目指す場合に考えられる勉強方法は3つ。
行政書士試験対策講座を開講している「予備校に通学」するか、同じく講座を開講している「通信講座を受講」するか、「独学」で挑戦するかです。
独学に関しては上で説明した通り。ある程度自信がある方や、法律知識のある方であれば可能ですが、こういった条件が揃っていない初学者の方にはおすすめできません。
そうなると勉強法は予備校通学か通信講座受講となります。
予備校と通信講座の大きな違いは「通学」です。この通学にはメリットもデメリットもありますが、特に社会人の方が試験に挑戦すると考えると、おすすめは通信講座となります。
予備校通学のメリットは、専門講師の授業をライブで受けられることや、予備校に通うことで勉強をする以外の選択肢がなくなり、勉強に集中できること。反対にデメリットは、仕事の都合で授業に出られない可能性があることや、通学時間が必要なこと、さらに受講料が高額であることなどが考えられます。
通信講座の受講料はさまざまですが、一般的に予備校通学の半額以下です。費用面でのメリットは非常に大きいといえます。
そのほかの通信講座のメリットなどを紹介していきましょう。
試験範囲が広いため効率的に学ぶのが合格率アップのコツ
行政書士試験の出題範囲は広く、短期間で試験対策をするには、効率的に学ぶことがポイントとなります。
初学者が独学で挑戦する場合の最大の問題点がここ。どの部分が重要で、どの部分が理解しにくいかなどが想像できないため、効率的な勉強スケジュールを組むのが難しくなります。
通信講座には独自の勉強カリキュラムがあります。このカリキュラムは、短期間の勉強で行政書士試験に合格するための最短ルートであり、あらかじめこのカリキュラムが組まれていることが大きなメリットです。
通信講座を利用するといっても、勉強自体は独学と同じく自宅で一人で行います。同じスタイルで勉強するのであれば、より効率よく学べる勉強方法がおすすめとなるのは当然のことでしょう。
マイペースで勉強ができる
通信講座をおすすめするもうひとつのポイントが「マイペースで勉強できる」という点です。予備校に通学する場合、勉強のペースは予備校が決めたカリキュラム通り進みます。すべての授業に出席し、このカリキュラム通りに勉強を進めることができれば、当然合格に大きく前進することになります。
しかし社会人の方が働きながら勉強をすると考えた場合はどうでしょう。予備校の授業がある日は絶対に残業や付き合いがないとは言い切れないでしょう。もし順調に授業に参加できても、授業のペースについていけない場合も考えられます。
一度カリキュラムから外れてしまうと、これを取り返すのは大変です。仕事をしながらと考えると、相当難しいことになるでしょう。
一方通信講座を受講する場合、カリキュラムをどんなペースで紹介していくかはある程度学ぶ方次第。残業が長引いたり、断れない付き合いの席があった場合は無理に進める必要はありません。
行政書士試験の勉強は効率よく学ぶのと同時に、マイペースで学ぶことも重要。この2つを同時に実現できるのが通信講座ということになります。
通信講座の中ではフォーサイトの行政書士講座がおすすめ
ネットで通信講座を検索すると、多くの講座がヒットするかと思います。さらに人気の高い行政書士試験対策講座は、多くの通信講座が開講しており、どの講座を選ぶべきか迷ってしまう方もいらっしゃるかと思います。
そこで、通信講座を選ぶ場合、チェックすべきポイントを紹介しましょう。
- 高い合格実績のある講座を選ぶ
- 自分に合った講座を選ぶ
- 安心して学べる講座を選ぶ
大事なポイントは主にこの3つ。高い合格実績は効率の良いカリキュラムの証明になりますし、自分に合った講座や安心して学べる講座は、マイペースで学べることに直結します。
この3つのポイント考えた場合、おすすめしたいのがフォーサイトの行政書士試験対策講座です。
高い合格実績で信頼できる通信講座
まずはフォーサイト受講生の、直近の合格率を確認しておきましょう。
| 2023年度(令和4年度) 行政書士試験合格率 | |
|---|---|
| 全国平均 | 13.98% |
| フォーサイト受講生 | 45.45% |
2021年度試験のフォーサイト受講生の合格率は38%。全国平均の3倍以上の数字を叩き出しています。受講生の3人に1人以上は合格している計算となり、この数字を見ても信頼度の高い講座であることが分かります。
フォーサイトの行政書士試験対策講座には、行政書士試験に精通した講師がおり、この高師がその年の行政書士試験で重要となりそうなポイントをしっかりと授業で解説しています。
授業の質は予備校の授業と同レベルかそれ以上。この質の高い授業を自宅で受講できるのがおすすめのポイントとなります。
初学者から経験者まで選べる3つのバリューセット
フォーサイトをおすすめする2つ目の理由は、選べる3つのコースがあることです。
行政書士を目指す方の中にはまったくの初学者の方から、受験経験者の方までいろいろな方がいらっしゃいます。すべての方に同じカリキュラムを提供するのはあまり効率的ではありません。
フォーサイトでは3つのバリューセットが用意されています。
| バリューセット1 | バリューセット2 | バリューセット3 | |
|---|---|---|---|
| 基礎講座 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 過去問講座 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 直前対策講座 | × | 〇 | 〇 |
| 答練講座 | × | × | 〇 |
| 過去問一問一答演習 | × | × | 〇 |
行政書士試験で重要になるのは、基礎講座と過去問講座。この2つに関しては全てのセットに含まれていますので、最低限の授業でも合格する自信がある方はバリューセット1でいいでしょう。
バリューセット3は全ての教材が含まれているセット。特に初学者の方におすすめのセットになります。
セットによって受講料も変わりますので、まずは自分の知識レベルをしっかりと認識し、自分に合ったセットを選択するようにしましょう。
全額返金保証制度で安心して学べる
最後に安心して勉強できるポイントを紹介しておきます。それが「全額保証制度」です。
これはバリューセット3に含まれる制度で、行政書士講座(バリューセット3)を受講した方で、一定の条件をクリアした方が、万が一行政書士試験に落ちてしまった場合、受講料の全額を返金するという制度。
返金保証があるということは、それだけ講座の中身に自信があるということ。フォーサイトの行政書士講座を、カリキュラム通りに消化していけばほぼ間違いなく行政書士試験に合格できるという自信があるのでしょう。
初学者の方など、本当に合格できるか不安という方もこの制度があることで安心して勉強に打ち込めるはず。安心して勉強することで合格率を高めることができるでしょう。
フォーサイト 行政書士講座まとめ
行政書士試験は難関資格と呼ぶほど難易度が高くはありませんが、簡単に取得できる資格というほど難易度は低くありません。
行政書士試験の難易度を、ほかの資格試験を用いて説明すれば、司法書士試験や中小企業診断士試験、社会保険労務士試験より易しく、宅地建物取引士試験や日商簿記2級の試験よりも難しいといったあたり。
受験資格に制限がないように、多くの方に合格するチャンスがある資格ではありますが、そのためにはある程度しっかりとした準備が必要になります。
行政書士試験を目指すのであれば、どの程度の難易度か、どういった問題が出題されるのかなど、行政書士試験の難易度をしっかりと認識し、その難易度に合わせた準備をするようにしましょう。
行政書士試験に短期間で合格するには、効率的な勉強方法がおすすめ。
予備校に通学するのもひとつの方法ではありますが、通える方は近隣に予備校がある方に限られます。資格予備校は人口の多い地域に集中していますので、全ての方におすすめの方法ではありません。また、そのほかにもいくつかデメリットがありますので、そのデメリットからもこの記事ではおすすめしていません。
おすすめは独学同様自宅で一人で、マイペースで学びつつ、効率的な勉強が望める通信講座。数ある通信講座の中では、フォーサイトの行政書士講座がおすすめです。
受講生の合格率が高く、自分に合ったコースを選べるうえ、万が一試験に落ちた場合も全額返金保証制度があるため、安心して効率的に学ぶことが可能です。
フォーサイトの講座の特徴や、バリューセットごとの違い、また全額返金保証制度の内容などは、無料で請求できる資料で確認することができます。
これから行政書士を目指そうと考えている方は、まずはフォーサイトで資料請求をし、講座の内容などを確認しましょう。資料請求をすることで、どのような教材でどのように学ぶのかのお試しが可能ですので、勉強のイメージもしやすくなります。
1分で完了!
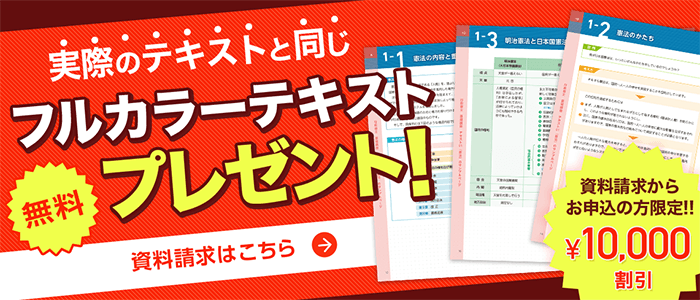
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ















 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


