法律の知識がなくても行政書士の問題、4回解いたら理解できた!


| 性別 | 男性 |
| 年代 | 30代 |
| 勉強期間 | 6ヶ月間 |
| 職業 | パート・アルバイト |
| 勉強法 | 暗記,記述式,過去問 |
| 商品 | CD,テキスト,問題集,資料請求 |
| 受験回数 | 初学者(1回目) |
| ダブルライセンス | 宅建 |
| 試験科目 | 憲法,行政法 |
| 学習スタイル | 通信講座,通学 |
■大学は工学部、法律知識は皆無です・・
3月から他の資格の試験勉強を開始していたのですが、5月から行政書士資格取得も決め、併せて勉強することにしました。2つとも1回で合格するつもりでしたが、行政書士の勉強にはあまり時間がないと思っていました。
ですから、効率のいい勉強が不可欠だと考えました。大学は工学部だったので、法律の知識は全くありません。もちろん不安だらけです。
■本屋さんで福澤先生の本に出会いました
本屋でたまたま見つけたのが「行政書士に一発合格できる本」です。そこには合理的な合格方法が載っていました。それに感動し資料請求したところ、送られて来たテキストはまさに望んでいたものでした。
テキスト内容はスリムで余分な知識を省いてあり、講義のCDも分かりやすかったので、早速申し込みました。それが5月です。
週2回、他の資格の学校への行き帰りには、行政書士の講義CDを聴いていました。聴いていて分かった講義CDの長所は、分からないところを繰り返し聴けることだと気づきました。通信講座はこのように時間の融通が利くので、通学より有利ではないかと思えます。
■法律はまず、全体を理解するところから
講師の福澤先生は、最初は細かいことにこだわらず、とにかく全体を理解することが先決であると説明されていたので、その言葉通りに講義CDをざっと聴きました。それから問題集に取り込みました。
もちろん1回目は全く解けません。ですから問題を読んだらすぐに答えを読み、分からない部分はテキストで確認するという方法を取りました。
2回目には普通に問題を解き、3回目には前回、2回目に解けなかった問題と不安がある問題のみを解いていきました。4回目にも前回、3回目で解けなかった問題と不安がある問題のみを解いていきました。
そうしているうちに、最初の福澤先生のアドバイスがよく分かったんです。つまり、法律の勉強は、最初に全体をおおまかに把握し、それに枝葉をつけるように細かい知識をつけていくと効率がいいということです。
■行政法には時間を割きました
行政書士試験で一番重要な科目は行政法です。ですから、得意科目にするために最も時間を割きました。
行政手続法は難しいので頑張りが必要です。地方自治法は行政組織法の1つですから行政法をからめて学習すると効率がいいです。憲法は、主な条文は暗記すべきでしょう。テキストに出てくる判例はすべて押さえたほうがいいと思います。
■「過去問」から派生して知識を補完
残りの教科は「過去問」さえやっていれば十分のはずです。とにかく情報を絞りこんであるテキストと「過去問」をまず押さえることです。マニアックな知識はいりません。記述式対策には別の勉強が必要だと思います。
国語は苦手でしたが、克服するために、毎日の勉強の始めは国語から始めることにしました。最初はかなり苦痛でしたが、1ヶ月ぐらいすると慣れてきて、本試験前までには得意科目になっていました。このように苦手な科目を先にすることによって、苦手意識を克服する方法はかなり有効だと思います。
本試験では社会科学の時事問題であまり得点できませんでしたが、「過去問」からそんなに離れた出題はされてないと思いました。「過去問」をまず押さえて、派生する事柄をチェックしていれば十分得点できると思います。
■試験では、慌てないこと。時間配分にも気をつけて
試験では不意をつく問題が出たとしても、動揺せず確実に解ける問題を得点していくことです。正誤問題においては、正しいものを求められているのか、間違ったものを求められているのか、注意が必要です。問題文の横に大きく「誤」などと書いておくと、ミスを防げると思います。
あとは時間配分に気をつけて、分からない問題は軽く飛ばし、1点を着実にかせぐという姿勢が大事だと思います。飛ばした問題の答えを、後で急に思い出すこともけっこうありますから。
■法律知識がなくてもフォーサイトだけで十分
合格するにはフォーサイトだけで十分です。法律の知識がなくても心配する必要はありません。皆さんも合格を目指して頑張って下さい。
3月から他の資格の試験勉強を開始していたのですが、5月から行政書士資格取得も決め、併せて勉強することにしました。2つとも1回で合格するつもりでしたが、行政書士の勉強にはあまり時間がないと思っていました。
ですから、効率のいい勉強が不可欠だと考えました。大学は工学部だったので、法律の知識は全くありません。もちろん不安だらけです。
■本屋さんで福澤先生の本に出会いました
本屋でたまたま見つけたのが「行政書士に一発合格できる本」です。そこには合理的な合格方法が載っていました。それに感動し資料請求したところ、送られて来たテキストはまさに望んでいたものでした。
テキスト内容はスリムで余分な知識を省いてあり、講義のCDも分かりやすかったので、早速申し込みました。それが5月です。
週2回、他の資格の学校への行き帰りには、行政書士の講義CDを聴いていました。聴いていて分かった講義CDの長所は、分からないところを繰り返し聴けることだと気づきました。通信講座はこのように時間の融通が利くので、通学より有利ではないかと思えます。
■法律はまず、全体を理解するところから
講師の福澤先生は、最初は細かいことにこだわらず、とにかく全体を理解することが先決であると説明されていたので、その言葉通りに講義CDをざっと聴きました。それから問題集に取り込みました。
もちろん1回目は全く解けません。ですから問題を読んだらすぐに答えを読み、分からない部分はテキストで確認するという方法を取りました。
2回目には普通に問題を解き、3回目には前回、2回目に解けなかった問題と不安がある問題のみを解いていきました。4回目にも前回、3回目で解けなかった問題と不安がある問題のみを解いていきました。
そうしているうちに、最初の福澤先生のアドバイスがよく分かったんです。つまり、法律の勉強は、最初に全体をおおまかに把握し、それに枝葉をつけるように細かい知識をつけていくと効率がいいということです。
■行政法には時間を割きました
行政書士試験で一番重要な科目は行政法です。ですから、得意科目にするために最も時間を割きました。
行政手続法は難しいので頑張りが必要です。地方自治法は行政組織法の1つですから行政法をからめて学習すると効率がいいです。憲法は、主な条文は暗記すべきでしょう。テキストに出てくる判例はすべて押さえたほうがいいと思います。
■「過去問」から派生して知識を補完
残りの教科は「過去問」さえやっていれば十分のはずです。とにかく情報を絞りこんであるテキストと「過去問」をまず押さえることです。マニアックな知識はいりません。記述式対策には別の勉強が必要だと思います。
国語は苦手でしたが、克服するために、毎日の勉強の始めは国語から始めることにしました。最初はかなり苦痛でしたが、1ヶ月ぐらいすると慣れてきて、本試験前までには得意科目になっていました。このように苦手な科目を先にすることによって、苦手意識を克服する方法はかなり有効だと思います。
本試験では社会科学の時事問題であまり得点できませんでしたが、「過去問」からそんなに離れた出題はされてないと思いました。「過去問」をまず押さえて、派生する事柄をチェックしていれば十分得点できると思います。
■試験では、慌てないこと。時間配分にも気をつけて
試験では不意をつく問題が出たとしても、動揺せず確実に解ける問題を得点していくことです。正誤問題においては、正しいものを求められているのか、間違ったものを求められているのか、注意が必要です。問題文の横に大きく「誤」などと書いておくと、ミスを防げると思います。
あとは時間配分に気をつけて、分からない問題は軽く飛ばし、1点を着実にかせぐという姿勢が大事だと思います。飛ばした問題の答えを、後で急に思い出すこともけっこうありますから。
■法律知識がなくてもフォーサイトだけで十分
合格するにはフォーサイトだけで十分です。法律の知識がなくても心配する必要はありません。皆さんも合格を目指して頑張って下さい。
6おめでとう
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。


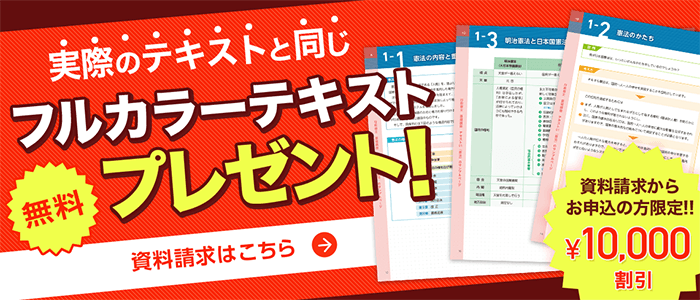













 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


