高い合格率を実現する
フォーサイト
3つの特徴
features
3
つの特徴受講生から大好評!
フルカラーテキスト
豊富な図とイラスト満載だから
分かりやすく、覚えやすい
分かりやすく、覚えやすい
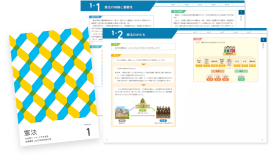
テキスト連動で理解を加速
講義動画
専用スタジオで収録しているから
音声もクリアで聞き取りやすい
音声もクリアで聞き取りやすい

いつでもどこでも学習できる
eラーニング
テキストも講義もダウンロード可能
問題演習機能も豊富
問題演習機能も豊富

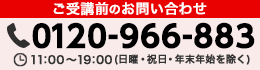
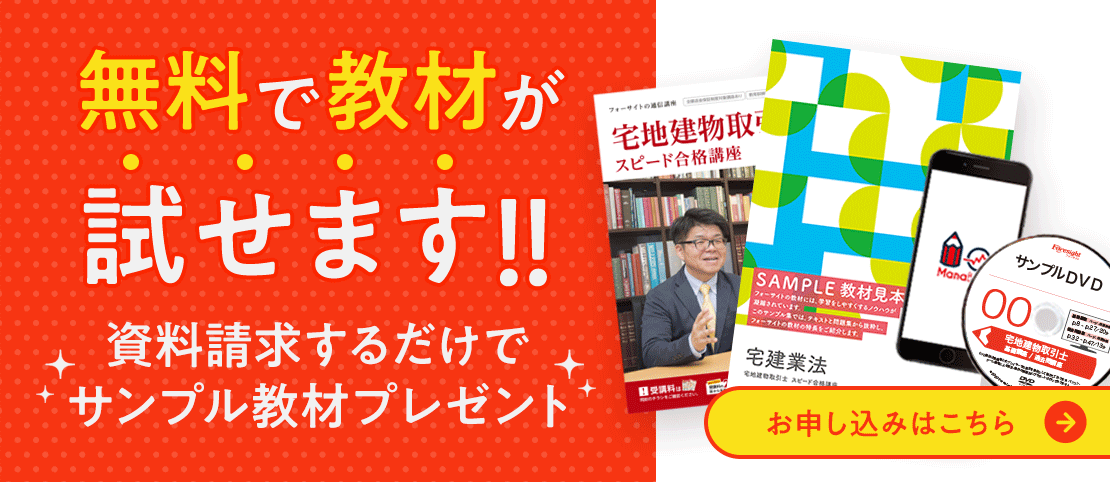

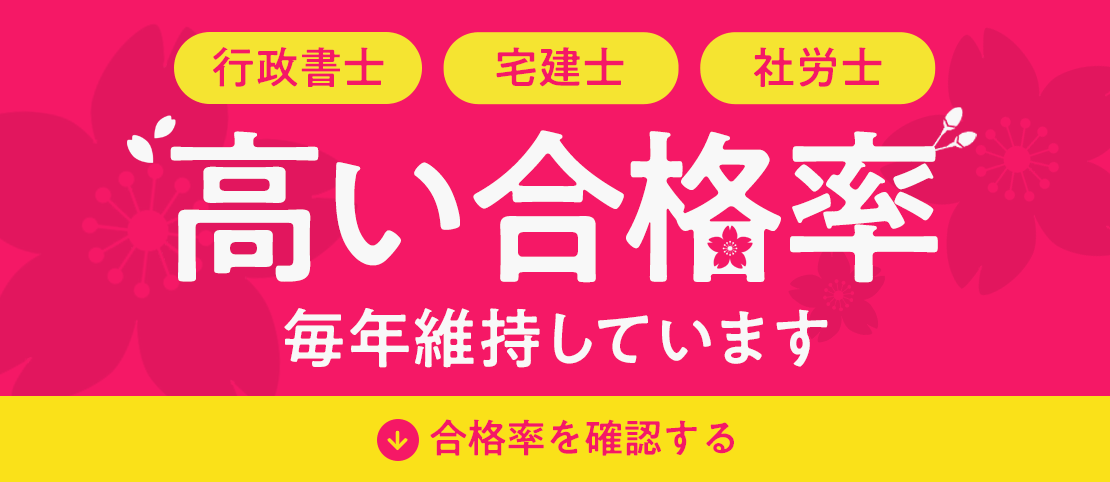
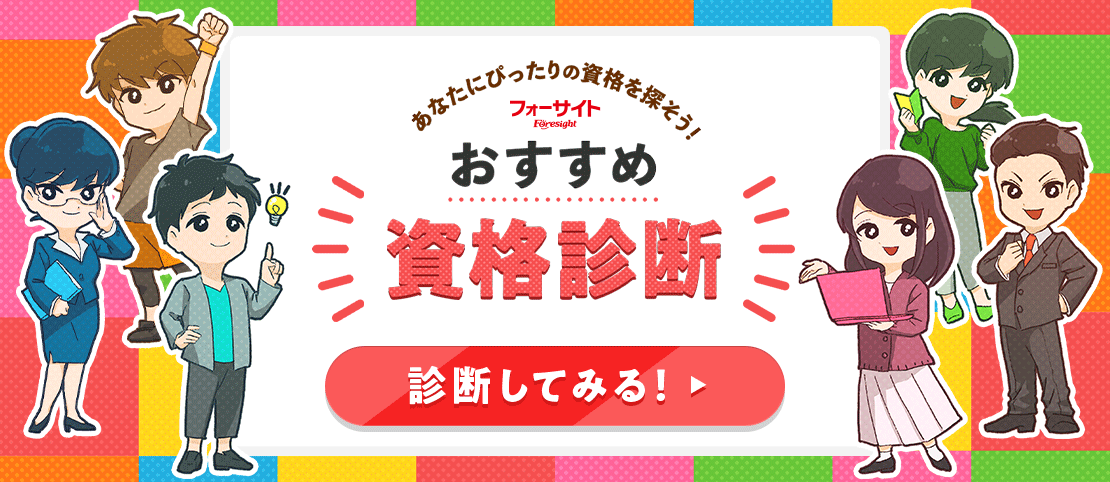


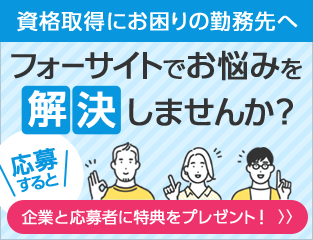

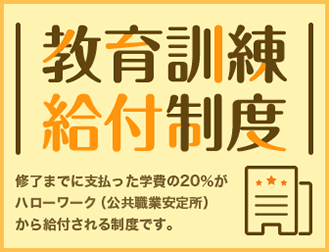
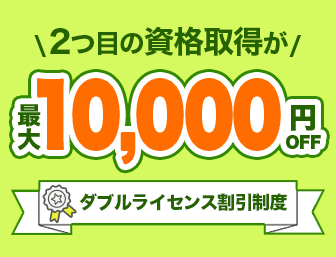
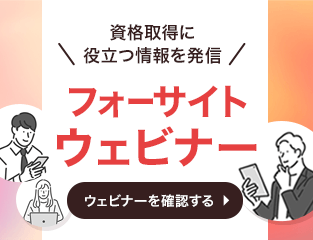















 0120-966-883
0120-966-883

