宅建士(宅地建物取引士)
不動産取引に関する契約を結ぶ際に、「重要事項の説明」を行うことが法律で唯一許されている国家資格です。
宅地建物取引士についてもっと知りたい方はこちら宅建士(宅地建物取引士)通信講座の費用
※再チャレンジセットのショッピングローン分割払い例:18回×3,100円(初回3,943円)
宅建士(宅地建物取引士) 一覧
単科講座がセットで
お得なバリューセット
-
バリューセット1基礎+過去問教育訓練給付制度59,800円
-
バリューセット2基礎+過去問+直前対策教育訓練給付制度64,800円
-
バリューセット3基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習教育訓練給付制度全額返金保証制度69,800円〜
宅建士(宅地建物取引士)の受講サポート
宅建士(宅地建物取引士)講座 合格実績
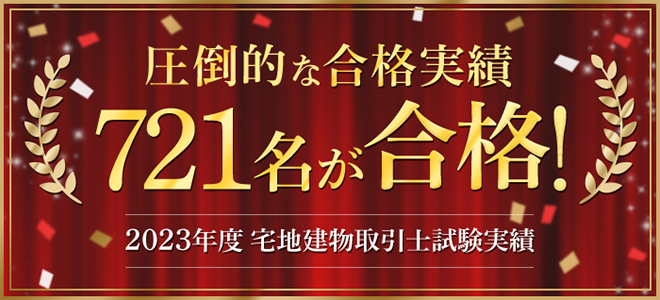
合格率の
※2023年度試験の実績です。
フォーサイト
宅建士(宅地建物取引士)の特徴
講師歴20年以上の実力派講師陣!

フォーサイト宅建講座の講師陣を率いる「窪田義幸」は、8万人以上の指導実績があるレジェンド講師です。
これまでの豊富な講師経験から、宅建試験の場合、どこで落ちるのか、どのように対策するのかを熟知しています。
安心してお任せください。
満足度驚異の90%以上こだわりのフルカラーテキスト!

今や、宅建通信講座のテキストはどの予備校もテキストはフルカラーですが、
フォーサイトのフルカラーテキストは、試験に出るだけのボリューム・重要度毎の配色・理解を助ける豊富なイラストで、高い合格率を実現しています!
あなたにピッタリの講座が見つかる

フォーサイトの宅建通信講座では、「初学者向けコース」と「学習経験者向けコース」があります。
法律の勉強経験がゼロの方はもちろん、独学の方や受験経験者など、あなたの学習経験にピッタリの教材が見つかります。
通信講座の枠を超えた、ライブ講義!

定期的にライブ講義があることで、学習のペースメーカーとなり、モチベーションも上がり、しかも、問題演習によって実力も着きます!
また、受講生同士のチャットで、学習の不安や喜びの交流する場になることもあり、多くの方が励まされています。
宅建士(宅地建物取引士)試験の苦手科目対策も万全

宅建試験において、出題範囲の多い「権利関係」や、苦手になりやすい「法令上の制限」もバッチリ対応します。
フォーサイトの通信講座では出題範囲のみを効率的に学習し、受講生の苦手傾向を分析した特別な問題演習機能があるので、苦手分野を徹底的に攻略できます!
宅地建物取引士通信講座の合格までのスケジュール
宅地建物取引士試験において、全国平均合格率を大きく上回る合格実績を誇るフォーサイト。 8万人以上の受講生を指導してきた実績を基に練り上げられたオリジナルカリキュラムが、合格の鍵です。 「合格点主義」で、忙しい人に配慮した教材・カリキュラムだから、フォーサイトなら最短3か月で宅建試験合格を目指せます。
インプット
アウトプット
8万人の受講生に選ばれた
高い合格率は当たり前!
フォーサイト通信講座合格プロセス
フォーサイト通信講座合格プロセス
選ばれる理由その1
忙しくても、自分のペースで学習できる!

働きながら、育児しながら合格を目指すのは難しいと考えていませんか?
フォーサイトの宅建講座なら、eラーニング「ManaBun」で通勤や昼休みの時間など、ちょっとしたスキマ時間で学習できます。
あなたのライフスタイルに合わせた学習スケジュールも自動で組み立てるので、自分のペースで迷わずに勉強できます。
eラーニングを詳しく見る
選ばれる理由その2
最強のコストパフォーマンス

フォーサイトが考える「合格に必要な教材」は、紙のテキスト・講義・eラーニングです。豊富で良質な教材を低価格で提供しているから、高いコストパフォーマンスを実現しています。
さらに、「不合格になったら、受講料がムダになる」という大きな不安も、フォーサイトの宅建通信講座なら適用条件さえクリアすれば、もし不合格だった場合でも受講料は全額返金されます。
だから、お金をムダにせず安心して勉強に集中することができます!

選ばれる理由その3
たった3か月で合格!最高のタイムパフォーマンス

宅建試験の合格には、標準学習時間として約6か月(300~500時間程度)の学習期間が必要となりますが、フォーサイトの通信講座をご利用いただいた方の中には、わずか3か月(200時間程度)で合格されている方もたくさんいます。
満点主義ではなく、合格点主義で教材を制作しているフォーサイトだから、少ない時間で、ムリなく最短合格が可能なのです。
カリキュラムを確認する 短期合格者の声見る
選ばれる理由その4
成長が実感できる。だから、続けられる!

勉強を無理なく続ける秘訣は、「私はできる!」という実感です。
フォーサイトの通信講座では、解答にかかった時間を記録できる問題集で、過去の自分を比べられるので、成長を実感しながら学習を進められます。
さらに、定期的なライブ講義やイラスト豊富なフルカラーテキストなど、楽しく勉強できます。
これらが、合格への大切な原動力です。
詳しく見る
宅地建物取引士通信講座
おすすめコンテンツ
講師を身近に感じられるコンテンツをご紹介します。
合格者インタビュー
-
 30代 / 主婦スケジュール機能とスキマ時間の活用で宅建合格!未就学児2人の母である山中さんは、宅建資格へのチャレンジをきっかけに産後初めて勉強されたとのこと。育児と勉強の両立に苦労...続きを見る
30代 / 主婦スケジュール機能とスキマ時間の活用で宅建合格!未就学児2人の母である山中さんは、宅建資格へのチャレンジをきっかけに産後初めて勉強されたとのこと。育児と勉強の両立に苦労...続きを見る -
 30代 / 会社員スキマ時間を利用して500時間の学習で一発合格!貿易会社で働き、6歳と3歳のお子様を持つ前川さん。周りの人が家を購入したことがきっかけで不動産の知識を得たいと感じたこと...続きを見る
30代 / 会社員スキマ時間を利用して500時間の学習で一発合格!貿易会社で働き、6歳と3歳のお子様を持つ前川さん。周りの人が家を購入したことがきっかけで不動産の知識を得たいと感じたこと...続きを見る -
 40代 / パートタイマー仕事と育児の両立をしながら宅建に合格できました!法学部法律学科出身の岩田さんは、学生時代に取れなかった宅建資格にずっと憧れを抱いていたそうです。子育てと仕事と勉強、全て...続きを見る
40代 / パートタイマー仕事と育児の両立をしながら宅建に合格できました!法学部法律学科出身の岩田さんは、学生時代に取れなかった宅建資格にずっと憧れを抱いていたそうです。子育てと仕事と勉強、全て...続きを見る -
 40代 / 会社員過去問の繰り返しが一発合格の決め手になりました!ホテルの宿泊部門に勤務されている栂﨑さん。勤務先で宅建取得を推奨していたことをきっかけに受験を決意し、絶対に一発で合格し...続きを見る
40代 / 会社員過去問の繰り返しが一発合格の決め手になりました!ホテルの宿泊部門に勤務されている栂﨑さん。勤務先で宅建取得を推奨していたことをきっかけに受験を決意し、絶対に一発で合格し...続きを見る -
 30代 / 会社員効率的に勉強し、200時間の学習で一発合格!不動産業界のデベロッパーで働く永吉さんは、フォーサイトの「全額返金保証制度」と「合格点主義」のキャッチコピーに魅力を感じ...続きを見る
30代 / 会社員効率的に勉強し、200時間の学習で一発合格!不動産業界のデベロッパーで働く永吉さんは、フォーサイトの「全額返金保証制度」と「合格点主義」のキャッチコピーに魅力を感じ...続きを見る -
 60代 / パートタイマースキマ時間で学習し、2度目の受験で宅建合格!パート社員として不動産会社の事務をしている天田さん。仕事と家事の両立で勉強時間の確保が難しかったようですが、スキマ時間に...続きを見る
60代 / パートタイマースキマ時間で学習し、2度目の受験で宅建合格!パート社員として不動産会社の事務をしている天田さん。仕事と家事の両立で勉強時間の確保が難しかったようですが、スキマ時間に...続きを見る -
 20代 / 学生不動産業界への就職を夢見て3か月で宅建に一発合格!現在大学3年生の金子さんは、不動産業界への就職を考えていることから、宅建試験の受験を決意。試験を受けるのは今回が初めてと...続きを見る
20代 / 学生不動産業界への就職を夢見て3か月で宅建に一発合格!現在大学3年生の金子さんは、不動産業界への就職を考えていることから、宅建試験の受験を決意。試験を受けるのは今回が初めてと...続きを見る -
 30代 / 自営業2か月以内の勉強で短期合格!自営業で働いている大野さんは、将来ご親族の所有する不動産を管理するにあたり、宅建試験の受験を決意。短期合格を目指し、1~...続きを見る
30代 / 自営業2か月以内の勉強で短期合格!自営業で働いている大野さんは、将来ご親族の所有する不動産を管理するにあたり、宅建試験の受験を決意。短期合格を目指し、1~...続きを見る
講師からのメッセージ

窪田 義幸 Kubota Yoshiyuki
″栄光を掴む″ための講義、
″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします。
みなさんにお願いがあります。最後には必ず栄光を掴んでください。意欲だけでは合格できませんが、意欲がなければ合格できないのが資格試験です。
私の知っている限り、合格された受講生は皆、粘り強かったといえます。
落ち込む時があってもあきらめずに勉強を続け、試験当日まで合格への強い意欲を持ち続けていました。
結果は必ずついてきます。

北川 えり子 Kitagawa Eriko
学びの楽しさをシェアしたい
子どものころには分からなかった学ぶ楽しさが、大人になってから初めて分かったという人は多いでしょう。大人は、自分の人生を充実させるために学ぶので、楽しさや喜びを純粋に実感できるのかもしれません。
学びは習慣です。そして、本来楽しいものです。資格取得を通じて、「大人が学ぶ」 ということの楽しさをあらためて知り、ぜひ習慣にしていきましょう。
学習はもちろん、例えば芸術や文化に関すること、日々の仕事に関することなど、興味を持って知識を深めることの楽しさを、みなさんとシェアしたいと思います。
無料資料請求で
クオリティを体感してください!

テキスト・eラーニングのサンプル教材のほか、
資料請求した方限定の割引情報など、たくさんの特典があります。
15時までなら即日発送!


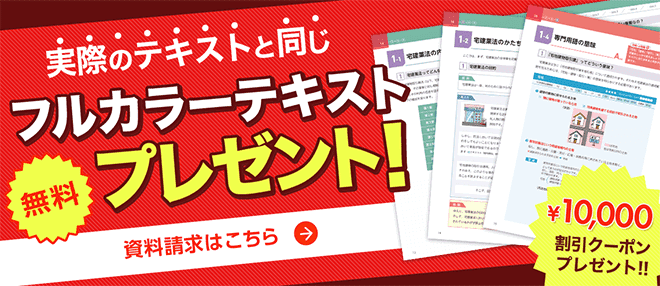
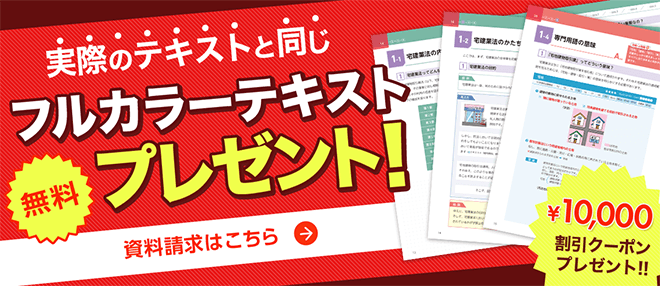
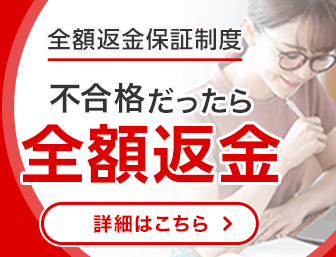


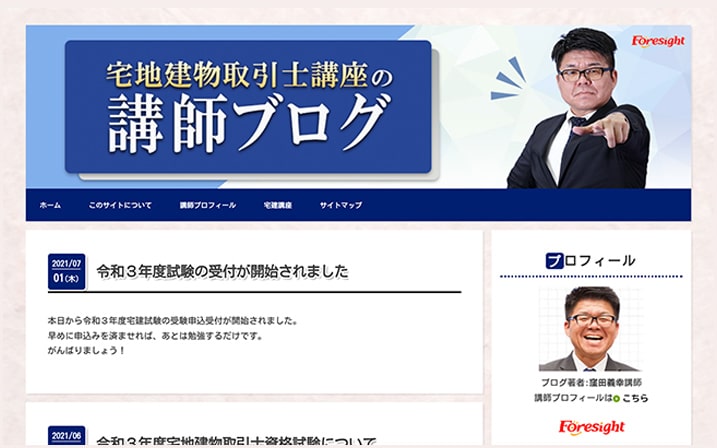


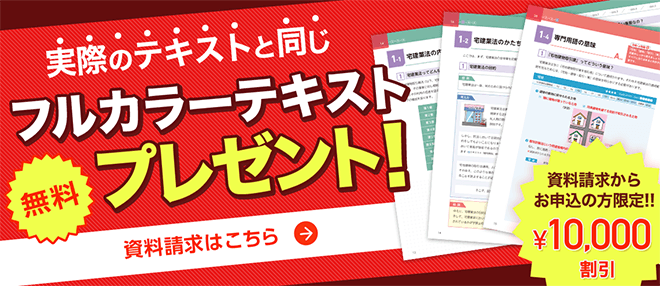
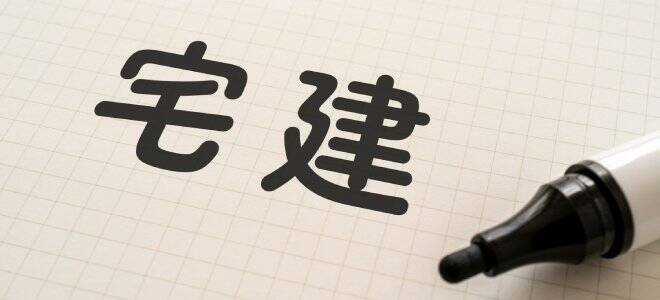













 ログイン
ログイン

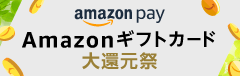

 0120-966-883
0120-966-883


