令和7年度 通関士試験の解答速報・試験講評
2025/10/10
解答速報
10月5日(日)に実施されました、令和7年度 通関士の解答速報と試験講評を公開いたします。自己採点も公開いたしますので、是非ご活用ください。
通関業法
| 第1問 | イ | 1 |
|---|---|---|
| ロ | 10 | |
| ハ | 9 | |
| ニ | 12 | |
| ホ | 13 | |
| 第2問 | イ | 14 |
| ロ | 1 | |
| ハ | 13 | |
| ニ | 12 | |
| ホ | 4 | |
| 第3問 | イ | 5 |
| ロ | 10 | |
| ハ | 2 | |
| ニ | 1 | |
| ホ | 6 | |
| 第4問 | イ | 13 |
| ロ | 9 | |
| ハ | 14 | |
| ニ | 12 | |
| ホ | 1 | |
| 第5問 | イ | 7 |
| ロ | 14 | |
| ハ | 6 | |
| ニ | 1 | |
| ホ | 9 | |
| 第6問 | 1,2,5 | |
| 第7問 | 3,5 | |
| 第8問 | 2,4 | |
| 第9問 | 1,2,3 | |
| 第10問 | 1,3,4 | |
| 第11問 | 5 | |
| 第12問 | 3 | |
| 第13問 | 4 | |
| 第14問 | 2 | |
| 第15問 | 3 | |
| 第16問 | 3 | |
| 第17問 | 4 | |
| 第18問 | 0 | |
| 第19問 | 2 | |
| 第20問 | 5 | |
関税法等
| 第1問 | イ | 8 |
|---|---|---|
| ロ | 11 | |
| ハ | 14 | |
| ニ | 4 | |
| ホ | 1 | |
| 第2問 | イ | 10 |
| ロ | 6 | |
| ハ | 7 | |
| ニ | 2 | |
| ホ | 12 | |
| 第3問 | イ | 6 |
| ロ | 5 | |
| ハ | 15 | |
| ニ | 11 | |
| ホ | 7 | |
| 第4問 | イ | 13 |
| ロ | 4 | |
| ハ | 5 | |
| ニ | 15 | |
| ホ | 6 | |
| 第5問 | イ | 15 |
| ロ | 4 | |
| ハ | 11 | |
| ニ | 8 | |
| ホ | 3 | |
| 第6問 | 1,3 | |
| 第7問 | 2,4,5 | |
| 第8問 | 2,5 | |
| 第9問 | 1,4 | |
| 第10問 | 1,4,5 | |
| 第11問 | 1,3 | |
| 第12問 | 3,5 | |
| 第13問 | 3,5 | |
| 第14問 | 1,3 | |
| 第15問 | 3,5 | |
| 第16問 | 2 | |
| 第17問 | 4 | |
| 第18問 | 5 | |
| 第19問 | 4 | |
| 第20問 | 3 | |
| 第21問 | 3 | |
| 第22問 | 3 | |
| 第23問 | 5 | |
| 第24問 | 3 | |
| 第25問 | 4 | |
| 第26問 | 4 | |
| 第27問 | 5 | |
| 第28問 | 2 | |
| 第29問 | 3 | |
| 第30問 | 3 | |
通関実務
| 第1問 | a | 1 |
|---|---|---|
| b | 13 | |
| c | 4 | |
| d | 6 | |
| e | 11 | |
| 第2問 | a | 9 |
| b | 6 | |
| c | 8 | |
| d | 5 | |
| e | 12 | |
| f | 1665000 | |
| g | 1245000 | |
| h | 1200000 | |
| i | 337500 | |
| j | 180000 | |
| 第3問 | 4,5 | |
| 第4問 | 2,3 | |
| 第5問 | 1,4,5 | |
| 第6問 | 2,5 | |
| 第7問 | 3,5 | |
| 第8問 | 39000 | |
| 第9問 | 55300 | |
| 第10問 | 9580000 | |
| 第11問 | 8498000 | |
| 第12問 | 9020000 | |
| 第13問 | 3 | |
| 第14問 | 2 | |
| 第15問 | 2 | |
| 第16問 | 4 | |
| 第17問 | 5 | |
試験講評
10月5日(日)に、「令和7年(第59回)通関士試験」が実施されました。受験された皆さま、お疲れ様でした。
今回の試験は、通関士として必須となる法令知識の確実な定着と、複雑な実務事例に対する応用力を厳しく試す内容となりました。近年の傾向通り、単なる暗記ではなく、制度の根拠と適用範囲を深く理解しているかが問われる、実力重視の試験であったと言えます。
I. 総論:実務と法令の「細部の正確性」が鍵
今回の試験で合格の鍵を握ったのは、「通関業法」では過去問実績のある論点を自信をもって正解できたこと、「関税法等」では過去問の知識をもとに未知の問題を正解できるとともに、新作問題となった設問の数値や例外規定の正確な知識が、合否を分ける要素となりました。さらに「通関実務」では正確な品目分類と、加算要素の正確な判断でした。
また、合格基準については、難易度から「通関業法」および「通関実務」については満点の60%以上、「関税法等」については満点の55%以上と推測します。
II. 各科目詳細
(1) 通関業法
「通関業法」は、通関士試験での典型的な論点を問う安定した出題でした。主要な論点は、通関業の定義、申告書等の審査・記名義務といった通関士の職責に関する基礎知識でした。特に、通関業の許可取消しや、それに伴う欠格期間に関する詳細な規定の理解が求められました。
また、通関業者が作成し、関税官署に提出する義務のある帳簿や書類の保存規定、および税関長による業務改善命令や通関士に対する懲戒処分に関する規定など、法令違反時のリスク管理に関する正確な知識が不可欠でした。
(2) 関税法等
「関税法等」は、特に関税評価、賦課徴収、特恵制度、保税制度の4テーマからは応用的な知識が問われました。
1.関税評価(取引価格の原則)
課税価格決定の根幹である関税定率法4条の適用要件、特に輸入貨物に関わる加算要素(ロイヤルティ、手数料、運送費)の範囲を正確に判断する能力が試されました。
2.賦課徴収
更正や修正申告に伴う納期限や延滞税の計算、過少申告加算税の課税要件、さらには納税申告後の更正の請求の期間など、手続上の期限に関する正確な知識などが問われました。
3.特恵関税制度
特恵関税の適用範囲や、特恵原産地証明書の保存期間、輸入通関時の各手続とNACCSの利用に関する知識など、実務で重要度が増している論点が出題されました。
(3) 通関実務
「通関実務」は、提示された資料を駆使した実務判断力を要求する内容でした。法令知識を基礎としながらも、設問に示された条件な利用を通じて、迅速かつ正確な結論を導く能力が要求される、通関士試験の真骨頂と言える出題内容でした。
1.輸出申告(分類)
第1問の飲料の輸出分類では、関税率表第20類(調製品)と第22類(飲料、アルコール)の注を厳密に読み込み、特にアルコール分の含有量に基づいて分類し統計品目番号を特定することが求められました。
2.輸入申告(分類)
籠細工、木製品、ブラシ類などの雑製品の分類において、第42類、第44類、第46類、第96類といった複数の類に跨る品目が出題され、それぞれの類注・項注の定義を正確に適用し、品目番号を特定することが求められました。
また、課税価格の算出においては、ロイヤルティ、宣伝費、販売促進費、運送費、さらには無償特定修理後の貨物など、加算要素および減算要素に関する複雑な事例設定がなされました。提供されたインボイス情報に基づき、最終的な課税価格を導き出すための高度な計算力と論理的思考力が試されました。
3.適用税率と計算
日EU・EPA、日英EPAに基づく税率の適用事例では、原産材料割合の計算を行い、適用税率を判断する実務的な能力が求められました。
以上
※解答速報はフォーサイト独自のものであり、正解を保証するものではありません。また、情報を予告なく更新することがあります。
※解答速報・試験講評に関するご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※この解答速報・試験講評の著作権は株式会社フォーサイトが有し、無断転載及び無断転用を禁じます。

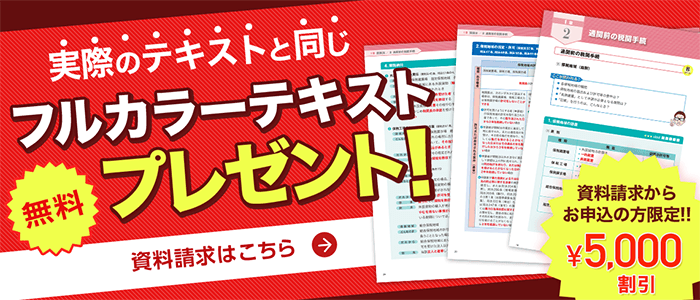


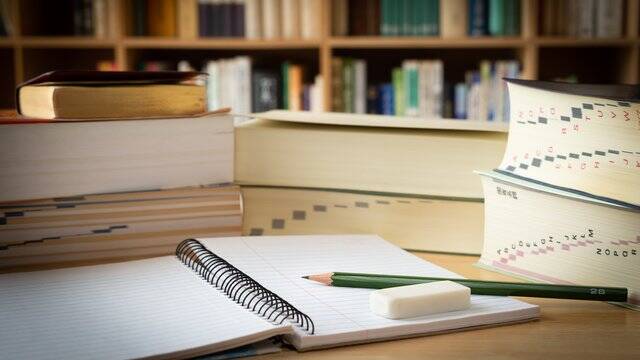




 ログイン
ログイン




