2025年1月26日(日) 実施 2級FP技能検定の試験講評
2025年1月26日(日)に、2級FP技能検定が実施されました。受検されたみなさま、お疲れ様でした。
今回は学科試験の一部科目で細かな知識が問われる問題も見られましたが、全体的には定番といえる基礎的なテーマが多く出題されていました。また、実技試験においても頻出テーマから多く出題されているため、全体的な難易度としては、「標準的」という印象でした。基礎的な問題を見極めて正解できれば、合格ラインである60%を十分クリアできる難易度だったといえます。
選択肢の作り方や知識の問われ方に変化が見られているものもありますが、解答に必要な知識に変わりはないため全体の出題傾向や難易度は大きく変わっていません。見慣れないものであっても、明らかに正誤が判断できるものから落ち着いて対処できていれば、全体としては合格基準である60%に到達することができる難易度だったといえます。
ライフプランニングと資金計画
科目全体としては頻出テーマで構成されていましたが、確定拠出年金や国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済の選択肢では細かな知識が問われていたため、「やや難化した」と感じた方が多かったのではないでしょうか。正誤判定に時間がかかる選択肢だったため、ここで問題を見極めることができたかどうかが試験全体の時間配分のポイントになったといえます。
リスク管理
過去問でも頻繁に問われている論点が多く出題されていましたので、過去問演習をしっかり行っていた方には得点しやすい内容だったといえます。なお、問題13で問われた「MVA機能を有する変額個人年金保険」については、知識が無い場合でも消去法で解答できる内容でした。
金融資産運用
過去問でも頻繁に問われている論点が多く出題されていました。「固定利付債券の利回り」、「株式の投資指標」は定番問題であるため、いずれも時間をかけずに対応したい問題です。なお、「イールドカーブ」は細かな知識であり出題頻度も低いため、一般的には「捨て問」といえますが、過去問で丁寧に対策していれば正誤を判断できる内容でした。
タックスプランニング
「インボイス制度」は5月試験、9月試験と連続で出題されました。その他のテーマも典型的・基本的な論点であるため、得点源にしたい科目でした。
不動産
これまでの出題傾向に変わりはなく、不動産に係る法律が中心に出題されていました。「宅地建物取引業法」も定番のテーマと言えます。科目全体をとおして過去問でも頻繁に問われている論点が多く出題されていましたので、過去問演習をしっかり行っていた方には得点しやすい内容だったといえます。
相続・事業承継
細かな知識が問われている選択肢もあり、「やや難しい」という印象がありますが、「民法上の贈与」や「贈与税の計算」、「相続対策としての生命保険の活用等」は確実に正解したい問題です。なお、「改正不動産登記法における相続登記」は2級では出題されたことがなく対策が難しいテーマでしたが、問われた内容は基本的な知識であるため、改正情報をしっかり学習していた方は正答できる問題でした。
実技試験の分析
出題内容については、投資信託の収益分配金、株式の投資指標、延べ面積の最高限度の計算、生命保険の保障内容、損益通算、法定相続分と遺留分、キャッシュフロー表の穴埋め計算、6つの係数を使った計算、バランスシート(純資産額の計算)等の定番問題を中心に構成されていました。
頻出テーマから多く出題されているため、過去問演習を確実に行い、解法や計算手順をしっかり習得していれば得点できた内容と言えます。
【第1問】FP総論
【第2問】金融資産運用
【第3問】不動産
【第4問】リスク管理
【第5問】タックスプランニング
【第6問】相続・事業承継
【第7問】【第8問】ライフプランニングと資金計画
【第9問】総合問題①
【第10問】総合問題②
最後に
2級FP技能検定の学習経験を生かし、みなさまが、益々ステップアップされることをお祈り申し上げます。
※試験講評はフォーサイト独自のものであり、正解を保証するものではありません。また、情報を予告なく更新することがあります。
※試験講評に関するご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※この試験講評の著作権は株式会社フォーサイトが有し、無断転載及び無断転用を禁じます。


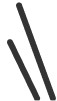
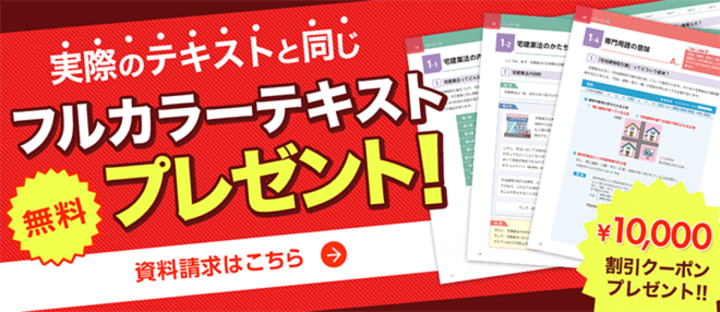
学科試験の分析