簿記の3級2級ともに定年を過ぎてから学習して合格

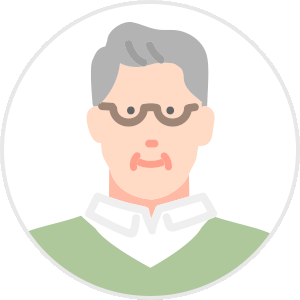
| 試験の種類 | 日商簿記3級,日商簿記2級 |
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 60代 |
| 試験年度 | 第148回 3級試験2018年(30年度)2月,第148回 2級試験2018年(30年度)2月 |
| エリア | 千葉県 |
| 勉強時間 | 300時間 |
| 勉強期間 | 5ヶ月間 |
| 職業 | 正社員(サラリーマン) |
| 商品 | 問題集 |
| 受験回数 | 初学者(1回目) |
| 試験科目 | 工業簿記 |
eラーニング使用回数
※eラーニングの使用回数となり、実際の学習時間とは異なります。
工場勤めで定年を迎え、「実は会社のこと何もわかっていなかったなぁー」と思い、実務とは真反対の経理関係の勉強をすることを思い立ちました。漫然と学習しても成果が分からないので、工業簿記のある日商簿記2級の資格取得を目標としました。
スケジュールは、10月中旬講座申込、11月に3級受験(準備期間1ケ月)、翌年2月に2級受験(準備期間3ヶ月)。教科書だけでは頓挫しそうなので映像教材のある通信教育を受けることにしました。受講講座はウェブで比較して一番安かったフォーサイトに決めました。
教材が届いて、3級の学習をスタート。学習期間1ケ月の前半をインプット、後半を演習に当てることにしました。、私の若い頃の簿記3級のイメージは「1週間の勉強で合格」だったのですが、実際は結構手ごわい。
さほど期待していなかった(小野先生、ゴメンナサイ!)映像教材がとても分かりやすくて、助かりました。通勤は片道2時間ちょっとあるのですが、読書で老眼が一挙に進んだことがあり、通勤時間帯の学習は避けました。
5時半起床、9時半帰宅の毎日の中で勉強時間を確保しないで流されがちとなってしまい、アウトプットには10日間を残すのみとなってしまいました。問題集に取り組んでも目安時間の3倍くらいかかるし、間違いも多いし、散々な結果でした。
うまくいかない理由を考えると、
①仕訳を間違える
②下書きに時間がかかる
③その転記を間違える
④計算ミス
⑤計算が遅い
⑥見直す時間がない、
ということでした。
これを、「回答用紙に直接仕訳けていく」ことで解決しました。例えば、残高試算表では、勘定科目は記入済ですので、左右の空白に1欄2行くらいの小さな字で仕訳けていきます。
コツは、借方貸方を必ず同時に記入することです。仕訳を3回くらい見直した後に合計します。計算は遅いままですが、小野先生がおっしゃるように(不思議と)合計は合うようになりました。
3級の合否を確かめる間も無く、2級の学習に突入。商業・工業簿記のインプットにそれぞれ1ヶ月、演習に1ヶ月のスケジュールで学習を進めました。
3級の反省から、ペース守るようにしました。インプットには苦手な部分を中心に教科書の内容を圧縮した「まとめノート」を作成しています。A4判で3級は8頁、2級は19頁に圧縮できています。必要な箇所をサッと見ることができるので、問題集での記憶定着も効率的にできました。
2級は計算量が増えるので、問題集は2回転しかできず、どうしても時間内に全問を解くまでの実力が付かなかったので、捨てる問題は最初から手を付けないようにしました。
おかげさまで、3級2級ともに1回の受検で合格することができました。最後は受験テクニックに頼った感はありますが、満点をとる必要はありません。時間内に合格点を取ればよいのです。
その意味でフォーサイトの教材は、ちゃんと満点を狙えるがムダがなく、最適であったと思います。
スケジュールは、10月中旬講座申込、11月に3級受験(準備期間1ケ月)、翌年2月に2級受験(準備期間3ヶ月)。教科書だけでは頓挫しそうなので映像教材のある通信教育を受けることにしました。受講講座はウェブで比較して一番安かったフォーサイトに決めました。
教材が届いて、3級の学習をスタート。学習期間1ケ月の前半をインプット、後半を演習に当てることにしました。、私の若い頃の簿記3級のイメージは「1週間の勉強で合格」だったのですが、実際は結構手ごわい。
さほど期待していなかった(小野先生、ゴメンナサイ!)映像教材がとても分かりやすくて、助かりました。通勤は片道2時間ちょっとあるのですが、読書で老眼が一挙に進んだことがあり、通勤時間帯の学習は避けました。
5時半起床、9時半帰宅の毎日の中で勉強時間を確保しないで流されがちとなってしまい、アウトプットには10日間を残すのみとなってしまいました。問題集に取り組んでも目安時間の3倍くらいかかるし、間違いも多いし、散々な結果でした。
うまくいかない理由を考えると、
①仕訳を間違える
②下書きに時間がかかる
③その転記を間違える
④計算ミス
⑤計算が遅い
⑥見直す時間がない、
ということでした。
これを、「回答用紙に直接仕訳けていく」ことで解決しました。例えば、残高試算表では、勘定科目は記入済ですので、左右の空白に1欄2行くらいの小さな字で仕訳けていきます。
コツは、借方貸方を必ず同時に記入することです。仕訳を3回くらい見直した後に合計します。計算は遅いままですが、小野先生がおっしゃるように(不思議と)合計は合うようになりました。
3級の合否を確かめる間も無く、2級の学習に突入。商業・工業簿記のインプットにそれぞれ1ヶ月、演習に1ヶ月のスケジュールで学習を進めました。
3級の反省から、ペース守るようにしました。インプットには苦手な部分を中心に教科書の内容を圧縮した「まとめノート」を作成しています。A4判で3級は8頁、2級は19頁に圧縮できています。必要な箇所をサッと見ることができるので、問題集での記憶定着も効率的にできました。
2級は計算量が増えるので、問題集は2回転しかできず、どうしても時間内に全問を解くまでの実力が付かなかったので、捨てる問題は最初から手を付けないようにしました。
おかげさまで、3級2級ともに1回の受検で合格することができました。最後は受験テクニックに頼った感はありますが、満点をとる必要はありません。時間内に合格点を取ればよいのです。
その意味でフォーサイトの教材は、ちゃんと満点を狙えるがムダがなく、最適であったと思います。
6おめでとう
簿記の合格体験記
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。
×











 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


