管理業務主任者のテキストと過去問を主に使った勉強方法

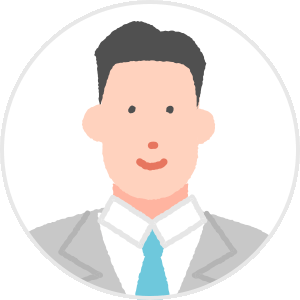
| 試験の種類 | 管理業務主任者 |
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 40代 |
| 試験年度 | 2018年(平成30年度) |
| エリア | 東京都 |
| 勉強時間 | 700時間 |
| 勉強期間 | 4ヶ月間(7月/8月〜) |
| 職業 | 自営業・会社経営 |
| 勉強法 | 過去問,参考書 |
| 商品 | DVD,テキスト,問題集,サポート |
| 受験回数 | 初学者(1回目) |
| ダブルライセンス | 宅建,行政書士 |
| 学習スタイル | 通信講座 |
受験してみようと思った切っ掛け
来年は今住んでいるマンションの理事会の役員が連番で回ってくるということもあって、もうすぐ8月も終わりの頃、マンション管理士を受けてみようと思ったんです。この資格合格率が10%弱って事で、結構難しいということが判明しました。
行政書士と宅建士は合格しているので、民法はなんとかなるとしてもそれ以外は何らかのサポートがないと厳しいかも知らないなって思いました。
フォーサイトにした理由
ネットでいろいろな書籍が推薦されていたので、本屋さんで実際に手に取って眺めたりしていたのですが、どうもピンとこないんですね。参考書が合う合わないっていうのは人それぞれだと思うので、一概には言えないですが、私には文章の羅列って言うか、スッと頭に入ってこないかったんです。
その中でフォーサイトの通信講座がオススメってのがネット上でも結構書かれていて、市販のテキストにはない何かを期待しつつ申し込むことにしました。
ところでマンション管理士と試験内容がかなり重なっている管理業務主任者という資格があります。試験内容が重なっているだけではなくて、試験日も1週間違いです。どうせなら一緒に受験勉強した方がいいし、片方受かったら次回もう一方を受験するときに免除科目もある。ということで両方の講座を申し込みました。
勉強方法
暫くして段ボールいっぱいのテキストが送られてきました。思っていた3倍くらいです。どうしようかと考えるまでもなく、DVDを視聴し始めることにしました。このDVDは要点のみの説明なので、テキストに重要そうなところをチェックするだけになります。
新規の分野を勉強する場合、まったく重要ポイントが分からないため、まずはさらっとテキストを読み終えたら過去問を解いてみます。最初は間違いだらけですが、構わずに先へ進みます。ここでは各分野ごとに問われている問題の傾向と分量を実体験するのが目的です。
テキストの厚みだけみればそれほど分量が多くないが、マンション管理士では区分所有法が超重要です。何度も手を替え品を替え問われているのがわかります。
2周目の過去問からは次のように勉強を進めています。
1.ある単元の過去問をやる
2.テキストの再チェックとノートへの簡単な整理
3.最後にもう一度その知識で判断を誤った過去問のポイントに適切に対応できているのかを確認
このやり方だと漫然と問題を解くよりも効率よく進められるんですね。ただ1周するのに3週間弱かかってしまい。2周目が終わったのが10月の終わり頃でした。
11月に入ってから
11月に入ってからは択一問題集をこなしつつ、予想問題をやったりしていたのですが、やはり区分所有法がガンになって今ひとつ歯が立たないんです。やはり過去問をやりこむしかないかと思い、過去問を解いていると少し引っかかるところがあるんですね。平成29年度の過去問をやったときの印象と過去問集に載っている問題の質というか傾向が若干違っているように思えるんです。
本試験
結局時間切れで臨むことになりました。マンション管理士、管理業務主任者ともに大体1時間と少しで一通り終わり、見直しに入りました。正直よく分からない問題も結構ありました。数字を知っているか知らないかとかですね。考えても仕方がないので適当に塗りつぶして提出しました。
マンション管理士は残念な結果でしたが、管理業務主任者は35点でなんとか合格することが出来ました。次はもう少し区分所有法に力を入れて勉強しようと思ってます。
来年は今住んでいるマンションの理事会の役員が連番で回ってくるということもあって、もうすぐ8月も終わりの頃、マンション管理士を受けてみようと思ったんです。この資格合格率が10%弱って事で、結構難しいということが判明しました。
行政書士と宅建士は合格しているので、民法はなんとかなるとしてもそれ以外は何らかのサポートがないと厳しいかも知らないなって思いました。
フォーサイトにした理由
ネットでいろいろな書籍が推薦されていたので、本屋さんで実際に手に取って眺めたりしていたのですが、どうもピンとこないんですね。参考書が合う合わないっていうのは人それぞれだと思うので、一概には言えないですが、私には文章の羅列って言うか、スッと頭に入ってこないかったんです。
その中でフォーサイトの通信講座がオススメってのがネット上でも結構書かれていて、市販のテキストにはない何かを期待しつつ申し込むことにしました。
ところでマンション管理士と試験内容がかなり重なっている管理業務主任者という資格があります。試験内容が重なっているだけではなくて、試験日も1週間違いです。どうせなら一緒に受験勉強した方がいいし、片方受かったら次回もう一方を受験するときに免除科目もある。ということで両方の講座を申し込みました。
勉強方法
暫くして段ボールいっぱいのテキストが送られてきました。思っていた3倍くらいです。どうしようかと考えるまでもなく、DVDを視聴し始めることにしました。このDVDは要点のみの説明なので、テキストに重要そうなところをチェックするだけになります。
新規の分野を勉強する場合、まったく重要ポイントが分からないため、まずはさらっとテキストを読み終えたら過去問を解いてみます。最初は間違いだらけですが、構わずに先へ進みます。ここでは各分野ごとに問われている問題の傾向と分量を実体験するのが目的です。
テキストの厚みだけみればそれほど分量が多くないが、マンション管理士では区分所有法が超重要です。何度も手を替え品を替え問われているのがわかります。
2周目の過去問からは次のように勉強を進めています。
1.ある単元の過去問をやる
2.テキストの再チェックとノートへの簡単な整理
3.最後にもう一度その知識で判断を誤った過去問のポイントに適切に対応できているのかを確認
このやり方だと漫然と問題を解くよりも効率よく進められるんですね。ただ1周するのに3週間弱かかってしまい。2周目が終わったのが10月の終わり頃でした。
11月に入ってから
11月に入ってからは択一問題集をこなしつつ、予想問題をやったりしていたのですが、やはり区分所有法がガンになって今ひとつ歯が立たないんです。やはり過去問をやりこむしかないかと思い、過去問を解いていると少し引っかかるところがあるんですね。平成29年度の過去問をやったときの印象と過去問集に載っている問題の質というか傾向が若干違っているように思えるんです。
本試験
結局時間切れで臨むことになりました。マンション管理士、管理業務主任者ともに大体1時間と少しで一通り終わり、見直しに入りました。正直よく分からない問題も結構ありました。数字を知っているか知らないかとかですね。考えても仕方がないので適当に塗りつぶして提出しました。
マンション管理士は残念な結果でしたが、管理業務主任者は35点でなんとか合格することが出来ました。次はもう少し区分所有法に力を入れて勉強しようと思ってます。
0おめでとう
マンション管理士・管理業務主任者の合格体験記
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。
×















 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


