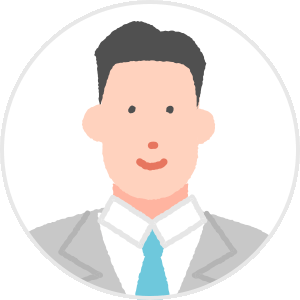
通関士の申告問題を5回ほど行い、最後は暗記するほどに
【通関士】
2019年(平成31年度)合格
- 勉強期間
- 1年間(10月〜)
- 受験回数
- 初学者(1回目)
- 職業
- 正社員(サラリーマン)
- 年代
- 50代
- 性別
- 男性
通関士試験に挑戦しようと思ったのが昨年11月。今年還暦を迎えるが、これまで輸出入業務に一切携わったことがないことから、通関業、関税法とは何ぞやという状況からの挑戦である。独学での合格は無理と判断し、ネットで色々調べた結果、評価の高いフォーサイトの通信教育を受講することとした。
2.勉強方法
12月から勉強を開始。試験まで10ケ月あること及び全然知識がないことからスケジュールは策定せずに、まずDVDで通関業法と関税法等を概観することとした。通関業法は頭に入ってくるが、若いころに比べ記憶力の落ちている身にとっては、分量も多く、複雑な関税法、関税定率法、関税暫定法、外為・外国貿易法はなかなか覚えることが出来ず、何度か挫けそうになったが、3月まではテキストでの勉強を継続した。
4月から6月の間は、通関業法と関税法等の問題集で過去問にチャレンジ。3回連続で間違った問題については整理ノートを作成した。過去問をやったことで、通関業法と関税法等については、ある程度、合格の見通しを得ることが出来た。
最後は、難題の実務である。単純な記憶となる品目分類(関税率表)は
試験直前の8月から覚えることとし、6月半ばから輸出入申告・計算問題にとりかかった。毎日、輸出申告、輸入申告問題を各々2問解くことを課して、通関実務対策編と合わせて、試験までに5回ほど行い、最後は回答を暗記するほどまでになった。また、この間、せっかく記憶した通関業法と関税法等の内容を忘れないよう、整理ノートで内容の確認を行った。
8月に入ってからは、再現問題集と模擬試験にとりかかり、試験までに
計4回実施した。これも、間違った問題については整理ノートに追記した。
試験前1ケ月となる9月は、実務の問題と併せて、テキストをもう1回見直して試験に臨んだ。
3.質問箱の活用
色々勉強しているうちに、似たような問題で回答が違うものがあることに気づき、その解明のために質問箱を活用させてもらった。8回質問したが、毎回、迅速に分かり易い解説をいただき、理解促進に大いに寄与した。通信教育の売りの一つである質問箱を活用しない手はない。
4.最後に
1問の正否が合格を左右することから、問題をよく読んで、ケアレスミスをしないことで試験に臨んだが、実務で3問ほど問題をよく読んでいれば間違っていなかったものがあったものの、初挑戦で合格することが出来た。
この10ケ月フォーサイトの教材だけで勉強してきたが、フォーサイトの教材を信頼し、しっかり勉強すれは合格できるということを自信をもってお薦めできる。


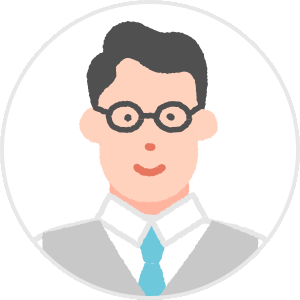
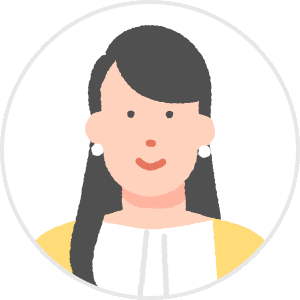

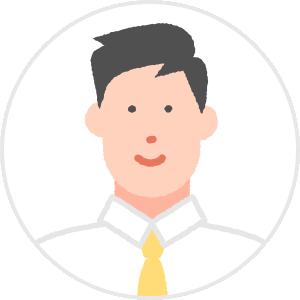
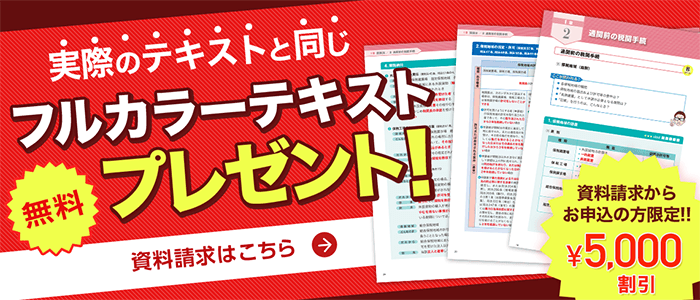


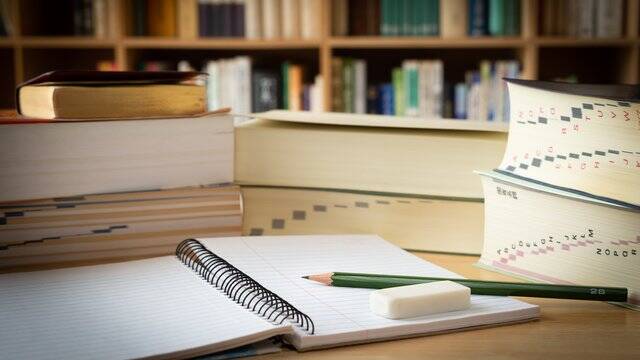






 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


