通関士試験の難易度は?合格率や難しい理由を解説!
更新日:2024年3月19日
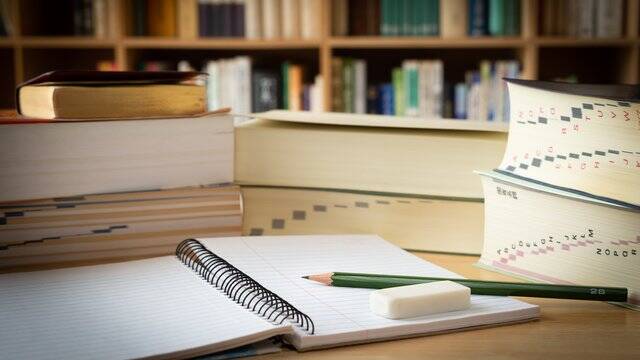
日本各地の税関において、輸出入の際に必要になる通関の業務を請け負っているのが通関士です。
日本は貿易で成り立つ国ですので、今後も通関士の仕事が減る、なくなるということはないでしょう。そんな通関士として働くために必要になるのが、通関士の資格。通関士資格を取得するために合格する必要があるのが通関士試験です。
通関士試験の難易度はどの程度か?合格率はどのくらいなのか?どのような対策が必要かなど、通関士試験の特に難易度に関する部分を解説していきます。
通関士とは
海外から日本国内の物を輸入する、日本国内から海外へ物を輸出する際、必要になるのが税関を通過させる行為、つまり「通関」です。
この通関業務を行えるのは、通関業者として認可を受けている企業のみ。そしてその通関業者が設置しなければいけないのが通関士となります。通関に関わる書類の申請など、通関にかかわる業務を行えるのは通関士のみ。つまり貿易をする以上、通関士の存在は必要不可欠ということになります。
通関士の資格を活かせるのは、通関業者が基本です。通関士として働くには、通関業者に勤務し、さらに財務大臣からの認可を受ける必要があります。一部物流会社やメーカーの中には、自社内に通関部門を持っている企業もあります。こうした企業に通関士が就職したとしても、通関業者としての認可を受けていない企業の場合通関士としての業務はできません。
こう聞くと通関士という資格は、一部限られた就職先しか選択できないように感じるかもしれませんが、通関士の資格を持っているということは通関に関する知識を持っていることの証明ともなります。
上記のように社内に通関部門を持っているメーカーや物流会社、また銀行等の金融機関でも通関士の知識は業務に活用できます。実際通関士の資格を持ちながら、通関業務以外の仕事に従事している方は多数います。
つまり通関士の資格を取得できるだけの知識も持つことは大きな意味があるということ。その知識は活用できる業界が比較的広く、転職を考えている社会人の方も取得を目指す価値のある資格ということになります。
そんな通関士になるための国家試験の難易度はどの程度のものかを解説していきましょう。
関連記事:通関士の詳細についてはこちら
通関士試験の難易度を合格率から推測
通関士試験の難易度を簡単に言ってしまえば「高い」ということになります。通関に関する国家資格はこの通関士資格のみ。また、通関に関する業務全般は、実質通関士の独占業務です。そんな資格試験が簡単ということはまずありません。
問題はどの程度高いのかという点。そんな難易度を、実際の数字から推測していきましょう。まず参考にするのは、過去に行われた通関士試験の合格率、また通関士試験の合格基準点から推測していきます。
通関士試験の合格率推移
最初に近10年間の通関士試験の合格率を紹介しておきましょう。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2014年度 | 7,692名 | 1,013名 | 13.2% |
| 2015年度 | 7,578名 | 764名 | 10.1% |
| 2016年度 | 6,997名 | 688名 | 9.8% |
| 2017年度 | 6,535名 | 1,392名 | 21.3% |
| 2018年度 | 6,218名 | 905名 | 14.6% |
| 2019年度 | 5,661名 | 708名 | 12.5% |
| 2020年度 | 5,934名 | 857名 | 14.4% |
| 2021年度 | 6,226名 | 929名 | 14.9% |
| 2022年度 | 5,640名 | 1,001名 | 17.7% |
| 2023年度 | 6,332名 | 1,534名 | 24.2% |
| 10年間平均 | 64,813名 | 9,791名 | 15.9% |
参照:税関HP
※全科目受験者の数値
通関士試験の合格率は15%前後といったところ。10年間の平均を算出すると、15.9%となります。
受験者の10人に1人以上の割合で合格者が出る試験ですので、合格率から見ればその難易度はそこそこ高いといったあたり。ほかの人気資格の合格率を見ると、宅地建物取引士試験が15%程度、行政書士試験が12%程度ですので、この2つの資格の間の難易度といってもいいかもしれません。
通関士試験の合格基準点
通関士試験の難易度を知るために、どの程度の得点を取れば合格できるのか、合格基準点をチェックしておきましょう。
| 試験科目 | 合格基準点 |
|---|---|
| 通関業法 | 各科目とも満点の60%以上 |
| 関税法等 | |
| 通関実務 |
通関士試験ではあらかじめ合格点が決まっている絶対評価が採用されています。絶対評価とは、あらかじめ設定されている合格点をクリアできれば、何人でも合格者が出るというタイプの試験です。
ちなみに絶対評価以外の合格基準としては、受験者の上位〇%が合格するという相対評価があります。相対評価は事前に合格点が決まっておらず、合格者数がある程度決まっている試験。
合格者数が決まっているため、受験者のレベルが高いと合格基準点も高くなる試験となります。
通関士試験は絶対評価。これは難易度を知るための大きなポイントとなりますので覚えておきましょう。
通関士試験の合格率にバラつきがある理由
上で紹介した近10年の合格率を見ると、比較的バラつきが大きいことに気づくかと思います。これが絶対評価の試験の特徴です。
絶対評価の試験は、合格基準点をクリアすれば何人でも合格者が出ます。つまり受験者のレベルや出題される問題のレベルで合格率が大きく変動する試験ということになります。
単純な合格率だけでは、通関士試験の難易度は推測しづらい部分がありますが、絶対評価だけに対策しやすい部分もあります。
絶対評価は、各科目で合格基準点をクリアすれば必ず合格できる試験です。つまり対策の勉強をする時点で、どの程度知識を身につければ合格できるかが想像しやすく、勉強の目標を立てやすいという試験になります。
通関士試験の推定偏差値
合格率や合格基準点から、通関士試験の難易度を推測しましたが、これでもやや分かりにくい部分があるかと思います。そこでほかの資格試験と比較してどの程度の難易度であるかを、偏差値という形で紹介していきましょう。
もちろん資格試験は、公式に偏差値を公表しているわけではありません。受験資格や出題難易度などから、独自に推測した偏差値という形で紹介していきます。数値に関しては参考程度という感覚で捉えておいてください。
通関士試験の推定偏差値は57
通関士試験の偏差値とともに、人気の高い資格試験の偏差値を紹介していきます。
| 資格 | 推定偏差値 |
|---|---|
| 裁判所事務官試験(大卒程度区分・一般職) | 72 |
| 中小企業診断士 | 67 |
| 社会保険労務士 | 65 |
| 行政書士 | 62 |
| マンション管理士 | |
| 日商簿記2級 | 58 |
| ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)2級 | 57 |
| 通関士 | |
| 宅地建物取引士(宅建士) | 55 |
通関士試験の難易度を偏差値で表すと57程度。宅地建物取引士よりもやや難易度は高く、マンション管理士や行政書士などよりはやや易しいというレベル。ほぼ同等の難易度としては、FP2級の試験が該当します。
大学入試で言えば「日東駒専」レベル
さらにイメージしやすいように、有名大学の偏差値と比較してみていきましょう。もちろん大学の偏差値は学部や学科によっても違いますし、偏差値を公表している団体(予備校など)によっても変わります。
あくまでもその大学が持つイメージの偏差値と比較していきますので、こちらも参考程度で考えていただければと思います。
| 大学レベル | 偏差値 | 資格試験 |
|---|---|---|
| 東大・京大 | 71以上 | ・裁判所事務官試験 ・司法試験(予備試験)等 |
| 早稲田大・慶応大・上智大 | 65~70 | ・社会保険労務士 ・中小企業診断士 ・司法書士 |
| MARCH (明治大・青山学院大・立教大・中央大・法政大) |
60~64 | ・行政書士 ・マンション管理士 |
| 日東駒専 (日本大・東洋大・駒沢大・専修大) |
55~59 | ・通関士 ・日商簿記2級 ・宅建士 ・FP2級 |
有名大学の偏差値ですが、まずは最高学府と呼ばれる東大・京大レベルを見てみましょう。このレベルの資格試験はごく一部で、司法試験の予備試験や、裁判所事務官採用試験などがこのレベルとなります。
さらに早慶上、MRACHレベルに対応する資格が上記の通り。そして通関士の難易度はいわゆる日東駒専のレベルということになります。
大学受験を経験した方はある程度イメージできるかと思いますが、日東駒専といえば、いわゆる難関大学とまではいかないものの、誰でも簡単に入れるレベルでもないといったところ。
通関士試験も同様で、超難関資格というわけではありませんが、誰でも簡単に独学で目指せる資格でもないということになります。
通関士試験に合格することを目指すのであれば、しっかりと対策する時間を確保し、さらにどのような試験になるかを知っておくことが重要となるでしょう。
通関士試験の難易度が高い理由
通関士試験の難易度に関して、実際の数値や、大学入試に置き換えたイメージで紹介してきました。通関士試験は難易度が高く、誰でも簡単に合格できるものではないということがお分かりいただけたかと思いますが、なぜこのような難易度になるのかを解説していきましょう。
簡単に言ってしまえば、通関に関する業務を行える唯一の国家資格だから難しいという事になりますが、ここでは実際に出題される問題の特徴などから、その難易度の理由を解説していきます。
法知識が必要
通関士試験の試験問題は、法律に関する問題が大半を占めます。その法律に関しても、通関業法や関税法など、普段の生活ではまず触れることのない分野の法律となります。
そもそも法律問題は、どんな資格試験の問題であっても対応が難しいと言われています。法律の文章には、非常に分かりにくい言い回しや、あまり見慣れない専門用語や単語が登場します。
大学等で法律の勉強をした方や、普段から法律に関する仕事をしている方以外には、なかなかとっつきにくい問題が多くなります。
そんな問題が大半を占めているというのが、通関士試験の難易度を高くしていると考えられます。
専門用語が多い
通関業務においては、通関時にしか使用されないような専門用語が使われます。こうした専門用語をマスターする必要があることが、通関士試験の難易度を高めていると考えられます。
専門用語を身に着ける、理解することは通関士試験の勉強を進める上でも重要。そもそも勉強をしている段階で多くの専門用語が登場しますので、専門用語をしっかりと理解できていないと、通関士試験の勉強自体が順調に進まないということになります。
実務に対応できる応用力が必要
試験科目の中に「通関実務」という科目があります。
通関士試験では、通関に関する法知識や専門用語を暗記するのはもちろん、身に着けた知識を実務の現場で活用する応用力も問われます。
新しい知識を単純に暗記するだけであれば、ある程度誰でも挑戦できますが、通関に関する法律や専門用語など、新たに覚えた知識に関してその内容をしっかり理解し、実務の中で活用していけるレベルまでにするには、やはり時間と根気が必要になります。
択一式
通関士試験は、複数の選択肢の中から適切な肢を選ぶ「択一式」が採用されています。「択一式なら解きやすい」というイメージがあるかもしれませんが、通関士試験の択一式は少々厄介です。というのも、「正答の肢がない設問」があるからです。
選択肢の中に適切な答えがない場合は「0」を選ぶようになっており、当てずっぽうで解答できないようになっています。
通関士試験合格に必要な勉強時間
通関士試験合格までの勉強時間の目安は、400~500時間です。1日2時間ずつ、毎日勉強を続けたとして、6~8ヶ月はかかる計算となり、腰を据えた取り組みが求められます。ただし、合格までに必要な勉強時間には、当然のことながら個人差があります。特に、試験対策に用いる教材やツールによって、学習効率は大いに変動します。
また、受験生活が長期に渡ればそれだけモチベーションが低下し、学習に悪影響を及ぼす可能性があります。通関士試験対策に独学で取り組む受験生も多いですが、対策講座を活用して短期間で効率良く合格を目指すのが得策です。
関連性のある資格や人気の資格との難易度比較
通関士試験は他資格と比較すると、どの程度の難易度なのでしょうか?ここでは、通関士と同じく人気の高い行政書士、社労士、宅建士の各国家試験について、合格率や勉強時間の観点から比較します。
行政書士試験と比較
通関士が輸出入手続の専門家なら、行政書士は許認可申請のプロと言えましょう。両試験の難易度を比較すると、行政書士試験の方が難易度が高いと考えて間違いないでしょう。
まず合格率の観点では、2019~2023年の過去5年間の平均合格率が、行政書士試験で約12%、通関士試験で18%となっており、行政書士試験が狭き門であることが分かります。
また、合格に必要な勉強時間の比較では、行政書士試験で概ね800時間、通関士試験で400~500時間が目安となるため、行政書士試験の方が多くの勉強時間を要することは明らかです。
参考:一般財団法人 行政書士試験研究センター 行政書士試験結果の推移
参考:税関 第57回通関士試験の結果
関連記事:行政書士の難易度についてはこちら
社労士試験と比較
通関士同様、手続業務を扱う専門家のひとつに、社労士が挙げられます。社労士は、労働・社会保険関係の諸手続きを独占業務として代行することができます。通関士試験と社労士試験の難易度比較では、社労士の方が難易度が高いと言えます。
2023年度社労士試験の合格率は6.4%であり、例年同程度の数字で推移しています。ただし、過去には合格率が2%台にまで落ち込んだ年度もある等、油断のできない試験でもあります。
目安となる勉強時間はだいたい800~1,000時間と言われており、通関士試験の倍ほどの時間の確保が必要です。
関連記事:社労士の難易度についてはこちら
宅地建物取引士試験と比較
通関士試験と比較すると、難易度的に合格を目指しやすいのが宅建士です。不動産取引の専門家として活躍できる宅建士は、通関士同様、取得後に就職や転職に活きる資格として知られていますから、取得しておいて損はないでしょう。
合格率は例年15~18%で推移しており、2023年度は17.2%でした。宅建士試験合格に必要な勉強時間は300~500時間であり、通関士試験と同じ位か、若干少ない勉強時間で合格を目指せます。
もっとも、宅建士試験が「合格を目指しやすい」というのは、あくまで「通関士試験と比較して」の話です。通関士も宅建士も一般的には難しい試験に位置づけられます。
参考:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 令和5年度宅地建物取引士資格試験結果
関連記事:宅建士の合格率についてはこちら
まとめ
通関士は通関業務に携わることができる唯一の国家資格であり、試験の難易度も高い試験と言われています。
通関士試験の出題科目は3科目。それぞれに対策のポイントがありますが、特に重視したいのが通関実務の対策です。通関士試験に合格した方は、実務経験の有無にかかわらず、通関士として登録すればすぐにでも実務ができる資格です。そのため、試験では通関士に必要な知識を身に着けるだけではなく、その知識を実務に活かせる応用力も必要となります。この応用力を試されるのが通関実務の科目です。
通関士試験は独学でも合格できるという意見もありますが、こうした資格の性格上、初学者の方が独学で目指すのはかなり難易度の高い挑戦となります。もちろんそれを承知で挑戦するという方もいらっしゃるかと思いますが、より確実に合格を目指すためには、独学以外の勉強方法がおすすめです。
独学以外の勉強方法でおすすめとなるのが通信講座の受講です。通信講座は独学同様、自宅でマイペースに勉強できる方法です。その上、独学で勉強する以上に効率的に学べるのが通信講座です。
通信講座の中ではフォーサイトの通関士講座です。フォーサイトでは初学者の方から、試験経験者の方まで、多くの方にとって見やすく理解しやすいオリジナルテキストがあり、さらに効率的に学べる勉強カリキュラムがあります。
さらに毎日のスキマ時間を勉強時間に活用できるeラーニング教材も充実しているため、毎日が忙しい社会人の方や専業主婦(主夫)の方でも効率的に勉強を進めることができます。
通関士試験を本気で目指したい方は、フォーサイトの通信講座の受講を考えてみるといいでしょう。気になる方はまず資料請求から始めてみましょう。











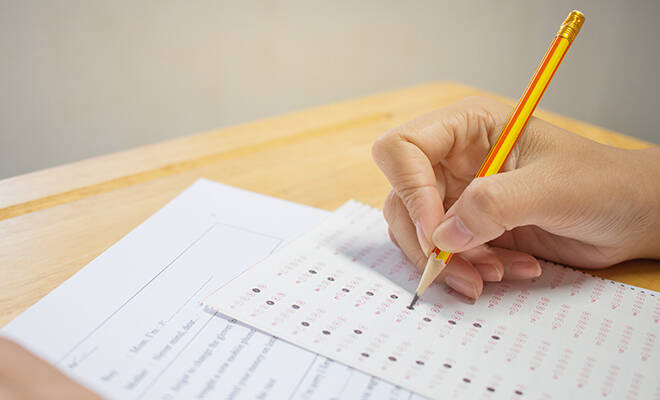
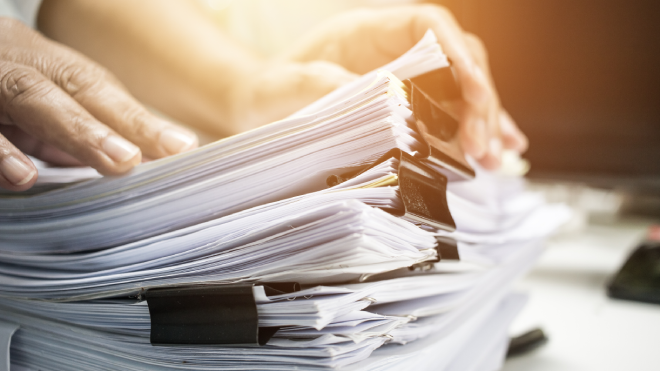

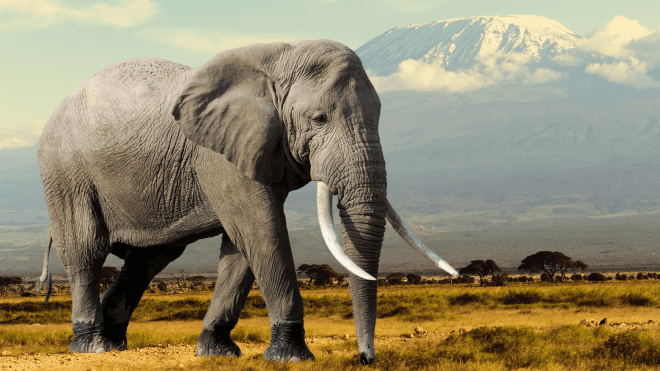


 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


