宅建の合格率はどのくらい?難易度や合格点についても解説
更新日:2023年12月18日

宅地建物取引士(以下:宅建士)の資格は、例年20万人前後の受験者がいる人気資格。
その試験の合格率は15~17%程度であり、過去10年の平均合格率は16.4%となっています。
合格率だけを見れば、そこまで難易度の高い試験には見えず、独学でも、初学者でも合格を目指せる試験に見えるかもしれません。
しかし、宅建士試験は近年難化の傾向も見せており、よりしっかりとした対策をしないと合格できない試験になっています。
そんな宅建士試験の難易度や合格率、さらに合格を目指すための最適な勉強方法などを紹介していきたいと思います。
これから宅建士試験に挑戦する予定の方は、しっかりと予備知識を蓄えてから挑むようにしましょう。
- 近10年の平均合格率は16.4%。およそ7.6人に1人の割合で合格していることになります。
- 近10年の合格基準点は最低が31点、最高が38点。10年平均は34.7点という結果になっています。
- 確実に宅建士試験に合格するには、できれば8割(40点)は得点できる実力を身に付けていないと難しいという難易度になっています。
フォーサイト窪田義幸のご紹介
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします。そのために全力で指導します。
宅建に合格すると人生が変わります。合格まで一緒に頑張りましょう!
宅建士試験の合格率推移
まずは宅建士試験の難易度を合格率から見ていきましょう。参考にする合格率は近10年の合格率。その推移を紹介します。
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年度 | 234,586名 | 186,304名 | 28,470名 | 15.3% | |
| 2014年度 | 238,343名 | 192,029名 | 33,670名 | 17.5% | |
| 2015年度 | 243,199名 | 194,926名 | 30,028名 | 15.4% | |
| 2016年度 | 245,742名 | 198,463名 | 30,589名 | 15.4% | |
| 2017年度 | 258,511名 | 209,354名 | 32,644名 | 15.6% | |
| 2018年度 | 265,444名 | 213,993名 | 33,360名 | 15.6% | |
| 2019年度 | 276,019名 | 220,797名 | 37,481名 | 17.0% | |
| 2020年度 | 10月試験 | 204,163名 | 168,989名 | 29,728名 | 17.6% |
| 12月試験 | 55,121名 | 35,261名 | 4,610名 | 13.1% | |
| 2021年度 | 10月試験 | 256,704名 | 209,749名 | 37,579名 | 17.9% |
| 12月試験 | 39,814名 | 24,965名 | 3,892名 | 15.6% | |
| 2022年度 | 283,856名 | 226,048名 | 38,525名 | 17.0% | |
| 合計 | 2,601,502名 | 2,080,878名 | 340,576名 | 16.4% | |
2020~2021年は2度試験が行われていますが、これは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、試験会場に入る受験者の数に制限を設けた影響であり、通常は年に1度の試験実施となります。
受験者数を見ると例年20万人前後の受験者がおり、これは資格試験の中でもかなり多い方といえるでしょう。
近10年の平均合格率は16.4%。およそ7.6人に1人の割合で合格していることになります。
合格率の数字から見る宅建士試験は、人気が高い資格試験であり、7~8人に1人は合格できる難易度の試験ということになります。
合格率を見るとそこまで難易度は高くない
国家資格の試験、しかも士業の試験ともなると、合格率が10%を切ることも珍しくありません。そう考えると合格率という観点からは、宅建士試験はそこまで難易度の高い試験ではないように見えます。
ただしこれは合格率という1つの指標から見た場合の結果であり、宅建士試験の難易度を正確に表しているものとは言い切れません。
そこで宅建士試験の難易度をほかのデータなどからも検証していきたいと思います。
関連記事:
宅建士の概要や仕事内容ついてはこちら
宅建士試験の合格基準点
試験の難易度を図る指標となるものの1つとして考えられるのが合格基準点です。合格基準点を紹介する前に、まずは宅建士試験の採点の概要から紹介していきましょう。宅建士試験は全50問が出題され、1問1点の50点満点で採点されます。
50点満点の試験であることを踏まえた上で、近10年の宅建士試験の合格基準点を見てみましょう。
| 年度 | 合格基準点 | |
|---|---|---|
| 2013年度 | 33点 | |
| 2014年度 | 32点 | |
| 2015年度 | 31点 | |
| 2016年度 | 35点 | |
| 2017年度 | 35点 | |
| 2018年度 | 37点 | |
| 2019年度 | 35点 | |
| 2020年度 | 10月試験 | 38点 |
| 12月試験 | 36点 | |
| 2021年度 | 10月試験 | 34点 |
| 12月試験 | 34点 | |
| 2022年度 | 36点 | |
| 10年平均 | 34.7点 | |
近10年で最低が31点、最高が38点。10年平均は34.7点という結果になっています。ご覧いただいてわかるように、宅建士試験では合格基準点が年度によって変化します。
宅建士試験ではこの合格基準点が決まっていません。いわゆる「相対評価」が導入されています。
資格試験の合格基準点の定め方には、「相対評価」と「接待評価」があります。「絶対評価」はあらかじめ合格基準点が決められており、その点数を超えた方は全員合格となる試験。つまり事前に決まっているのは合格基準点であり、合格者数・合格率は決まっていません。
一方「相対評価」の試験は事前に合格基準点が決まっておらず、合格者数・合格率がある程度決められている試験。受験者全員の採点が終わり、成績上位〇%、もしくは成績上位〇名が合格する試験です。事前に決まっているのは合格率や合格者数で、それに合わせて合格基準点を定めるという試験。
絶対評価の試験は、試験で〇点取れば合格という明確な目標があるため、比較的対策がしやすい試験です。しかし相対評価の試験は、何点取れば合格できるのかが決まっていません。受験者のレベルが高ければ、合格基準点も高くなりますし、問題レベルが低くても合格基準点は高くなります。
事前の対策で目標を立てにくいのが相対評価の試験であり、宅建士試験もこの点で対策が難しい、難易度の高い試験ということができます。
宅建士試験の難易度を解説
近10年の合格率と合格基準点を紹介してきました。これらの数値などから、宅建士試験の難易度をもう少し詳しく解説していきたいと思います。加えて近年の難易度の傾向も紹介していきましょう。
近年の難易度の傾向
宅建士は2015年に「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が変更されました。名称が変更され、「士業」の1つとなったこともあり、試験の出題難易度は高くなったといわれています。
2015年度試験の合格基準点を見ると、近10年で最低の31点となっています。上記の通り宅建士試験は相対評価の試験ですので、合格率や合格者数は大きく変動していません。その中で合格基準点が下がったということは、それだけ出題難易度が高くなった証拠といえるでしょう。
しかし試験の出題難易度が上がったと分かった以降は、受験生もそれなりの対応をします。そのため2016年以降は徐々に合格基準点も上がり始め、2020年度の10月試験では38点という高い水準になりました。
これまで宅建士試験は35点、7割正解できれば合格ラインと言われていましたが、近年は出題難易度が上がっている中でそれ以上の得点能力が問われているともいえます。
確実に宅建士試験に合格するには、できれば8割(40点)は得点できる実力を身に付けていないと難しいという難易度になっています。
大学入試で例えると?
少々強引ではありますが、宅建士試験の難易度を偏差値で表現してみましょう。もちろん正確な偏差値というわけではなく推定の偏差値となりますが、偏差値で表現することで、大学入試のレベルと比較して考えていきたいと思います。
宅建士試験の推定偏差値は55前後と言われています。偏差値は50で平均ですから、平均よりやや難しいというのが宅建士試験の難易度ということになります。
偏差値55前後を大学入試のレベルに当てはめると、日東駒専と呼ばれる大学のレベルあたりと考えられます。
イメージとしては、独学でも合格できる方はいるものの、簡単に合格できる難易度ではなく、確実に合格を目指すのであれば、予備校や塾に通いしっかり受験対策を行う必要がある難易度です。
宅建士試験も同様で、独学で合格したという方はいるものの、誰でも簡単に独学で合格を目指せる難易度ではなく、多くの方が予備校や通信講座を利用して合格を目指しているというレベルの難易度となっています。
宅建士試験を他の資格試験と難易度を比較
さらに宅建士試験の難易度をわかりやすくするために、ほかの資格試験と難易度を比較していきたいと思います。
比較対象とするのは同じ士業の資格や、不動産関係の仕事に就いている方が受験するケースが多い資格、さらに受験者数が多い資格など、ある程度宅建士と共通点がある資格と比較していきます。行政書士試験と比較
宅建士同様受験資格なしで受験できる士業として、行政書士試験と難易度を比較していきます。
行政書士試験の推定偏差値は62程度と言われています。
行政士試験では民法を始め、幅広い法知識が問われ、試験範囲、出題難易度ともに宅建士試験よりも難易度が高い試験といえます。
試験の難易度としては宅建士試験よりも行政書士試験の方が高いといえるでしょう。
関連記事:
行政書士の難易度の詳細はこちら
FP2級試験と比較
宅建士試験と同様に受験者数が多い、人気の資格としてFP2級の試験と難易度を比較していきたいと思います。
FP2級の推定偏差値は57。FP2級には受験資格があり、この点でやや宅建士試験よりも受験のハードルは高いといえます。
FP2級の出題範囲は資産運用や金融商品、さらに相続や保険、年金など幅広く、不動産取引の範囲に限られている宅建士試験と比較すると、勉強すべき分野は多岐にわたるといえます。
受験資格の存在と受験範囲の広さ、さらに実技試験の存在などを加味すると、宅建士試験よりもFP2級試験の方が若干難易度は高いと考えられます。
関連記事:
FP2級の難易度の詳細はこちら
マンション管理士と比較
不動産関係の仕事をしている方が目指す資格として、マンション管理士と宅建士の難易度を比較していきましょう。
マンション管理士の推定偏差値は62。マンション管理士の試験では、マンションの管理運営にかかわる知識はもちろん、大規模修繕の知識や、建物の構造などの知識も問われます。
宅建士試験と比較すると出題される分野が広く、より多くの知識が求められる試験です。宅建士試験と比較するとマンション管理士試験の方がやや難易度が高い試験ということができるでしょう。
管理業務主任者と比較
マンション管理士とともに取得を目指す方が多いのが管理業務責任者の資格です。こちらも不動産関係の仕事をしている方の受験が多い資格。そんな管理業務主任者の推定偏差値は55と言われています。
管理業務主任者試験は、マンション管理士試験と比較すると若干出題範囲が狭く、宅建士試験と同等の難易度であるといえます。
関連記事:
管理業務主任者試験の合格率の詳細はこちら
社会保険労務士(社労士)と比較
宅建士と並ぶ人気国家資格に、社労士があります。働き方改革や老後2000万円問題等が話題となる中、労務管理・年金の専門家である社労士に注目が集まっているようです。
社労士試験の推定偏差値は、65と言われています。出題科目が異なるため単純比較はできませんが、難易度としては宅建よりも上と考えることができます。
関連記事:
社労士の難易度の詳細はこちら
社労士と宅建士の比較の詳細はこちら
試験科目別の難易度をチェック
ここまで宅建士試験全体の難易度を、合格率やほかの資格との比較で紹介してきました。ここからはより宅建士試験を細分化し、出題される科目別の難易度に注目して紹介していきたいと思います。
まずは宅建士試験の出題科目、及び配点に関してまとめておきましょう。
| 出題科目 | 出題数・配点 |
|---|---|
| 権利関係(民法) | 14問・14点 |
| 法令上の制限 | 8問・8点 |
| 宅建業法 | 20問・20点 |
| 税制・その他 | 8問・8点 |
| 合計 | 50問・50点 |
ご覧の通り、宅建業法、民法といって法律知識を問われる科目の出題数が多くなっています。
ここから科目別の難易度を紹介しますが、難易度と重要度は別の問題です。難易度の高い科目が重要というわけではありませんし、難易度が低いからと言って重要ではないという話ではありませんのでご注意ください。
権利関係(民法)
権利関係の科目は、民法の知識が問われる科目となります。出題される問題の難易度で考えれば、出題される4科目の中で最難関といえるでしょう。
民法の基本的な考え方をしっかりと理解していないと解答できない問題が多く、単純に暗記すれば正解できるというタイプの科目ではありません。
権利関係の出題数が2番目に多い科目です。まずはある程度勉強し、その後はほかの暗記で対応できる科目の暗記に集中。その後にしっかりと時間をかけて対策すべき科目といえるでしょう。
ある程度時間を確保しておかないと対策ができない難易度の科目となっています。
法令上の制限
出題難易度という点では比較的易しいのが法令上の制限の科目。過去の問題を見てもしっかり暗記ができていれば対応できる問題が多く、むしろ取りこぼしたくない科目といえます。
出題数も8問とそこまで多くはありませんので、しっかり重要項目を暗記し、取りこぼさないように準備しましょう。
関連記事:
法令上の制限の詳細はこちら
宅建業法
出題数では最多の20問が出題される宅建業法。宅建士試験においてもっとも重要度の高い科目といえるでしょう。
気になる出題の難易度は低いといえます。そもそもそこまで多くない宅建業法という法律の中から20問が出題されますので、おおよその出題傾向は偏ってきます。しっかり過去問などでその傾向を把握していれば、対策難易度はそこまで高くないでしょう。
難易度が低く出題数が多い宅建業法だけに、ここは満点を取るくらいの気持ちで取り組む科目。宅建業法の問題の難易度が高いと感じているようでは、宅建士試験の合格は難しくなります。
トータルで40点を目指す以上、宅建業法の20点は取りこぼせないところ。満点を目指して準備をしましょう。税制・その他
税制・その他の科目に関しては、科目の中で出題難易度に大きな差がつきやすい科目といえます。簡単な問題もありますが、難問に属する出題があるのもこの科目の特徴。
特に注意したいのが税制の勉強です。税制の勉強に関しては、まともに勉強をしようとするとかなり奥が深く、範囲も広くなってしまいます。宅建士試験で出題される税制の問題はそこまで難易度の高い問題ではありませんので、ここで多くの勉強時間を割いてしまわないように注意しましょう。
効果的な対策はやはり過去問対策。どのような問題が出題されるのか、どのような知識が問われるのかをしっかり把握し、効率的に勉強していきましょう。
宅建士試験は独学でも可能?
宅建試験は、独学でも十分に合格を狙える試験です。テキストを中心に覚えるべき法律の知識を正しく学び、十分に問題演習に取り組むことで、合格基準点に近づくことができるでしょう。
ただし、法律的な条文解釈や宅建試験特有の専門用語の理解がネックとなる可能性は極めて高く、法律初学者にとって独学は容易ではありません。また、幅広い試験範囲を出題傾向に沿って学習する必要がありますから、資格学習に不慣れな方の独学も要注意です。
関連記事:
宅建士試験の勉強時間の詳細はこちら
フォーサイトの宅建士講座の合格率は75%
ここまで宅建士試験の難易度に関して解説をしてきました。合格率から見るとそこまで難易度は高くないものの、相対評価の試験であること、科目ごとにも難易度に差があることを考えると、独学で目指すのは簡単ではない試験ということになります。
また、宅建士試験は年に1度の実施。1度受験に失敗してしまうと、次の試験まで1年間勉強を続ける必要があり、これは大きなタイムロスとなります。
宅建士試験を目指す方は、できれば1度の挑戦で確実に合格を目指したいところ。そこでおすすめしたいのが通信講座の利用、特にフォーサイトの通信講座の利用です。
2022年度宅建士試験における、フォーサイト受講生の合格率はなんと75%。全国平均が17%ですから、圧倒的な合格実績ということになります。この75%の受講者の方の中には初学者の方も多く含まれており、非常に信頼できる講座ということができます。
ではなぜフォーサイトの受講生がここまで高い合格率を残せるのか。そのポイントを紹介していきましょう。
受講料・お申込みについてフォーサイトの宅建士講座おすすめポイント
宅建士試験の勉強をすると考えた場合、勉強方法は3つ。独学か、通信講座を利用するか、予備校に通学するかです。
フォーサイトの紹介をする前に、なぜ予備校ではなく通信講座をおすすめするのかを簡単に説明しておきましょう。
宅建士試験の難易度は、それなりの難易度ではあるものの、独学でも合格できる方はいるレベルです。独学で学ぼうとしている方の背中を少し押すことができれば、十分合格が目指せる資格。そのためには予備校よりも通信講座がおすすめとなります。
予備校は通学をしなければいけませんが、通信講座は自宅で勉強しますので、まず通学時間が必要ありませんし、毎週決まった曜日・時間に勉強する必要もありません。マイペースで時間を無駄にせず学べる勉強方法になります。
つまり、宅建士試験対策には予備校よりも通信講座がおすすめということ。
では、そんな通信講座の中でもおすすめとなる、フォーサイトの講座のポイントに関して紹介しましょう。
お得な3つのバリューセット
フォーサイトの宅建士講座には3つのバリューセットがあります。まずはそれぞれのセット内容を紹介しておきましょう。
バリューセット1 セット内容

バリューセット2 セット内容

バリューセット3 セット内容

バリューセット1はすでに宅建士試験の勉強をしている方や、宅建業務に携わっている方におすすめの基本的なセットとなります。
バリューセット2は宅建士試験に初挑戦となる方におすすめ。初挑戦の方は試験が近づくと勉強が足りているか不安になることも多いかと思います。そんな方向けに直前対策講座が提供されるセットとなっています。
バリューセット3は、バリューセット2の内容に科目別答練講座が加わった、宅建士講座のフルセットとなるセットになります。宅建士試験に初挑戦で、かつ宅建士試験に関する分野の勉強が初めてである初学者の方におすすめのセットです。
このようにフォーサイトでは、受験者のレベルの合わせて選べる3つのバリューセットがあり、より多くの合格者を輩出することに成功しています。
ManBunで勉強効率大幅アップ
フォーサイトをおすすめするもうひとつのポイントがManaBunの存在です。フォーサイトではeラーニング教材にも力を入れており、このeラーニング教材をManaBunとして提供しています。
上で紹介したすべてのバリューセットにこのManaBunは含まれています。
具体的にManaBunに含まれているのは、デジタルテキスト、講義動画、講義動画の音声データ、演習問題などなど。
eラーニング教材は毎日のスキマ時間に活用することを中心に構成されていますので、講義動画は15分程度の短時間動画になっていますし、スマホの小さな画面で見ても見やすい構成になっています。
ManaBunを活用し、毎日のスキマ時間を勉強時間に変えることで、より短期間で宅建士合格を目指せるでしょう。
1分で完了!

まとめ
宅建士試験では相対評価が採用されており、合格基準点は33~38点あたり。確実に合格するには8割程度は正答できる実力が必要です。
合格率はおおよそ15~17%の範囲で変動していますが、近年難易度が難化の傾向を見せており、よりしっかりとした実力を身に着けておきたい試験となっています。
宅建士試験は4科目が出題されますが、難易度が高いのは民法に関する正確な知識が求められる権利関係の科目。比較的難易度が低いのが、出題数がもっとも多い宅建業法に科目です。
宅建業法の科目は満点を目指し、出題数の科目を取りこぼさないようにしつつ権利関係で得点を重ねるというのが合格に近づくイメージ。
そのためには効率的な勉強が必要となり、それにおすすめとなるのが通信講座フォーサイトの宅建士講座です。
豊富なバリューセットや充実のeラーニング教材で、より短期間でより確実に合格を目指しましょう。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
●フォーサイト講師ブログ



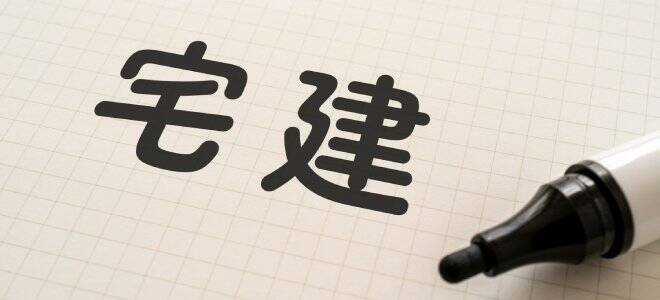










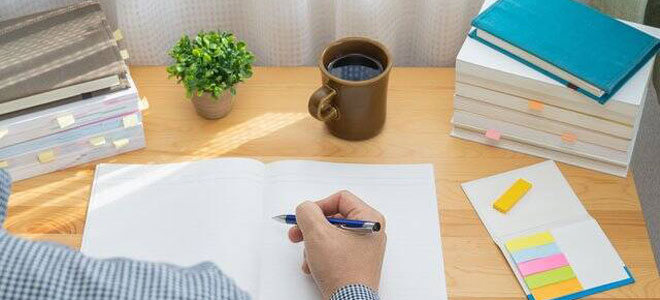

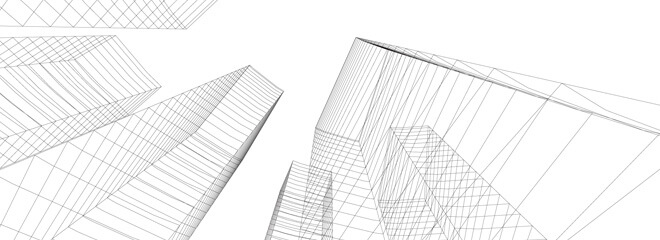





 ログイン
ログイン




 0120-966-883
0120-966-883


