令和6年(2024年)の宅建試験日はいつ?申込みから合格までのスケジュール、注意事項まで紹介
更新日:2024年5月20日
宅建(宅地建物取引士)試験を受験する予定の方にとって最も大切な情報は「試験日」です。いつから勉強を始めるか、もう始めているなら学習のペースが間に合うのかなど、受験を決めている方にとっては気になる情報でもあります。
この記事では、令和6年度(2024年度)の宅建試験日や申込みから合格までのスケジュール、受験資格、試験形式・科目と問題・配点、合格率・合格基準、注意事項、合格するためのコツ・ポイント、通信講座がベストである理由、高い合格率を誇る通信講座「フォーサイト」の特徴について解説します。
宅建試験は、コツ・ポイントを押さえた学び方を実践すれば、多くの人が合格を目指せる資格です。これを読んで、合格への自信につなげてください。
- 令和6年度(2024年度)宅建試験の試験日は、令和6年10月20日(日)の予定です。
- 受験の詳細が確定する6月から申込みに向けて動き出しましょう。
- 宅建試験の合格発表は、試験日の26日(土日祝日を除く)後に行われます。令和6年度(2024年度)は、11月下旬の予定です。
- 宅建試験は、この数年受験者数20万人を超える人気の国家資格です。
- 過去5年の合格率は15〜17%の間で推移しています。
- 宅建試験の合格までの平均受験回数は2回と言われています。
- いきなりテキストを開いて勉強を始めるのではなく、まずは宅建試験の全体の内容を知り、どういった勉強が必要なのかを理解しましょう。
- 宅建試験に必要な勉強時間は、独学の場合300~500時間程度と言われています。
フォーサイト窪田義幸のご紹介
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします。そのために全力で指導します。
宅建に合格すると人生が変わります。合格まで一緒に頑張りましょう!
令和6年度(2024年度)宅建試験の試験日

令和6年度(2024年度)宅建試験の試験日は、令和6年10月20日(日)の予定です。正式には、令和6年6月7日(予定)に行われる官報公告により確定します。
宅建試験の試験は、過去10年に次の日程で実施されました。
| 年度 | 試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 令和6年10月20日(日)予定 | 令和6年11月26日(火)予定 |
| 令和5年度(2023年度) | 令和5年10月15日(日) | 令和5年11月21日(火) |
| 令和4年度(2022年度) | 令和4年10月16日(日) | 令和4年11月22日(火) |
| 令和3年度(2021年度)① | 令和3年10月17日(日) | 令和3年12月1日(水) |
| 令和3年度(2021年度)② | 令和3年12月19日(日) | 令和4年2月9日(水) |
| 令和2年度(2020年度)① | 令和2年10月18日(日) | 令和2年12月2日(水) |
| 令和2年度(2020年度)② | 令和2年12月27日(日) | 令和3年2月17日(水) |
| 令和元年度(2019年度) | 令和元年10月20日(日) | 令和元年12月4日(水) |
| 平成30年度(2018年度) | 平成30年10月21日(日) | 平成30年12月5日(水) |
| 平成29年度(2017年度) | 平成29年10月15日(日) | 令和29年11月29日(水) |
| 平成28年度(2016年度) | 平成28年10月16日(日) | 平成28年11月30日(水) |
| 平成27年度(2015年度) | 平成27年10月18日(日) | 平成27年12月2日(水) |
宅建試験は、毎年1回、10月の第3日曜日、午後1時~午後3時に実施されます。過去には、新型コロナウイルス感染症の影響により試験会場が不足し、年2回実施されることもありました。現在は元に戻り、年に1回実施されています。
宅建士試験の試験公告~合格発表までのスケジュール
宅建試験の試験日の次に頭に入れておきたいのが、合格発表までのスケジュールです。受験の詳細が確定する6月から申込みに向けて動き出しましょう。
| 6月第1金曜日(原則) | 1:試験公告 |
|---|---|
| 7月上旬から 【インターネット】下旬まで 【郵送】中旬まで |
2:申込み |
| 3:受験手数料の納付 | |
| 10月下旬 | 4:受験票の交付 |
| 10月の第3日曜日 | 5:試験当日 |
| 11月下旬 | 6:合格発表・合格後の手続き |
令和5年度までは、はがきにより試験会場が通知されていました。しかし令和6年度からは試験会場のみの通知は行われず、受験票で確認できる方法に変わります。
それでは、宅建試験のスケジュール1〜6までを確認していきましょう。
1:試験公告
はじめに確認したいのが、試験公告です。試験公告とは、その年に実施される宅建試験の情報が官報に発表されることを言います。原則6月第1金曜日に発行され(「インターネット官報 」でも閲覧できます)、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページにも同時に掲載されます。
試験公告を見て、試験日や申込み期間・方法、合格発表までのスケジュールなどを確認しましょう。
2:申込み
受験の申込みは、7月上旬に始まります。申込み方法はインターネットと郵送の2種類あり、どちらかを選ぶことができます。
インターネットによる申込み
インターネットによる申込みは、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページのインターネット申込み入力画面から行います。その後の流れは次の通りです。
| ① | 試験会場選択 |
|---|---|
| ② | 決済方法選択 (クレジットカード決済/コンビニ決済のいずれか) |
| ③ | 機構からデータ到達の確認メールが届いて申込み完了 |
| ④ | コンビニ決済を選択した場合はコンビニでの支払い |
申込みに必要なものは、顔写真の画像ファイル、クレジットカード(コンビニ支払いを選択した場合は不要)です。
郵送による申込み
郵送による申込みは、次の手順で行います。
| ① | 受験申込書の入手 |
|---|---|
| ② | 受験手数料をゆうちょ銀行の窓口、もしくはATMで支払う |
| ③ | 受験申込書を記入し、日附印のある振替払込受付証明書、もしくはご利用明細票と顔写真を添付する |
| ④ | 受験申込書一式を簡易書留郵便で送る |
①受験申込書は、書店などで無料配布されています。配布場所は、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページに一覧が掲載されます。また、郵送による取り寄せも可能です。郵送を希望する場合は、同機構ホームページの説明に従い、手続きを行いましょう。
申込みに必要なものは、受験申込書、顔写真、日附印のある振替払込受付証明書、もしくはご利用明細票です。
郵送による申込み期間は、インターネットよりも短いので、受験申込書を早めに入手して写真の準備や支払いを済ませておくと良いでしょう。
3:受験手数料の納付
受験手数料は、申込み時や申込み後(インターネット申込みの場合)に納付します。令和6年度の受験手数料は、8,200円の予定です。納付の方法は、前述の通り申込み方法により異なります。
- インターネットの場合
申込み時にクレジットカード決済をする、もしくは申込み後にコンビニで支払います。支払い方法はどちらかを選ぶことができます。 - 郵送の場合
受験申込み前に、ゆうちょ銀行窓口、もしくはATMで支払います。その際、日附印のある振替払込受付証明書(窓口の場合)もしくはご利用明細票(ATMの場合)を受け取り、受験申込書に添付します。
4:受験票の交付
受験申込みを終えたら、10月上旬に受験票が交付されます。受験票が届いたら、受験番号、氏名などの基本的な情報や、試験会場を確認しましょう。
※試験会場の通知は、これまで別途はがきにて行われていましたが、令和6年度より受験票に通知されることになりました。受験票の到着より先に試験会場を知りたい場合は、次の方法があります。
- インターネット申込の方
ウェブサイト「宅建試験マイページ」で確認 - 郵送申込の方
専用のお問い合わせダイヤルで確認
いずれも8月下旬以降に利用できる予定です。詳しくは試験公告を確認してください。
5:試験日当日
令和6年度(2024年度)宅建試験の試験日は令和6年10月20日(日)、試験時間は13時~15時までの2時間に予定されています。ただし、登録講習修了者*は、13時10分〜15時までの1時間50分です。
試験の前に、受験に際しての注意事項の説明があるので、12時30分(登録講習修了者*は12時40分)までに着席している必要があります。また、試験中の途中退出はできないので、トイレは済ませておきましょう。
*登録講習修了者については、後ほど詳しく説明します。
6:合格発表・合格後の手続き
宅建試験の合格発表は、試験日の26日(土日祝日を除く)後に行われます。令和6年度(2024年度)は、11月下旬の予定です。
合格発表は、一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページにて行われます。合格者の受験番号のほか、合否判定基準、試験問題の正解番号が掲載されるので、併せて確認しましょう。なお、アクセスできるのは、翌年7月末までです。
また、合格者には合格証書等が簡易書留郵便にて届きます。不合格者には結果の通知はされません。
<合格後の手続き>
宅建士(宅地建物取引士)として業務を行うためには、受験した試験地の都道府県で登録をする必要があります。合格証書と一緒に届いた「宅地建物取引士資格登録等の手続について」をよく読み、必要があれば手続きを進めましょう。
試験に関する問い合わせ先は?
試験に関して分からないことや確認したいことがあった際には、宅建試験を実施している一般財団法人 不動産適正取引推進機構や都道府県の協力機関に連絡します。
■試験に関する問い合わせ先
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 試験部(宅建試験)TEL 03(3435)8181
受付時間9:30~17:30、土日祝・年末年始をのぞく - 都道府県の協力機関 一覧はこちらから(同機構のホームページにジャンプ)
問い合わせる前に、同機構のホームページ内にある「宅建試験のFAQ」を参照し、当てはまる質問があれば参考にすると良いでしょう。
宅建試験(宅地建物取引士資格試験)とは?

ここで、そもそも宅建とはどのような資格なのかを簡単にまとめてみます。
宅建試験は、この数年受験者数20万人を超える人気の国家資格です。合格すれば不動産取引の専門家として企業で活躍したり開業したりできるほか、自宅の購入や実家の相続など、人生の大きなイベントに知識が活かせるなどのメリットがあります。そのため性別に関係なく、多くの人が宅建試験に挑戦しています。
また、宅建試験は、宅地建物取引業法に基づいて都道府県知事が実施する試験です。一般財団法人 不動産適正取引推進機構と各都道府県の協力機関が試験の運営を行っています。
宅建試験の受験資格
宅建試験の受験資格は、「日本国内に居住している人」のみです。年齢や学歴などに関係なく受験できます。
ただし、合格後に資格登録をする場合は、一定の条件を満たしている必要があります。条件は宅地建物取引業法18条に定められている通りです。これから宅建の資格を使って仕事をしようと思ったら、試験の範囲でもあるので一度確認しておくと良いでしょう。
宅建試験の試験形式・科目と問題数・配点
次に、宅建試験の試験形式・科目と問題数・配点を確認しましょう。宅建試験は5つの科目から構成されています。試験形式は、全て4肢択一のマークシート方式です。問題数は全部で50問、配点は各1点です。問題数の内訳は次の通りです。
| 科目 | 問題数 |
|---|---|
| 権利関係 | 14 |
| 法令上の制限 | 8 |
| 税・その他の関連知識 | 3 |
| 宅建業法 | 20 |
| 税・その他の関連知識(免除科目) | 5 |
| 合計 | 50 |
ここで、登録講習修了者について解説しておきましょう。
■登録講習修了者とは…
登録講習修了者とは、「所定の講習を受けた後に、この修了試験に合格した人」を言います。所定の講習を受けるには、次の受講条件を満たす必要があります。
-受講条件-
- 宅地建物取引業に従事していること
- 受講申込時と登録講習受講期間中に有効な「宅建業従業者証明書」を所持していること
です。
登録講習修了者は、試験科目5問が免除され(「免除科目」と呼ばれています)、試験時間も10分短くなります。たった5問とはいえ、問題を解かずに5点を獲得できるので、宅建業に携わる方はぜひ受けておきたい講習です。なお、受講料は有料です。
宅建士試験の難易度・合格率・合格基準
続いて、宅建試験の難易度・合格率・合格基準です。宅建試験の合格基準は、その年により異なります。過去5年を振り返ってみると、50点満点中34~38点が合格基準点になっています。つまり、およそ7割前後の得点が必要です。
さらに、過去5年の合格率は15〜17%の間で推移しています。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和5(2023) | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% | |
| 令和4(2022) | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% | |
| 令和3(2021) | 10月試験 | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% |
| 12月試験 | 24,965人 | 3,892人 | 15.6% | |
| 令和2(2020) | 10月試験 | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% |
| 12月試験 | 35,261人 | 4,610人 | 13.1% | |
| 令和元(2019) | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% | |
合格率は決して良くはありませんが、他の国家試験に比べると難易度はそれほど高くないと言われています。宅建試験は、多くの人がさまざまな事情により受ける試験です。そのため、試験の難易度が合格率に反映しているというよりも、しっかり勉強をすれば合格も可能であると捉えた方がより現実に近いかもしれません。
参考までに、効率的に勉強を進められる通信講座「フォーサイト」を利用している人の宅建試験の合格率は76.1%です(2023年)。
| 全国平均 | 17.2% |
|---|---|
| フォーサイト受講生 | 76.1% |
通信講座「フォーサイト」では、良質の教材を使い、経験豊富な講師から学ぶことができます。勉強する意欲を高めて地道に取り組めば、それほど難関な試験ではないと言えるでしょう。
試験当日の注意事項
宅建の試験の概要に触れたところで、試験当日の注意事項に移ります。まず、前述の通り、試験中の途中退出はできません。試験時間は2時間(登録講習修了者は1時間50分)です。決して短くはないので、トイレを済ませておきましょう。試験室内は禁煙で、飲食も原則として禁止されています。
また、試験会場へは公共交通手段を利用します。受験票に記載された方法に従いましょう。試験会場構内の駐車は禁止されています。車で来場することのないように注意してください。自家用車での送迎も、会場周辺の交通渋滞や遅刻の原因となるのでやめましょう。
もう一つ注意したい大事な点は、持ち込めるもの持ち込めないものを知っておくことです。
試験に持ち込めるものと持ち込めないもの
試験のためにせっかく持って行ったものが当日使えない、ということにならないように、事前に持ち込めるものと持ち込めないものを把握しておきましょう。
まずは、当日持参するものをチェックしていきます。
■試験当日に持参するもの
- 受験票
- BかHBの黒鉛筆またはシャープペンシル(左記以外は解答しても無効になります)
- プラスチック製の消しゴム
- 鉛筆削り(任意)
- 腕時計(試験会場に時計がない場合があります)
上記は、任意のもの以外は忘れずに持参しましょう。次に、試験に持ち込めるものと持ち込めないものを確認します。
| 持ち込めるもの | 持ち込めないもの |
|---|---|
| 試験当日に持参するもののうち、腕時計に関しては時計機能のみもの | スマートフォン・携帯電話 スマートウォッチ タブレット端末 イヤホン 置時計ほか |
試験に持ち込めないものは、試験中は封筒に入れる、あるいは卓上には置かないといった対応が必要です。所持していることが分かった場合は、不正行為とみなされるので注意しましょう。
その他、持っていると良いのが、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)です。受験票の顔写真で本人確認が難しい場合、身分証明書の提示を求められることがあります。
宅建試験が実施されるのは年に何回?
宅建試験は、毎年1回、10月の第3日曜日、午後1時~午後3時に実施されます。令和6年度(2024年度)の宅建試験は、令和6年10月20日(日)の予定です。
年に1回なので、チャンスは多くありません。資格を取得したいタイミングと学習計画をしっかり立てて、試験の準備を行いましょう。
宅建の平均受験回数
宅建試験の合格までの平均受験回数は2回と言われています。最初の受験で不合格になったとしても、多くの受験生が2回目で合格できることが分かります。つまり、諦めずに勉強を続けることが大切です。
とはいえ、1回で合格するに越したことはありません。そのためには、合格するためのコツ・ポイントをつかむことも重要です。次に、宅建試験のためにしておきたい対策をご紹介します。
宅建士試験に合格するためのコツ・ポイントは?
宅建士試験に合格するためのコツ・ポイントは主に2つあります。いずれも、勉強を始める前、あるいは初期の段階で取り組みたい内容です。
そのため、いきなりテキストを開いて勉強を始めるのではなく、まずは宅建試験の全体の内容を知り、どういった勉強が必要なのかを理解しましょう。
出題傾向・形式を把握する
宅建試験に合格するための1つ目のコツ・ポイントは、出題傾向・形式を把握することです。
宅建試験の試験範囲は、権利関係や法令上の制限、税・その他の関連知識と範囲が広いのが特徴です。これらを全て同じように力を入れて取り組むのは、効率的とは言えません。宅建試験は1問1点なので、出題数の多い宅建業法が得点源になります。これらを重点的に学ぶことが、合格への近道になるでしょう。
必要な勉強時間を把握する
もう1つのコツ・ポイントは、必要な勉強時間を把握することです。
宅建試験に必要な勉強時間は、独学の場合300~500時間程度と言われています。この時間を試験日までの残り時間に割り振り、勉強のスケジュールを立てていきます。
または、平日にどれくらい勉強できるのか、休日は、連休は、と確保できる勉強時間から受験が可能な年の見通しを立てるのも1つの方法です。こうして勉強の計画を立てることで、目標に向かって確実に進むことができます。
宅建試験に合格するための勉強時間については、こちらの記事でもご紹介しています。併せてご覧ください。
関連記事:
宅建士試験に合格するための勉強時間についてはこちら
宅建士最短合格なら通信講座がベスト
宅建試験に最短で合格したいなら、独学でも予備校でもなく通信講座がベストです。その理由は、次のような魅力があるからです。
➀忙しくても自分のペースで勉強できる
通信講座は、いつでもどこでも学習ができるのがメリットです。仕事や家事、育児などで「勉強する時間がない」というときでも、通勤・通学の時間や家事の合間などを利用して学習を進められます。
②トータルでコスパが高い
通信講座は予備校の授業料よりも割安であるほか、通学のための交通費もかかりません。そして何より、通信講座で効率的に学んで短期間で合格できれば、時間と労力が最小限で済むため高コスパです。
③学習のサポートが受けられる
分からないことが出てきたとき、独学では解消できないこともあります。一方、通信講座は、受講者の質問に回答してくれるサポート体制が整っています。問題を解決するまでに多くの時間を費やすことなく、スムーズに学習を進められます。
フォーサイトの宅建士通信講座の特徴
通信講座がベストといっても、さまざまな種類の中からどれを選べば良いのか迷うこともあるでしょう。そこでおすすめしたいのが、「フォーサイトの宅建士通信講座」です。フォーサイトの魅力は、76.1%(2023年)の高い合格率だけではありません。その他の魅力も3つご紹介します。
➀3か月のスピード合格!高い実績がある
合格するための平均受験回数は2回と言われる中、わずか3か月のスピード合格を果たしたフォーサイトの受講生も多くいます。「早く資格を取りたい」「勉強を長期間続けたくない」という方も、フォーサイトなら短期間で合格を目指すことが可能です。
②不合格でも安心「受講料全額返金保証制度」
フォーサイトは、万が一不合格でも、受講料を全額返金してくれる制度があるので安心です。「不合格になったら、受講料が無駄になってしまうのではないか」という心配があるかもしれません。大丈夫です、無駄にはなりません。
③満足度90%以上!こだわりのフルカラーテキスト
フォーサイトのフルカラーテキストは、試験に必要な情報量があることと、重要な箇所はカラーで分かりやすいことで、多くの受講生が絶賛しています。良質なテキストを選ぶことは、合格への近道です。
通信講座を体感するなら資料請求しよう!
通信講座のことをもっと知りたいと思ったら、まずは無料の資料請求をしましょう。通信講座を受けるのは初めての方や、一度挫折した経験のある方などは、勉強が続けられるのか不安に思うかもしれません。そうした方こそ、資料を請求して不安を解消しませんか。
資料請求をすると、次のような体験が待っています。
①実際に使われるテキストを確認できます
サンプルテキストや問題集が届くので、分かりやすいか、勉強しやすいかをチェックできます。また「受講生の満足度90%以上のテキストが見てみたい」という方も歓迎です。実際の教材に触れることで、学習のイメージをつかむことができます。
②eラーニングの使いやすさを見極められる
スマホがあればどこでも学習できるeラーニングを無料で体験できます。通勤・通学、家事の合間などにぜひ試してみてください。テキストを開く気力がないときも、スマホで気軽に勉強できるのが良いところです。自分の生活の中でどう活用できるのか、実際に利用して確認できます。
③非売品のオリジナル書籍をプレゼント
高い合格実績はどうやって生まれるのか、フォーサイト合格メソッドが詰まったオリジナル書籍をプレゼントします。書籍は、どこを探しても手に入らない非売品です。まずは何から始めたら良いのか分からない人にもおすすめ。これを読んで、宅建合格への道をスタートしてください。
1分で完了!
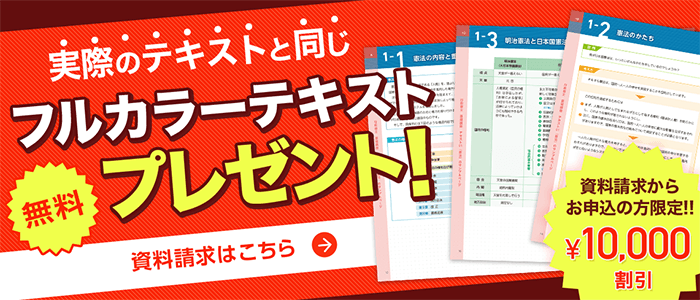
効率良く&短期での合格を目指すなら通信講座
宅建試験の合格率は高くありませんが、決して手の届かない資格ではありません。どう学ぶか、どう勉強時間を確保するかによって、短期の合格も可能です。そのためには、多数の合格者を出している通信講座フォーサイトの合格メソッドを活用してください。効率よく合格に近づくことができます。まずは、無料の資料請求をお待ちしています。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
●フォーサイト講師ブログ



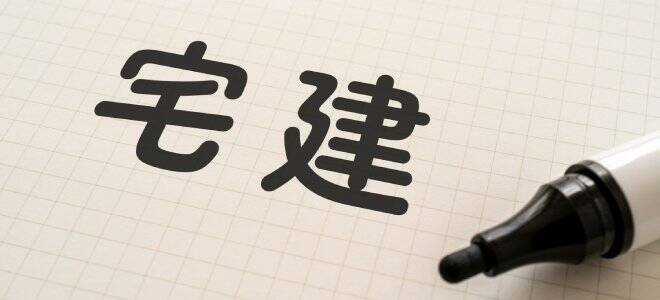










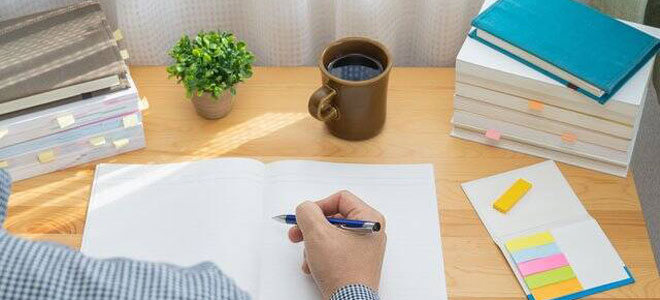

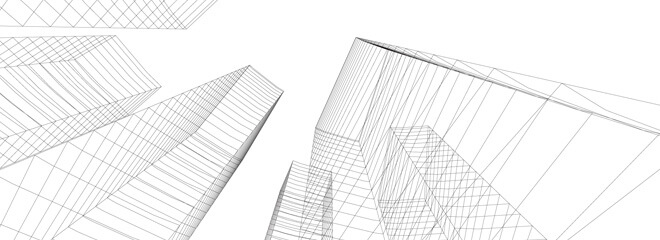





 ログイン
ログイン




 0120-966-883
0120-966-883


