宅建士試験に合格するための勉強時間は?独学でも合格できる?効率的な勉強方法も紹介
更新日:2023年12月20日
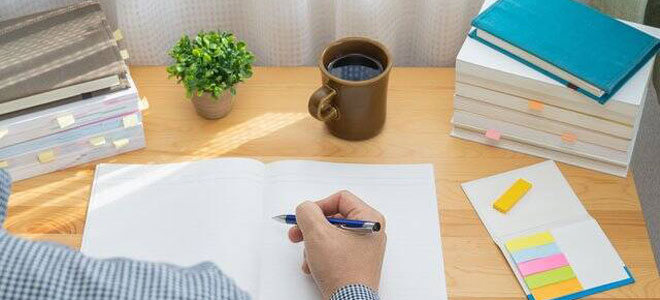
毎年20万人前後の受験者がいる人気資格「宅地建物取引士(以下:宅建士)」。
宅建士試験の例年の合格率は15%前後であり、簡単に合格できる試験ではありません。この宅建士試験は、独学でも合格できるのか?合格するために必要なポイントは?独学で目指す場合の効率的な勉強方法は?など、独学で宅建士試験に挑戦する時に持っておきたい知識をまとめて紹介していきます。
宅建士試験の難易度やどんな知識を問われるかなどをしっかりと把握して、できるだけ短期間で合格できるよう、しっかりと準備しましょう。
- これまでに法律を学習したことのない受験生が、初めて宅建士試験に挑戦するにあたって必要な勉強時間は、一般的に500時間前後と言われています。
- 宅建士試験に独学で合格できるかどうかでいえば、独学でも十分合格を目指せます。
- テキスト選びのポイントは、自分のレベルに合ったものを選ぶこと、最新のものを選ぶこと、そして参考書や問題集は同じ出版社の同じシリーズでそろえることです。
フォーサイト窪田義幸のご紹介
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします。そのために全力で指導します。
宅建に合格すると人生が変わります。合格まで一緒に頑張りましょう!
宅建試験に合格するために必要な勉強時間
宅建士試験合格のために必要な勉強時間は、受験生によって差があります。具体的には、試験科目について、あらかじめどの程度知識があるかによって異なります。ここでは、受験生の学習歴に応じた勉強時間数を考えてみましょう。
初心者の場合
これまでに法律を学習したことのない受験生が、初めて宅建士試験に挑戦するにあたって必要な勉強時間は、一般的に500時間前後と言われています。
宅建士受験生の場合、「10月第3日曜日に実施される宅建士試験に向けて、4月から試験対策を開始する」というスケジュールが王道ですが、受験生の大半が、十分な学習量をこなせずに試験本番を迎えるようです。
というのも、宅建士合格に必要な500時間を確保するためには、4月から毎日コンスタントに2時間30分、学習に取り組まなければならない計算になるためです。社会人であれば働きながら、学生であれば学校に通いながら、毎日必要な時間を確保して勉強を続けることは、容易なことではありません。
既に知識がある場合
一方で、すでに宅建士試験科目を学んだことのある方であれば、宅建士合格までに必要な勉強時間はぐんと短縮されるます。例えば、宅建士の試験科目に「権利関係」がありますが、これに含まれる「民法」は、公務員や行政書士等のあらゆる試験に出題される法律です。
また、大学で法律科目を履修された方にとっても、民法は主要法令として比較的なじみ深い法律ではないでしょうか。そのため、宅建士試験対策に先立ち、民法を学習したことのある方であれば、「権利関係」に要する勉強時間が少なくて済むということになります。
もっとも、既修者に関わる勉強時間数の想定は各人の知識量に応じて異なりますが、概ね200時間から300時間程と考えておくのが適切です。
宅建試験の合格率と難易度
宅建士試験の合格率は、例年15~17%程で推移しています。100人の受験生の中から、5~7人程度が合格者となる計算です。この割合を高いと捉えるか、それとも低いと考えるかは人それぞれですが、合格は決して容易ではありません。
また、難易度に関して言えば、2015年度本試験以降、出題の難化が顕著となっている点に注意が必要です。こうした背景には、「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へと名称変更(士業化)があります。
関連記事:
宅建の合格率の詳細はこちら
宅建試験は独学でも合格できるのか?
宅建士試験に独学で合格できるかどうかでいえば、独学でも十分合格を目指せます。
とはいえ、誰でも簡単に合格できるというわけではありません。宅建士には不動産取引の現場で、買主(または借主)に対する重要事項説明を行うという独占業務があります。この重要事項説明は単純に説明するだけではなく、説明した内容を買主(借主)にしっかりと理解してもらう必要があります。
そのためには、不動産に関する正しい知識や法令に関する知識が必要になります。こうした知識があるかどうかを試されるのが宅建士試験となります。
試験範囲は広く、また専門用語も多いため、しっかりと勉強をしていく必要があります。これを独学でこなせるという方は、独学でも合格を目指せるでしょう。
具体的には、実際にほかの資格試験に独学で合格したことがあり、独学で学ぶノウハウを持っている方や、現状不動産業界で働いており、ある程度の基礎知識を持っている方、大学等で法律に関する勉強をしており、法律に関するした知識のある方などであれば独学でも十分に目指せるでしょう。
こうした知識のない、いわゆる初学者の方が独学で宅建士を目指すのは、かなりハードルの高い勉強方法になります。しっかりと勉強期間を確保して挑むようにしましょう。
宅建試験に独学で挑戦する3つのメリット
特に初学者の方にとって、独学で宅建士試験を目指すのはなかなか難しいことです。それでも独学で挑戦するメリットがあるのかどうか。
独学で目指す際に考えられる3つのメリットを紹介していきましょう。
マイペースで勉強できる
独学の場合、どの程度の勉強期間を確保するのか、どのくらいのペースで勉強するのかなどもすべて自分で決めることになります。つまり、自分のペースで勉強を進められます。
宅建士試験を目指す勉強方法は独学以外に、宅建士試験の対策講座を開講している予備校に通学する、通信講座を利用するという方法が考えられます。
特に予備校に関しては、予備校の作成したカリキュラム通りに勉強を進めることになります。とはいえ、社会人の方にとってこれは簡単ではありません。
社会人である以上、ある程度残業時間もありますし、断りづらい仕事上の付き合いや接待などもあるでしょう。予備校の授業が行われる日に、必ず予備校に通える保証はありません。
こうした仕事の都合やプライベートの事情なども考慮し、マイペースで学べられるのは独学の大きなメリットとなります。
通学時間が無駄にならない
社会人の方にとって、資格試験のための勉強時間を確保するのは簡単ではありません。毎日仕事をしながら確保できる勉強時間は2時間程度でしょう。
予備校に通学するということは、予備校に通う通学時間が必要ということ。片道30分だとしても、往復で1時間必要になります。通学時間は単なる移動時間です。貴重な勉強時間の内、これだけの時間を単なる移動時間で消費するのはデメリットといえるでしょう。
独学であれば、自宅で勉強できますので通学時間は不要。それだけ多くの勉強時間を確保できるというメリットが考えられます。
費用を抑えられる
予備校や通信講座を利用するには、当然ですが受講料が必要になります。独学では、この受講料が不要となります。
独学で学ぶために必要な費用は、参考書や問題集を購入する代金、そして受験するのであれば模試の受験料といったところ。まったく無料で学べるわけではありませんが、受講料を支払うことに比べれば出費は大幅に抑えられます。
経済的なメリットが大きい。これも独学のメリットとなります。
独学に向いている方の特徴
独学で宅建士試験合格を目指すには、ある程度のメリットがあります。では、そのメリットを享受できる、独学に向いている方はどのような方でしょう。
独学で学ぶことは、毎日のように自宅で、一人で勉強を続けることになります。上記の通り、独学で目指すのは、ある程度の勉強期間が必要であり、この期間勉強を続ける必要があることと同じです。
こうした地道な作業を、毎日コツコツと続けられる、根気強い方は独学に向いていると考えられます。
また、独学で勉強する場合に注意すべきは勉強効率の確保。勉強の効率が下がれば当然勉強時間も長くなり、勉強に対するモチベーションが下がってしまう可能性があります。
勉強効率を確保するには、あまり根を詰めすぎないことも重要。勉強した範囲を完璧にマスターしようとするなど、完璧主義の方はあまり独学に向いているとは言えません。
常にポジティブに物事を考えられる、ある程度楽観的な人の方が独学で勉強するのに向いている方と考えられるでしょう。
宅建試験に独学で合格するために必要な勉強時間
宅建士試験に合格するに必要な勉強時間は、独学の場合300~500時間程度と言われています。もちろん個々の持つ知識や、勉強に対する姿勢、勉強に対する慣れなどで勉強時間も変わってきます。
この記事では以降、独学で必要な勉強時間は500時間という前提で話を進めていきたいと思います。
社会人の方が500時間の勉強時間を確保するには、どの程度の勉強期間が必要か計算しておきましょう。仕事のある日は毎日2時間、週末は1日5時間ずつ勉強すると考えると25週間、およそ半年ほどの勉強期間でクリアできます。
宅建試験を独学で勉強する際のポイントと勉強方法
独学で宅建士試験を目指す場合、より効率的に学ぶために必要となるポイントに関して解説していきましょう。
テキスト選びは慎重に
独学で勉強を進める場合、もっとも重要になるのがテキスト選びです。
宅建士試験は毎年20万人前後が受験する人気資格。そのため市販のテキストも数多く発売されています。このテキストの中から自分に合ったテキストを探し出すのが最初の難関です。
テキスト選びのポイントは、自分のレベルに合ったものを選ぶこと、最新のものを選ぶこと、そして参考書や問題集は同じ出版社の同じシリーズでそろえることです。
市販のテキストにはそれぞれ特徴があります。初学者を強く意識しているものや、ある程度した知識がある方が採点で合格を目指すためのものなど、特徴はそれぞれです。まずは自分のレベルに合ったものを見つけましょう。
同じシリーズで統一するのは、テキストによって勉強の進め方の違いがあり、重点ポイントにも差があるからです。同じシリーズの物でそろえると、テキストの進み具合に合わせて問題集も進ますので利用しやすくなります。
最新のものを選ぶことに関しては、後に説明しますが法改正対策です。人気資格の参考書だけに、古本なども多く見つかるかと思いますが、古本などよりも最新のものを選ぶことをおすすめします。
試験の全体像を把握しよう
宅建士試験の出題範囲はかなり広く、全ての範囲を漠然と学んでいるとかなりの勉強時間が必要になります。また、全ての出題範囲を完璧に理解しようとするのも勉強効率という点ではおすすめできません。
そこで参考書や過去問などを利用し、試験の全体像を早い段階で把握するのがおすすめ。どの分野を重点的に学ぶべきかが理解できれば、無駄な勉強時間を使わず、勉強効率は飛躍的に上がるでしょう。
無理のない勉強スケジュールを考える
独学で勉強を進める場合、自分で勉強スケジュールを立てることが重要です。上の項目でも触れましたが、漠然と勉強を進めるのはあまり効率的とは言えません。しっかりと勉強スケジュールを組んで、そのスケジュール通りに勉強を進めましょう。
このスケジュールですが、作成のポイントは余裕を持って作ること。勉強スケジュールを考えるのは、勉強を始めたころです。つまりもっとも勉強に対するモチベーションが高いタイミングです。
そのため、つい無理なスケジュールを組んでしまいがちですがこれはNG。勉強がスケジュール通りに進まなくなると、勉強に対するモチベーションは下がっていきます。モチベーションの低下は勉強効率の低下につながり、さらにスケジュールから遅れてしまう可能性が高まります。
スケジュール作成の場合は、十分余裕を持って、無理のないスケジュールになることを意識しましょう。
インプットとアウトプットのバランスが重要
宅建士試験では法令問題も多く出題されます。法令問題以外にも暗記が必要な科目は多く、勉強においては正しい知識を覚えていくことが重要になります。
知識を身に付けると聞くと、どうしてもインプットに偏った勉強が中心となりがちですが、短期間で新しい知識を定着させるには、アウトプットが重要になります。
演習問題や過去問、例題なども活用し、インプットとアウトプットをバランスよく取り入れながら、地道に知識を増やしていきましょう。
最新の法改正をチェック
テキストの項目で少し触れましたが、宅建士試験では最新の法改正にも注目する必要があります。宅建士試験では法令問題が多く、こうした法律が改正されると当然覚えるべき内容も変わってきます。
テキストは最新のものがおすすめとしたのは、この法改正対策。古いテキストで勉強してしまうと、現在の法律に対応できない可能性があります。宅建士の試験に関しては、毎年法令基準日が設けられますので、この基準日の法律に対応したテキストで学ぶようにしましょう。
独学で目指す際の勉強スケジュール
独学で目指す場合に必要な勉強時間は500時間。500時間の勉強時間を確保するために必要な勉強期間には個人差があるかと思います。そこで、勉強期間ごとの勉強スケジュールの例を紹介していきたいと思います。
ここでは勉強期間が3ヶ月、半年、1年の3つのパターンを紹介していきます。
宅建士試験は例年10月に開催されていますので、この試験日を基準に考えていきましょう。
| 勉強期間1年間 | 勉強期間半年間 | 勉強期間3ヶ月間 | |
|---|---|---|---|
| 必要な勉強時間 | 500時間 | 1日あたりの勉強期間 | 平日:1時間 週末:2時間半 |
平日:2時間 週末:5時間 |
平日:4時間 週末:10時間 |
| 勉強開始時期 | 11月 | 4月 | 7月 |
勉強期間が1年間の場合
| 勉強内容など | |
|---|---|
| 11~12月 | 【試験の全体像をつかむ時期】 ・参考書をひと通り読む ・過去問に挑戦する ・上記の情報を参考に、以降半年間のスケジュールを考える |
| 1~6月 | 【知識をしっかりと身に着ける時期】 ・インプットとアウトプットを繰り返して必要な知識を身に着ける ・全体を1周だけではなく、2~3周と繰り返す ・全体の勉強が終わった以降で模試を受験する |
| 7~10月 | 【自身の弱点を克服する時期】 ・模試の結果などから自身の弱点を把握し補強する ・過去問を繰り返し解き、内容を理解しながら確実に答えられるようにする |
1年間の勉強期間があれば、ある程度余裕を持った勉強計画が立てられます。大まかな勉強の流れを解説していきます。
最初の2ヶ月は試験の全体像をつかむための期間です。まずは参考書を読み、どのような内容を学ぶのかを確認します。読み進める中で多くの疑問点があるかと思いますが、あまり気にせずどんどん読み進めることが大切です。
参考書を1~2周読み込んだら、過去問など演習問題に挑戦します。もちろんしっかり勉強したわけではありませんので、この時点で点が取れないのは当然です。そのため、得点は気にする必要はありません。必要なのは、出題の傾向や、どんな知識が問われるかを知ること。分からない問題は勘で答えるのではなく、分からないまま白紙にしておくのがおすすめです。
ここまでで試験の全体像や、理解が難しいポイントを把握し、続く6ヶ月の勉強スケジュールを考えます。重点的に学ぶべき分野などを理解していれば、効率的なスケジュールが組めるでしょう。
続く6ヶ月は本格的な勉強期間です。参考書を読みながら、ひとつひとつの項目を理解しながら勉強を進めます。知識を定着させるためにインプットとアウトプットを繰り返しながら進めましょう。
参考書は1周だけではなく、時間が許す限り繰り返し勉強するようにしてください。
6ヶ月間でしっかり学んだら、模試に挑戦してみましょう。例年夏場以降は、多くの予備校や通信講座で宅建士試験の模試を開催しています。
この時点で受験する模試は、結果以上に内容に注目。どの分野で得点が取れて、どの分野が苦手かを把握するのが重要になります。
最後の4ヶ月は、改めて勉強を進める期間。特に模試の結果自分の弱点と分かった部分を重点的に学んでいきましょう。ある程度弱点が補強できたタイミングで、改めて模試を受けるのも効果的。直前の模試は内容だけではなく結果にもこだわって挑戦しましょう。
勉強期間が半年の場合
| 勉強内容など | |
|---|---|
| 4月 | 【試験の全体像をつかむ時期】 ・参考書をひと通り読む ・過去問に挑戦する ・上記の情報を参考に、以降半年間のスケジュールを考える |
| 5~8月 | 【知識をしっかりと身に着ける時期】 ・インプットとアウトプットを繰り返して必要な知識を身に着ける ・全体を1周だけではなく、2~3周と繰り返す ・全体の勉強が終わった以降で模試を受験する |
| 9~10月 | 【自身の弱点を克服する時期】 ・模試の結果などから自身の弱点を把握し補強する ・過去問を繰り返し解き、内容を理解しながら確実に答えられるようにする |
勉強の流れは基本的に1年間の勉強期間と同じです。試験の全体像を把握してから本格的な勉強を始め、模試などで弱点を見極めて弱点を補強するという流れです。
ただし1年間のケースと違い、勉強期間が半減するのがポイント。全体像の把握も勉強の進め方も、効率化を意識して進める必要があります。
勉強期間が3ヶ月の場合
| 勉強内容など | |
|---|---|
| 7~8月 | 【知識をしっかりと身に付ける時期】 ・参考書をひと通り読む ・過去問に挑戦する ・インプットとアウトプットを繰り返して必要な知識を身に付ける ・全体を1周だけではなく、可能な限り繰り返す |
| 9月 | 【自身の弱点を克服する時期】 ・過去問を繰り返し解き、内容を理解しながら確実に答えられるようにする |
独学で、3ヶ月の勉強期間で合格を目指すのはかなり厳しい挑戦になります。全体像をつかむのに2週間、全体の勉強で6週間、弱点克服で4週間程度しか時間が取れませんので、効率的に、集中して勉強を進める必要があります。
また、効率的に学ぶために、テキスト選びも重要になります。時間がないとはいえ、テキスト選ぶにはある程度時間をかけるようにしましょう。
理想としては模試を受験するのがおすすめですが、何しろ勉強期間がありません。模試を受けるために勉強スケジュールを変更するくらいなら、模試は受けずに本番に挑むのもひとつの選択です。
模試を受験しない場合、過去問などでしっかり対策し、自分の弱点を把握するようにしましょう。
独学で挑戦する場合の科目別勉強時間配分と勉強ポイント
宅建士試験の試験科目は4科目。ここからはこの科目ごとの勉強のピントを紹介していきます。同時に、どの科目にどの程度の時間を割くべきかどうかも紹介していきましょう。
もちろんここで紹介するのは目安の時間。独学で挑戦する場合は、自分の得手不得手を加味して調整していってください。
民法(権利関係)はじっくり時間をかけて理解する
民法は全体でも2番目に出題数が多い科目です。出題数が多いため、当然勉強時間も長くなります。民法の勉強には150時間ほどの時間を確保するようにしましょう。
民法の分野で学ぶ項目は、ほかの科目を勉強する際にも基礎となる部分があります。極端に言ってしまえば、民法が理解できていないと、ほかの科目の勉強も進めづらくなることに繋がります。
出題数以上にしっかりと時間をかけ、単純に暗記するだけではなくその内容を理解していくようにしましょう。
権利関係に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
宅建業法は出題数がもっとも多い科目
宅建士試験において、もっとも出題数が多いのが宅建業法です。
当然それだけ多くの勉強時間が必要となります。宅建業法の勉強には180時間ほど確保するのが理想です。
出題数が多いため、それだけ勉強する範囲も広くなりますが、例年の出題を見ると、そこまで難易度の高い問題が出題されるわけではありません。出題されるのは宅建業法を理解しているかどうかという点。
しっかり宅建業法の考え方を理解し、この科目で取りこぼしがないように準備しましょう。
法令上の制限は専門用語に注意
法令上の制限の科目は、宅建士試験の科目の中でももっとも勉強に苦しむ科目かもしれません。
法令で使用される文章は独特な言い回しや、普段目にしない用語も多く、なかなか頭に入りにくいという特徴があります。大学などで法律の勉強をされた方にとってはそこまで難しくないかもしれませんが、初学者の方はこうした言い回しなどで苦労する可能性があります。
法令上の制限に必要な勉強時間は100時間程度。じっくり時間をかけて理解していくようにしましょう。
法令上の制限に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
税制その他はできるだけ短時間でマスター
税制その他の科目はそこまで出題数も多くない科目です。印象としては参考書を読み、過去問で出題傾向を把握しておけば十分に対応できる科目になります。
税制その他にかける勉強時間は70時間ほど。しっかり出題傾向を把握し、ここでも、できるだけ取りこぼさないようにしましょう。
税制その他に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
独学では特に過去問対策が重要
独学で宅建士試験に挑む場合、重要になるのが過去問による対策です。宅建士試験は人気資格のため、過去問を探すにもそこまで苦労することはないでしょう。
多くの資格試験で過去問対策は必要と言われていますが、宅建士試験でもこれは同じ。では、過去問対策をすることでどのような効果を得られるのかを紹介していきます。
過去問対策に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:
宅建士試験の過去問の詳細はこちら
過去問から頻出ポイントを把握
宅建士試験はそこまで大きく出題傾向が変わる試験ではありません。出題傾向が変わらないため、それだけ過去問の重要性が高いといえるでしょう。
過去問に挑戦することで出題の傾向がつかめるほか、自分の弱点を把握でき、頻出項目を知ることもできます。
こうした情報をもとに、自分の勉強スケジュールを立てる、または立て直すことも可能。
タイミングを見ながら過去問対策を繰り返すのが独学で合格を目指す大きなポイントとなります。
何度も繰り返して確実に解けるようにする
過去問対策を行う場合、重要なのは何度も同じ問題を繰り返していくという点です。
記事内でも何度か解説していますが、宅建士試験で出題される範囲の法律も、適時法改正を繰り返しています。そのためあまりに古い過去問では、現状の法制度とは違う解答になるケースがあります。
過去問を用意する場合は法改正にも注意し、近3~5年程度の過去問に限るといいでしょう。
過去問を利用した対策のポイントは、解答を暗記するのが目的ではないという点です。何度も同じ問題を繰り返していると、解答自体を暗記してしまうこともあるでしょう、重要なのは解答を覚えることではなく、なぜその回答になるのか、その理屈を理解することです。
過去問対策では、何を問われているのか、そしてどのような理屈でその解答に辿り着くにかをしっかりと理解できるようにしましょう。
短期間で合格を目指すのであればフォーサイトの通信講座がおすすめ
宅建士試験は独学でも合格を目指せる試験です。とはいえ、より短期間で、より効率的に合格を目指すのであれば、独学にはこだわらず通信講座を利用するのがおすすめです。
予備校と違い、通信講座の場合は自宅で、一人で勉強をする形になります。独学と同じくマイペースで勉強でき、当然ですが通学時間も必要ありません。
また、通信講座は勉強を始めてから利用することも可能。独学で挑戦を始めたものの、勉強を進める中で独学では厳しいと感じたら、その時点からでも利用可能です。
そんな通信講座の中では、フォーサイトの宅建士講座がおすすめ。フォーサイトの講座をおすすめする理由をいくつか紹介していきます。
宅建講座の詳細はこちら短期合格を念頭に置いた洗練されたカリキュラム
フォーサイトの宅建士講座には、短期間での合格を念頭に置き、効率的に学べるテキストとカリキュラムが用意されています。宅建士試験に合格するのに満点は必要ありません。例年の傾向を見るとおよそ7割得点できれば合格が目指せます。
フォーサイトは満点主義ではなく合格点主義。必要な知識を必要な分だけ身に着けるため、より短時間の勉強時間で合格を目指せます。フォーサイトを利用した場合、宅建士試験合格に必要な勉強時間は200時間程度。それだけ効率的に学べます。
独学で目指す場合、大きなポイントとなるテキスト選びと勉強スケジュールの立案。フォーサイトを受講すれば、合格点主義で見やすいオリジナルテキストと、そのテキストに沿ったカリキュラムが手に入ります。
これだけでも合格する可能性は大きく跳ね上がるでしょう。
スキマ時間を有効活用できるeラーニング教材
もうひとつフォーサイトをおすすめする理由がeラーニング教材の充実です。
手持ちのスマホやタブレットで、場所を選ばずに勉強ができるeラーニング。フォーサイトではeラーニングに適したデジタル教材も数多くそろっています。
一部を紹介すると、まずは短時間でも勉強できる15分程度の短時間の講義動画。もちろんスマホの小さな画面で観ることを想定した専用動画のため、見やすく聞き取りやすいのも特徴です。
さらに講義の音声のみのデータや、デジタルテキスト、さらにスマホでも簡単にチャレンジできる演習問題など、充実の教材があります。
勉強時間の確保が難しい社会人や主婦(主夫)の方でも、ちょっとしたスキマ時間を勉強時間に変えられるため、より効率的に学ぶことが可能です。
1分で完了!

まとめ
宅建士試験は独学でも合格を目指せる難易度の試験です。とはいえ、宅建士試験がどのような試験なのか、どのように対策すべきかなどを理解していないと、簡単に合格できるものではありません。
独学で目指す場合は、テキスト選び、勉強スケジュールの立て方、勉強の進め方など、いろいろなポイントに気を配り、万全の態勢で挑みましょう。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
●フォーサイト講師ブログ



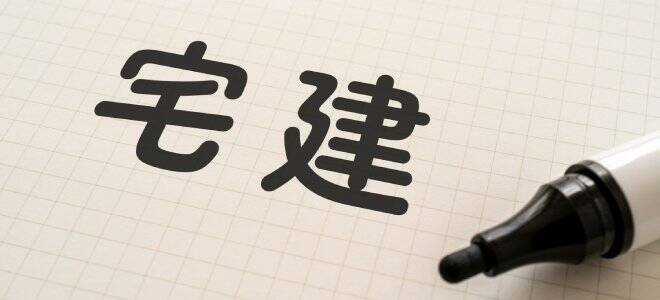












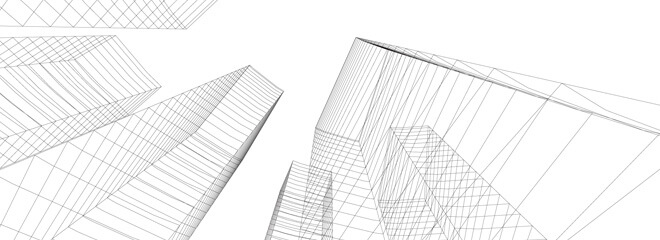





 ログイン
ログイン




 0120-966-883
0120-966-883


