社労士の難易度はどのくらい?合格率が低い理由から他資格との難易度の違いまで解説
更新日:2023年12月18日

雇用者と労働者の間に起きる問題に関して、解決の手助けをする役割を担う社会保険労務士(以下:社労士)。
この社労士の資格を持つと、企業内で活躍できるのはもちろん、将来的には独立開業も視野に入ります。
社労士資格を取得するには、国家試験に合格する必要がありますが、この社労士試験の難易度はどの程度のものなのか?社労士試験の出題範囲、出題内容、過去の合格率などから、社労士試験の難易度に関して解説していきたいと思います。
- 社労士資格を取得するには、社労士試験に合格する必要があります。
- FP試験と社労士試験は一部同じような項目を学ぶ試験であるものの、広く浅い知識が問われるのがFP試験で、より深く細かい知識が求められるのが社労士試験です。
- 行政書士試験は広く浅く、社労士試験は狭く深く学ぶ必要があるという点でやや違いがあります。
- 宅建士よりも出題範囲は社労士試験の方が広く、さらに出題される問題の難易度も社労士試験の方が難易度が高い傾向にあります。
- 社労士の例年の受験者数は4万人程度。受験者数の少ない試験ということになります。
- 社労士試験は8科目が出題されますが、科目ごとに足切り点が設定されています。
- 社労士試験には科目別合格の制度はありません。
フォーサイト小野賢一のご紹介
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう。そうすることで、少しずつ実力が身につきます。
社労士試験に合格することで、「なりたい自分」になれます。「なりたい自分」をめざして頑張りましょう!
社会保険労務士(社労士)の難易度
社労士資格を取得するには、社労士試験に合格する必要があります。まずはこの社労士試験の難易度を、ほかの人気資格の試験難易度と比較して紹介していきます。
ちなみにここで紹介するほかの資格との難易度に関して、簡単にまとめておきましょう。
司法書士試験>社労士試験=FP1級≧行政書士>FP2級=宅建士>FP3級
上の難易度の順番はあくまでもイメージですが、大きく間違ってはいないかと思います。ではなぜこういった形になるのか。試験内容の違いや難易度に関して比較していきましょう。
ファイナンシャル・プランニング技能士と社労士の難易度の違い
一般的にFPと呼ばれるファイナンシャル・プランニング技能士資格。FP資格には1~3級がありそれぞれ難易度が違います。
FP試験も2級以上となると難易度の高い試験となりますが、社労士試験との違いはどこにあるのかを考えてみたいと思います。
FP試験は、ライフプランニングに関するあらゆる分野から問題が出題されます。金融商品の知識や、税制、年金制度、保険制度など勉強する範囲は多岐にわたります。
一方社労士試験では、労働基準法を中心として、労務に関する深い知識が必要となります。同じ法律問題と言っても、出題される問題の難易度は社労士試験の方が高く、ここが社労士試験の難易度の高さとなります。
大げさに言ってしまえば、FP試験と社労士試験は一部同じような項目を学ぶ試験であるものの、広く浅い知識が問われるのがFP試験で、より深く細かい知識が求められるのが社労士試験というイメージ。試験の対策をする場合の難易度は、社労士試験の方が1枚上という印象です。
ただし、FP試験も1級の試験になると、筆記式の問題が出題されるなど、難易度が上がりますので、FP1級試験の難易度は、社労士試験の難易度と同等と考えることもできます。
行政書士と社労士の難易度の違い
社労士試験と同様に、法律問題が出題の中心となる行政書士試験。出題される範囲としては、行政書士試験の方が広範囲と言えるかと思います。
ただし出題される問題の難易度という点では、行政書士試験よりも社労士試験の方が難易度が高い傾向。行政書士試験は広く浅く、社労士試験は狭く深く学ぶ必要があるという点でやや違いがあるといえます。
また、行政書士試験と社労士試験の大きな違いが出題数。社労士試験は全ての試験を合わせて110題出題され1問1点の110点満点。一方行政書士試験は60問出題されて300点満点の試験です。
1問1点の試験は、1問にかかる重要度が高くなります。1問間違えたせいで合格基準点に達さないというケースが少なくないからです。一方60問で300点満点の試験は、1問平均5点の配点。満点が300と大きいことから、仮に1問ケアレスミスで間違えても、合否には大きく影響しないというケースが考えられます。
似たような法律問題が出される試験ですが、この配点・出題数の差は大きく、ミスが許されない社労士試験の方が出題難易度は高いといっていいでしょう。
双方の試験の例年の合格率を見ると、行政書士試験で10%程度、社労士試験で6%程度となっています。さらに受験資格に注目すると、行政書士試験は受験資格なし、社労士試験は大卒など、ある程度の受験資格があります。
一般的に受験資格がある試験ほど受験生のレベルは高く、その中で行政書士試験よりも合格率が低い社労士試験は、行政書士試験よりも難易度の高い試験であるといえるでしょう。
関連記事:
行政書士の難易度や合格率はどのくらい?他資格との比較から合格点まで徹底検証
宅地建物取引士と社労士の難易度の違い
労務関係の法律問題が多い社労士試験に対し、不動産取引に関わる法律問題が多く出題されるのが宅地建物取引士(以下:宅建士)試験です。
どちらも法律の中でも限定的な部分から出題される試験ですが、それでも出題範囲は社労士試験の方が広く、さらに出題される問題の難易度も社労士試験の方が難易度が高い傾向にあります。
宅建士試験も社労士試験同様に1問1点という配点の試験。そのためちょっとしたミスが合否に関わるという点では同じです。
ただし、宅建士試験は受験資格なし、さらに科目ごとの足切り点なしですので、この点は社労士試験と大きく違います。
総合的に試験の難易度を考えると社労士試験の方がかなり高く、合格率も低い試験となります。
関連記事:
宅建の合格率はどのくらい?難易度や合格点についても解説
社労士と宅建、取るならどっち?難しさやダブルライセンスに注目
司法書士と社労士の難易度の違い
法律問題が多く出題される試験の中でも、難関試験に位置付けられる司法書士試験。この司法書士試験と社労士試験の違いを確認しておきましょう。
不動産や法人の登記を代行する司法書士。さらに認定司法書士となれば、少額裁判の代理人を務める資格も持ちます。
そのため試験範囲は非常に広く、法律に関してしっかりとした知識を持っていないと合格できない試験となっています。出題範囲の広さは社労士試験よりも広く、出題難易度は社労士試験と同等の難易度の高い試験となります。
解答方式の違いでは、司法書士試験では筆記問題が出題されるという点も挙げられます。同じ法律問題であれば、択一式や選択式よりも記述式の方が難易度は高く、この点でも司法書士試験の方が難易度の高い試験であると言えるでしょう。
司法書士試験の例年の合格率は3~5%程度。受験資格なしの試験のため、直接比較はできないものの、それでも社労士試験と同等、もしくはそれ以上の難関試験であることが分かります。
試験全体の難易度という点では、司法書士試験は社労士試験よりも難易度の高い試験であると考えていいでしょう。
関連記事:
司法書士試験の難易度は?難しい理由や合格率を解説!
社会保険労務士(社労士)試験の合格率は?
社労士試験の難易度を知るために、続いては社労士試験の合格率をチェックしていきましょう。
社労士試験は毎年1度の実施。例年8月後半に実施されています。そんな社労士試験の過去10年間の合格率をまとめます。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 49,292名 | 2,666名 | 5.4% |
| 2014年 | 44,546名 | 4,156名 | 9.3% |
| 2015年 | 40,712名 | 1,051名 | 2.6% |
| 2016年 | 39,972名 | 1,770名 | 4.4% |
| 2017年 | 38,685名 | 2,613名 | 6.8% |
| 2018年 | 38,427名 | 2,413名 | 6.3% |
| 2019年 | 38,428名 | 2,525名 | 6.6% |
| 2020年 | 34,845名 | 2,237名 | 6.4% |
| 2021年 | 37,306名 | 2,937名 | 7.9% |
| 2022年 | 40,633名 | 2,134名 | 5.3% |
| 10年合計 | 402,846名 | 24,502名 | 6.1% |
過去10年でもっとも合格率が高かったのは2014年の9.3%、反対にもっとも合格率が低かったのが2015年の2.6%です。例年の合格率はおおよそ5~7%程度で、10年間の平均を見ると6.1%となっています。
合格率が10%を切る試験はいわゆる難関試験といわれるもの。社労士試験も合格率が2桁に乗ることはほぼなく、難易度の高い難関試験の一つと考えていいでしょう。
合格率は低く難易度の高い試験
例年の受験者数は4万人程度。人気の高い資格試験であれば、10万人を超える事も珍しくありませんが、社労士試験はこうした試験と比較すると受験者数の少ない試験ということになります。
とはいえ、社労士が人気のない資格というわけではありません。簡単に受験できないほど難易度の高い試験のため、受験者数がある程度絞られると考えた方がいいでしょう。また、社労士試験には大卒など学歴による受験資格もあり、こうした点も受験者数には影響していると考えられます。
受験資格があり、さらにある程度しっかりと準備をしてきた方のみが挑戦している試験と考えると、こうしたレベルの高い受験者の中でも合格率が10%に満たないというのは、かなり難易度が高い試験であることの証左といえます。
これから社労士試験に挑戦する方は、しっかりと準備を行い挑戦するようにしましょう。
関連記事:
社労士の試験内容や試験科目について解説
社会保険労務士(社労士)試験の合格率が低い理由
社労士試験の合格率は6%前後。この数字だけでも十分低い数字ということが分かりますが、さらに受験資格があると考えると、相当難易度の高い試験であることが分かります。
では、社労士試験がここまで合格率が低い理由をいくつか紹介していきたいと思います。
これから社労士資格を目指すという方は、社労士試験の持つ合格率が低い理由をしっかりと理解し、その対策も考えながら受験準備、勉強を進めていきましょう。
試験科目が多く勉強範囲が広い
社労士試験の合格率の低さ、難易度の高さの理由の1つに、試験範囲の広さが挙げられます。社労士試験で出題されるのは10分野8科目。一般的な資格試験でも8科目というのは非常に多く、それぞれしっかりと対策する必要があるというのも難易度が高い理由になります。
試験当日は、午前中に8科目の選択問題が出題され、午後に同じ8科目の択一式問題の試験を受験します。試験科目は労働基準法や国民保険法など法律問題が中心ですが、労務関係の法律や年金関係の法律など、分野の違う法律から出題があるため、対策には多くの時間が必要となります。
さらに試験問題の中には一般常識を問う問題もあり、単純に法律を暗記するだけではなく、時事ニュースや最新の法令などの情報収集も必要となります。
資格試験としては対応すべき分野が多く、勉強時間の調整が難しいというのが、難易度が高い試験である大きな要因でしょう。
科目ごとに足切り点が存在する
社労士試験は8科目が出題されますが、科目ごとに足切り点が設定されています。足切り点は、科目ごとに加え、試験方式ごとに設定されています。また、合格基準点は年度ごとに変動する相対評価の試験となっています。
参考に2021年度試験の合格基準点を紹介していきましょう。
★2021年度合格基準点
・選択問題 総得点24点以上(40点満点)、かつ各科目3点以上(5点満点)
・択一問題 総得点45点以上(70点満点)、かつ各科目3点以上(10点満点)
上記の条件をすべて満たして初めて合格となります。出題科目が多い上、各科目ごとに合格基準点が設定されるため、すべての科目を平均的にしっかりと勉強しなければいけません。
さらにポイントは「相対評価」という点。社労士試験では、合格基準点が試験前には決まっておらず、試験の結果から合格基準点を設定する評価方法を採用しています。考え方としては、事前にある程度合格する人数が決められており、合格基準点が決まっていない試験です。いってみれば大学入試や高校入試の試験と同じ評価基準となります。
ちなみに相対評価に対して、事前に合格点が決まっていて、合格者数に制限がない試験を絶対評価の試験といいます。こちらは、合格点をクリアできれば何人でも合格者が出るというもの。身近で分かりやすい例としては、自動車などの運転免許試験が絶対評価の試験です。
相対評価の試験では、受験者のレベルが高くなると、必然的に合格基準点も高くなるため、事前の対策が難しいという点が挙げられます。事前に出題範囲と合格点が分かっていれば、「これくらい点が取れるようにすれば合格できる」という目標が設定できますが、この目標設定が難しいのが相対評価の試験。
社労士試験の合格率が低い理由は、相対評価である程度合格者数が決まっている試験であるという点も含まれるでしょう。
科目別合格の制度がない
受験科目が多く、さらに科目ごと、試験ごとに合格基準点がある社労士試験。資格試験で科目ごとの足切り点を設定している試験では、科目別合格の制度が導入されていることも珍しくありません。
科目別合格とは、一度合格基準点をクリアした科目に関しては、以降数年間合格扱いとなり、受験免除になるという精度です。
しかし社労士試験にはこの科目別合格の制度はありません。つまり常に8科目全科目を受験し、また全科目で合格点をクリアしなければいけないということ。
こちらも社労士試験の合格率の低さ、難易度の高さに直結している大きな理由でしょう。
社会保険労務士(社労士)試験は独学でも可能?
合格率およそ6%の難関・社労士試験合格を目指す上では、まず第一に「学習方法の選定」が重要です。例年、独学で挑戦する受験生は少なくありませんが、結論から言えば、独学は非効率であると言わざるを得ません。
もちろん、法律学習の経験の有無や、学習のために確保できる学習時間数、資格対策への慣れ・不慣れ等、各人の能力や条件に依る部分が大きいのですが、おそらく多くの社労士受験生にとって独学受験は茨の道となるでしょう。
関連記事:
社労士は独学で合格できる?効果的な勉強方法についても解説
難易度の高い社会保険労務士(社労士)試験の合格率を高めるには?
社労士試験は合格率が6%前後と非常に低く、難易度の高い試験と言われています。その難易度の高さはここまで説明してきた通り。ポイントは8科目と多い試験科目を、平均的にしっかりと点数を取れるように準備するという点です。
社労士試験は年に1度の実施です。1度の受験で失敗してしまうと、次の挑戦まで1年という長い時間が必要になります。勉強期間が長くなればなるほど、勉強に対するモチベーションも落ちてしまうもの。できれば1度の挑戦で合格したいところです。
では難易度の高い社労士試験に合格するために、どんな勉強方法がいいのかを考えていきましょう。
通信講座を利用して効率的に勉強する
社労士試験に独学で合格しようとした場合、800~1,000時間の勉強時間が必要と言われています。平日は仕事という社会人の方をイメージすると、平日毎日2時間勉強し、土日祝日に5時間勉強して1年間で合格できるかどうかというレベル。独学で挑戦して合格することは可能ですが、かなり難しいというのが正直なところです。
では勉強期間を2年間確保すればということになりますが、2年間毎日休まず勉強を続けるのはかなり難しいこと。また、モチベーションの管理という点でも難しくなります。
より短期間で社労士試験に合格するためには、独学ではなく、より効率的な勉強方法がおすすめということになります。そんな効率的な勉強を実現できるのが、通信講座の受講です。
通信講座をおすすめするのは、まず通学時間という移動時間が必要ないという点。予備校に通学する場合は、どうしても通学時間という無駄な移動時間が発生してしまいますが、通信講座は自宅で勉強しますので、この無駄がありません。
通信講座には、社労士試験に精通した専門講師やスタッフがいます。こうした専門講師やスタッフが、毎年の出題傾向を予想し、社労士試験に向けてもっとも効率よく学べるように組んでいるのがカリキュラムです。)
独学でテキスト通りに勉強するより、効率的に無駄を省いて勉強できるため、より短い勉強時間で合格を目指せます。こうした効率的な勉強方法で学ぶことで、より社労士試験に合格する可能性は高くなるでしょう。
フォーサイトの社労士講座がおすすめ
社労士試験対策講座を開講している通信講座は数多くありますが、その中でもおすすめなのがフォーサイトの社労士講座です。
フォーサイトの社労士講座には、上で説明した通り、社労士試験に精通した講師・スタッフが揃っています。そんなスタッフが考えた効率的に学べるオリジナルテキスト、カリキュラムがあれば、より効率的に学ぶことができるでしょう。
また、フォーサイトの社労士講座には、初学者、試験経験者、実務経験者など、受講生のレベルに合わせた3つのバリューセットがあります。社労士試験の勉強が初めて、資格試験の勉強が初めてという方は初学者の方向けのセットを、すでに社労士試験に挑戦したことがある、実務に就いているという方には、経験者向けのセットなど、受講生のレベルに合わせて選べるのも、フォーサイトをおすすめする理由となります。
フォーサイト 社労士通信講座まとめ
社労士試験は合格率が低く、難易度の高い資格試験です。いわゆる難関資格のひとつであり、独学で挑戦するのは不可能ではないものの、かなり難易度の高い挑戦となります。
社労士試験の合格率が低い理由はいくつか考えられますが、もっとも大きいのは受験科目の多さと、科目ごと、試験方式ごとの足切り点の存在でしょう。
社労士試験は8科目が出題され、それぞれの科目に足切り点が設定されています。しかも基本的に1問1点の試験であり、出題数が少ないため、1問間違えるだけで合格点に届かない可能性がある試験です。
難易度の高い社労士試験に合格するためには、8科目全てを平均的に学び、ミスなくしっかりと解答していく必要があります。
また、社労士試験には科目別合格の制度がないため、受験する場合は8科目全てを受験し、すべての科目で合格点を取る必要があります。一度不合格となっても、翌年以降、再び8科目に挑戦しなければいけないため、合格は容易ではありません。
そんな難易度の高い社労士試験に合格するためには、効率的に学ぶのが大きなポイントとなります。そのためには独学にはこだわらず、通信講座の利用がおすすめ。特に受講生のレベルにより、選べる3つのバリューセットがあるフォーサイトの社労士講座がおすすめとなります。
1分で完了!
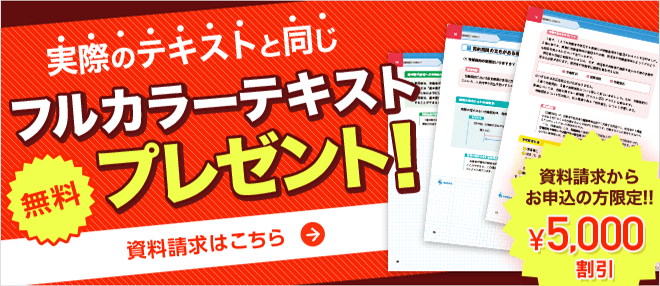
小野賢一(おの けんいち)
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師




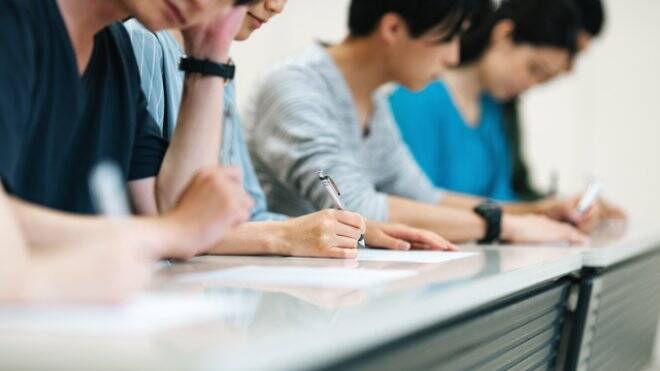

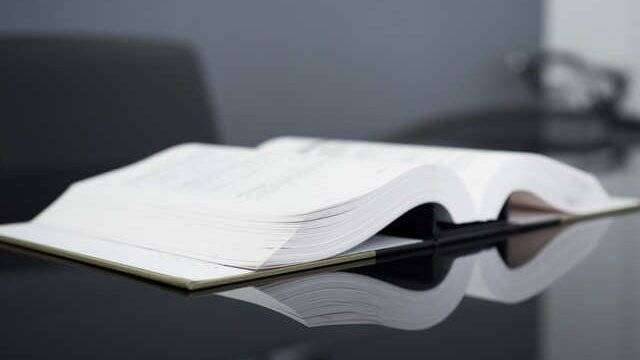









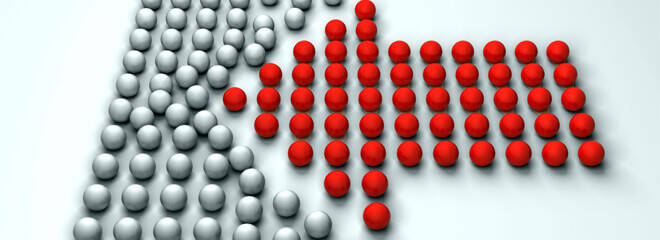
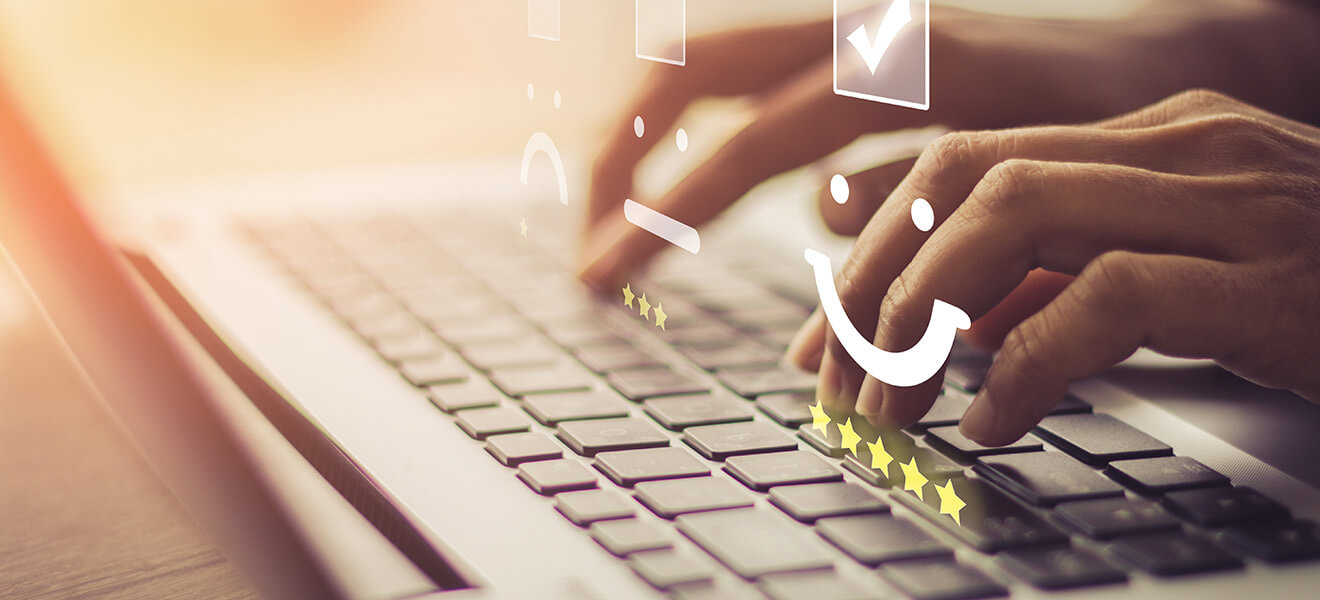





 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


