司法書士試験の難易度は?難しい理由や合格率を解説!
更新日:2024年3月22日
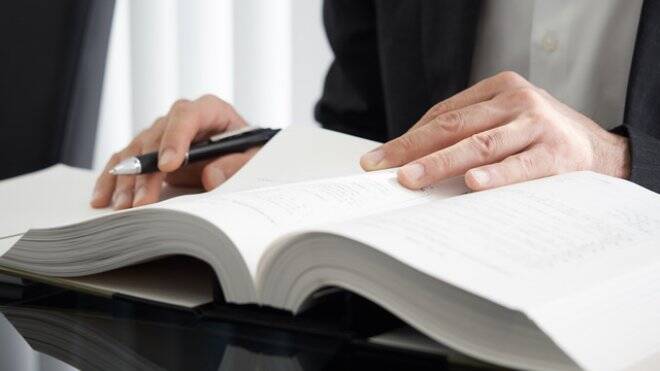
司法書士とは
皆さんが「法律家」と聞いて真っ先に思い浮かべるのはおそらく「弁護士」だと思いますが、一般市民にとっての身近な法律家といえば「司法書士」です。
日常生活における法律上の手続きの際には、実際のところ、弁護士ではなく司法書士のお世話になることの方が多いのではないでしょうか?
例えば、マイホーム購入の際の不動産登記や会社設立に伴う法人登記、相続関連では遺言書作成や家族信託手続、遺産管理業務、さらに高齢者や障がい者を対象とした成年後見業務等、私たちの生活に欠かすことのできないテーマにおいて、司法書士の業務範囲は多岐に渡ります。
司法書士になるためには、国家資格である司法書士試験に合格し、司法書士会へ登録を行うことが必要です。
関連記事:司法書士の詳細についてはこちら
司法書士試験の難易度は?
市民の身近な法律家である司法書士になるためには、難関・司法書士試験に合格しなければなりません。
法律系国家資格の中では、司法試験の次に難しいと言われる司法書士試験。その難易度を、合格率や他資格との比較から考察しましょう。
司法書士試験の合格率
司法書士試験の合格率は、例年3~5%台の低い数字で推移しています。2023年度は、受験者数13,372人に対して最終合格者695人となっており、合格率は約5.2%でした。2023年度の合格者の平均年齢は41.14歳、男女比は7:3となっています。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 13,372名 | 695名 | 5.2% |
| 令和4年度 | 12,727名 | 660名 | 5.2% |
| 令和3年度 | 11,925名 | 613名 | 5.1% |
| 令和2年度 | 11,494名 | 595名 | 5.2% |
| 平成31年度 | 13,683名 | 601名 | 4.4% |
行政書士試験と比較
法律系資格の登竜門である行政書士試験合格後、司法書士へのステップアップを考える方も多いのではないでしょうか?両試験の難易度の差は、まず「試験科目」の違いにあります。
行政書士試験は、憲法 、民法 、行政法 、商法 、基礎法学からの出題です。これに対し司法書士試験は、憲法、民法、刑法、商法に加え、不動産登記法や商業登記法等の専門性の高い法律の知識が求められます。
合格率の観点でも、2023年度行政書士試験の合格率が13.98%であったのに対し、司法書士試験は合格率約5.2%ですから、難易度の差は歴然です。
関連記事:行政書士の難易度についてはこちら
社労士試験と比較
労働・社会保険関係法令の知識が問われる社労士試験もまた、合格率の観点では司法書士試験同様、難易度の高い国家資格のひとつに数えられます。
社労士試験の合格率は概ね6~7%であり、年度によっては司法書士試験の合格率を下回ることがあるものの、社労士試験の方が合格率が高く、目指しやすいと言えます。
試験科目の観点では、社労士試験と司法書士試験で重複がないため比較が困難ですが、主要科目数の多い司法書士試験の方が、難易度は上がると考えて良いでしょう。さらに出題形式の比較でも、すべてマークシート方式の社労士試験よりも、記述式のある司法書士試験の方が難しいと言えます。
関連記事:社労士の難易度についてはこちら
宅地建物取引士試験と比較
司法書士試験同様、不動産関係法令の知識が問われる国家資格に宅建士があります。宅建士試験の合格率は概ね15~18%で推移しており、2023年度の試験結果によると17.2%でした。合格率だけを見ると、宅建士試験について「司法書士ほどではないが、かなりの難関なのでは?」と感じられるかもしれません。
しかしながら、試験科目が4科目のみ、出題は全てマークシート方式、加えて比較的素直な出題が多いことから、法初学者でも比較的短期間で合格を目指しやすい資格と言えます。よって、宅建士試験と司法書士試験の難易度の差は歴然です。
関連記事:宅建の難易度についてはこちら
司法書士試験の難易度が高い理由
司法書士試験は難易度が高く、合格率も非常に低い試験として知られています。司法書士試験に対する一般的なイメージとしては、司法試験ほど難しくはないものの、税理士試験や社会保険労務士試験、弁護士試験とは遜色ない難易度という印象を持つ方が多いのではないでしょうか?
司法書士には「市民の身近な法律家」としての活躍が期待され、登記や相続等、日常生活に関わる幅広い法律の知識が問われます。具体的には、すべての法律の基礎となる憲法や民法の他、民事訴訟法や不動産登記法等のあまりなじみのない科目を含む11科目が試験範囲となっています。
司法書士試験の難易度を考える場合、こうした科目数や出題の難易度、さらに合格判定の厳しさを考慮するのが一般的です。 しかし、出題範囲の広さや問題の難易度をどう判断するかは、どうしても個人差が出る部分です。
この記事では個人の感覚に依らない、司法書士試験の難易度を客観的に判断できる要素をいくつかまとめていきます。
試験時間が非常にシビア
入学試験にしても、資格取得試験にしても、受験の際に重要になるのが、試験中の集中力です。どれだけ集中して問題にあたることができるかは、合否を考えた場合非常に重要なポイントといえるでしょう。
しかしいくら鍛えても人間の集中力にはある程度の限界があります。あまり長時間の試験では集中力が持続せず、試験時間の後半になるとケアレスミスが頻発するようなケースも考えられます。
司法書士試験は一次試験の筆記試験と、二次試験の口述試験によって合格者が選ばれます。問題は一次試験の筆記試験。筆記試験は1日で終了しますが、その試験時間がシビアな試験となっています。
司法書士試験の筆記試験は午前と午後に分かれており、午前の試験が択一式35問を120分で解答します。午後の試験は択一式35問と記述式2問を180分で解答することになります。
1日でトータル5時間の試験を受けるだけでも体力的に大変ですが、午後の試験は3時間でも足りないほどのボリュームです。いかに択一問題を効率的に回答し、記述式を解く時間を確保できるかどうかにかかっています。
突破が難しい合格基準点
司法書士試験には合格点のほかに合格基準点が設けられています。合格点は総得点に対して設定されますが、合格基準点は試験の分野ごとに設定され、この合格基準点を必ずクリアしていないと、いくら総得点で合格点をクリアしていても合格はできません。
合格基準点は3つの分野に分けて設定されます。
- 午前の試験(択一式35問・105点満点)
- 午後の試験(択一式35問・105点満点)
- 午後の試験(記述式2問・70点満点)
参考までに、令和2年度(2020年度)の司法書士試験における合格基準点をご紹介しましょう。
- 午前の試験(択一式35問・105点満点) → 75点(正答率:71.4%)
- 午後の試験(択一式35問・105点満点) → 72点(正答率:68.6%)
- 午後の試験(記述式2問・70点満点) → 32点(正答率:45.7%)
記述式試験の合格基準点のみ低いように思えますが、記述式試験は設問における法解釈や対応をひとつ間違えると、出題全問が不正解になってしまう試験です。その点を考慮すると、この合格基準点も決して低いものとはいえません。
令和2年度に関しては、おおよそ7割程度の正答率で合格基準点はクリアということになりますが、この基準点は毎年変更されています。
その年の受験者全員の正答率から合格基準点が設定されるため、全体を平均的に70%応えられれば合格基準点をクリアできるとも限りません。
また、この点数はあくまでも足切りの参考とする基準点であり、合格判別を行うボーダーラインはさらに高いところに設定されますのでご注意ください。
相対評価で合格者数が限定的
司法書士試験の合格ラインは毎年変動する相対評価が採用されています。資格試験の合格判定方法は、この相対評価か絶対評価があります。
絶対評価は合格点があらかじめ決められており、その合格点をクリアすれば何人でも合格者が出る試験です。主に受験者の能力測定をするような資格試験で多く採用されている方式で、有名なところではファイナンシャルプランナー試験や日商簿記の試験などがあります。
取得した時点で独占業務を持つような国家資格の試験では絶対評価はあまり採用されていません。有名な資格では行政書士試験が絶対評価の試験ですが、それ以外の国家試験の評価方法は、ほぼ相対評価となります。
相対評価の試験は、事前に合格点が決められておらず、受験者のテストの成績によって合格点が算出されます。
そのため受験者全体のレベルが高ければ合格点は高くなり、逆であれば低くなります。相対評価の場合、事前に決められているのは合格者の人数であり、合格点はその人数に合わせて上下することになります。
事前に勉強することを思うと、あらかじめ合格点が決まっており、そこを目標に勉強する方が、気分的には楽です。しかし、合格点が決まっていない相対評価のテストは、いくら勉強をしてもし過ぎるということはありません。
すべての受験者がそのつもりで準備してきますので、必然的に合格難易度は高くなります。
司法書士試験合格のためのポイント
法律系国家資格の中では、司法試験に次ぐ難関となる司法書士試験。何の戦略もなく、ただやみくもに勉強していては、いつの間にか「万年受験生」と化してしまう可能性大です。司法書士試験合格には、学習のコツをおさえる必要があるのです。
戦略的な学習計画の立案
まず、「戦略的な学習計画の立案」は不可欠です。司法書士試験対策は長丁場となりますが、ダラダラ学習は百害あって一利なし。受験を決意しても、弱気になってつい先延ばしにしたくなりますが、受験年度を決めたらその年に必ず受験しましょう。
学習計画立案では、本試験日から逆算して、各段階での「目標到達度」と、到達に向けて「日々取り組むこと」を細かく決めていきましょう。
合格に必要なことに的を絞った学習
また、「合格に必要なことに的を絞った学習」を意識することも大切です。司法書士試験合格のために、膨大な試験範囲をまんべんなく網羅する必要がありますが、完璧主義に陥ると学習に偏りが生じたり、出題傾向から外れた分野が気になったりして、結果的に合格を逃すことになりかねません。
あくまで「合格」を目標に、出題傾向に沿って、狙われるポイントのみを効率良く習得しましょう。
モチベーションに左右されない取り組み
そして何より、「モチベーションに左右されない取り組み」を継続的に行っていくことは、長く険しい司法書士受験生活を支える基礎となります。
長く試験勉強を続けていれば、幾度となくやる気の低下に襲われます。心境に左右され、いちいち歩みを止めていては、あっという間に時間切れです。やる気がある日も、イマイチな日も、淡々と学習をこなす姿勢が求められるのです。
まとめ
司法書士試験の難易度を一言で表せば「難関試験である」という言葉に尽きます。司法書士試験を目指し、十分に勉強してきた受験者たちの中でも、合格できるのは1割にも満たないほどの難しさです。
多くの方は司法書士試験に合格するために、数年間の準備期間を用意し、何度か受験を続けながら自身の弱点を知り、そこを補強しながら最終的に合格をしています。
司法書士試験が難関である理由はいくつかあります。憲法知識から民法、登記関連の法律など広範囲にわたる受験科目がまず考えられます。しかも、合格基準点が存在するため、試験範囲に得手不得手があると合格は難しくなります。
準備段階で大変なのが、合格判断が相対評価であるという点です。相対評価は受験者の上位数%が合格するという評価方法のため、目安となる合格点がありません。つまりどれだけ勉強してもしすぎるということはなく、ゴールのないマラソンを強いられているような感覚になります。
司法書士試験に合格するために70台後半の偏差値が求められるのは、実際に計算しても間違いないでしょう。かつて学校の勉強でここまでの偏差値を記録したことがない方には合格は難しい試験なのでしょうか?
学校の受験勉強との大きな違いは、司法書士試験の問題は法律問題に限られるということです。学校の入試で言えば、数学や英語は無視して、国語の勉強だけを続け、国語の偏差値だけを上げればいいということになります。
確かに簡単ではありませんが、不可能でもありません。そんな難しい課題をクリアするためには、独学や予備校通学よりも通信講座がおすすめです。
予備校は決められたカリキュラム通りに学ぶことになりますが、そのペースについていけなくなった時点で勉強を積み重ねていくことが難しくなります。独学はマイペースを守れるものの、自分の弱点を把握するのが難しいという問題があります。
通信講座はマイペースで勉強をしながら、自身の弱点を指摘してもらえますので、こうした難関試験には非常に強い勉強方法といえます。
通信講座を上手に利用して、効率よく勉強するようにしましょう。








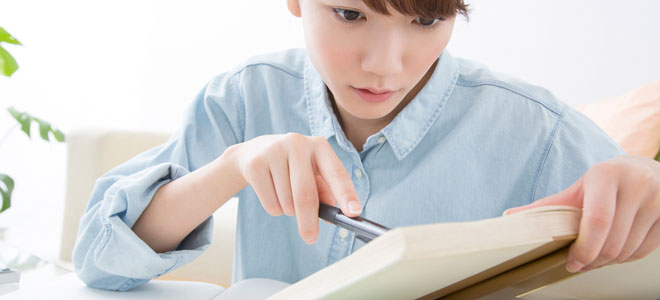


 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


