司法書士とは?仕事内容や試験、魅力について紹介
更新日:2024年3月4日

司法書士とは?
司法書士とは、市民の身近な法律家として、登記又は供託手続の代理に携わる職業です。活躍の場は、不動産売買や賃貸契約、会社設立、後見制度や相続等、多岐に渡ります。
また、認定を受けることで簡裁訴訟代理等関係業務にも携わることができるようになります。
弁護士との違い
同じ法律関係の業務を行う弁護士と司法書士の業務の違いをまとめておきましょう。弁護士は法律に関する相談を受け、裁判には代理人として出廷することができます。
もちろん司法書士も自身の分野に関する法律の相談に乗ることはできますが、なんでも相談に乗ることができるわけではありません。
法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成が可能といっても、依頼人の代理として法廷に出廷できるわけではありません。
ただし、司法書士の中でも「認定司法書士」の資格を持っていると一部裁判に代理人として出廷することができます。司法書士が代理人を務めることができるのは、「債権額が140万円以下の簡易裁判」のみですが、この条件に当てはまる案件であれば、弁護士同様、依頼者の相談に乗り、法廷に出廷することが可能です。
行政書士との違い
公的機関に提出する書類の作成を主な業務とする点では、行政書士とも近い業務ということになります。
行政書士と司法書士の違いは、作成する書類の提出先です。市区町村役場など、官公署に提出する書類に関しては行政書士が、法務局や裁判所、検察庁などに提出する書類に関しては司法書士が作成することになっています。
司法書士の仕事内容は主に7つ
ここからは具体例とともに司法書士の仕事内容に関して、改めてまとめていきましょう。司法書士の業務は大きく分けて3つ。書類作成と代理・代行とコンサルティングです。それぞれの業務を確認していきましょう。
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物に関わる状況や権利関係を登記簿に記載する手続きのことです。対象不動産の所在地や面積、所有者の住所・氏名、担保がついているかどうか等の詳細を公の帳簿に記録しておくことで、不動産取引や相続に伴う権利変動時に安全かつ円滑な手続きが実現します。
不動産登記は、土地及び建物の物理的現況に関わる「表題登記」と所有権に関する「権利登記」に分かれ、前者を土地家屋調査士が、後者を司法書士が行います。
商業登記/会社設立
商業登記とは、法人設立から清算までの一定の事項を登記簿に記載する手続きのことです。株式会社等の法人を設立した際には、会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員の氏名等の法定の事項を登記しなければならず、これらの内容に変更があった際にもまた変更登記が必要となります。
商業登記により法人の内容を公開することで、法人との取引の安全性を高めることができます。司法書士にとって商業登記とは、不動産登記と並ぶ主要業務に位置づけられます。
相続関連業務
司法書士は相続手続きの専門家であり、相続関連業務特有の複雑多岐に渡る諸手続きに対応します。具体的には、相続人調査や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の他、負債が多い場合の相続放棄に関わる手続き、未成年の相続人がいる場合の特別代理人選任申立、遺産相続で争いが生じた際の遺産分割調停の申立に関わる書類作成を行うことができます。
併せて、生前の遺言書作成相談や、死後に発見された遺言書の検認等も司法書士の業務分野です。
簡裁訴訟代理等関係業務
2003年4月施行の改正司法書士法により、司法書士は法務大臣の認定を受けることで、簡易裁判所における訴訟代理業務を行うことができるようになりました。具体的には、請求金額140万円以下の身近な金銭トラブルについて、司法書士が本人に代わって弁論や調停に臨んだり、裁判外での和解交渉を代理したり等が主な業務です。
通常の訴訟に依らない簡易的な手続きにより、迅速に問題解決を図ることができます。簡裁訴訟代理等関係業務を扱う認定司法書士となるためには、日本司法書士会連合会が実施する特別講習を修了し、簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験する必要があります。
成年後見業務
司法書士は、成年後見制度においても幅広く活躍しています。成年後見制度とは、加齢や病気等により判断能力が十分でないとされる人々への法的保護措置です。
司法書士は成年後見人として、不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続等の「財産管理」や、介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認等の「身上保護」に関わる法律行為について、高齢者や障がい者の意思決定支援を行います。今後ますます高齢化が進む日本においては、更なる需要拡大が見込まれます。
供託業務
「供託」とは、債権者が行方不明である等の場合に、債務者が国家機関である供託所に金銭や物品等の財産を預けてその管理を委ねることで、債務履行と同じ法的効果を得ることができる制度です。
債権者と連絡が取れないからといってそのまま放置していれば、債務者側の債務不履行として法的に不利な立場に立たされることになりますが、供託制度を利用することでそのような事態を防ぐことができます。供託に関わる手続きの代行は、不動産登記や商業登記同様、司法書士の独占業務です。
企業法務コンサルティング
この他、会社法や企業法務に精通する司法書士は、企業にとっての身近なコンサルタントとしての活躍が期待されます。法改正対応はもちろん、株主・債権者対応、法的文書の整備、株式公開支援、企業間トラブルや事業継承、企業再編への助言等、企業法務を包括的にサポートすることができます。
ひと昔前と比較すればコンプライアンスの重要性が格段に高まり、企業活動がますます複雑さを増す中、企業法務コンサルタントとしての司法書士への需要はより一層拡大するものと予想されます。
参考:日本司法書士連合会「司法書士の業務」参考:司法書士法第3条
司法書士になるには?
司法書士として仕事をするためには、まずは資格を取得する必要があります。司法書士資格を取得する方法は2つ。国家試験に合格するか、実務経験から資格を得るかです。
いずれかの方法で司法書士となる資格を得たら、管轄の司法書士会に登録を行うことで、司法書士としての業務を行うことが可能です。
司法書士試験に合格する
司法書士となるもっともポピュラーな方法が、国家試験でもある司法書士試験に合格することです。
司法書士試験は毎年7月に一次試験が行われ、10月に二次試験が行われます。一次試験が筆記試験、二次試験は口述試験となり、この双方に合格することで司法書士資格を得ることになります。
| 一次試験時間割 | 出題科目 | 出題方式 | 出題数合計 |
|---|---|---|---|
| 午前の部 |
憲法 | 多肢択一式 3問 | 多肢択一式 35問 |
| 民法 | 多肢択一式 20問 | ||
| 刑法 | 多肢択一式 3問 | ||
| 商法(含・会社法) | 多肢択一式 9問 | ||
| 午後の部 (180分間) |
民事訴訟法 | 多肢択一式 5問 | 多肢択一式 35問 |
| 民事保全法 | 多肢択一式 1問 | ||
| 民事執行法 | 多肢択一式 1問 | ||
| 司法書士法 | 多肢択一式 1問 | ||
| 供託法 | 多肢択一式 3問 | ||
| 不動産登記法 | 多肢択一式 16問 記述式 1問 |
||
| 商業登記法 | 多肢択一式 8問 記述式 1問 |
一次試験の筆記試験は上記の通り、11の科目を5時間の試験で解答していきます。筆記試験の配点は3つに分けられています。
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 午前の部 択一式試験 | 105点 |
| 午後の部 択一式試験 | 105点 |
| 午後の部 記述式試験 | 70点 |
合計280点満点の試験となりますが、科目ごとに合格基準点が設けられており、この合格基準点をすべてクリアしないと、総得点で合格ラインを超えていても足切りにあい合格することはできません。
すべての科目を平均的に学び、確実に得点する必要があります。
実務経験による認可
一定以上の実務経験があれば、口述式の試験のみで司法書士資格を得ることも可能です。以下、定められている実務経験を挙げていきましょう。
- 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官として登記、供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって、これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あった者
- 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
かなり限られた実務経験ですが、これらの経験があれば筆記試験なしで司法書士資格を得ることが可能となります。
司法書士の仕事の魅力
司法書士の仕事は、最初にご紹介した通り、「司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある」と定められています。司法書士の実際の業務、そして司法書士倫理の最初に規定されているこの言葉を考えると、司法書士の仕事の全容が見えてきます。
司法書士に相談に来る依頼者の多くは、自身の知識や経験では解決できない大きな問題を抱えており、司法書士を頼ってきているケースがほとんどです。
こういった依頼者の要望に応え、持っている法知識を使用して問題を解決することが司法書士の業務となります。目の前で困っている方に対し、最適な方法を提示しその問題を解決することができるのは仕事として大きな魅力といえるでしょう。
ただし、こういった感謝をされるような結果を導き出すのは簡単ではありません。司法書士の元に持ち込まれる案件に関して言えば、まったく同じ状況の案件というのはほぼありません。案件ごとにかかわる人やおかれた状況が違いますので、すべての案件に同じ対応というわけにはいきません。
たびたび改正、改定される法律に関する正しい知識を常に持ち続け、最適な方法を見つけ出す必要があります。単純な不動産登記の代理といっても、ひとつでも間違えれば、依頼者の財産に大きな問題を生じさせかねません。
ひとつひとつの案件は厳しいもののそれだけやりがいのある業務が多く、それだけにやり遂げた時の達成感、充実感は非常に大きい魅力的な仕事といえるでしょう。
司法書士の将来性
司法書士という仕事に関して、将来性を悲観する見方があるのは事実です。その大きな理由としては、まず司法書士の人数が増加傾向にあるということ、そして世界的に進むデジタル化の流れです。
司法書士に定年はありません。資格を持つ方個人が望めば、何歳になっても業務を行うことは可能です。毎年司法書士試験が行われ、一定数の司法書士が誕生しており、司法書士として登録している人数は増加の傾向にあります。さらに世界的に進むデジタル化が、司法書士の将来性が悲観的であるという根拠です。
しかし、司法書士の業務をしっかりと把握すれば、将来性がないというのは極論であり、そんなことはないということが分かるはず。そんな司法書士の将来性について考えてみたいと思います。
AI技術の進化で仕事がなくなる?
人工知能AIの研究は進み、多くの分野にAI技術が採用されるようになっています。AI技術がさらに進化すれば、例えば不動産登記や法人登記といった、形の決まった業務はAI技術に置き換えられる可能性は考えられます。
しかし、ことはそう簡単に進まないでしょう。確かにAI技術の進化は目覚ましいものがありますが、その分安全性という点では進化していないというのが現状です。
法人登記や不動産登記は、登記を行う方の財産にかかわる非常に重要な業務となります。この業務を安全性に不安が残るAI技術に任せることができる方がどの程度いるでしょう?AI技術が進化するということは、それと並行してAI技術を悪用する技術も進化し続けるということ。ここが大きな問題でしょう。
司法書士が自身の手で書類を作成し、その内容を登記する依頼者としっかり確認しながら進める方が依頼者の安心という点では非常に大きいでしょう。
仮に登記自体がデジタル方式となっても、その登記を行うのは当事者、もしくは代理が可能な司法書士ということになり、司法書士の業務が減ることはほぼないと考えていいのではないでしょうか。
司法書士の仕事がなくならない理由
さらに司法書士の業務は、AIなどが代行できる比較的単純なものばかりではありません。上でも少し紹介しましたが、司法書士事務所に持ち込まれる案件にはいろいろなケースがあります。
案件ごとに状況やかかわる権利関係が複雑なケースが多く、こういったケースに対処できるのはやはり司法書士ということになります。
さらに司法書士の業務のひとつである、コンサルティングや相談に関しては、まずAIで置き換えることができない業務です。
司法書士の業務は専門性が高く、同じ案件がいくつも存在しないものですので、仕事が減る、なくなるということはまず考えなくていいかと思います。むしろ、多様化が叫ばれる現代の日本を考えれば、今後司法書士が扱う業務も多様化していく可能性が高く、より優秀な司法書士が多く求められる社会となっていくでしょう。
これから司法書士を目指すのであれば
司法書士として成功するカギは、「専門分野を作ること」にあります。司法書士の業務範囲は多岐に渡りますが、特定分野に特化することで、集客や業務遂行が格段にしやすくなるからです。
まずは司法書士試験合格を目指す中で関係法令をまんべんなく学び、晴れて合格した後にはご自身の興味関心やキャリアから専門分野の絞り込みを行えると良いでしょう。「合格点主義」のフォーサイト司法書士通信講座は、忙しい受験生の短期間合格をサポートします。
まとめ
司法書士は法律の専門家であり、試験の難易度も高い難関資格です。業務の中心は法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成、および申請の代行を行うこと。特に法務局で行う不動産登記や法人登記など、登記の代理申請が中心であることが多いようです。
さらに特別研修を受け、認定司法書士となれば、簡易裁判所で行われる少額訴訟に関する相談やアドバイス、代理出廷など、弁護士同様の仕事も可能になります。
AI技術の進化で、司法書士の仕事が減少していくという見方もありますが、司法書士の取り扱う案件は個別に状況が違うものが多く、一概にAI技術で置き換えられるものではありません。
司法書士は将来的にも有望な資格であり、これから目指すという方にもおすすめの資格となります。これから司法書士を目指す方は、自身の得意分野を持つといいでしょう。司法書士の人数が増えていることは事実であり、ライバルとの違いをしっかりと持つことが司法書士として成功するコツのひとつになります。
得意な分野を見つけたら、その分野に関する法律知識をしっかりと身に着け、どのような要望にも対応できるようにしましょう。また、分野ではなく得意な業務に特化するのもおすすめ。
登記代行に特化する、遺言書の作成、執行の財産管理などに特化するなどもひとつの方法です。自身で司法書士として独立開業する前に、司法書士事務所などに就職しいろいろな業務に携わることで、得意な業務ができるかもしれません。
とはいえ得意分野を持つかどうかはまず司法書士資格を取得してから、まずは難関試験である司法書士試験に合格することを目指しましょう。







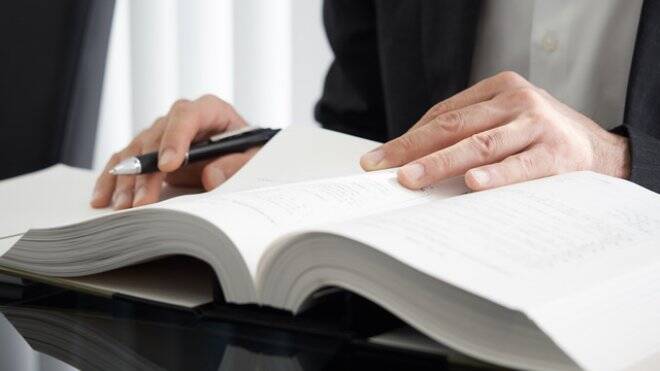
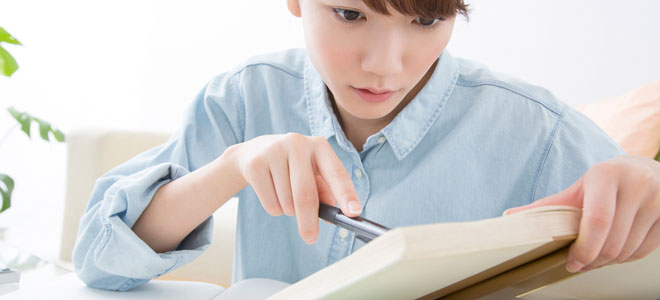


 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


