司法書士試験に合格するための勉強時間は?スケジュールや勉強法も詳しく解説
更新日:2024年1月22日
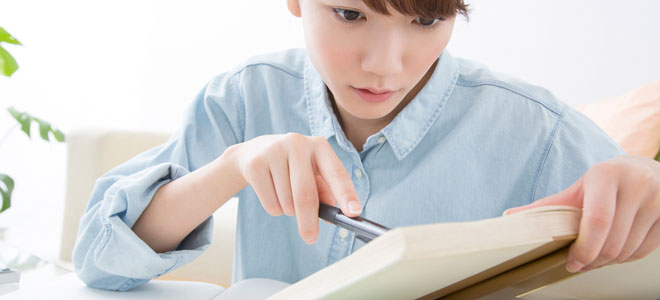
司法書士試験は非常に難易度の高い試験です。
そのため合格を目指すためには多くの勉強時間が必要な試験となります。
勉強時間が長くなるということは、よりしっかりと勉強スケジュールを立て、より効率的に学んでいくのが重要です。
では、司法書士試験に合格するためにはどの程度の勉強時間が必要なのか?勉強スケジュールとはどのように立てればいいのか?合格を目指すための効果的な勉強法はあるのか?などといった点に関して詳しく解説していきましょう。
司法書士試験に合格するためには3,000時間の勉強時間が必要
司法書士試験に合格するためには、独学でおよそ3,000時間の勉強時間が必要と言われています。
3,000時間と聞いてもどの程度の勉強時間なのか想像しにくいかもしれません。社会人の方が1日8時間労働し、週休2日であると考えて、およそ1年半の労働期間でおよそ3,000時間の労働時間となります。それと同じくらいと考えると勉強時間の長さがイメージできるかと思います。
出題科目数が11科目と非常に多い
司法書士試験に合格するために必要な勉強時間が非常に長くなる理由の一つとして、司法書士試験の出題範囲の広さが挙げられます。
司法書士試験で出題される試験科目は全部で11科目。ほかの資格試験と比較しても科目数は多く、しかもこの11科目に関してかなり細かく勉強する必要があります。
司法書士は法律問題の専門家として、顧客の相談に乗り、顧客の悩みを解消するための方法を提案する仕事です。そのため単に法律を知っているというだけではなく、状況によりどの法律とどの法律を組み合わせて考えるかといった考え方が必要となります。
単に法律を丸暗記するだけではなく、それぞれの関連性を知り、しっかりと理解しなければいけません。
そのために長い勉強時間が必要となります。
例年の合格率が3~5%という難関試験である
司法書士試験の例年の合格率は、およそ3~5%程度。資格試験の合格率としてはかなり低いレベルであり、それだけ難易度の高い試験であるといえます。
また、司法書士試験では相対評価の採点方式が採用されています。事前に合格ラインは決まっておらず、毎年受験者の上位3~5%のみが合格できる試験となっています。相対評価の試験は、目標とする点数が定まっておらず、それだけ対策が難しい試験です。
司法書士試験の詳しい難易度に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士試験の合格率についてはこちら司法書士試験合格を目指す場合の勉強スケジュール
司法試験に合格するためには、長い勉強時間が必要です。しかも単に勉強時間を確保するだけではなく、しっかりと勉強スケジュールを立てて、そのスケジュールに沿って消化していく必要があります。
では、その勉強スケジュールはどのように設定するのがいいのでしょうか。まずはどの程度の期間でスケジュールを立てるべきかについて解説していきましょう。
働きながら合格を目指すなら1年半~3年を目安に
まずは社会人として働きながら司法書士を目指す場合のスケジュール感です。毎日の家事が忙しい専業主婦(主夫)の方も、このスケジュールをイメージするといいかもしれません。
司法書士試験合格を目指す方の中にも、いろいろな方がいらっしゃるかと思います。大学で法律の勉強をした方や、実務の中で法律に馴染みがある方などは、一般的な方よりも短い勉強時間で司法書士試験の合格を目指せます。
こういったある程度知識がある方であれば1年半ほど、そうではない方は2~3年は勉強期間が必要になるでしょう。
自分の知識量を考え、3,000時間の勉強時間を確保できる勉強期間を定めましょう。
勉強に専念できる環境であれば1年~1年半での合格を目指そう
大学生の方や、求職中の方、または司法書士試験のために仕事を辞めて勉強に集中する方などは、働きながらという方よりも多くの勉強時間を確保できるかと思います。そのため司法書士試験合格のために必要な勉強期間も短くなります。
勉強期間が短くなると、集中力を持って勉強することができますので、より効率的に学べるというメリットもあります。
勉強に専念できる環境であれば、できれば1年程度の勉強期間で、長くとも1年半ほどの勉強期間で司法書士試験合格を目指せるようにスケジュールを考えましょう。
働きながら取得を目指す場合の勉強スケジュールイメージ
一般的な社会人の方が、実際に司法書士試験合格を目指す場合、どの程度の勉強期間が必要かを考えてみます。
条件として必要な勉強時間は3,000時間、仕事は週休2日で、祝日は休み、さらに年間で有給が10日与えられるという前提で計算していきます。また、休日に確保できる勉強時間は、平日の2倍という前提で計算していきます。
| 勉強期間 | 平日の勉強時間 | 休日の勉強時間 |
|---|---|---|
| 12ヶ月(1年間) | 6時間 | 12時間 |
| 18ヶ月(1年半) | 4時間 | 8時間 |
| 24ヶ月(2年間) | 3時間 | 6時間 |
| 30ヶ月(2年半) | 2.5時間 | 5時間 |
| 36ヶ月(3年間) | 2時間 | 4時間 |
上の条件で計算すると、勉強期間ごとの1日の勉強時間は上記の通りとなります。
1年半で合格できるのは一部の方のみ
まずは短期間で合格するスケジュールをイメージしてみましょう。1年間の勉強期間で司法書士試験合格を目指すためには、平日毎日6時間、休日12時間という勉強時間が必要です。これだけの勉強時間を確保できるのであれば、計算上3,000時間の勉強時間は確保できます。
しかし、一般的な社会人の方が、平日に1日6時間の勉強時間を確保するのは現実的に不可能な話。そう考えると、1年間というスケジュールで司法書士試験に合格するというのはまず不可能ということになります。
1年間というスケジュールで司法書士試験合格を目指せる方は、一定以上した知識がある方のみ。特に初学者の方などはまず1年間では合格できないでしょう。
現実的には2年以上の勉強期間を確保したい
上で紹介した表を見ると、現実的に司法書士試験合格を目指せる勉強スケジュールとなると、最低2年間といったところでしょう。
2年間のスケジュールであれば、平日3時間、休日6時間の勉強時間でクリア可能です。社会人の方にとって、平日毎日3時間というのは、厳しいところですが、平日の勉強時間を2時間にして、休日の勉強時間を8~9時間とすればクリア可能です。
これから司法書士試験を目指す方は、最低でも2年間、余裕を持つのであれば3年間ほどの勉強スケジュールを組んで勉強を始めるのがおすすめです。
司法書士試験の概要
司法書士試験の簡単な概要を紹介しておきます。
司法書士試験は年に1度の実施。試験は筆記試験と口述試験で行われ、筆記試験に合格すると口述試験を受験できるようになります。
司法書士試験に受験資格はないため、学歴や職歴に関係なく誰でも受験は可能。これから司法試験に挑戦する方は、試験日程を確認し、試験日から逆算してスケジュールを立てるようにしましょう。
司法書士試験の概要に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士試験の内容の詳細はこちら効率よく司法書士試験合格を目指すためには?
司法書士試験に合格するためには3,000時間という長い勉強時間が必要です。効率よく司法書士試験合格を目指すための考え方は2つ。ひとつは勉強の質を上げて3,000時間よりも短い勉強時間で合格する方法、もうひとつはより効率的に勉強時間を確保する方法です。
ここではこの2つの方法を実現できるような、勉強のポイントに関して紹介していきます。
勉強スケジュールを立てて実行する
勉強効率を上げる、勉強の質を上げるためには、しっかりと計画的に学ぶ必要があります。そのためにはしっかりと勉強スケジュールを考え、かつそのスケジュールを確実に消化していく必要があります。
勉強スケジュールの立て方に関しては後の項目で詳しく説明していきます。
自分に合った勉強法で効率化を図る
司法書士試験を目指す勉強方法には、自分一人で勉強する独学と、通信講座を受講する方法と、予備校に通学する方法があります。
それぞれの勉強方法には、メリットもデメリットもありますので、どの勉強方法がベストというわけではありません。これから司法書士試験を目指す方は、それぞれの勉強方法のメリットとデメリットを理解し、自分に合った勉強方法を選ぶようにしましょう。
自分に合った勉強方法で勉強することで、勉強の質を上げる、効率化することができますので、まずはどの方法で勉強するかを見定めるのが重要になります。
毎日のスキマ時間を有効活用する
社会人の方でも専業主婦(主夫)の方でも学生の方でも、毎日の生活の中には必ずスキマ時間というものがあります。
通勤や通学の電車の中や、洗濯機が回っているのを待っている時間など、ちょっとした時間がスキマ時間となります。
たかが数分、十数分といったスキマ時間でも、塵も積もれば…ではありませんが毎日続ければ大きな勉強時間になります。仮に1日30分のスキマ時間を勉強時間にできれば、1年で182時間の勉強時間となります。
毎日の生活リズムを変えずに、より多くの勉強時間を確保できる一つの方法となり、勉強スケジュールも多少なりとも楽になりますので覚えておきましょう。
インプットに偏りすぎない
司法書士試験では法律に関する問題が数多く出題されます。法律に関する勉強をするとなると、暗記をしようとする方が多くなりますが、物を覚えるにあたってはインプット同様にアウトプットしていくことが重要になります。
一度インプットした知識を、長期的に記憶するためには、その記憶をアウトプットすることが重要になります。アウトプットとは、覚えた知識に関してほかの方に言葉で説明したり、演習問題に挑戦したりすることで可能になります。
司法書士試験の勉強でのアウトプットとなると、演習問題に挑戦するのが一般的。単純にインプットするだけではなく、バランスよくアウトプットしていくことで、効率的に知識を身に着けられるようになります。
六法全書に慣れる
司法書士試験において重要な参考書は、やはり六法全書ということになります。
六法全書と聞くと非常に分厚く、また小難しい言葉が多いため、特に初学者の方はとっつきにくいかもしれません。しかし、司法書士になるためには、六法全書に慣れる必要があります。
もちろん試験の勉強でも必要ですし、司法書士として働く中でも六法全書が頼りになるというケースは多数あります。司法書士試験の勉強の段階で、六法全書に慣れておくのが重要です。
わからないことがあれば六法全書を引くという癖がつけば、六法全書に登場する独特な単語や言い回しなどにも慣れることができますので、勉強効率も上がるでしょう。
出題科目と出題割合をしっかりと把握する
まずは何より司法書士試験の出題科目と出題割合をしっかりと把握するのが先決です。当然ですが出題数が多い科目の勉強時間は多めに確保する必要があります。
この記事の序盤でも紹介しましたが、司法書士試験では11科目が出題されます。この出題科目の中で、出題の中心となるのが、「民法」、「会社法」、「不動産登記法」、「商業登記法」の4科目です。
当然ですがこの4科目は多くの勉強時間を確保する必要があります。特に民法に関してはほかの法律の基礎ともなる法律ですし、勉強範囲も非常に広くなりますので、しっかりと勉強時間を確保するようにしましょう。
試験の出題傾向をつかむ
続いては司法書士試験の出題傾向の把握です。例えば民法の問題に関しても、同じ民法の中でも頻出される項目と、そうではない項目があります。こうした出題傾向は、テキストを読み込む、過去問や演習問題に挑戦することでどんどん把握していけるでしょう。
おすすめは勉強を始める前にまずはテキストを通しで読むこと。もちろん勉強を始める前ですから、分からない点も多数あるかと思いますが、あまり気にせずドンドン読み進めましょう。
テキストを読み込むことで、司法書士試験で頻出する項目などに気づくかと思います。こうした項目が重要な項目です。
資格試験の勉強では、過去問対策は試験直前にというイメージが強いかもしれませんが、司法書士試験のような難易度の高い試験では、序盤からドンドン過去問対策を利用していくのがおすすめです。
勉強スケジュールの立て方
では司法書士試験を目指す際に重要になる勉強スケジュールの立て方に関して説明していきます。
この勉強スケジュールの考え方は、司法書士試験はもちろん、ほかの資格試験の勉強でも同じように活用できますので覚えておきましょう。
試験日から逆算して考える
具体的な勉強スケジュールを考える場合は、まずはゴール地点を設定し、そのゴール地点から逆算してスケジュールを立てます。ゴール地点とは当然司法書士試験の試験日です。
スケジュールは逆算してまずは毎月の勉強目標を立てましょう。
スケジュールを立てる場合のポイントは、緩すぎず、ハード過ぎずということ。勉強のペースに関しては個人差がありますので、どんなペースがベストというのはありません。自分の勉強ペースを把握して、自分なりのスケジュールを考えましょう。
スケジュールが緩すぎても、ハードすぎても、勉強に対するモチベーションが下がる可能性は高くなります。モチベーションを維持できるように、自分なりの勉強ペースを考えましょう。
できるだけ細かなスケジュールの落とし込む
上の要領で、毎月ごとの勉強目標を立てたら、その目標を達成するための週ごとのスケジュールを考えましょう。
週ごとのスケジュールを立てたら、今度は毎日のスケジュールに落とし込みます。勉強スケジュールはできるだけ細かく組むのがおすすめのスケジュールの立て方。
毎日の勉強スケジュールを組めれば、そのスケジュールをクリアすることで、小さいながらも達成感を感じることができます。達成感を感じることは、モチベーションの維持に役立ちますので、しっかり細かいスケジュールを立てて、確実にクリアしていくようにしましょう。
司法書士を目指すおすすめの勉強法
司法書士試験を目指す際の勉強方法は上でも紹介したように3つあります。その3つの勉強方法の中から、一般的におすすめできる勉強方法に関して紹介していきましょう。
独学で合格を目指せる方はごく一部
司法書士試験に合格するためには長い勉強時間が必要です。勉強時間が長くなるということは、勉強する期間も長くなるということ。勉強する期間が長くなれば、勉強に対するモチベーションも下がりやすくなり、モチベーションが下がれば勉強効率は下がり、より多くの勉強時間が必要になるという悪循環に陥ります。
そう考えると独学で司法書士試験合格を目指すのはかなり厳しいといえます。独学で司法書士試験に合格できる方はごく一部。特に初学者の方にはあまりおすすめできない勉強方法といえるでしょう。
予備校か通信講座がおすすめ
独学がおすすめできないということは、おすすめとなる勉強方法は通信講座か予備校ということになります。
予備校や通信講座を利用することで、勉強効率は上がり、間違いなく勉強時間は短くなります。特に初学者の方にはどちらかの勉強方法がおすすめとなります。
予備校・通信講座のメリット
予備校や通信講座を利用すると、より短い勉強時間で司法書士試験合格を目指すことができます。そんな予備校や通信講座を利用するメリットに関していくつか紹介していきます。
【共通のメリット】オリジナルテキストが手に入る
予備校にも通信講座にも、オリジナルテキストというものがあります。このオリジナルテキストがあれば勉強効率は間違いなく上がると言えます。
予備校にしても通信講座にしても、司法書士試験講座の新たな受講生を獲得することが重要。そのためには受講生の合格率というのが重要になります。受講生の合格率を上げるために、より効率的に学べるように考え抜かれているのが、オリジナルテキストということになります。
【共通のメリット】効率的な勉強スケジュールが手に入る
予備校にも通信講座にも、独自の勉強カリキュラムがあります。この勉強カリキュラムは上記のオリジナルテキストを基に作成されており、司法書士試験に合格するためにより効率的に学べるように勉強の順番や、項目ごとの勉強時間も考えられています。
独学の場合、テキスト探しもスケジュールの立案も自力ですが、その2つに労力を割く必要がなくなるのが予備校や通信講座を利用するメリットとなります。
【予備校のメリット】専門講師の授業をライブで受講できる
予備校独自のメリットとしては、専門講師の授業をライブで受講できることが挙げられます。ライブで受講できるということは、分からない部分ができたらその都度直接質問をして、問題解決することも可能ということになります。
【予備校のメリット】勉強するしかない環境に身を置ける
予備校のもうひとつのメリットは、予備校の教室で勉強ができるという点です。
予備校の教室は、自分の好きなものや趣味のものが並ぶ自宅とは違い、勉強をするしかない環境です。否が応でも勉強するしかない環境ですので、勉強に集中しやすくなります。
集中することができれば、当然勉強効率は上がりますので、これは大きなメリットとなります。
【通信講座のメリット】自宅でマイペースで学べる
通信講座独自のメリットとしては、自宅でマイペースで学べるという点。予備校の場合、決まった曜日などに通学する必要があります。しかしその曜日に急に残業が入る、お子さんの体調が悪くなるなどといったことがあれば、授業を受けることができません。
通信講座では自分で勉強ペースを決められるので、急な残業や出張、家庭の事情があっても柔軟に対応できます。
勉強スケジュールの基本的な部分はカリキュラムに沿って、細かなスケジュールは自身の事情なども加味して決めることができます。
【通信講座のメリット】日本全国どこでも高品質な授業が受けられる
通信講座の大きなメリットは、日本全国どこにいても、同じく高品質な講義が受けられるということ。
予備校の場合、自宅の近所に予備校がないと、そもそも通学ができません。そんな予備校は人口の多い都市部に集中していますので、地方部に住んでいる方はなかなか通学できませんが、通信講座はその心配がありません。
まとめ
司法書士試験は合格率が低く難易度の高い試験です。そのために必要な勉強時間は3,000時間程度必要であり、勉強時間の確保が大きな問題となります。勉強時間3,000時間と考えると、社会人の方であれば2年以上は勉強期間が必要です。
ある程度の勉強時間を確保できれば、あとはしっかりと勉強スケジュールを考え、そのスケジュールを確実にこなしていくのが重要です。
より短期間で、効率的に合格を目指すのであれば、独学にはこだわらず、予備校や通信講座を利用するのがおすすめです。








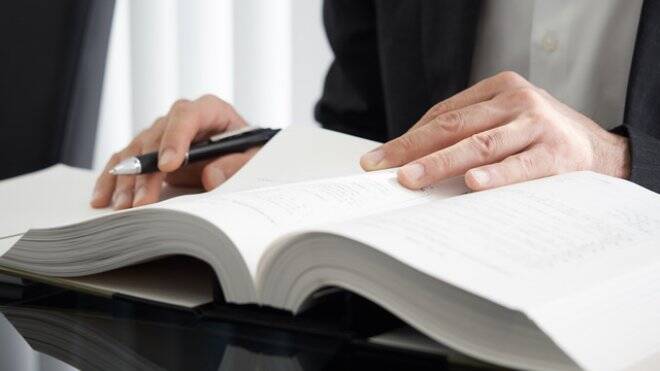


 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


