社労士試験合格に必要な勉強時間はどのくらい?受験資格から最短で合格を目指す方法を解説
更新日:2023年12月20日

社会保険労務士(以下:社労士)試験は、一般的に難関試験として知られています。
社労士試験は出題される科目が多く、それぞれに対応するには長い勉強時間が必要です。
一般的に初学者の方が社労士試験に合格するには、どの程度の勉強時間が必要になるのか?その勉強時間を確保するにはどの程度の期間が必要なのか?より効率的に勉強時間を確保するにはどうすればいいのかなど、社労士試験と勉強時間に関して解説していきます。
これから社労士試験を目指すという方は、この記事を参考に、勉強スケジュールを考えてみましょう。
- 独学で社労士試験合格に必要な勉強時間はおよそ800~1,000時間程度。
- 予備校や通信講座を使うと必要な勉強時間の目安は500~800時間程度。
- 社労士試験合格を目指すのであれば、事前に1年以上の勉強時間を確保する必要がある。
- 社労士試験の模試に関しては、毎年7月に集中して実施される傾向がありますが、この模試は必ず受験する。
フォーサイト小野賢一のご紹介
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう。そうすることで、少しずつ実力が身につきます。
社労士試験に合格することで、「なりたい自分」になれます。「なりたい自分」をめざして頑張りましょう!
社会保険労務士(社労士)試験合格に必要な勉強時間
社労士試験に合格するためには、ある程度の勉強時間が必要になります。
もちろん社労士としての実務経験がある方や、大学等で社労士試験の出題分野を勉強したことがあるという方と、社労士試験に関してまったくの初学者の方では、必要な勉強時間に差が出ますが、いずれにせよある程度まとまった勉強時間が必要であることは変わりません。
まずは、社労士試験に合格するために必要な勉強時間を、勉強方法別に紹介していきましょう。
独学の場合
自宅で自力で勉強を進める独学は、マイペースで勉強を進められる反面、もっとも勉強時間が長くなる勉強法です。
独学を選ぶ場合は、社労士としての実務経験や勉強の経験がより大きくものを言います。独学の場合、勉強をする中で分からない部分があった場合、自力で解決する必要があり、初学者の方はこうした解決に時間がかかるため、どうしても勉強時間全体も長くなってしまうからです。
独学で社労士試験合格に必要な勉強時間はおよそ800~1,000時間程度。もちろん個人差がありますので、800時間以内で合格する方もいらっしゃいますし、1,200時間勉強しても合格できないという方もいらっしゃいます。
社労士試験に合格する目安としては1,000時間程度の勉強時間を確保する必要があると考えておきましょう。
予備校や通信講座を利用する場合
予備校や通信講座を利用する場合、社労士試験合格のために必要な勉強時間は一気に短くなります。
予備校にしても通信講座にしても、社労士試験に精通した専門講師の授業を受けることができ、不明点も丁寧に解説してもらうことができるからです。
また、各予備校や通信講座で、社労士試験に合格するために必要な知識を、効率的に学べるような勉強カリキュラムがあります。このカリキュラムに沿って実力をつけていくことで、より短期間で合格を目指せるということになります。
必要な勉強時間の目安は500~800時間程度。場合によっては独学の半分程度の勉強時間で社労士試験合格を目指せると言われています。
社会保険労務士(社労士)試験の勉強はどれくらいの期間が必要?
社労士試験に合格しようと思えば、予備校や通信講座を利用しても500時間以上、独学では1,000時間近い勉強時間が必要です。
これだけの勉強時間を確保するのに、どの程度の勉強期間が必要かを計算していきたいと思います。
社労士試験の受験者データを見ると、受験者の中心となるのは社会人の方ですので、ここでは一般的な社会人の方が、これだけの勉強時間を確保するのに必要になる勉強期間を計算してみたいと思います。
一般的な社会人の生活からイメージ
一般的な平日勤務、土日祝日休みという社会人の方の、1日の生活をイメージしてみましょう。
毎朝7時に起床し、8時に出勤。夜はある程度の残業時間も加味し、20時に帰宅し、夜は1時に就寝するというケースで考えてみましょう。
朝の時間は出勤の準備で忙しいかと思いますので、このスケジュールでは勉強時間を確保するのは簡単ではありません。勉強時間を確保するとなると、夜帰宅してからということになりますが、夜帰宅してから就寝までの時間は5時間ということになります。
この5時間の間に夕食を摂り、入浴をし、家事等もこなすと考えると、現実的に勉強に充てられる時間は最大でも3時間、現実的には1~2時間といったところではないでしょうか。
土日祝日は終日勉強に充てられるというケースも考えられますが、土日祝日にはある程度予定が入るもの。家族のための時間も必要ですし、友人や恋人と過ごす時間もあるでしょう。
そう考えると、年間平均で考えた場合、土日祝日は1日5時間程度の勉強時間が現実的かと思います。むしろこれでもかなりの時間を勉強時間に割く形となるでしょう。
社労士試験に挑戦すると決めた1年間は、家族や周囲の人にも協力してもらい、できるだけ勉強時間を確保できるようにしておく必要があるでしょう。
1年以上確保するのがおすすめ
平日2時間、土日5時間というペースで勉強すると想定すると、1週間で確保できる勉強時間は20時間です。1年間は約52週間ですから、単純計算で1年間に1,040時間の勉強時間を確保できるという計算になります。
もちろん1年の間には、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み、シルバーウィークなど、大きな連休がありますので、計算以上の勉強時間が確保できる可能性はあります。
しかし、こうした連休こそプライベートの予定が入るもの。そう考えれば1年間で1,000時間という勉強時間は、社会人にとってギリギリ確保できるかどうかという時間とも考えることができます。
つまり、社労士試験合格を目指すのであれば、事前に1年以上の勉強時間を確保する必要があるということになります。
社会保険労務士(社労士)試験合格に向けての勉強スケジュールイメージ
社労士試験のように、長い勉強時間が必要となる資格試験の勉強では、勉強スケジュールをしっかりと立てるのが重要になります。
そこで、社労士試験合格のための簡単な勉強スケジュールを、勉強開始時期ごとにわけて紹介していきましょう。もちろんここで紹介するのは一例ですので、実際の勉強スケジュールは自身の都合なども踏まえて、きっちりと立案するようにしてください。
社労士試験は例年8月の下旬に行われ、年に1度の実施です。この8月下旬をゴール地点として、3つのパターンを紹介します。
【勉強期間15ヶ月程度】春に勉強をスタートさせる場合
まずは前年春に勉強を始める場合のスケジュールです。勉強期間はおよそ15ヶ月間。上で計算した勉強期間よりも余裕のあるスケジュールで挑戦する場合の勉強の進め方となります。
| 時期 | 勉強内容 | 勉強時間 |
|---|---|---|
| 前年6~9月 | 全体を通して学ぶ(1周目)
|
300時間程度 |
| 前年10~12月 | 全体を通して学ぶ(2周目)
|
250時間程度 |
| 1~3月 | 全体を通して学ぶ(3周目)
|
250時間程度 |
| 4~6月 | 全体を通して学ぶ(4周目)
|
250時間程度 |
| 7~8月 | 直前対策
|
150時間程度 |
社労士試験の出題範囲全体を通した勉強を3~4周ほどできるスケジュール。周回ごとに重点的に学ぶポイントを設定すると、より効率的に学べるでしょう。
勉強時間も1ヶ月で75時間程度と、比較的余裕のあるスケジュールですので、実現するのも難しくないかと思います。それでも全体の勉強時間は1,200時間ほど確保できますので、このスケジュールであれば独学でも十分社労士試験合格も可能となります。
また、社労士試験の模試に関しては、毎年7月に集中して実施される傾向があります。この模試は必ず受験し、最後の2ヶ月は模試の結果から判明した、自身の弱点となる部分を中心に勉強するのがおすすめ。同時に過去問対策も進め試験に備えましょう。
【勉強期間12ヶ月程度】夏に勉強をスタートさせる場合
社労士試験を目指す方が考えるスケジュールとしては、一番多いのがこのパターンではないでしょうか。毎年の社労士試験終了後に勉強をスタートさせ、翌年の社労士試験を目指すスケジュールです。
| 時期 | 勉強内容 | 勉強時間 |
|---|---|---|
| 前年9~12月 | 全体を通して学ぶ(1周目)
|
360時間程度 |
| 1~3月 | 全体を通して学ぶ(2周目)
|
270時間程度 |
| 4~6月 | 全体を通して学ぶ(3周目)
|
270時間程度 |
| 7~8月 | 直前対策
|
150時間程度 |
翌年の試験までに何とか3周分の勉強時間を確保するために、毎月90時間の勉強時間で計算しています。平日2時間、土日5時間のペースを乱さず、1年間続ける必要があります。
1周目の最後に年末年始、3周目の中盤にゴールデンウィーク、試験直前にお盆休みと大きな連休が入りますので、この連休を上手に活用して勉強を進めるようにしましょう。
この場合もやはり7月に社労士試験の模試を受験するのが推奨です。最後の2ヶ月間は弱点補強と過去問対策の期間と割り切って直前対策に集中しましょう。
【勉強期間9ヶ月程度】秋に勉強をスタートさせる場合
では勉強期間9ヶ月間で社労士試験合格を目指せるかどうかを確認してみましょう。12月に勉強をスタートし、翌年の社労士試験を目指すスケジュールです。
| 時期 | 勉強内容 | 勉強時間 |
|---|---|---|
| 前年12月~2月 | 全体を通して学ぶ(1周目)
|
300時間程度 |
| 3~6月 | 全体を通して学ぶ(2周目)
|
400時間程度 |
| 7~8月 | 直前対策
|
150時間程度 |
9ヶ月間で合格できるだけの勉強時間を確保するには、1ヶ月で100時間の勉強時間を確保して足りるかどうかというレベル。1ヶ月100時間となると、平日2時間、土日5時間の勉強時間では足りなくなりますので、より多くの勉強時間を確保する必要があります。
ここまでスケジュールを詰め込んでも、全体を勉強できるのは2周が精一杯でしょう。この2周の間にしっかり自身の弱点を把握する、試験の全体像をイメージする、過去問対策を行うなどをこなしていく必要がありますので、単に勉強時間を確保するだけではなく、集中して勉強する必要があります。
この勉強スケジュールで合格できるのは、やはりある程度社労士試験に関しての予備知識がある方や、ほかの資格試験に独学で合格した経験がある方でしょう。初学者の方にはあまりおすすめできないスケジュールです。
生活の中で勉強時間を捻出するためには
多くの社会人の方は忙しい毎日を過ごしていらっしゃるかと思います。そんな毎日の生活の中で、しっかりと勉強時間を確保するのは簡単ではありません。
また、社労士試験のように、ある程度難易度の高い試験の勉強は長期間にわたります。勉強期間が長期間にわたると、勉強に対するモチベーションは下がりやすくなり、モチベーションが下がると勉強効率も下がります。勉強効率が下がれば、当然ですが合格に必要な勉強時間も長くなってしまうという悪循環に陥ってしまいます。
この点からも長期間安定して勉強を続けるのは、非常に重要なポイントとなります。
そこで長期間安定して勉強時間を確保するためにできる方法や、勉強時間を捻出するコツに関して紹介していきましょう。
できるだけ規則正しい生活を続ける
おすすめの方法としては、毎日規則正しい生活を送るという方法があります。
毎日できるだけスケジュールを決め、そのスケジュール通りに行動することで、勉強時間もしっかり確保することができるでしょう。
また、毎日スケジュール通りに勉強を続けることで、勉強することを習慣づけることもできます。社労士試験を目指す方の中にも、勉強は得意ではない、苦手という方も多いかと思います。
こういう方こそ規則正しい生活を意識し、毎日決まった時間に机に向かうようにしましょう。勉強を習慣づけることができれば、勉強すること自体が苦ではなくなり、勉強効率もアップしていくでしょう。
スキマ時間などの有効な活用法を考える
勉強時間を、しっかりと準備を整えて机に向かう時間と考えると、1日の中でそこまで多くの勉強時間は確保できないことになります。
そこで活用したいのが毎日のスキマ時間です。1日の生活の中で、スキマ時間というのは意外と多いもの。社会人の方であれば、毎日の通勤電車に乗っている時間や、ランチ後のちょっとした休憩時間などがその代表的な例でしょう。また、主婦(主夫)の方であれば、洗濯機が回っている間の時間などもスキマ時間といえます。
こうしたスキマ時間にテキストを開く、演習問題を1問解くというだけでも勉強時間と考えることができます。
毎日の生活の中で、合計30分間のスキマ時間を見つけ、その時間を勉強時間に換えることができれば、1ヶ月で15時間、1年で182時間の勉強時間を確保できることになります。
特に勉強時間の確保が難しい社会人の方などは、このスキマ時間を有効活用するだけで、勉強が一気に進む可能性があります。
スキマ時間を上手に勉強時間に変換し、効率的に勉強を進められるように工夫しましょう。
社会保険労務士(社労士)試験は難しい?
社労士試験の難易度は、「試験範囲の広さ」と「合格率の低さ」が物語っています。労働・社会保険関連法令の主要8科目に加え、一般知識としてさらに多くの関係法令からの出題があります。
総合得点だけでなく、各科目にも合格基準点が設定されている点も、社労士試験合格が難しいとされる所以です。例年6%程の合格率からも、難易度の高さが伺えます。
関連記事:
社労士の難易度の詳細はこちら
社会保険労務士(社労士)試験は独学でも合格できる?
社労士試験の難易度の高さにも関わらず、例年独学受験生は後を絶ちません。
独学には、自分のペースで学習できる、費用を抑えることができる等のメリットはありますが、社労士試験対策として独学が適切であるかと問われれば、そうとは言えません。独学の場合、傾向学習が困難だったり、効率の悪さから対策期間が長期化したり等が考えられます。
関連記事:
社労士の勉強方法の詳細はこちら
最短で社会保険労務士(社労士)試験合格を目指すなら?
社労士試験に合格するためには1年程度の勉強期間が必要です。この勉強期間を短縮するにはどのような方法があるでしょうか。
勉強期間を短くするためには、1日の勉強時間を増やすか、全体の勉強時間を減らすしかありません。ここで紹介しているように、社会人の方にとって、これ以上勉強時間を確保するのは簡単ではありません。そう考えれば、全体の勉強時間を減らすことを考えた方が現実的でしょう。
その方法を紹介していきます。
関連記事:
社労士の勉強時間の詳細はこちら
独学よりも通信講座の利用がおすすめ
より短期間で社労士試験合格を目指すのであれば、独学にはこだわらず、通信講座を利用するのがおすすめとなります。
通信講座には、社労士試験に精通した専門講師がおり、こうした講師を中心にスタッフが最も効率の良い勉強法を考えています。そのため独学と比較すれば、はるかに効率的に勉強を進めることができ、結果勉強期間を短縮することも可能ということになります。
もちろん同じことは予備校通学にも言えます。しかし予備校に通学する場合は、ある程度デメリットがありますので、その点は理解しておく必要があります。
そんなデメリットに関しては、次の項で解説していきます。
予備校よりも通信講座をおすすめする理由
専門講師の講義を受講できる、効率的に学べるカリキュラムがあるという点では、予備校も通信講座も同じです。その中で通信講座をおすすめする理由に関しても説明しておきましょう。
予備校への通学は、効率の良い勉強方法ですが、問題は教室に通学しなければいけないという点。社会人である以上、授業がある日に急な残業が入る、出張が入る、断れない接待の予定が入るという可能性は否定できません。
予備校最大のメリットは、専門講師の授業を生で受講できることですが、そのメリットを享受できない可能性があるわけです。
さらに予備校への通学時間も問題です。この記事でも説明してきた通り、社会人の方が社労士試験合格のための勉強時間を確保するのは簡単ではありません。そんな貴重な時間を、通学時間という単なる移動時間で消費してしまうのは得策ではありません。
通信講座は自宅で受講が可能。通学時間は必要ありませんので、すべて勉強時間に充てることができますし、仕事の都合で急に忙しくなっても、マイペースで勉強を続けることができますので、社労士試験を目指す方にも最適な勉強方法といえます。
効率的に学べるフォーサイトの社労士講座
社労士試験の対策講座を開講している通信講座は数多くありますが、中でもおすすめとなるのがフォーサイトの社労士講座です。
フォーサイトの社労士講座を受講すれば、500時間程度の勉強時間で合格を目指すことも可能。上で紹介した勉強スケジュールよりも、余裕を持ったスケジュールを組んでも、十分に合格を目指せるでしょう。
フォーサイトの社労士講座をおすすめする理由をいくつか紹介しておきましょう。
専門講師が考えた効率よく学べるカリキュラム
フォーサイトには、社労士試験に精通した専門講師やスタッフが在籍しています。専門講師が講義を行ってくれるのはもちろん、スタッフとともにより効率的に学べるカリキュラムを考えています。
社労士試験は出題範囲も広く、勉強する順序や重点を置くポイントなどをしっかりと見極めないと、無駄に勉強時間を消費してしまいかねません。
また、フォーサイトの社労士講座は満点主義ではなく合格点主義でカリキュラムを組んでいます。社労士試験で合格点を取るために必要な勉強を、より効率よく進めるのが目的。不要な勉強を省いているため、より短期間での合格を目指すことが可能です。
理解しやすいテキスト
フォーサイトをおすすめするポイントのひとつに、そのカリキュラムを組む基礎となるオリジナルテキストがあります。
フォーサイトのオリジナルテキストの製作にも、社労士試験に精通した専門講師、スタッフが関わっており、より効率的に学べるようにポイントをおさえたテキストになっています。
オリジナルテキストはデザインや色遣いも工夫されており、大事な部分が一目で分かるような作りになっています。
スキマ時間を有効活用できるManaBun
フォーサイトの社労士講座には、eラーニング教材「ManaBun」がついてくるセットがあります。このManaBunには、デジタルテキストや演習問題はもちろん講義動画や講義の音声データなど、さまざまな教材が搭載されています。
通勤電車の中など、毎日のスキマ時間にも、手元にあるスマホひとつで勉強をすすめられるため、勉強時間の確保がしやすくなるでしょう。
さらにManaBunには自動スケジュール機能も搭載。毎日の自分の生活スケジュールを登録すると、勉強に充てられる時間をManaBunが自動で見極めスケジュールを組んでくれます。自分では気づきにくいスキマ時間をしっかりと勉強時間として活用できるため、より効率的に勉強が進められます。
分かりやすいテキストに専門講師の講義、さらにスキマ時間を有効できるeラーニング教材で、より短期間での合格が目指せるのがフォーサイトの社労士講座です。
フォーサイト 社会保険労務士講座まとめ
社労士試験に独学で合格するためには、800~1,000時間の勉強時間が必要と言われています。一般的な社会人の生活を考えると、1,000時間の勉強時間を確保するのに、1年間ほどの勉強期間が必要になるでしょう。
勉強期間が長期間になると、勉強に対するモチベーションは落ちやすくなり、勉強効率は下がり、勉強効率が下がるとより多くの勉強時間が必要になるという悪循環に陥りかねません。
より短期間での合格を目指すのであれば、独学にはこだわらず、通信講座の受講がおすすめ。マイペースで勉強を進められる上に、効率的に学べるカリキュラムも手に入りますので、独学よりも短い勉強時間で合格が目指せるでしょう。
通信講座の中では、テキストやeラーニング教材が充実しているフォーサイトの社労士講座がおすすめ。eラーニング教材ManaBunを有効活用すれば、より短い勉強時間での合格も可能。具体的には500時間程度の勉強時間でも合格を目指すことができます。
500時間の勉強時間は、社会人の方でも半年あればクリアできる勉強時間。余裕を持ったスケジュールを組んでも、8~9ヶ月程度の勉強期間で合格を目指せるでしょう。
小野賢一(おの けんいち)
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師




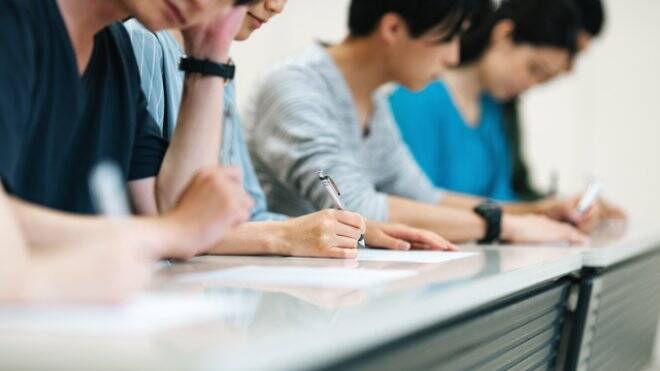

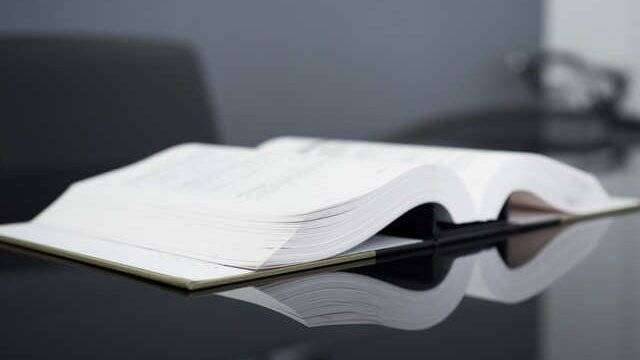









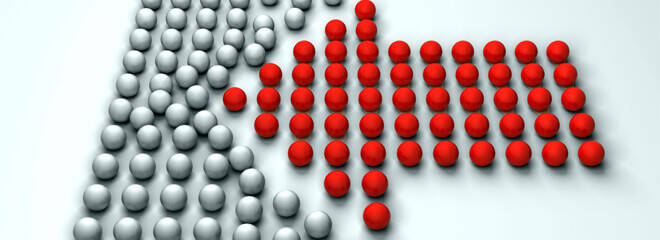
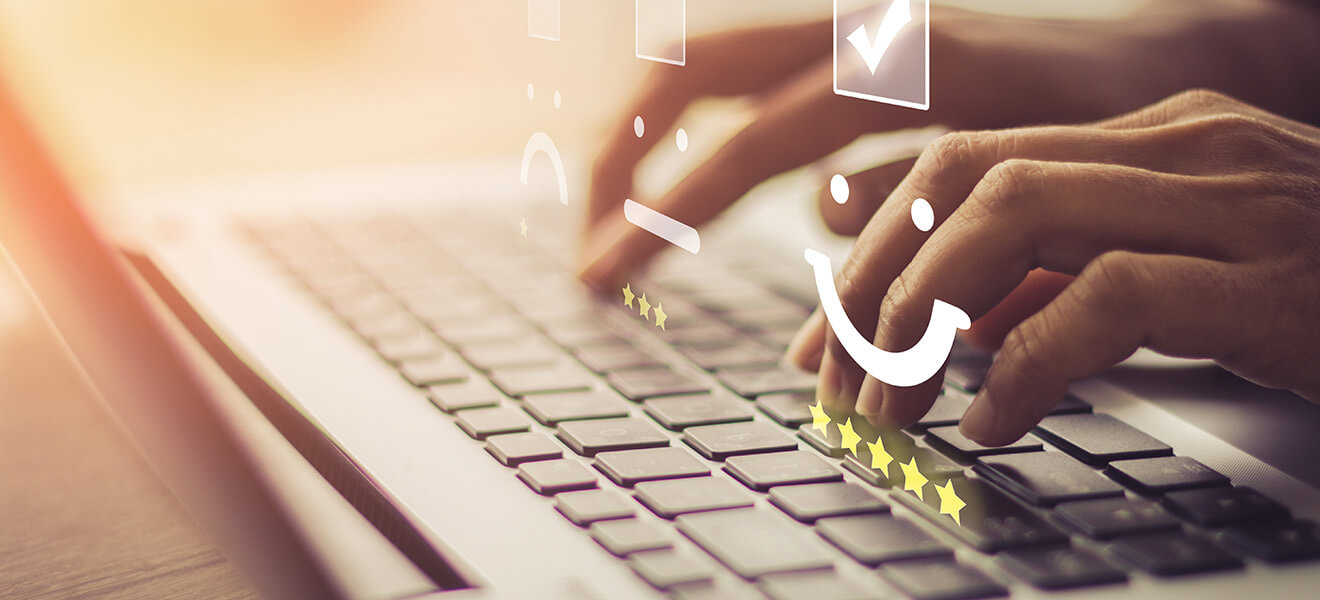





 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


