保育士の給料事情は?2023年の最新情報
更新日:2024年1月22日

特に都市部においては依然保育士不足が問題となっています。
両親が共働きをしたくとも、保育士が少ないため保育園に空きがなく、子供が預けられないという状況は完全に解消されているわけではありません。
そんな不足が叫ばれる保育士の給料は現状どのような状況なのか。この記事では保育士の給料の現状や、近年の傾向、さらに給料をアップするための方法などをまとめていきたいと思います。
保育士の給料の現状は?
不足が叫ばれる保育士ですが、その給料の実体はどのようになっているのか。参考に厚生労働省が発表する「令和4年度賃金構造基本統計調査」の結果から保育士の給料をチェックしてみましょう。
参考に幼稚園教諭の給料も併せて紹介します。
| きまって支給する 現金給与額 |
年間賞与その他 特別給与額 |
年収 | |
|---|---|---|---|
| 保育士 | 266,800円 | 712,100円 | 3,913,700円 |
| 幼稚園教諭 | 267,400円 | 785,900円 | 3,994,700円 |
保育士と幼稚園教諭の給料を比較するとほぼ同レベル。ボーナスの部分で多少の差があるとはいえ、年収としてもほぼ同等ということができます。
保育士と幼稚園教諭は給料面では同等ですが、ニュースで目にするのは保育士不足であり、幼稚園教諭の不足というニュースは聞きません。
これは単純に保育園の需要が増えているというのが理由です。かつては結婚した女性が家に入り、専業主婦となるケースが多かったこともあり、こどもを幼稚園に通わせる親が多かったと考えられます。
しかし近年では長引く不景気の影響や、時代背景もあり両親が共働きという家庭が増えています。そのために求められるのが保育園。そして保育士ということでしょう。
給与所得者全体との比較
同じく「令和4年度賃金構造基本統計調査」から、給料を取得している方全体の平均給料と、保育士に多い女性の平均給料に関して調べてみました。
| きまって支給する 現金給与額 |
年間賞与その他 特別給与額 |
年収 | |
|---|---|---|---|
| 女性のみ | 251,800円 | 628,400円 | 3,650,000円 |
| 男女計 | 307,700円 | 905,700円 | 4,598,100円 |
男女計の平均給料、および平均年収をみると保育士よりも給料で4万円ほど、年収で70万円ほど高いというデータとなっています。
女性の平均給料と比較すると給料で1万円ほど、年収で25万円ほど保育士の方が高いというデータになっています。
保育士不足のニュースを見ると、待遇面の問題も取り上げられていますが、給料という点ではそこまで安いということはありません。保育士不足の問題は、保育士の数が少なく、保育士一人が請け負う業務が膨大になっているのが問題なのかもしれません。業務が大変な割には給料が安いというのが問題なのでしょう。
保育士の給料の傾向
保育士の給料に関して、さらに詳しい状況を知るために、詳細なデータからいくつかの傾向をチェックしていきたいと思います。
過去5年の保育士平均給料の推移
まずは近年の保育士の給料に関する情報です。近年の保育士の給料の推移を知るために、各年度の賃金構造基本統計調査から各年度の保育士の給料をチェックしましょう。
| 年度 | きまって支給する 現金給与額 |
年間賞与その他 特別給与額 |
年収 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 241,000円 | 700,300円 | 3,592,300円 |
| 2019年 | 246,000円 | 695,200円 | 3,647,200円 |
| 2020年 | 249,800円 | 747,400円 | 3,745,000円 |
| 2021年 | 256,500円 | 744,000円 | 3,822,000円 |
| 2022年 | 266,800円 | 712,100円 | 3,913,700円 |
過去5年で保育士の毎月の給料は25,000円ほどアップ。年収では30万円ほど上がっており、給料は上昇傾向ということができます。
2018年の給料所得者全体の平均年収が約440万円ですから、給料所得者全体の年収は、この5年で約20万円アップしています。それと比較しても保育士の給料アップ率は高く、ほかの職業と比較しても給料のアップ幅は大きいといえます。
保育士の給料のアップ率が高い理由の一つとして、国としての政策があります。2020年には保育士不足解消のための施策として「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」の制度が導入され、2021年には給料が7,000円ほどアップしています。
地域別の保育士の給料傾向
保育士不足のニュースで取り上げられるのは、人口の多い都市部が中心です。人口が減少傾向の地方部では、待機児童もなく、保育士が不足しているというニュースもあまり聞きません。
そこで都道府県別の保育士の給料をチェックしてみたいと思います。チェックするのは日本国内で三大都市とされる東京都、大阪府、愛知県と、2021年度の出生率データから出生率が高かった宮崎県、島根県、沖縄県という3つの県。
この6都府県の保育士の平均給料をチェックしてみましょう。
| 都道府県 | 2021年度 出生率 |
きまって支給する 現金給与額 |
年間賞与その他 特別給与額 |
年収 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1.13 | 302,000円 | 884,300円 | 4,508,300円 |
| 大阪府 | 1.43 | 291,400円 | 747,400円 | 4,244,200円 |
| 愛知県 | 1.30 | 254,300円 | 633,800円 | 3,685,400円 |
| 宮崎県 | 1.69 | 243,200円 | 786,000円 | 3,704,400円 |
| 島根県 | 1.68 | 226,100円 | 785,600円 | 3,498,800円 | 沖縄県 | 1.86 | 228,100円 | 350,200円 | 3,087,400円 |
各都府県の平均給料を見ると、全般的に都市部の方が給料は高い傾向にあります。都市部はそもそもどんな職業でも給料は高い傾向にある上、特に保育士が不足しているため、給料が高くなっていると思われます。
同じ保育士として働くのであれば、より都会に近い地域の方が、給料は高くなるということになります。
保育士の初任給は?
続いては保育士の初任給に関してチェックしていきましょう。賃金構造基本統計調査から「経験年数0年」の平均給料を紹介しておきましょう。
| きまって支給する 現金給与額 |
年間賞与その他 特別給与額 |
年収 | |
|---|---|---|---|
| 経験年数0年 | 219,400円 | 46,800円 | 2,679,600円 |
経験年数0年ということで、いわゆるボーナスがほとんど支給されないため、年収は低くなりますが、毎月の給料は22万円程度ということになります。
続いて給料所得者全体の平均初任給をチェックしましょう。
| きまって支給する 現金給与額 |
年間賞与その他 特別給与額 |
年収 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 220,800円 | 25,800円 | 2,675,400円 |
| 女性 | 216,500円 | 27,800円 | 2,625,800円 |
| 男女計 | 218,600円 | 26,800円 | 2,650,000円 |
初任給を比較すると、保育士の初任給は給料取得者全体の平均とほぼ同等ということになります。
実際の初任給は?
実際の初任給をネット記事などで調べてみると、おおよそ17万円程度というのが目立ちます。これは恐らく手取りの金額。初任給の額面金額が22万円の場合、手取りは約17万円となります。
一見安そうに感じるかもしれませんが、給料所得者全体の平均も同程度ですので、特別保育士の初任給が安いということはないようです。
保育士の勤続年数による給料のアップ率は?
続いて保育士として働いていく中で、どのように給料がアップしていくのかを見るため、年代別の平均給料をチェックしていきます。
| 平均 勤続年数 |
きまって支給する 現金給与額 |
年間賞与その他 特別給与額 |
年収 | |
|---|---|---|---|---|
| 20~24歳 | 2.0年 | 230,800円 | 474,100円 | 3,243,700円 |
| 25~29歳 | 4.8年 | 248,200円 | 684,600円 | 3,663,000円 |
| 30~34歳 | 7.3年 | 258,800円 | 666,400円 | 3,772,000円 |
| 35~39歳 | 9.4年 | 270,800円 | 764,200円 | 4,013,800円 |
| 50~54歳 | 12.2年 | 287,900円 | 800,700円 | 4,255,500円 |
| 55~59歳 | 14.3年 | 289,300円 | 709,500円 | 4,181,100円 |
| 65~69歳 | 18.2年 | 273,400円 | 660,000円 | 3,940,800円 |
保育士の平均給料も、ほかの一般的な職業同様に、年代が上がるごとに、経験年数が長くなるごとに上がる傾向にあります。同じ職場で継続して勤務することで、給料はアップしていくでしょう。
ただし、保育士という職業は女性の方が多い傾向があります。女性の方は出産や育児という人生における大きなイベントもあり、継続して働き続けるというのが難しいというのも事実。実際上の表の平均勤続年数の数字を見ても、50代前半でも平均勤続年数は12.2年とさほど長くありません。
特に女性の保育士の方は、勤続年数による給料アップというのは難しいといえるかもしれません。
保育士の給料に影響する要因
保育士の給料に影響するのは、年齢や勤続年数だけではありません。そんな保育士の給料に影響を与える要因に関していくつか紹介していきたいと思います。
主に給料をアップさせるポイントを紹介していきましょう。
所有している資格
まず、最初に知っておくべきことは、保育士として働く場合、保育士資格は取得必須ではないということです。正確には保育士資格がない場合、「保育補助」として働くことになるのですが、一般的には保育士も保育補助もまとめて「保育士」と認識されます。
もちろん保育士という資格がある以上、保育士にはできて、保育補助にはでない業務がありますので、給料という面では保育士の資格を持っている方が高くなるでしょう。
さらに保育士の仕事で活用できる資格はほかにもあります。医療保育専門士や、絵本専門士などの資格を併せ持つことでも給料アップを望めるでしょう。
勤務形態
保育士には女性が多く、その中には育児中という方も少なくありません。保育士として働きたいものの、常勤は難しいという方も多いかと思います。
そのため保育士にはいろいろな働き方があり、常勤保育士以外に非常勤保育士、パート、アルバイトといった働き方があります。
当然ですが常勤保育士の方が給料自体は高くなります。より給料アップを目指す方は、常勤保育士として働けるように、就職活動を頑張りましょう。
勤務地域
上で少し説明した通り、地方部よりも都市部の方が給料は高い傾向にあります。これは都道府県単位だけの話ではなく、同一の都道府県内でも同様です。
同じ都道府県内でも、人口の多い中心部の方が保育士の給料は高い傾向にあり、人口の少ない地方部の方が給料は安くなるかと思います。
保育士として、より高い給料で働くことを希望するのであれば、今住んでいる所から通える範囲で、できるだけ人口の多い都市部で就職するようにしましょう。
同じ施設における勤続年数
これは上でも説明した通りで、勤続年数が長くなれば給料もアップする傾向にあります。つまり保育士として転職をするより、同じ施設で働き続けた方が給料アップを期待できるということ。
ただしこれは一概に給料をアップさせる方法とも言い切れない部分があります。私立の保育園に関しては、施設ごとに給料も昇給ペースも違います。ほかの施設に転職した方が給料はアップする可能性があります。
また公立保育園で働く場合は、同じ施設で働き続けると給料が上がるというわけではありません。このあたりに関しては後に解説していきます。
役職
保育士の中にも当然ですが役職があり、役職が就くことで給料がアップすることもあります。いわゆる役職手当というもので、基本的には上で紹介した勤続年数と関係する給料アップの方法といえるでしょう。
ただし役職がつくかわりに残業代が支給されなくなるというケースもあり、給料は上がっても、年収は大きく変わらないなどといったケースもありますので、このあたりは勤務先次第ということになります。
私立と公立による違い
上でも少し触れましたが、保育園には私立と公立があります。また、私立と公立で給料の傾向も違いますので、事前によくチェックしてどちらで働くかを考えた方がいいでしょう。
実際に私立と公立で給料にどのような違いがあるかに関しては、次の項で詳しく紹介します。
私立保育園と公立保育園はどちらが給料が高い?
ここからは私立保育園と公立保育園での給料の違いを解説していきます。どちらが給料が高いのか、どちらで働く方が有利なのかなど、私立と公立における給料の違いを解説していきましょう。
公立保育士は公務員
公立保育園で働く保育士は、公務員として働く形になります。つまり、保育士資格を取得した上で、公務員試験を受験し、合格する必要があるわけです。
公立保育園の保育士の給料に関しては、公務員としての給料となりますので、原則としては一般的なサラリーマンよりも若干安い給料設定と考えて間違いありません。
公立保育園で保育士として働くメリットは、勤続年数によってきっちり年次昇給を期待できることです。扱いは公務員ですから、昇給は確実に行われます。また、公務員ですので、倒産するということもありません。
長く働くという点ではメリットが大きい公立保育士ですが、いくつか懸念すべきポイントもあります。そのひとつが異動に関して。公立保育士は公務員のため、同一自治体内で定期的に異動が発生します。異動により通勤が大変になるケースもありますし、新たな職場でまた新たに人間関係を構築する必要もあります。
もちろん異動して勤務する施設が変わっても、公務員としての勤続年数は変わりませんし、異動により給料が下がるということはありませんので、給料という面では大きな問題ではありません。とはいえ定期的な異動が得意ではないという方は働きにくいかもしれません。
もうひとつは募集人員に関して。特に地方部など、公立の保育士に余裕がある自治体の場合、保育士として公務員試験に合格しても、働く場所がないというケースもあります。また保育園ではなく、児童福祉施設などで働くケースもありますので、この点は覚えておきましょう。
長く働くことができれば、生涯年収という点では私立保育園を超えるケースが多いのが公立保育士の特徴です。
私立保育園は施設次第
私立保育園で働く保育士の場合、給料はその施設次第ということになります。一般的に同じ年代、同じ勤務年数の公立保育士と比較した場合、より給料が高いのは私立保育士となります。
給料は安いものの、私立保育園を経営しているのは学校法人など民間企業になりますので、昇給ペースは安定しない傾向にあります。また、経営母体の経営状況次第では当然閉園や倒産ということも考えられるため、安心して働けるかどうかを見極めなければいけません。
比較的短期間働くのであれば私立保育園の方が給料は高くなる傾向にありますが、長期間保育士として働き続けるのであれば公立保育園の方が有利。ただし、公立保育園で働くためには公務員試験を受験する必要があり、その公務員試験には年齢制限がありますので、このあたりも考慮する必要があるでしょう。
特別高収入の保育士はいない?
保育士の資格を持ち、保育士として働く方の中で、特別高収入の方がいるかと言えば実は高収入の保育士というのはほとんどいません。高収入の保育士がいないのは、国としての規定が原因となっています。
そんな国の規定に関して解説していきましょう。
保育園に存在する「公定価格」
保育園の運営費に関しては、国からも公費が投入されています。保育園としての収入は原則保護者からの保育料ですが、その保育料があまり高くなりすぎないように、国が補助しているということです。
つまり、一般的な保育園の収入は、保護者からの保育料とこの公費ということになり、この2つの合計を「公定価格」と呼びます。
国が規定するこの公定価格は毎年決められており、国からの公費は公定価格から保育料を差し引いた金額ということになります。
保育園としての純粋な収入アップは保育料のアップですが、保育料がアップすれば公費が減少しますので、結果的に保育園としての収益はアップしないということになります。
特別高収入な保育士がほとんどいないというのは、保育園の収益がほぼ安定しており、特別儲けの大きい保育園がないというのが大きな原因となります。
保育士が給料アップを目指すポイント
ここまで保育士の給料の現状や、給料が決まる仕組み、さらに勤務先により給料の違いなどを解説してきました。これらの情報を踏まえた上で、現実としてこれから保育士を目指す方、すでに保育士として働いている方が、より給料アップを目指す方法を考えてみましょう。
まずは何より保育士資格の取得
これから保育士として働くことを目指す方は、まずは保育士資格を取得しましょう。保育士として給料アップを目指す、またより働くチャンスを増やすといった意味でも保育士資格の取得は重要なポイントとなります。
すでに保育士(保育助手)として働いている方も、これから保育士として働いていくのであれば、保育士資格の所得を目指しましょう。
保育士資格の取得には、受験資格が必要です。受験資格は学歴や実務経験などが必要になりますので、必要な条件を満たせるように準備しておきましょう。
公立か私立かを選択する
保育士資格を取得し、保育士として働くことを目指す場合、まずは公立か私立かを選ぶ必要があります。
あくまでも給料という面で考えた場合、長期間働くのであれば公立、短期間働くというのであれば私立の方が有利になるという基本を理解した上で、どちらで働くかを考える必要があります。
公立保育士を目指すのであれば、公務員試験を受験する必要があります。公務員試験の受験には年齢制限がありますので、注意が必要です。
保育士以外の資格を取得
保育士として働き始めたら、基本的に勤続年数が長くなるほど給料も上がる傾向にあります。勤続年数だけではなく、ほかの要素でも給料アップを目指したいという場合は、保育士資格以外にも保育の現場で役立つ資格を取得しましょう。
どんな資格で給料アップができるのかは、働いている施設が設定している資格手当や、勤務している中で必要なものを見極めて考えるといいでしょう。
勤務施設内で昇進を目指す
特に私立保育園に勤務する場合は、その施設内で昇進を目指すのも給料アップに繋がります。もちろんそのためには勤務年数も重要ですし、勤務先での働き方も重要になります。
昇進に伴い役職がつくことで給料もアップしていくでしょう。
給料の高い施設に転職する
特に私立保育園に関しては、施設によって給料にも差があります。より給料の良い施設に転職するというのも給料アップのひとつの方法です。
私立保育園ごとの給料に関しては、転職情報などをチェックするしかありませんが、今勤務している保育園の給料が安いと感じている場合は、ほかの施設を探すのもいいでしょう。
もちろん転職にはリスクもあります。希望した転職先に必ず就職できるというわけではありませんので、慎重に考えるのがおすすめです。
まとめ
2022年度の統計データによると、保育士の平均年収は390万円程度。給与所得者全体の平均と比較すると低めではありますが、女性の平均年収と比較すればやや高いという結果になっています。
2022年時点では、上記のような傾向ですが、保育士の給料は近年上昇傾向にあり、給与所得者全体の上昇率と比較してもさらに優秀な上昇率を示しています。
保育士不足は国としても大きな問題となっていますので、国が保育士の待遇改善のための制度を導入しているのも大きな要因のひとつ。今後も保育士の待遇が改善されないようであれば、さらに新たな制度の導入もあるかもしれません。
保育士としてより高い給料で働くためには、なんといっても保育士資格の取得が重要なポイントとなります。保育士資格の受験には受験資格が必要ですので、自身がクリアできる条件を見つけて保育士資格を取得しましょう。
保育士として働く中で給料アップを目指すのであれば、働き方も重要なポイント。特に公立で働くか、私立で働くかは大きなポイントとなりますので、労働条件や給料の特徴などを把握した上でどちらで働くかを決めるといいでしょう。








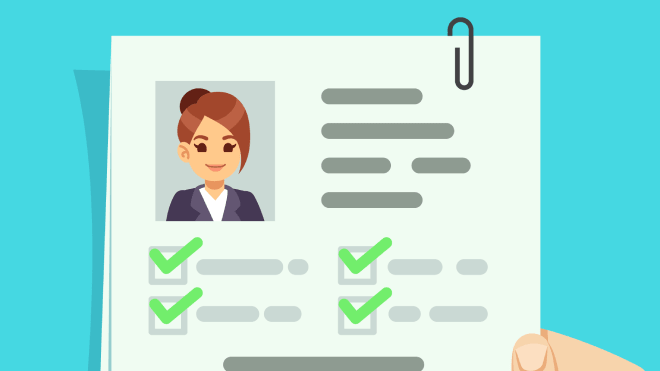
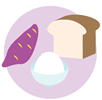




 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


