保育士試験は年に2回!受験資格は必要?
更新日:2024年1月22日

保育士として働くためには、保育士試験に合格し、保育士資格を取得するのがおすすめです。
ではその保育士試験とはどんな内容の試験なのでしょうか?
保育士試験の合格率や試験内容はもちろん、受験資格や受験料、試験会場、さらに試験対策の勉強方法など、保育士試験に関する細かな部分までまとめて解説していきたいと思います。
保育士試験概要
保育士として働く場合は、保育士資格があるとより働きやすくなります。そのためにもまずは保育士試験に合格する必要があります。そんな保育士試験の内容・概要に関して解説しておきましょう。
保育士試験の実施タイミングから、試験科目の内容まで細かく説明していきます。
保育士試験の試験内容をしっかりと把握し、受験準備を進めましょう。
保育士試験は年に2度実施
保育士試験は2023年現在、1年に2度の実施となっています。2014年以前は年に1度の実施でしたが、保育士不足が社会問題になったことから、保育士の絶対数を増やすために2015年度から年に2度の実施になっています。
保育士を増やすといっても試験内容が変わったり、試験の難易度が下がったりということはありません。試験対策はしっかりと行う必要があります。
日程の参考として、2023年度試験の日程を確認しておきましょう。
2023年度 保育士試験 試験日程 |
||
|---|---|---|
| 筆記試験 | 実技試験 | |
| 前期試験 | 4月22日(土)・23日(日) | 7月2日(日) |
| 後期試験 | 10月21日(土)・22日(日) | 12月10日(日) |
試験は前期試験と後期試験に分けられ、前期試験は4・7月に実施、後期試験は10・12月に実施されます。
もちろん試験の難易度や内容に関しては同じ試験となりますので、どちらのタイミングで受験しても差はありません。
試験は筆記試験と実技試験
上の表を見てもらっても分かる通り、保育士試験はマークシート方式の筆記試験と実技試験で行われます。マークシート方式の筆記試験に合格すると実技試験を受験できるようになりますので、イメージとしては筆記試験が一次試験、実技試験が二次試験となります。
筆記試験には受験科目免除の制度もありますので、科目免除制度の詳細に関しては、全国保育士養成協議会のHPでその内容を確認しておきましょう。
試験内容などの詳細はこの後の項で解説しますが、まずは筆記試験合格を目指しましょう。
保育士試験の申し込み方法は2種類
保育士試験の受験申し込みの方法は、全国保育士養成協議会のHPからオンラインで申し込む方法と、受験案内を入手し、郵送で申し込む方法の2種類です。
オンラインで申し込む場合は、まずはマイページ登録を行いましょう。その後、試験概要で試験の内容をきちんと確認してから、申し込み専用フォームから顔写真や証明書類などをアップロードして、必要事項を入力すれば申し込み手続きは完了です。
郵送申し込みの場合、まずは受験案内を郵送で請求します。受験案内には受験申込書が同封されていますので、その申込書に必要事項を記入します。
受験料の払い込みが完了したら、その払い込み証明書や証明書類なども同封し、簡易書留で郵送すれば申し込み手続きは完了となります。
どちらの方法でも申し込みは可能ですが、時間がかからないのはオンライン申し込み。郵送申し込みは受験案内の手配から申し込みまでそれなりの日数がかかりますが、オンライン申し込みであれば、必要書類さえ揃っていれば15~20分程度で申し込みが完了します。
また、オンライン申し込みを利用すると、受験申し込みに関する各種手数料の一部を節約することができますし、試験後には試験結果もオンライン上で確認できるようになります。
オンライン環境が整っている方は、オンラインで申し込むのがおすすめです。
保育士試験の受験料
保育士試験の受験料は12,700円です。当然ですが申し込み方法によってこの金額が変わるということはありません。金額は変わりませんが、納付方法は申し込み方法で変わってきますので注意しましょう。
オンライン申し込みの場合、受験料の納付方法はクレジットカードかコンビニエンスストア払いになります。クレジットカード払いの場合、オンライン申請の際に同時にクレジット決済を行い、承認されればその場で納付完了。オンライン申請の完了と同時に受験申し込みも完了します。
コンビニエンスストア払いの場合、一度受験申請が完了してから、指定された期日までにコンビニエンスストアで納付を行います。納付機関に関しては、メールで細かな内容が送られてきますので、メールを受信できるように設定しておきましょう。
受験料の納付が確認されれば、申し込み完了メールが届きます。
郵送申し込みの場合は、受験申込書や必要書類とともに納付証明書を同封する必要があります。
郵送申し込みの受験料納付に関しては1点注意すべきポイントがあります。納付はゆうちょ銀行のみとなりますが、納付は必ず窓口で行うようにしてください。受験案内書に同封されている受験料の払い込み用紙を使用すれば、ゆうちょ銀行のATMでも納付自体はできますが、ATMでは納付の証明書が発行されません。
納付証明書がないと受験の申し込みはできず、もちろん納付した受験料も無駄になってしまいます。必ず郵便局の窓口での手続きを行い、納付証明書を発行してもらうようにしましょう。
保育士試験の試験会場
保育士試験の試験会場は、47都道府県すべてに設置され、人口が多い都道府県や、面積の広い都道府県、離島がある都道府県に関しては、同一都道府県内に複数の試験会場が設置されます。
自身が住んでいる都道府県以外でも受験は可能ですが、受験資格に関して、都道府県知事の認定を受けている資格で受験する場合、認定されている都道府県でしか受験できません。
ほかの都道府県で受験する場合は、受験する都道府県知事の認定を改めて受ける必要がありますので、あらかじめ自身の受験資格の内容はきちんと把握しておきましょう。
筆記試験と実技試験に関しては、同一の都道府県で受験をしなければいけません。筆記試験を東京都で、実技試験を神奈川県でという受験はできませんのでご注意ください。
もうひとつ注意すべきは、複数試験会場が設置される都道府県では、原則試験会場までは選択できないという点。東京都や大阪府など、複数の試験会場が設置される都道府県では、どの会場での受験になるかは、申し込み後の結果次第となります。
試験会場が選べるのは、面積の広い北海道と、離島にも会場が設置される沖縄県のみとなります。
保育士試験の筆記試験に関して
ここからは保育士試験のさらに詳しい試験内容や合格基準点に関して紹介していきます。まずは筆記試験の試験内容と合格基準点の内容に関してです。
試験はすべてマークシート方式
筆記試験はすべてマークシート方式で行われます。出題形式は〇×を選ぶ二択方式や、正しい選択肢を選ぶ択一式などいろいろな形式となります。
マークシート方式ですから、問題内容が理解できなくても、勘で正解できる可能性はありますが、保育士試験の筆記試験は出題数が多く、勘だけでは当然合格はできません。とはいえ、分からないといって白紙で提出するのは意味がありませんので、必ず解答を埋めて提出するようにしましょう。
試験問題の内容に関しては、各科目における基本的な要素である場合がほとんどです。また、試験の出題内容に関しては傾向もありますので、過去問やテキストを見て、重点的に学ぶべきポイントを見極めて効率的に勉強するのがおすすめです。
試験科目は9科目800点満点
保育士試験の筆記試験の出題科目は全部で9科目、800点満点となります。
| 試験日 | 試験時間 | 出題科目 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(土) | 11:00~12:00(60分) | 保育の心理学 | 100点 |
| 13:00~14:00(60分) | 保育原理 | 100点 | |
| 14:30~15:30(60分) | 子ども家庭福祉 | 100点 | |
| 16:00~17:00(60分) | 社会福祉 | 100点 | |
| 10月22日(日) | 10:00~10:30(30分) | 教育原理 | 50点 |
| 11:00~11:30(30分) | 社会的養護 | 50点 | |
| 12:00~13:00(60分) | 子どもの保健 | 100点 | |
| 14:00~15:00(60分) | 子どもの食と栄養 | 100点 | |
| 15:30~16:30(60分) | 保育実習理論 | 100点 |
上の表が2023年度後期試験のスケジュールです。筆記試験は2日間で行われます。
各科目の出題内容に関しては、そこまで複雑な出題はありません。基本的な内容が問われる問題が多いのが特徴です。それぞれの科目において、ポイントとなる部分を把握しておけば、十分対応できる内容となっています。
合格基準点は各科目60点以上
保育士試験の合格基準点は各科目60点以上です。「教育原理」と「社会的養護」の科目に関しては、それぞれ30点以上の得点が必要です。
筆記試験は800点満点となりますので、各科目60点以上かつ総得点480点以上で合格ということになります。
試験科目が多い試験ですが、それぞれの科目の出題傾向や、その科目で問われる内容を把握しておけば、十分に対応できる試験ですので、科目の出題傾向や出題内容を把握して、しっかりと対策を行いましょう。
科目別合格の制度と免除期間の延長
保育士試験の筆記試験には科目別合格の制度があります。
科目別合格の内容は、全科目で60点以上が取れなくても、60点以上取れた科目に関しては科目別合格となり、合格した年度を含めて以降3年間は受験免除となります。
「教育原理」と「社会的養護」の科目に関しては、同一年度に同時に30点以上を取得するのが条件となります。
科目別合格の免除期間に関しては、指定された施設での実務経験によって、免除期間が最長5年間に延長される制度があります。合格期間延長を希望する場合は、全国保育士養成協議会のHPで、免除期間延長に関する条件の内容を確認しておくといいでしょう。
保育士試験には、科目別の合格制度に加え、筆記試験の部分合格制度もあります。筆記試験全科目に合格すれば、合格した年度も含めて3年間は筆記試験自体が免除となります。
筆記試験の試験内容を確認し、一度の挑戦では合格は難しいと感じた方は、出題内容から合格できそうな科目に絞って、科目別合格を目指すのも一つの方法となります。
ただし、受験科目が少ないからと言って、受験料が安くなることはありませんのでご注意ください。
保育士試験の実技試験に関して
保育士試験の筆記試験に合格すると、実技試験を受験することができます。その実技試験は3科目。この3科目の内2科目を選択して受験し、合格する必要があります。
まずは実技試験の3科目の内容に関して紹介していきましょう。
音楽に関する技術
音楽に関する技術の科目の試験内容は、弾き語りです。ただの弾き語りではなく、保育園児に聴かせることを目的とした弾き語りになっているかどうかが審査されます。
使用できる楽器はピアノ、アコーディオン、ギターの3種類。この中から得意な楽器を選び、楽曲を演奏しながら歌う試験です。
課題曲は2曲で、試験公示の時点で発表されますが、発表されるのは曲名とコード進行のみ。実際の試験では自分なりにアレンジして演奏しながら歌う形となります。このアレンジの内容に関しても審査の対象となります。
課題曲の内容をイメージし、より園児たちが興味を持つようなアレンジを考えて試験に挑みましょう。
造形に関する技術
造形に関する技術の試験内容は、絵を描く試験となります。
絵のテーマは「保育の状況をイメージした絵」となりますが、具体的な内容に関しては試験当日の発表となります。
作画に使用できるのは鉛筆と色鉛筆(24色程度)のみですので、基本としてはデッサン力が求められる試験内容といえるでしょう。
課題が試験当日発表ということで、どんな内容の課題が提示されるかが分からない状態で対策を行う必要があります。どんな内容の課題にも対応できるように準備しておく必要があります。
言語に関する技術
言語に関する技術の試験内容は、簡単に言ってしまえば読み聞かせの技術が審査されます。
課題となる物語は試験公示の時点で発表されます。発表される物語は4つ。その中から1つを選んで、その物語の内容を3分間でまとめて読み聞かせをする能力が問われます。
言語に関する技術は、いわゆる素話の能力が求められます。読み聞かせにおいては絵本や人形の使用はできません。あくまでも話して聴かせるだけで園児たちの興味を引き、3分間で話をまとめ、その内容を伝える必要があります。
ちなみに2023年度後期試験での課題は「ももたろう」、「3びきのこぶた」、「おおきなかぶ」、「3びきのやぎのがらがらどん」の4作品。例年こうした知名度の高い昔話が課題として選ばれる傾向にあります。
課題の物語に関しては、その内容をしっかりと理解してどのように伝えるかを考えておきましょう。
保育士試験・実技試験の合格基準点
保育士試験の実技試験は各科目ともに50点満点です。受験するのは2科目ですから、それぞれの科目で30点以上を取得すれば合格となります。
試験の出題内容がそれぞれ違いますので、まずは自分が受験する科目を決め、しっかり準備をしなければいけません。
しかし、実技試験に関してはその対策が難しいのがポイント。自分なりにしっかりと内容を理解し対策をしたとしても、自分の対策が正しいのかどうかを判断するのが難しく、自力で対策を続けるのはかなり難易度が高くなります。
できれば保育士試験に精通している方に相談するのがベスト。それができない場合は、動画などで試験内容のポイントを確認するなど、対策の仕方を考えておきましょう。
保育士試験の合格率
保育士試験は合格基準点が6割とあらかじめ決まっています。いわゆる絶対評価の試験であり、その点では対策がしやすい試験ではあります。
事前に合格基準点が決まっていて、その点をクリアした方全員が合格できる試験内容ですので、保育士試験の合格率は年度によって大きなバラつきがあります。合格率の目安は20~30%程度ですが、試験対策の段階では合格率は意識せず、自分が合格基準点をクリアできるように準備しましょう。
保育士試験の合格率に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
保育士試験の合格率の詳細はこちら保育士試験の受験資格
保育士試験に関しては、試験内容以上にポイントとなるのが受験資格に関してです。保育士試験には受験資格があり、学歴や実務経験など、いろいろな項目が設定されています。
分かりやすい受験資格としては、大卒や短大卒といった学歴による資格ですが、中卒や高卒の方でも受験ができるように、いろいろな条件があります。保育士を目指す方は、まずは受験資格に関してどのような内容があるのか確認しておきましょう。
保育士試験の受験資格の細かな内容に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
保育士試験の受験資格についてはこちら保育士試験を目指す勉強方法とそのポイント
保育士試験を目指す場合、3つの勉強方法が考えられます。自分自身の力だけで目指す独学と、通信講座を受講する方法と、資格取得専門の予備校に通学する方法です。
保育士試験の試験内容、難易度を考えれば、独学でも十分合格を目指すことはできます。
しかし、通信講座や予備校を利用した方が、より効率的に合格を目指せるのは間違いありません。
そんな3つの勉強方法の特徴や、メリット・デメリットなどを紹介していきましょう。
独学で目指す
独学で保育士試験を目指すメリットとしては、まずは費用があまりかからないという点が挙げられます。
もうひとつはマイペースで勉強できるという点。予備校のように授業時間が固定されていませんので、自分のペースに合わせて勉強を進めることができます。
独学のデメリットは、試験の内容に関して詳しく解説してくれる人がいないということが挙げられます。予備校や通信講座には、専門講師による講義がありますが、独学ではこういった講義がありません。
試験勉強の内容で分からない部分があった場合、その部分の解決は自分の力でしなければいけません。内容によっては解決が難しく、それにより勉強時間が長くなることがデメリットといえます。
もうひとつ、保育士試験の試験内容から考えられる大きなデメリットとしては、実技試験対策が挙げられます。実技試験対策は自分で行っている対策の内容が正しいのかどうかを自分自身で判断するのが難しい部分があります。
保育士試験の実技試験の内容に関して解説している動画などを参考に、自分なりに対策できるように準備しておきましょう。
予備校に通学する
勉強時間を短縮し、より短期間で保育士試験合格を目指せる勉強方法が予備校への通学です。予備校に通学することで、通信講座と同様に、効率的に学べるオリジナルテキストと、勉強カリキュラムが手に入ります。
懸念の実技試験対策に関しても、直接講師の方に見てもらえる予備校もあり、この点ではもっともおすすめの勉強方法ということになります。
そんな予備校通学のデメリットですが、大きなデメリットは勉強内容などではなく、そもそもの立地の問題が挙げられます。
資格取得講座を開講している予備校は、基本的に人口の多い都市部に集中しています。地方部に住む方は、そもそも通える予備校がないという問題があります。
実技試験対策としては最適な勉強方法ではありますが、この通学時間と、あとは高額となる授業料がデメリットといえるでしょう。
通信講座を受講する
通信講座で保育士試験対策をするのはおすすめの勉強方法です。
メリットとしては、保育士試験に精通した専門講師の講義を受講でき、また保育士試験の内容からもっとも効率的に学べるように考えられたオリジナルテキスト、カリキュラムがあるという点です。
保育士試験は筆記試験の試験科目が多い試験ですが、通信講座のカリキュラムに沿って勉強することで、効率的に必要な知識が身につくでしょう。
通信講座を受講する場合のデメリットはほとんどなく、強いて言えば独学よりも費用がかかるという点くらいです。それでも予備校に通学するよりも費用は抑えることができます。
もうひとつの問題は実技試験対策ですが、通信講座を選ぶ際に、実技試験対策の講義も行っている講座を選べばこの点も大きな問題とはなりません。通信講座を選ぶ場合は、講座の内容をチェックし、実技試験対策もついている講座を選ぶようにしましょう。
まとめ
保育士試験は年に2度実施されており、筆記試験と実技試験で合否が決まる国家試験となります。
試験内容に関して簡単に解説すると、まずは9科目の筆記試験に挑戦します。全科目6割以上の得点を取ることができれば筆記試験に合格でき、実技試験が受験できるようになります。
実技試験は3つの科目があり、その中から2科目を選択して受験します。試験の内容はこの記事でも解説していますので、参考にしてください。
筆記試験と実技試験の両方に合格すれば保育士試験合格です。
保育士試験の出題内容を考えると、筆記試験に関してはある程度独学でも対策可能ですが、問題は実技試験の対策でしょう。動画で勉強するなど対策法を用意しておきましょう。
保育士試験を目指すのであれば、独学にこだわらず、通信講座や予備校への通学も検討するのがおすすめです。







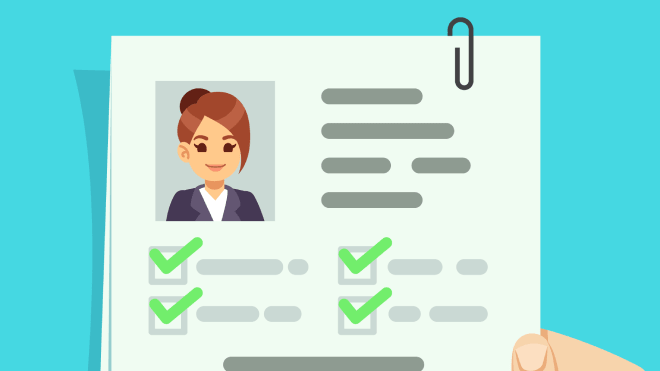
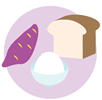




 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


