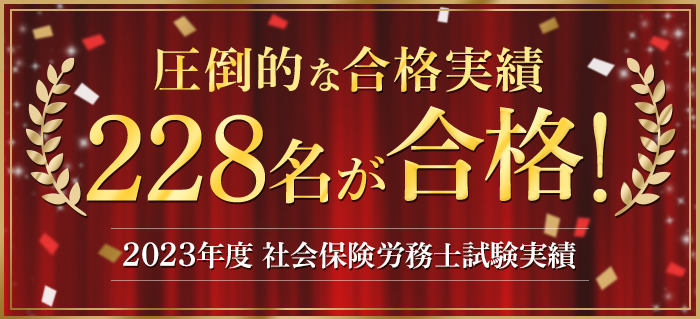なぜ受験するべきか?合格率を高めるための心構え
社会保険労務士試験の合格率を少しでも高めるためには、どのような心構えで臨むべきでしょうか。まず前提として、せっかく出願したのであれば、絶対に受験することをおすすめします。その理由の一つは、受験すれば合格の可能性がゼロではなくなるからです。もちろん、ただ受験するだけでなく、少しでも合格の可能性が高い状態で本試験に臨みたいと考えるのは当然です。では、そのために具体的に何をすれば良いのでしょうか。本記事では、合格率を高めるための考え方と、自身のレベルに応じた対策について解説していきます。まずは、受験することの意義を再確認し、合格に向けた意識を高めることが重要です。
あなたはどのレベル?受験生を7つのランクに分類

ここでは、受験生の学習状況や実力に応じて、便宜的に合格率の高い順にランク付けを行いました。ランクは1から7まであり、ランク1が最も合格から遠い状況、ランク7が最も合格に近い、あるいは確実な状況を示します。各ランクが受験生全体に占める割合の目安も示しています。このランク付けは、ご自身の現在の立ち位置を客観的に把握し、今後の学習戦略を立てる上での参考となるでしょう。自分がどのランクに該当するのかを確認し、少しでも上のランクを目指すことが、合格率を高めるための第一歩となります。
ランク1・2:学習初期段階の壁とその割合
まず、最も初期段階であるランク1は、試験範囲の学習がそもそも1周できていない層です。具体例としては、労働保険関連科目は一通り学習したものの、社会保険関連科目が途中までしか終わっていない、といったケースが挙げられます。このような状況の受験生は意外にも多く、受験生全体の約4割程度存在すると考えられます。 次にランク2は、試験範囲の学習を1周は終えたものの、内容の理解が十分に伴っていない層です。とりあえず1周することを目的としてしまい、知識の定着が不十分な状態です。この層も受験生全体の約2割程度いると見られます。ランク1、ランク2の段階では、まだ合格に必要な知識のインプットや理解が不足している状態と言えます。
ランク3・4:知識はあるが基準点・合格点に届かない層
ランク3は、試験範囲の学習を2周以上行い、内容の理解も伴っているものの、択一式試験において基準点割れを起こしてしまう科目がある層です。例えば、全体の総得点としては合格ラインに近い良い点数を取っていても、特定の科目、仮に健康保険法で10点満点中2点しか取れなかった場合、基準点(通常4点)に満たないため、その時点で不合格となってしまいます。このような受験生が全体の約15%程度存在します。 続くランク4は、択一式試験において全ての科目で基準点を突破するものの、総合得点が合格点に到達しない層です。例えば、全科目が満遍なく5点ずつ取れたとすると、各科目の基準点はクリアしていますが、合計点は70点満点中35点となります。択一式の合格基準点が仮に45点だとすると、合格点には10点届いていないことになります。このような層も、受験生全体の約1割程度いると考えられます。ランク3、4の段階では、知識の穴を埋め、得点力をさらに伸ばす必要があります。
ランク5:択一式は得意だが選択式が壁となる受験生 (全体の8%)
受験生ランクの中で、ランク4とランク5の間には一つの大きな壁が存在し、ここから合格の可能性が飛躍的に高まります。いわゆる「ワンチャン」が見えてくるのがこのレベルからです。 ランク5に該当するのは、もし社会保険労務士試験が択一式だけであれば、何回受験しても不合格にならないレベルの実力を持つ層です。しかし、社労士試験には選択式試験が存在します。選択式試験は各科目5点満点で、そのうちの3点が基準点となることが多く、択一式に比べて基準点割れを起こしやすいという特徴があります。そのため、択一式の実力は十分でも、選択式のいずれかの科目で基準点割れを起こしてしまい、結果的に不合格となる可能性があるのです。このランク5の受験生は、全体の約8%程度存在すると考えられます。択一式の安定した得点力に加え、選択式対策が合格への鍵となります。
ランク6・7:合格にかなり近い、または確実な上位層
ランク6まで到達すると、合格率はかなり高まります。このレベルの受験生は、選択式試験で基準点割れを起こす可能性がある科目が、「社会保険に関する一般常識」と「労務管理その他の労働に関する一般常識」の2科目に限定されるような層です。一般常識科目は範囲が広く対策が難しいとされるため、ここだけが弱点となっているケースです。このランク6の受験生は、全体の約6.5%程度と推定されます。
そして最後のランク7は、どのような問題が出題されても、何回受験しようが、社会保険労務士試験には絶対に合格するというレベルの層です。これは非常に高いレベルであり、正直なところ、指導する立場の講師であっても、なかなかこのランクに達している人は少ないと言えるほど、卓越した実力を持つ方々です。このレベルに到達すれば、合格はほぼ確実と言えるでしょう。
上位ランクを目指すための具体的な学習戦略
自分がどのランクにいるかを把握したら、次は少しでも上のランクを目指して学習を進めることが重要です。これは、ランクが低いからといって諦めるべきという意味では全くありません。
例えば、ランク1(試験範囲未了)の方は、このままでは合格が厳しい状況ですので、まずはランク2に上がることを目標に、試験範囲を最低1周終わらせることを目指しましょう。ラストスパートでまずは1周やり遂げるという経験が、たとえ今年の結果に結びつかなくても、翌年以降の学習に必ず繋がります。
ランク2(理解不足)の方で、自分は理解が伴っていないという自覚がある場合は、問題演習とその結果を踏まえたテキストの振り返りを繰り返すことが重要です。演習を通じて知識の曖昧な部分を明確にし、テキストで確認することで、知識の精度を高めていくことができます。
また、選択式試験に不安がある場合は、テキストの精読を徹底し、重要語句やその周辺知識を正確に覚えること、そして選択式の問題演習を通じて、空欄補充形式に慣れ、解答の精度を高めていくことが必要になります。諦めずに一つ上のランクを目指して努力を続けることが、合格への道を切り開きます。
まず目指すべきは「ランク5」!その理由とは
多くの受験生にとって、まず現実的な目標として目指すべきは「ランク5」と言えます。ランク5とは、繰り返しになりますが、「もし社労士試験が択一式だけであれば、何回受けても不合格にならない」というレベルの実力です。
なぜランク5を目指すべきかというと、このレベルに到達している受験生は決して少なくないからです。毎年、「選択式さえ基準点をクリアできていれば合格だったのに」という受験生は後を絶ちません。つまり、択一式で安定して合格レベルの得点を取れる実力を身につけることが、合格への最低条件であり、かつ最も重要なステップの一つなのです。
択一式で合格レベルの力をつけることができれば、あとは選択式対策に注力することで、合格の可能性は大きく高まります。まずは、択一式で他の受験生に引けを取らない、むしろリードできるような実力を確立すること。このランク5のレベルに向けて、日々の学習を積み重ねていくことが非常に大切です。

まとめ:現状を把握し、ラストスパートで合格可能性を高めよう
今回は、社会保険労務士試験の合格率を少しでも高めるための方策について、受験生をランク別に分類し、それぞれの特徴と目指すべき方向性について解説しました。
最も重要なのは、まずご自身の現在の学習状況や実力が、紹介したランクのどのあたりに位置するのかを客観的に把握することです。現状を正確に認識することで、今後何をすべきか、どの点に注力すべきかが見えてきます。そして、少しでも上のランクに上がれるよう、残された時間でラストスパートをかけることが、合格可能性を高めるための鍵となります。ランク1や2の方も、諦めずにランクアップを目指し、ランク3以上の方も、弱点を克服し更なる実力向上を目指して、最後まで全力を尽くしてください。