行政書士の勉強は長い長い道のりをずっと歩くようなもの

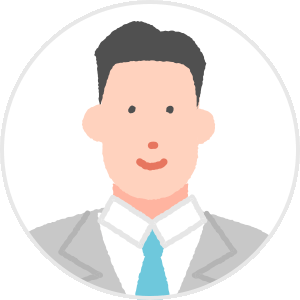
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 50代 |
| 試験年度 | 2015年(27年度) |
| エリア | 東京都 |
| 勉強時間 | 400時間 |
| 勉強期間 | 9ヶ月間 |
| 職業 | 正社員(サラリーマン) |
| 勉強法 | 過去問 |
| 商品 | eラーニング |
| 受験回数 | 初学者(1回目) |
eラーニング使用回数
※eラーニングの使用回数となり、実際の学習時間とは異なります。
受験勉強が山登りに例えられることがありますが、登るというハードな行為に伴う苦しさの印象が強過ぎて、私の場合はその例えは違和感がありました。
今回の行政試験の受験勉強は、私にとっては平坦な道を歩き続けて目的地まで歩いていく、ただし相当遠いのでその距離を期日までにどれだけ詰められるかの勝負だったように思います。
途中、きつめの上り坂やゆるい下り傾斜の道がありましたが、少しずつ前に進むイメージをいつも持ちながら取り組むことができたと思います。
やる気を持ちながら歩き続けるためにはまず目的地との距離を測る必要があります。そこで闇雲に過去問に挑戦してしまうのは、距離を測らずいきなりダッシュし出すのに似ています。
走り出してもすぐに息切れして動けなくなるように、あまり予備知識がない状態で行政書士試験の問題にかかるとその難しさに圧倒されます。
5択でしかも問題文が長い、専門用語がどんどん出てきてどれも正しい(或いは間違っている)ように思える・・ まず始めにしなければならないのは、自分が今いる位置(=知識レベル)とゴールまでの距離感(=合格レベルの力)の間合いを測ること。
それが教科書をまずは読むことだと思います。通読してみて一通り分かった気になります。
その上で過去問にチャレンジしてみます。そうするとどれだけ教科書の読み込みや理解が足りなかったかがわかってきます。一方で解ける問題もあり、目的地までの間合いが感覚としてつかめます。
距離を掴んでからの勉強は、教科書の熟読でした。判例の論理構成や行政手続きのフローなどもフォーサイトの教科書はしっかりカバーしてくれているので完璧に理解できるまで読み込み、過去問でその理解を確認するという作業を繰り返しやりました。
平日は早朝出勤して始業までの時間を利用し教科書・過去問を、帰りの電車ではスマホで道場破りにアクセスし、「単語カード」と「確認テスト」を使って苦手分野の克服に時間を使いました。
当日の試験では見たこともないような問題も必ず出ますが、そういう問題は他の人にとっても見たことのないもの、焦ることなく臨むのが大事だと思います。
そういう意味では模擬試験をやっておくのも有効だったなと振り返って思います。
今回の行政試験の受験勉強は、私にとっては平坦な道を歩き続けて目的地まで歩いていく、ただし相当遠いのでその距離を期日までにどれだけ詰められるかの勝負だったように思います。
途中、きつめの上り坂やゆるい下り傾斜の道がありましたが、少しずつ前に進むイメージをいつも持ちながら取り組むことができたと思います。
やる気を持ちながら歩き続けるためにはまず目的地との距離を測る必要があります。そこで闇雲に過去問に挑戦してしまうのは、距離を測らずいきなりダッシュし出すのに似ています。
走り出してもすぐに息切れして動けなくなるように、あまり予備知識がない状態で行政書士試験の問題にかかるとその難しさに圧倒されます。
5択でしかも問題文が長い、専門用語がどんどん出てきてどれも正しい(或いは間違っている)ように思える・・ まず始めにしなければならないのは、自分が今いる位置(=知識レベル)とゴールまでの距離感(=合格レベルの力)の間合いを測ること。
それが教科書をまずは読むことだと思います。通読してみて一通り分かった気になります。
その上で過去問にチャレンジしてみます。そうするとどれだけ教科書の読み込みや理解が足りなかったかがわかってきます。一方で解ける問題もあり、目的地までの間合いが感覚としてつかめます。
距離を掴んでからの勉強は、教科書の熟読でした。判例の論理構成や行政手続きのフローなどもフォーサイトの教科書はしっかりカバーしてくれているので完璧に理解できるまで読み込み、過去問でその理解を確認するという作業を繰り返しやりました。
平日は早朝出勤して始業までの時間を利用し教科書・過去問を、帰りの電車ではスマホで道場破りにアクセスし、「単語カード」と「確認テスト」を使って苦手分野の克服に時間を使いました。
当日の試験では見たこともないような問題も必ず出ますが、そういう問題は他の人にとっても見たことのないもの、焦ることなく臨むのが大事だと思います。
そういう意味では模擬試験をやっておくのも有効だったなと振り返って思います。
3おめでとう
行政書士の合格体験記
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。
×


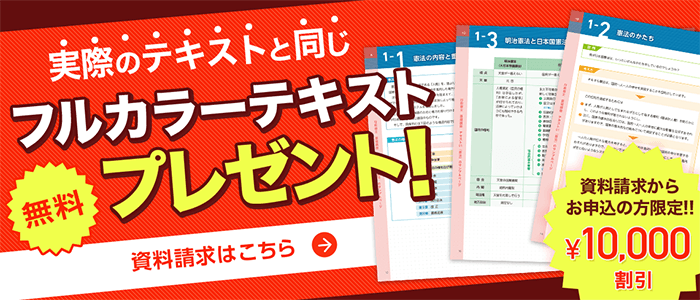















 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


