行政書士とは?仕事内容や向いている人の特徴、取得するメリットを解説
更新日:2023年7月13日

官公署に提出する書類の作成や、書類の申請代行、さらに顧客からの相談に乗る業務など、行政書士の仕事は幅広いのが特徴です。
しかし仕事内容が多岐にわたることから、実際にどのような仕事をするのかなどが分かりにくくなっている部分もあるかと思います。
そこでこの記事では行政書士の仕事内容や、行政書士に求められる能力、行政書士としての働き方や活躍分野など、行政書士の仕事に関して解説していきたいと思います。
- 行政書士の主な業務は書類の作成とそれにかかわる相談業務、そして許認可申請の代理を行うことです。
- 行政書士を取得するメリットとは「就職や転職で役立つ」「法律知識が身につく」「独立開業を目指せる」「比較的取得難易度が低い」が挙げられます。
- 行政書士試験は年1回、11月の第二日曜日に実施され、合格発表は翌年の1月末。年齢・学歴・国籍を問わず、誰でも受験できます。
- 3つの特徴「コミュニケーション力がある」「責任感が強い」「貪欲に仕事に向かい合うことができる」がある方が行政書士に向いています。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
行政書士とは?
行政書士と司法書士は、両方とも「法律を扱う国家資格」なので、比較・混同されることが多いのですが、取り扱い業務が異なります。
行政書士は、官公署に提出する許認可などの書類を作成・手続きの代行をするのが主な業務です。
司法書士は、登記や供託にまつわる書類の作成と、その手続きの代行業務が主な仕事になります。
行政書士の仕事内容
行政書士は、企業や個人の代わりに、煩雑でわかりづらい官公署に提出する書類の作成をしたり提出の代行をしたりします。
行政書士の仕事内容を大きく分けると、「書類作成」「許認可申請の代理」「相談」の3種類です。
関連記事:
行政書士の仕事内容についてはこちら
官公署に提出する書類等の作成
「官公署に提出する書類などの作成」は、行政書士の大切な仕事の一つです。「官公署とは、各省庁・都道府県庁・市/区役所・町/村役場・警察署・消防署・税務署ほかのこと。
それらに提出する書類は「許認可(許可認可)」が多く、会社設立手続き・建設業の営業許可・飲食店や遊戯店の開店許可ほか、1万以上もの種類があるのです。
書類作成には時間がかかります。また、間違いや不備があると再度作成を求められることも。行政書士は、書類作成の時間がない・作成が困難などの悩みを持つ依頼者の代理で、書類を作成し申請の代行をします。
書類作成にあたっての相談業務
「官公署への提出書類」のほかにも、「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」の作成も行政書士の仕事です。
「権利義務に関する書類」とは、主に相続関係や契約書関係で、「事実証明に関する書類」は、会社関係や会計・調査の書類などになります。
それらの書類作成のためには、依頼者からさまざまな相談を受けることになり、個人・業務上の秘密に接することも少なくありません。そのため、行政書士には行政書士法で「守秘義務」が課せられています。「相談業務」は、書類を作成しない場合でも依頼者に相談料の請求が可能です。
許認可申請の代理
行政書士は、「官公署に提出する書類作成」だけではなく、依頼者の代理として申請手続きを行うことができます。
行政関係の書類は非常に複雑で、自治体により申請先や書類の中身も違うことも多く、また、申請の手続きごとに出向く官公署も異なり「行き慣れている場所」ではないので、時間も手間もかかります。
会社の設立やお店の開店を控えている人にとっては、書類の作成・申請で時間がかかり過ぎてしまうのは避けたいもの。そんな依頼者に代わって、官公署に行き慣れている行政書士が、許認可申請手続きを進めることが多いのです。
行政書士を取得する4つのメリット
行政書士の仕事内容に関して簡単に解説しましたが、この行政書士の資格を取得するメリットに関して説明しておきましょう。
就職や転職で役立つ
行政書士として仕事をするためには、独立開業するのが基本です。しかし、行政書士の資格を取得するということは、それだけの法知識を身に付けていることの証明にもなります。
こうした法律知識は一般の仕事の現場でも十分役立てることができますので、行政書士としての仕事をしなくても、取得しているだけで就職や転職で有利になるケースがあります。
特に一般企業の法務関係の職に就く場合などは、行政書士の法知識が役立つでしょう。
また、行政書士試験に挑戦し合格したという事実は、地道に努力を続け、結果を残すことができる人間であるというアピールにもなりますので、この点でも就職活動・転職活動では有利といえるでしょう。
法律知識が身につく
上でも触れたとおり、行政書士の資格を取得するには豊富な法律知識が必要です。こうした法律知識は、仕事で活かせるのはもちろんプライベートでも役立てることができます。
行政書士資格を取得するのに重視すべきは民法の分野。民法とは、われわれ国民の生活に密接している法律ですので、その知識があることは大きなメリットといえるでしょう。
独立開業を目指せる
行政書士の資格を取得し、行政書士としての業務を行う場合、各地に設置されている行政書士会に登録する必要があります。基本的には行政書士として独立開業を行う形であり、行政書士として働いていく方の多くは独立をしています。
独立開業が可能ということは、働き方もある程度自分で決めることができるということ。
人よりたくさん働いて多くの収入を得るのもいいですし、余裕を持った働き方で趣味の時間や家族と過ごす時間を大切にする事も可能。
自分らしい生き方、働き方を選択できるのは資格を取得する大きなメリットといえるでしょう。
比較的取得難易度が低い
行政書士はある程度権限が認められている八士業のひとつ。この八士業の資格の中では、比較的取得難易度が低いというのもポイントでしょう。
もちろん行政書士の資格自体は取得が簡単な資格ではありません。独学で目指す場合、1,000時間ほどの勉強時間が必要とも言われており、仕事をしている社会人の方が目指す場合は1年以上の勉強期間が必要な資格です。
しかし、法律系の資格を見た場合、それでも難易度は低い部類に入るといえます。
ちなみに八士業のほかの7つの資格は、弁護士、弁理士、税理士、土地家屋調査士、司法書士、社会保険労務士、海事代理士であり、総じて行政書士よりも難易度の高い資格となっています。
行政書士の試験とは
行政書士試験は、法律系の国家資格で年に1回実施されます。合格率が低く、難易度が高いものの合格基準は明確です。しっかり対策を立て計画的にポイントをおさえた学習を積み重ねれば、初学者でも合格を目指せます。
行政書士の試験概要
行政書士試験は、「一般社団法人行政書士試験研究センター」が年に1回実施する国家試験です。
【試験スケジュール】
-
試験の公示
7月初旬に、試験の詳細が行政書士試験研究センターのホームページにて発表されます。 -
受験申し込みの受付
受験申し込みは、7月下旬〜8月下旬の間にインターネットか郵送にて受け付けています。申し込みの際には、受験手数料を支払う必要がありインターネットの場合はクレジットカード、郵送の場合は専用口座への振り込んでください。 -
受験票の送付
例年10月中旬〜下旬に受験票が送付されます。 -
試験日
試験は11月の第二日曜日、時間は午後1時〜4時の3時間です。 -
合格発表
翌年の1月末に合格発表があり、行政書士試験研究センターのホームページや事務所掲示板で確認できます。
【試験会場】
試験会場は、各都道府県の大学・ホテル・多目的ホール・商業ビルなどで開催されています。受験申し込み時に希望する場所を選べますが、定員オーバーなどの場合は先着順となるため、早めに申し込むほうが確実です。試験会場の場所は、受験票に記載されます。
【受験資格】
行政書士試験は、年齢・学歴・国籍を問わず、誰でも受験できます。
関連記事:
>行政書士試験について詳しくはこちら
行政書士の試験内容
行政書士の試験内容は、大きく2種類に分かれます。「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関連する一般知識等」です。
【法令等】
行政書士として業務を遂行するために必要な法律知識の科目です。
-
基礎法学
法学全般の基礎知識が問われます。非常に範囲が広いのですが、基本的な法令用語や原則などをしっかり学ぶ必要があります。 -
憲法
国民の自由や権利を定めた「人権分野」では判例を、国家の運営について定めた「統治分野」は条文を中心に学習を進めるとよいでしょう。 -
民法
長文の読解能力など、「国語力」が問われます。76点と配点が高いので、十分に対策して得点できるようにしましょう。 -
行政法(地方自治法含む)
条文について細かい知識が問われるので、暗記だけ済ませるのではなく、同時に理解を深める学習を行うことも必要です。 -
商法・会社法
商法はテキスト・過去問を中心に学習し、会社法は条文を中心に学習するといいでしょう。
【一般知識】
行政書士として業務を遂行するために必要な一般知識の科目です。
-
政治・経済・社会の分野
政治は国内外の政治制度や日本の選挙制度について、経済は金融政策や財政問題など、社会では社会保障など、幅広く出題されます。 -
情報通信・個人情報保護の分野
情報通信は、最新のインターネットや通信手段に関して、個人情報保護は個人情報保護法から出題されます。 -
文章理解
現代国語の問題になります。並べ替え・穴埋め・文章要旨の把握などの問題がメインです。
試験問題は、全部で60問(300点満点)です。
「法令等」の科目の問題数は46問(配点は244点)で「一般知識」の科目の問題数は14問(配点は556問)となっています。
問題式は、「5肢択一式」(5つの選択肢の中から1つ選ぶ)・「多肢選択式」(20個ある選択肢の中から、正解を4つ選ぶ)・「記述式」(40文字くらいの文章にまとめる)となります。
関連記事:
行政書士試験の試験科目についてはこちら
行政書士の難易度・合格率
行政書士試験の、過去5年間の合格率を見てみましょう。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2018年度 | 12.70% |
| 2019年度 | 11.48% |
| 2020年度 | 10.72% |
| 2021年度 | 11.18% |
| 2022年度 | 12.13% |
行政書士試験は、毎年、4万人〜5万人の人が受験している中で、合格率は平均11〜12%ほどです。
国家資格の中では「法律の勉強はやったことがない」という人でも挑戦しやすい試験ではあるものの、難易度が高い試験です。
計画的にポイントを絞った学習を重ねる必要があるでしょう。
関連記事:
行政書士試験の試験科目についてはこちら
行政書士のやりがいは?
行政書士の資格を取得し、行政書士として働くと考えた場合、やはりやりがいがあるのかどうかという点は気になるところ。
では、行政書士という仕事にはどのようなやりがいがあるのか、この点を確認していきましょう。
困っている人を手助けできる
行政書士の主な業務は書類の作成とそれにかかわる相談業務、そして許認可申請の代理を行うことです。こうした仕事を行政書士に依頼してくる方は、自分ではできすに困っている方ということになります。
行政書士の仕事は、基本的に困っている方の手助けを行う事にほかなりません。そして、その困っている方と直接話をし、解決した時には感謝をしてもらえる。それが行政書士の仕事です。
サラリーマンの方の中には、自分が従事している仕事がどれだけ他の方の助けになっているか実感しにくい仕事をしている方も多いかと思います。もちろんどんな仕事でも、最終的には誰かほかの方の役に立つものであり、どこかで感謝されているのは間違いありません。
しかし、その感謝を直接感じられないという方も多いかと思います。
直接目の前で困っている方を手助けし、直接感謝を受けられる仕事というのは非常にやりがいを感じるもの。行政書士の仕事内容はまさにこういったタイプの仕事であるといえます。
努力次第で高収入を目指せる
繰り返しになりますが、行政書士として仕事を行う方の多くは独立開業をしている方です。独立開業するということは、自分自身が経営者になるということ。そして自分が頑張れば頑張った分だけ収入に反映することができるということになります。
独立開業という働き方にはメリットもデメリットもあります。
デメリットは、基本的に全ての業務を自分で考えて行う必要があるということ。経理、宣伝、広告、営業など、一般的な企業では各部署に分かれて行っている業務を、自分自身の判断で行う必要があるということになります。
それだけ業務は多忙を極めますが、それゆえのメリットもあります。それが自分の収入を自分で決められるという点。
頑張って事務所としての収入が上がれば自分の収入に反映することができるのは、独立開業する大きなメリットとなります。
もちろん、収入にはそこまでこだわらず、十分に休みをとってマイペースで働きたいという場合も自分が経営者となる独立開業であれば対応可能。
こうした自由な働き方が選択できるのは行政書士として働くやりがいにつながるでしょう。
行政書士に向いている方の特徴
行政書士としての仕事内容を考慮したうえで、ではどのような方が行政書士に向いているのか、この点を考えていきたいと思います。
コミュニケーション力がある
行政書士の仕事の中心は書類の作成。書類の作成は一人でも行えますので、あまりコミュニケーション能力は必要ないと考えている方も多いかもしれませんがそれは違います。
書類を作成するといっても、その書類が何のために必要なのか、どのような事情で作成するのかなど、作成する理由がわからなければ作成することはできません。
つまり、書類を作成するということは、その書類の作成を依頼してきた顧客と、しっかり話し合う必要があるということ。さらに言えばその顧客を獲得するために営業活動をする必要があるということになります。
行政書士の資格を取得し、事務所を開けば自然に仕事が入ってくるなどと言うことはありません。当然ですが宣伝広告を行い、自ら営業活動を行って仕事を取ってくるということになります。
そう考えればコミュニケーション能力は必須。むしろ重要視すべきポイントとも言えるでしょう。
また、行政書士の仕事はほかの士業との共管業務が多いのも特徴。税理士や司法書士、弁護士などとともに1つの案件をこなしていくことも多いので、こうした他士業の方とのコミュニケーションも不可欠です。
責任感が強い
どの仕事もそうですが、行政書士の仕事もミスが許されない仕事です。仕事の中心が書類の作成ですので、その書類の作成でミスを犯すようでは、仕事が集まってくることはありません。
行政書士はひとつひとつの仕事に真摯に向き合い、さらに全ての仕事に責任感を持って当たるのが「当たり前」であり、こうした責任感の強さは行政書士には必須のスキルといえるでしょう。
貪欲に仕事に向かい合うことができる
独立し行政書士事務所を開いた場合、どれだけ仕事にどん欲に向き合えるかというのは大きなポイントとなります。
行政書士の仕事は、ただ待っているだけでポンポンと入ってくるものではありません。ひとつの仕事に対し貪欲に向き合っていかないと、なかなか仕事が集まらず、収入面でも厳しくなってしまいます。
貪欲に仕事に向き合い、その仕事を責任感を持ってこなし、顧客としっかりコミュニケーションを取る。この繰り返しで顧客から信頼される行政書士となることができます。顧客から信頼されるようになれば、その顧客から新規顧客を紹介してもらえることもあり、さらに仕事は増えていくでしょう。
行政書士として働き、収入を上げていくにはこうした素養が必要ということになります。
行政書士が活躍できる分野
行政書士とは書類作成のスペシャリストです。それと同時に豊富な法律知識を持つ人材ということになります。
そんな行政書士が活躍できる分野は非常に多岐にわたります。どんな業種の方も、職種の方も、官公署に書類を提出する必要があれば、当然行政書士を頼ることになります。
行政書士が活躍できる分野は全ての分野といっても過言ではないでしょう。
行政書士の資格を持ち、企業で働くと考えた場合、行政書士の知識が活かせるのは法務の部門や経理の部門。特に内勤のデスクワークが活躍の場となることが多いようです。
行政書士の働き方
行政書士の資格を持ち働く場合、どのような働き方が考えられるのか。行政書士の働き方を紹介していきましょう。
もちろん基本は独立開業ということになりますが、それ以外にも考えられる働き方も紹介していきます。
企業内行政書士
行政書士としての仕事を行い対価を得るには、行政書士会への登録が必要です。企業に勤務している方には難しく、基本的に企業内で働く行政書士は、資格を活かすのではなく資格取得のために身に着けた知識を仕事に活用しています。
ただし、勤務している企業が認めていれば、企業に勤めながら行政書士登録を行い、行政書士としての仕事をすることも可能。
日本国内ではあまり認められるケースは多くありませんが、企業が認めればこうした働き方も可能です。
独立開業行政書士
行政書士として仕事をする場合、もっともポピュラーな方法がこの独立開業です。
自分で事務所を構え経営者となりますので、営業から経理まで仕事は多岐にわたりますが、自分らしく働くことができるのも事実。
企業に勤めるサラリーマンの方とは違い、働けば働いた分だけ収入はアップしますし、比較的休みを取りやすくもなります。
副業行政書士
平日はサラリーマンとして企業などに勤務し、本業が休みの日に行政書士として働くというのが副業行政書士。
副業で行政書士として仕事をする場合はいくつかの問題点があります。
ひとつ目の問題は本業である企業が副業を認めているということ。副業として行政書士として仕事できるかどうか、まずは勤務している企業に確認しましょう。
もうひとつの問題点は、行政書士として働くのが土日祝日に限られる場合、官公署が休みの場合が多く、書類の提出などの代行業務が行えないという点があります。
週末に副業として行政書士業務を行うもう一つの問題点は、収入と行政書士会への登録料のバランスです。官公署に提出する業務ができない状況で副業を行っても、比較的高額な行政書士会への登録料が支払えるか難しいところです。
こうした問題点を克服できれば、副業として働くのもひとつの働き方となるでしょう。
行政書士になるにはどうすればいいか?
行政書士として働くには、まず行政書士の資格を取得する必要があります。しかし、資格を取得したからと言って、すぐに仕事ができるということではありません。
では、行政書士の資格の取得方法、そして働くために必要な手続きを紹介しましょう。
関連記事:
行政書士試験の受験資格など詳しくはこちら
行政書士試験に合格する
行政書士の資格を得る方法はいくつかありますが、もっとも分かりやすいのが行政書士試験に合格することです。
行政書士試験は年に1回実施され、受験資格はなく誰でも挑戦できる試験となっています。試験の難易度は決して低くなく、合格するためには独学で1,000時間程度の勉強時間が必要と言われています。
これから行政書士を目指すという方は、まずこの試験に合格することを目標としましょう。
試験合格以外の方法も
行政書士の資格を取得するには、試験に合格する以外の方法もあります。
- 弁護士、税理士、弁理士、公認会計士の資格所有者は行政書士試験を受験しなくても行政書士資格が得られる
- 公務員として17年以上行政業務に携わった方は「特認制度」で資格を得ることができる
条件はつきますが、上記の2つのケースは行政書士試験に合格せずとも行政書士の資格を取得することができます。
試験合格後行政書士会に登録する
行政書士試験に合格しただけでは、「行政書士試験に合格した人」というだけで、行政書士として認められるということにはなりません。
行政書士として仕事をするには、各地に設置されている行政書士会に登録を行う必要があります。
登録にあたっては登録料の支払いや、事務所の申告などの条件があり、ある程度の手間とお金、そして時間が必要になります。
行政書士会への登録は、行政書士として働くと決めた時点で考え始めるのがいいでしょう。
行政書士とのダブルライセンスに相性の良い資格とは?
「士業」で活躍する人は、複数の資格を持つケースが多いものです。
特に行政書士資格は、試験科目が重複している資格もあり、勉強の成果を活かせるのでダブルライセンスを狙いやすくなります。
独立開業の武器にもなるでしょう。
司法書士
司法書士は、書類作成・申請代理業務が行政書士と共通していますが、裁判所・検察庁・法務局を相手にする仕事です。司法書士試験はさらに出題範囲が広く、難易度も高くなります。けれども両方とも独占業務があり、ダブルライセンスを取得すれば仕事の範囲も広がり、独立開業した際、ワンストップのサービスを提供できるのもメリットです。
関連記事:
司法書士の仕事内容についてはこちら
社会保険労務士
社会保険労務士はいわば「労務関係のプロフェッシナル」。仕事内容も、それらに関連する書類作成・提出代行・コンサルティングが主で、保険・年金・労務管理などが専門になります。
行政書士とダブルライセンスを取得すれば、社労士として顧客の会社の労務仕事を請け負いつつ、行政書士として顧客の生活上の悩みに乗って手助けすることもできるでしょう。
FP(ファイナンシャルプランナー)
FPは、生活に関連する身近なお金のことを扱う資格です。両方の資格ともに業務の幅が広いのですが、特に「相続」に関する仕事は相性が抜群。
FPは、最も顧客に最適なプランを提供できますが、実際に書類作成や手続き代行をすることはできません。ダブルライセンスを取得すればプラン提案から実際の手続きまですべて請け負えます。
中小企業診断士
中小企業診断士は経営コンサルティングが主な仕事です。けれども、もし顧客企業が新会社を設立したり行政庁の許認可を得ることが必要となったりした場合、それに関する公的書類の作成・提出が必要になります。
そんなときダブルライセンスを取得していればワンストップサービスで仕事を請け負え、企業からの信頼もさらに増すでしょう。
関連記事:
中小企業診断士について詳しくはこちら
宅地建物取引士
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引のプロとなる資格です。そして行政書士が取り扱う書類の中には不動産関連書類もたくさんあります。
ダブルライセンスを取得していれば、「不動産相続」「不動産の売却」に関する案件で、宅建士としての不動産の知識が役立ち、行政書士として関係書類作成などまで通して請け負うことができます。
関連記事:
宅建について詳しくはこちら
行政書士Q&A
行政書士の仕事内容や働き方に関して紹介してきました。そのうえで行政書士を目指したいという方が持つであろう疑問に関してQ&A方式で回答していきましょう。
- 行政書士の主な業務は?
-
行政書士の主な仕事内容は以下の通りです。
- 官公署に提出する書類の作成(及びそれに関する相談業務・申請代行)
- 権利義務に関する書類の作成(及びそれに関する相談業務・申請代行)
- 事実証明に関する書類の作成(及びそれに関する相談業務・申請代行)
基本的には、書類作成・相談業務・申請代行が3つの業務の柱となります。多くの分野に関する書類の作成を行いますので、民法を中心に幅広い法律知識が求められます。
- 行政書士資格の有効期限は?
- 行政書士資格に有効期限はありません。
行政書士資格に関しては、有効期限や更新手続きなどは必要ありません。一度取得すれば、欠格事由に該当しない限りその資格は有効です。
そのためにも将来的に独立開業を考えているという方は、若いうちに取得するのがおすすめ。年を経てから取得するのはより難易度が高くなります。
- 行政書士の将来性は?
-
AI化やデジタル化が進んでも行政書士の仕事に大きな影響はないと考えられます。
単純に書類を作成するなどの仕事はAIなどで代用できる未来があるかもしれません。しかし、どこにどのような書類を提出すべきかなど、顧客の相談業務に関してはやはり人の手で行う方が、顧客は安心するかと思います。
また。単純な書類作成ではなく、いろいろな事情を加味したうえでの作成や、認可申請などはフレキシブルに対応できる行政書士の存在が重要になるかと思います。
ただし、行政書士も今のままで問題ないというわけではありません。社会がデジタル化していくのであれば、行政書士もその流れに乗る必要があります。
どうしても将来性が気になるという方は、行政書士と相性がいい資格を取得しダブルライセンスを持って働くという方法も考えられます。
まとめ
行政書士とは書類作成のスペシャリストです。官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、さらに事実証明に関する書類を作成するという独占業務を持ち、幅広い法律知識が求められる資格となります。
行政書士の資格の特徴としては、まず受験資格がないことが挙げられます。年齢、性別、学歴、職歴はもちろん国籍も不問の資格ですので、誰でも挑戦できる資格となります。
さらに法律関係の士業資格としては試験難易度は低い方で、取得しやすいという点もポイントでしょう。
行政書士の将来性に対して不安に持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、困っている顧客に対し、親身に相談に乗るというのはAIなどには難しい業務。行政書士の仕事がなくなるということはあまり想像しにくいところです。
こうした顧客の相談を直接受ける、直接感謝を受けることができるというのは行政書士の仕事のやりがい。非常に魅力的な仕事といえるでしょう。
行政書士として働くのは独立開業が基本です。独立開業することで営業や経理など、いろいろな業務が必要となります。ただし、自分が頑張った分だけ収入に反映できますし、自分らしく働くことも可能になります。 行政書士とは、どの街でも必ず必要となる法律のスペシャリストであり、どこにでも活躍の場は広がっています。これから行政書士を目指すという方は、将来どのような働き方をするかなども想像しておくといいかもしれません。
行政書士 最短合格なら通信講座がベスト
行政書士試験という難関を最短で乗り越えるための答えは、通信講座にあります!通信講座が推奨される明確な理由があります。
➀通信講座なら自己のペースで効率的に学習できる
時間や場所を選ばず、利用可能な瞬間を学習に充てることができます。これは通勤や通学の途中、または家事や昼休みなど、日常の隙間時間にも柔軟に勉強できることを意味します。忙しくても、生活リズムに合わせて自由に学習を進められます。
②経済的にお得です。
対面式の講座には、授業料とは別に交通費が加わりますが、通信講座では受講料が割安に設定されており、移動のための費用も不要です。
③サポート体制の面で優れています。
独学での勉強では解決が難しい疑問点も、通信講座ではサポート体制がしっかりと整っているため、気軽に質問でき、スムーズに勉強を続けることが可能です。不安を感じることなく学びを深めることができます。
フォーサイトの行政書士 通信講座の特徴
高合格率が魅力のフォーサイト提供の行政書士通信講座について、その特色を解説します。
➀たったの4ヶ月で行政書士試験に合格!
一般には1年の学習期間が推奨されますが、フォーサイトの講座を利用すれば、4ヶ月で合格する受講生もいます。フォーサイトは合格を最優先に考えた教材開発を行っており、その結果、短期間での合格が可能になっています。
②不合格に終わっても大丈夫!
受講した費用はしっかり全額返金されます。
③フォーサイトが提供するフルカラーテキストは、満足度が90%以上という驚きの実績
試験内容を充分に網羅しており、重要な情報は色分けされ、理解を促進する多くのイラストが特徴で、これらが合格率を高めています。
④講師経験20年以上のベテラン講師陣
福澤繁樹先生、五十嵐康光先生、北川えり子先生が指導を担当しているフォーサイトの行政書士講座では、彼らの豊富な経験と専門知識を活かし、カリキュラムに基づいた授業と教材の作成が行われています。
⑤「eライブスタディ」は、通信講座でもライブのオンライン講義を受けられる新しい形式です。
自習中心の通信教育では学習ペースが落ちがちですが、定期的なライブ授業に参加することで、学習リズムを一定に保つことが可能になります。
行政書士 通信講座を体感するなら資料請求しよう!
通信講座に手を出したことがない方や、一度挑戦して挫折した経験のある方々にとって、もう一度通信講座に挑戦することは大きな不安につながるかもしれません。その不安を解消する第一歩として、無料の資料請求から始めてみるのが良いでしょう。
資料を請求した際には、以下の体験がお待ちしています。
➀サンプルテキストや問題集に目を通すことで、実際に使われている教材を手に取り、どれほどわかりやすく、学習しやすいかを実感できます。
②eラーニングを無料で体験するチャンスがあります。 これを通じて、スマホがあればいつでもどこでも勉強可能なことを実際に感じることができます。
③最短で行政書士試験に合格するためのテクニックを詰め込んだノウハウ書をプレゼントいたします。
1分で完了!
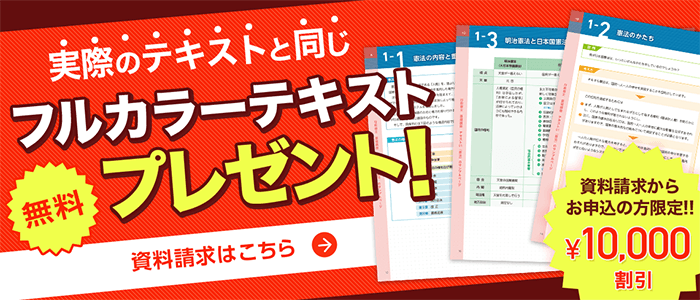
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ















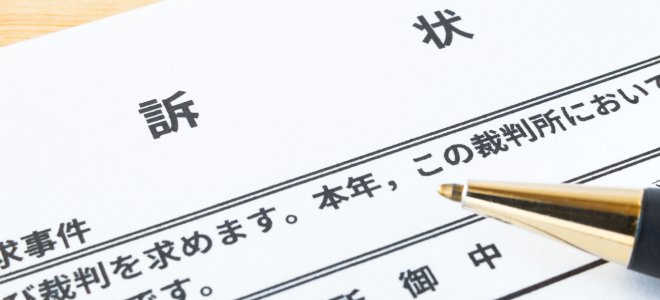


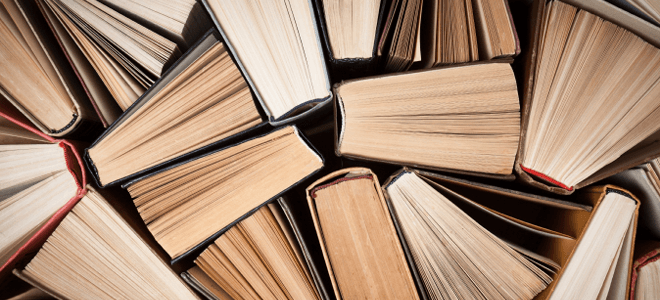



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


