行政書士試験とはどのような試験?
更新日:2019年9月26日

行政書士試験は、法律系国家資格の中では比較的合格しやすい試験であると言われています。一方で、合格率は10%前後と決して高くはありません。
どのような試験科目があるのか、試験内容について理解を深めましょう。
- 行政書士は、行政書士法にもとづく国家資格者であり、書類の作成、提出の代理、または代行を行ったりすることができます。
- 試験科目は「行政書士の業務に関し必要な法令等(法令等科目)」と「行政書士の業務に関連する一般知識等(一般知識科目)」があります。
- 試験は毎年11月の第2日曜日に実施されます。
- 行政書士試験は、絶対評価式の試験です。
- 試験範囲は非常に広いので、まずは合格ラインの6割を目標にメリハリをつけた学習を心がけましょう。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
行政書士とは?
まず、行政書士とはどのような資格なのでしょうか。
行政書士は、行政書士法にもとづく国家資格者であり、他人の依頼を受けて報酬を得て、以下のような書類を作成したり、提出の代理、または代行を行ったりすることができます。また、それらの書類作成の相談に応じることもできます(=コンサルティング業務)。
| 書類の種類 | 例 |
|---|---|
| ①官公署に提出する書類 |
|
| ②権利義務、事実証明に関する書類 |
|
上記の例は代表的なものですが、それ以外にも扱える書類の種類は非常に多く、8,000種類〜10,000種類とも言われています。そのため、ある一定の業務に専門特化する行政書士もいれば、様々な種類の業務を幅広く行う行政書士もいます。そういった意味では、個性の発揮しやすい仕事であるとも言えるでしょう。
なお、行政書士試験に合格すると、すぐに行政書士として登録し、業務を行うことができます。申請から登録までに約1ヶ月〜1ヶ月半の審査期間が設けられています。
行政書士試験の概要
試験科目は、「行政書士の業務に関し必要な法令等(法令等科目)」と「行政書士の業務に関連する一般知識等(一般知識科目)」があります。
出題される法令等科目は、憲法、行政法、民法、商法、基礎法学の5つであり、46問のうち、行政法が22問と、大きなウェイトを占めています。
一般知識科目の出題範囲は、政治・経済・社会、情報通信、個人情報保護、文章理解です。「択一式」と「記述式」での出題があります。
行政書士試験の試験日
行政書士試験は、毎年11月の第2日曜日に実施されます。(※令和6年(2024年)の試験日は11月10日(日)です。)試験日程は、午後1時から午後4時までの3時間です。
正確な試験日、試験日程については、試験実施団体である「一般財団法人 行政書士試験研究センター」のホームページを確認するようにしてください。なお、例年7月末頃に試験の公示が行われ、8月末頃に出願が締め切られます。
行政書士試験の試験会場
試験会場は、全国で約60箇所の中から受験を希望する会場を選んで申し込みます。試験会場の詳細については、「一般財団法人 行政書士試験研究センター」のホームページを確認してください。
行政書士試験は難しい?
行政書士試験は、年齢や性別、学歴等に関係なく、誰でも受験することができます。そのため、とても人気度の高い試験です。
記述式問題が毎年3問出題される!
行政書士試験では、記述式が毎年3題出題されます。
出題科目は民法1問、行政法2問です。
事例問題に対して、40文字前後で解答する形式となっています。
字数はさほど多くはありませんが、ポイントを押さえた解答が求められ、配点も1問20点、合計で60点と高いです。
その点が、マークシート方式のみの試験に比べると、難易度の高さにつながっています。
対策としては、過去問題等で形式をつかみ、ポイントを押さえて部分点を確実に確保する書き方を身につけることが大切です。
一般知識のウェイトも大きい!
民法や行政法などの法令等科目に加えて、一般知識科目の出題がある点も、行政書士試験の大きな特徴です。
出題範囲は「政治・経済・社会」「情報通信技術」「個人情報保護法」「文章理解」と非常に幅広く、難易度も、普段ニュースを目にしていれば容易に解答できるものから、行政書士の実務に関する知識が求められるようなものまで幅広く、対策が取りづらい面があります。
一方で、一般知識科目単体でも4割という基準点が設けられており、おろそかにすることもできません。法令等科目で満点近い点数を取ったのに、一般知識科目で基準点を満たせず、不合格だった、という悔しい例もあります。
日頃から時事問題等にアンテナを張っておくことが望ましいです。
相対評価ではなく絶対評価。合格ラインは6割
合格基準は、以下の3つをすべて満たすことです。
- 全体で6割以上(300点満点中180点以上)
- 法令等科目で5割以上(244点中122点以上)
- 一般知識科目で4割以上(56点中24点以上)
行政書士試験は、この基準を超えた人全員が合格する絶対評価式の試験です。
勉強を進めていく上で、完璧を目指す必要はありません。試験範囲は非常に広いので、まずは合格ラインの6割を目標に、基礎的な事項を中心に、メリハリをつけた学習を心がけましょう。
独学で受験するなら、学習計画が重要
独学での試験勉強の場合、他の受験生の状況が見えにくいために、試験まで勉強のモチベーションを保つことが難しいというデメリットがあります。
試験日まで充実した学習を継続するためには、学習計画を立て、学習のたびに見直すことが非常に重要です。
合格体験記を読んでみる、合格後の自分の姿をイメージする、こまめに小テストを行い、目標を達成できたらご褒美を設定する、など、モチベーションを一定に保つための工夫を行いつつ、学習計画に沿って学習を進めましょう。
まとめ
行政書士試験の合格率は10%程度と決して高くはないものの、これまで見てきたようなポイントを押さえた学習をしっかりと継続できれば、独学でも合格することも可能です。
効率よく最短で合格を目指すならば通信講座がおすすめです。
行政書士試験は絶対評価式であり、6割以上の点数が取れればよいということ、そのためには基礎的な事項を確実に理解することが大切であるということ、この二点を念頭に置いて、試験日まで頑張っていきましょう!
行政書士講座 最短合格なら通信講座がベスト
難易度が高い行政書士試験を手早くクリアするためには、通信講座を利用するのが最適です。この選択が一番良いと言われる理由があります。
➀通信講座は忙しい人に最適!!
通信講座なら自分自身のペースでどのような環境でも学習が可能になります。まさに、通勤時間や自宅での空き時間、仕事の休憩中など、いつでもどこでも勉強ができる柔軟性が鍵です。どれだけ仕事、家事、育児に追われていても、各自の生活スタイルに適した学習が実現できます。
②費用面でのメリットがあります。
直接通学する講座は授業料に加えて交通費も必要ですが、通信講座を利用すれば、受講費用が比較的安く、かつ交通費を気にする必要がありません。
③学習サポートが充実しています。
市販のテキストでの自習では出会った疑問を自分で調べる必要がありますが、通信講座では質問対応や学習アドバイスなど、豊富なサポートが用意されています。そうした支援のおかげで、わからない点を残さずにしっかりと学習を進めることができます。
フォーサイトの行政書士講座 通信講座の特徴
ここでは、高合格率で知られるフォーサイトの行政書士通信講座の主な特徴をご紹介します。
➀わずか4ヶ月での合格実績あり!
通常、行政書士試験の合格には約12ヶ月の準備期間が見込まれますが、フォーサイトのコースを受講すれば、4ヶ月で合格することが可能です。この短期間での成功は、フォーサイトが合格点を目指した教材作りに注力しているからこそ実現できます。
②合格できなかった場合でも心配無用です!
受講料は全額戻ってきます。
③満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト
試験に必要な情報量、重要情報のカラー分け、理解を深めるイラストが豊富に含まれており、それが高い合格率につながっています!
④フォーサイトの行政書士講座は、講師歴20年以上を誇る福澤繁樹先生、五十嵐康光先生、北川えり子先生の実力派の講師陣によって運営
これら経験豊富な教師たちが、講座のカリキュラムに沿った質の高い授業や教材を提供しています。
⑤通信講座でありながら、ライブ配信の授業が受けられる「eライブスタディ」
周期的に実施されるライブ配信講義のことです。一般的に通信講座は独学が基本ですが、このシステムを利用することで、授業のペースを保ちやすくなり、学習進度の遅れを防ぐことができます。
フォーサイトの行政書士講座 通信講座を体感するなら資料請求しよう!
これまで通信講座の経験がなかったり、試してみて途中で断念したことのある方々は、通信講座の開始に際して不安を感じるのが普通です。そんな時は、まず無償の資料請求から試してみることを推奨します。これが不安を軽減する手始めになります。
資料請求によって、こんな特別な体験が受けられます。
➀教材のサンプルや問題集を見ることで、実際の教材がどのようなものかを体験し、その理解のしやすさや学習のしやすさを評価できます。
②無料でeラーニング体験が可能です。 スマートフォンがあれば、場所を選ばずにいつでも学習できるメリットを直接体感することができます。
③行政書士試験合格の秘訣を集めたノウハウ書が、無料で提供されます。
1分で完了!
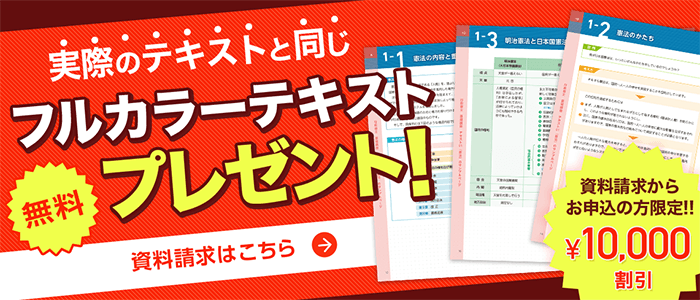
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ















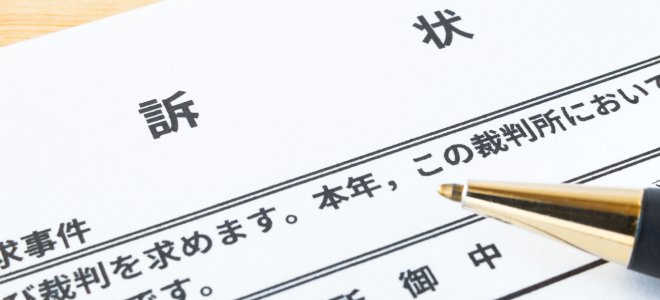


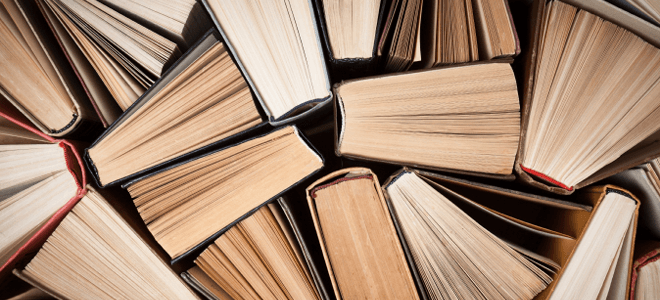



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


