行政書士のテキストと問題集に本格的に取り組んだのは9月から!

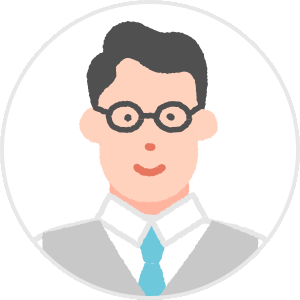
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 40代 |
| 試験年度 | 2016年(28年度) |
| エリア | 香川県 |
| 勉強時間 | 400時間 |
| 勉強期間 | 1年間 |
| 職業 | 無職 |
| 勉強法 | 記述式,選択肢,過去問,模試 |
| 商品 | DVD,テキスト,問題集 |
| 受験回数 | 初学者(1回目) |
| 試験科目 | 憲法,民法,行政法,商法,基礎法学,一般知識,会社法 |
私はこの年齢まで行政書士という資格自体知りませんでした。
勤めていた会社が労働基準法も知らない会社だったので、社労士の資格を取ろうと思い調べていた時に初めて行政書士という資格を知りました。
12月に教材が届き、最初の1か月半くらいは1日4、5時間まずはテキストを理解出来なくても最後まで読み進めるという福澤先生のいう通りに基礎法学、憲法、民法、行政法を2回はざっと目を通しました。
初学者の私には理解出来ず。
3回目にはぼんやりと把握することが出来たので、覚えていくことに心がけました。3回目が終わって問題集に取り掛かり3割程度の正解だったのを覚えています。
その後の7か月間は毎日の残業と休日出勤でテキストを見る気力もなく、ただ毎日毎日見るともなくDVD で民法と行政法を流し続けてそのまま眠る生活でした。
日曜日だけは4時間勉強をすると決めて問題集を解き、間違った所だけテキストで復習その繰り返しです。一般知識を除けば156点だけ取れば受かるのだからと自分に言いきかせて焦らない、焦らないと。
9月のおわりに退職したので、それから1日に5時間は民法、行政法をまた問題集をして、間違った所だけ復習。この頃の民法と行政法の正解率は60%弱くらいだったと思います。
商法もテキスト、DVD を2回くらい最後まで目を通し、1日30分ほど問題集から復習、問題集から復習しました。会社法は1回目を通し問題集をしたけれど理解出来ないのでそこで終わりにしました。
一般知識も個人情報保護法関係だけ目的条項を覚え、あとは何となくぼんやりと覚える程度に抑え、時間があれば民法、行政法の問題集からテキストの復習の繰り返しを最後まで続けました。
記述対策は最後の2週間くらいで遅かったと後悔しました。記述をすることで理解出来ていないところが解ってきたり、知識が増えることにもっと早く気付くべきでした。
試験は、時間配分も分からないので、問題文の正しいのを答えよか、誤っているのを答えよかを間違えないように、その部分に下線を引き、良く確認してから問題を解くことには注意しました。
問題のほとんどは過去問で見たような選択肢が多かったので落ち着いて解答出来ました。
記述式の財産分与の目的はという問題が終了5分前まで全く解らなかったですが、落ち着け落ち着けととりあえず何か書くことと思いひらめきで3つ書きギリギリ終了でした。
あとで解答見た時にほぼ合ってると思い合格は確信しました。
私が思ったことは試験は落ち着いて、諦めずにです。勉強は解らないところだけ繰り返しすること。覚えるのではなく、理解することが大事だと思いました。
私はフォーサイトの教材以外使っていないし、模試も受けていません。この教材だけで200点取れました。
良い教材をありがとうございました。
勤めていた会社が労働基準法も知らない会社だったので、社労士の資格を取ろうと思い調べていた時に初めて行政書士という資格を知りました。
12月に教材が届き、最初の1か月半くらいは1日4、5時間まずはテキストを理解出来なくても最後まで読み進めるという福澤先生のいう通りに基礎法学、憲法、民法、行政法を2回はざっと目を通しました。
初学者の私には理解出来ず。
3回目にはぼんやりと把握することが出来たので、覚えていくことに心がけました。3回目が終わって問題集に取り掛かり3割程度の正解だったのを覚えています。
その後の7か月間は毎日の残業と休日出勤でテキストを見る気力もなく、ただ毎日毎日見るともなくDVD で民法と行政法を流し続けてそのまま眠る生活でした。
日曜日だけは4時間勉強をすると決めて問題集を解き、間違った所だけテキストで復習その繰り返しです。一般知識を除けば156点だけ取れば受かるのだからと自分に言いきかせて焦らない、焦らないと。
9月のおわりに退職したので、それから1日に5時間は民法、行政法をまた問題集をして、間違った所だけ復習。この頃の民法と行政法の正解率は60%弱くらいだったと思います。
商法もテキスト、DVD を2回くらい最後まで目を通し、1日30分ほど問題集から復習、問題集から復習しました。会社法は1回目を通し問題集をしたけれど理解出来ないのでそこで終わりにしました。
一般知識も個人情報保護法関係だけ目的条項を覚え、あとは何となくぼんやりと覚える程度に抑え、時間があれば民法、行政法の問題集からテキストの復習の繰り返しを最後まで続けました。
記述対策は最後の2週間くらいで遅かったと後悔しました。記述をすることで理解出来ていないところが解ってきたり、知識が増えることにもっと早く気付くべきでした。
試験は、時間配分も分からないので、問題文の正しいのを答えよか、誤っているのを答えよかを間違えないように、その部分に下線を引き、良く確認してから問題を解くことには注意しました。
問題のほとんどは過去問で見たような選択肢が多かったので落ち着いて解答出来ました。
記述式の財産分与の目的はという問題が終了5分前まで全く解らなかったですが、落ち着け落ち着けととりあえず何か書くことと思いひらめきで3つ書きギリギリ終了でした。
あとで解答見た時にほぼ合ってると思い合格は確信しました。
私が思ったことは試験は落ち着いて、諦めずにです。勉強は解らないところだけ繰り返しすること。覚えるのではなく、理解することが大事だと思いました。
私はフォーサイトの教材以外使っていないし、模試も受けていません。この教材だけで200点取れました。
良い教材をありがとうございました。
3おめでとう
行政書士の合格体験記
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。
×


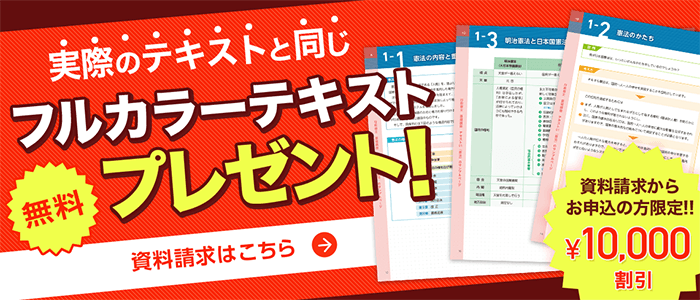















 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


