行政書士の問題の取り組み方の紹介。試験では残り10分で3問直しました

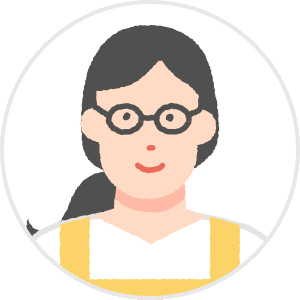
| 性別 | 女性 |
| 年代 | 50代 |
| 試験年度 | 2017年(29年度) |
| エリア | 大阪府 |
| 勉強時間 | 1000時間 |
| 勉強期間 | 8ヶ月間 |
| 職業 | パート・アルバイト |
| 勉強法 | 過去問,模試 |
| 商品 | テキスト,問題集,合格手帳,eラーニング |
| 受験回数 | 初学者(1回目) |
| 試験科目 | 憲法,民法,行政法,商法,基礎法学,一般知識 |
eラーニング使用回数
※eラーニングの使用回数となり、実際の学習時間とは異なります。
教材の取り組み方ですが、まず、テキストのない一般知識B(文章問題)を解いてしまい、その後、雑学要素もあって取り組みやすい一般知識A、テキストが他教科に比べて圧倒的に薄い基礎法学、商法の順番でテキストを一読し、過去問に目を通しました。
当然のことながら憲法、民法、行政法を後回しにしたツケは大きく、試験直前まで苦しみました。
ただ、もし最初に民法もしくは行政法に手をつけていたならば、間違いなく挫折していました。無事に試験当日を迎えるために、どのテキストから始めるかを考えることは大切だと思います。
各教科の過去問は早くに手をつけ、その解説をしっかり読み込みました。最初は解けなくても出題傾向は見えてきます。
また、文章問題、記述問題が不得意だと思われる方は、早めに市販の問題集を一冊追加して解いてみるのも手です。
私は記述の得点次第でギリギリ合格ラインを上回るような気がしたこと、また、部分点を狙う意味もあって、10月に入ってから市販の問題集を購入し、突貫工事で片づけました。かえって動揺を呼び込むのではとも思いましたが、やらないことで不安が残るよりも、やったことで不安を消すほうを選びました。
実際の試験では、まったく歯が立たない問題もありましたが、あれだけ解いてわからないのだから仕方がないと、動揺することなく諦め、気持を切り替えることができました。
合格手帳は一番活用しました。自分の勉強時間の多い少ないが一目瞭然ですから、プレッシャーにもなりましたが、励みにもなりました。
道場破りでは、確認テストの設問、解説をすべてワードにまとめなおしました。これだけで、一冊の総合問題集のようになり、試験前日にはできないところだけを選び、全教科の最終確認に活用しました。
過去問の難易度ですが、たとえA(やさしい問題でとりこぼしのできない問題)であってもテキストに扱いがなく、参照しようがないものもあります。この場合、やはり、設問の解説を読み込むか、自分で調べるほかないように思います。
また、テキストの内容は、Aゾーン(最重要)、Bゾーン(重要)、Cゾーン(必須)に分かれてはいましたが、手抜きできるゾーンがなく(なにしろ、最重要、重要、必須ですので)、結局はすべてのゾーンを均等に勉強したように思います。
それはつまり、テキストをくまなく勉強するということでした。
試験問題を解く順番は、フォーサイトの模試を二度解くことで自然と決まってくると思います。私の場合は問題冊子の後ろから解いていきました。
時間配分は、一般知識→記述→多肢選択に60分、残りの40問に90分。得意科目から解くというより、大きくブロック分けしたような感覚です。そして、記入ミスの有無を確認、または答えを一つに絞り切れなかったものに戻って再考するのに30分。
一度決めた答えは下手に直さないほうがいいとも思いますが、試験後半を過ぎれば緊張が解け、頭のまわりも良くなってくるので、迷った答えが明確な根拠のもとで一つに絞れることが起こってきます。
私は残り10分で、3問の答えを書き直して正解でした。どうか最後の最後まであきらめないでください。
試験終了後はとにかく、力を出し尽くしたという満足感、もう勉強しなくてもいいという開放感で本当にうれしかったです。答え合わせは一切せずに合格発表の日を迎えました。
自分の番号を見つけた時は逆に戸惑い、自分の受験番号を間違えて記憶しているのではと受験票を再確認したくらいです。
50代の、法律勉強未経験の私がフォーサイトの教材+市販記述問題集一冊だけで合格できました。みなさまも合格を手にできますように。
当然のことながら憲法、民法、行政法を後回しにしたツケは大きく、試験直前まで苦しみました。
ただ、もし最初に民法もしくは行政法に手をつけていたならば、間違いなく挫折していました。無事に試験当日を迎えるために、どのテキストから始めるかを考えることは大切だと思います。
各教科の過去問は早くに手をつけ、その解説をしっかり読み込みました。最初は解けなくても出題傾向は見えてきます。
また、文章問題、記述問題が不得意だと思われる方は、早めに市販の問題集を一冊追加して解いてみるのも手です。
私は記述の得点次第でギリギリ合格ラインを上回るような気がしたこと、また、部分点を狙う意味もあって、10月に入ってから市販の問題集を購入し、突貫工事で片づけました。かえって動揺を呼び込むのではとも思いましたが、やらないことで不安が残るよりも、やったことで不安を消すほうを選びました。
実際の試験では、まったく歯が立たない問題もありましたが、あれだけ解いてわからないのだから仕方がないと、動揺することなく諦め、気持を切り替えることができました。
合格手帳は一番活用しました。自分の勉強時間の多い少ないが一目瞭然ですから、プレッシャーにもなりましたが、励みにもなりました。
道場破りでは、確認テストの設問、解説をすべてワードにまとめなおしました。これだけで、一冊の総合問題集のようになり、試験前日にはできないところだけを選び、全教科の最終確認に活用しました。
過去問の難易度ですが、たとえA(やさしい問題でとりこぼしのできない問題)であってもテキストに扱いがなく、参照しようがないものもあります。この場合、やはり、設問の解説を読み込むか、自分で調べるほかないように思います。
また、テキストの内容は、Aゾーン(最重要)、Bゾーン(重要)、Cゾーン(必須)に分かれてはいましたが、手抜きできるゾーンがなく(なにしろ、最重要、重要、必須ですので)、結局はすべてのゾーンを均等に勉強したように思います。
それはつまり、テキストをくまなく勉強するということでした。
試験問題を解く順番は、フォーサイトの模試を二度解くことで自然と決まってくると思います。私の場合は問題冊子の後ろから解いていきました。
時間配分は、一般知識→記述→多肢選択に60分、残りの40問に90分。得意科目から解くというより、大きくブロック分けしたような感覚です。そして、記入ミスの有無を確認、または答えを一つに絞り切れなかったものに戻って再考するのに30分。
一度決めた答えは下手に直さないほうがいいとも思いますが、試験後半を過ぎれば緊張が解け、頭のまわりも良くなってくるので、迷った答えが明確な根拠のもとで一つに絞れることが起こってきます。
私は残り10分で、3問の答えを書き直して正解でした。どうか最後の最後まであきらめないでください。
試験終了後はとにかく、力を出し尽くしたという満足感、もう勉強しなくてもいいという開放感で本当にうれしかったです。答え合わせは一切せずに合格発表の日を迎えました。
自分の番号を見つけた時は逆に戸惑い、自分の受験番号を間違えて記憶しているのではと受験票を再確認したくらいです。
50代の、法律勉強未経験の私がフォーサイトの教材+市販記述問題集一冊だけで合格できました。みなさまも合格を手にできますように。
1おめでとう
行政書士の合格体験記
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。
×


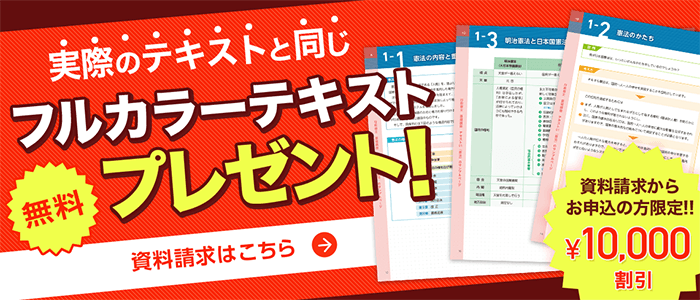















 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


