「過去問」は少なくとも4回、多いところで10回解く!行政書士の勉強を7時間以上/日!

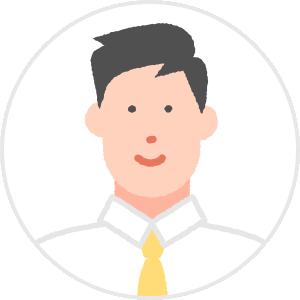
| 性別 | 男性 |
| 年代 | 20代 |
| 勉強期間 | 9ヶ月間 |
| 職業 | パート・アルバイト |
| 勉強法 | 過去問,模試 |
| 商品 | CD,テキスト,問題集 |
| 試験科目 | 憲法,民法,行政法,基礎法学,一般知識 |
| 学習スタイル | 通信講座,予備校 |
山田先生の「行政書士に面白いほど受かる本」には、その幅広い仕事内容や各教科の詳細、得点の取り方などが分かりやすく載っていました。それを読み、試験に挑戦してみようと思い、通信講座を申し込んだのが2月です。
教材が届いてからしたのは、受講ガイドを読みながらのプラン作りです。
そのプランとは──
2月下旬~3月下旬は基礎法学。3月中旬~3月までは憲法を学ぶ。4月~5月中旬が行政法。5月中旬~6月までが地方自治法。7月は、民法。8月は予備月です。9月は苦手分野の克服とし、10月は苦手分野の見直しと模擬試験としました。
進め方としては──
1. 各科目のスケジュールをしっかりと意識する。
2. 講義CDを聞きながらテキストを二回り読む。
3. 「過去問」を順番に解きながら、問題集の説明通り、○△×を記入する。正解しても○印は全て解説の説明が理解できるまでつけない。各科目の期間内に3~4回はまわせるように1日の問題数を設定する。
分からない問題はテキストでチェック。どうしても分からないものは、質問する。
4. 普段の車移動中もプラン通り、講義CDを何度も聴く。
5. 各科目の終了日前までには確認テストを提出する。
1日の勉強時間は5~6時間でした。結果的には7月中に終わらせる予定が8月中旬くらいまでかかりました。
一般知識は、主に文章理解に絞り、1時間の勉強の始めに「過去問」を中心に30分くらいやっていました。苦手なものは先にやるほうが、気が楽だと思います。
時事対策は、新聞の語句解説を毎日切り取り、専用のノートに貼り、勉強の休憩時間に読んでいました。この切り貼りは、試験前日まで欠かさずにやっていました。
記述対策としては、各科目の勉強がある程度進んでから、テキストにある専門用語をマーカーでチェックしていました。
8月、各科目の「過去問」を4~5回まわし終わったところで、試験に慣れるために、9月下旬まで週1回予備校の講座に参加しました。間違えた問題はチェックし繰り返し解きました。と同時にフォーサイトのテキストの該当箇所に付箋を貼り、余白に必要事項を記入していきました。
また「過去問」の△×の問題も解いていきました。車中での講義CDは9月まで勉強してきた順に繰り返し聴いていました。8月の勉強時間は1日5~6時間です。
10月になると、「過去問」と予備校講座で間違えた問題(△×の問題)をさらに繰り返し解きました。「過去問」は少ないところで4回くらい、多いところで10回くらい解きました。講義CDは条文を覚えるため、憲法のみを聴いていました。10月の勉強時間は1日7~8時間です。
気持ちを維持するのに役立つ合格体験記は、教材とともに持ち歩き、休憩時間などに何度も読みました。いい言葉やアドバイスに、テキストと同じようにラインを引いたり、マーカーで塗ったりして目立つようにしていました。
講義CDに入っている福澤先生の励ましもありがたかったです。
今回経験したこと、学んだことを活かして、他資格などの勉強も続けていきたいと思っております。受験生の皆様も、合格を目指して頑張ってください。
教材が届いてからしたのは、受講ガイドを読みながらのプラン作りです。
そのプランとは──
2月下旬~3月下旬は基礎法学。3月中旬~3月までは憲法を学ぶ。4月~5月中旬が行政法。5月中旬~6月までが地方自治法。7月は、民法。8月は予備月です。9月は苦手分野の克服とし、10月は苦手分野の見直しと模擬試験としました。
進め方としては──
1. 各科目のスケジュールをしっかりと意識する。
2. 講義CDを聞きながらテキストを二回り読む。
3. 「過去問」を順番に解きながら、問題集の説明通り、○△×を記入する。正解しても○印は全て解説の説明が理解できるまでつけない。各科目の期間内に3~4回はまわせるように1日の問題数を設定する。
分からない問題はテキストでチェック。どうしても分からないものは、質問する。
4. 普段の車移動中もプラン通り、講義CDを何度も聴く。
5. 各科目の終了日前までには確認テストを提出する。
1日の勉強時間は5~6時間でした。結果的には7月中に終わらせる予定が8月中旬くらいまでかかりました。
一般知識は、主に文章理解に絞り、1時間の勉強の始めに「過去問」を中心に30分くらいやっていました。苦手なものは先にやるほうが、気が楽だと思います。
時事対策は、新聞の語句解説を毎日切り取り、専用のノートに貼り、勉強の休憩時間に読んでいました。この切り貼りは、試験前日まで欠かさずにやっていました。
記述対策としては、各科目の勉強がある程度進んでから、テキストにある専門用語をマーカーでチェックしていました。
8月、各科目の「過去問」を4~5回まわし終わったところで、試験に慣れるために、9月下旬まで週1回予備校の講座に参加しました。間違えた問題はチェックし繰り返し解きました。と同時にフォーサイトのテキストの該当箇所に付箋を貼り、余白に必要事項を記入していきました。
また「過去問」の△×の問題も解いていきました。車中での講義CDは9月まで勉強してきた順に繰り返し聴いていました。8月の勉強時間は1日5~6時間です。
10月になると、「過去問」と予備校講座で間違えた問題(△×の問題)をさらに繰り返し解きました。「過去問」は少ないところで4回くらい、多いところで10回くらい解きました。講義CDは条文を覚えるため、憲法のみを聴いていました。10月の勉強時間は1日7~8時間です。
気持ちを維持するのに役立つ合格体験記は、教材とともに持ち歩き、休憩時間などに何度も読みました。いい言葉やアドバイスに、テキストと同じようにラインを引いたり、マーカーで塗ったりして目立つようにしていました。
講義CDに入っている福澤先生の励ましもありがたかったです。
今回経験したこと、学んだことを活かして、他資格などの勉強も続けていきたいと思っております。受験生の皆様も、合格を目指して頑張ってください。
66おめでとう
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。
×


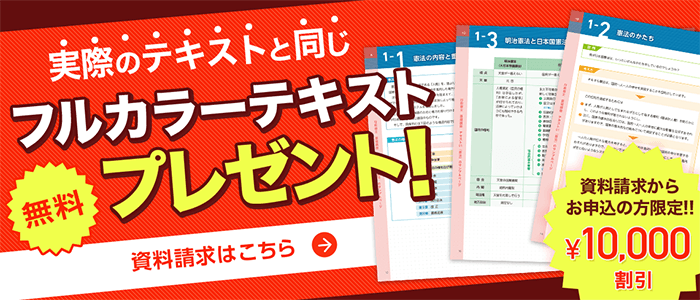















 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


