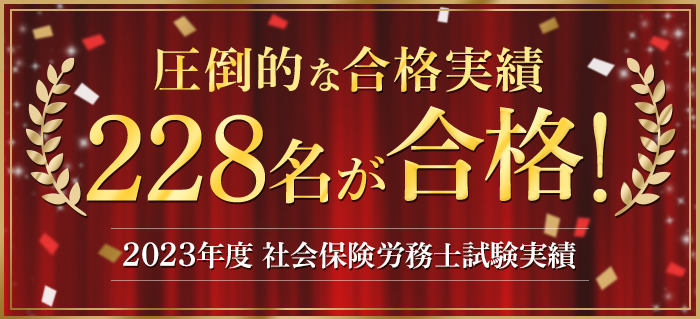「社労士チャンネル」の法改正ウォッチです。このシリーズでは、社会保険労務士の視点から、社会保険制度に関連する最新の法改正の中でも、特に「数字」が関わる重要な変更点に焦点を当てて解説しています。
今回のテーマは、後期高齢者医療制度における「窓口負担割合の見直し」です。この見直しにより、これまでの制度に新たな割合が導入されました。
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方々が加入する医療保険制度であり、これまでは自己負担が原則1割とされていました。しかし、今回の法改正によって、その窓口負担のあり方が変わります。具体的に何割の負担が新たに導入されたのか、そしてどのような方が対象となるのかなど、制度改正の核心部分を詳しく解説していきます。
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方々が加入する医療保険制度です。この制度では、医療費の7割を保険が負担します。75歳以上の方の多くは年金暮らしであるため、負担能力が高くないことを考慮し、自己負担については原則として1割と定められています。しかし、中にはお仕事をしており、比較的高い報酬を得ている方もいらっしゃいます。このような現役並みの所得があり、負担能力が高いと判断される方については、例外的に自己負担が3割とされていました。つまり、これまでの後期高齢者医療制度における自己負担割合は、原則1割と例外3割の2択でした。
新たな窓口負担割合(2割負担)の導入

これまでの後期高齢者医療制度における自己負担割合は1割または3割でしたが、今般の法改正により、新たに2割負担の区分が導入されました。この2割負担となる区分は「一定以上所得者」と呼ばれます。これにより、自己負担割合は1割、2割、3割の3区分となりました。今回の見直しは、後期高齢者医療制度における医療費窓口負担の仕組みに大きな変更をもたらすものです。
負担割合見直しの背景と目的
今回の窓口負担割合の見直しには、日本の社会構造の変化が大きく影響しています。令和4年版厚生労働白書によると、後期高齢者の医療費の約5割は公費(税金)で賄われており、さらに約4割は現役世代からの後期高齢者支援金によって支えられています。つまり、後期高齢者医療制度は、その財源の大部分を公費や現役世代からの支援に依存している構造です。残りの約1割を75歳以上の後期高齢者の保険料で負担するという支え合いの仕組みとなっています。
近年、少子高齢化が進行し、令和4年度にはいわゆる団塊の世代が後期高齢者となり始めました。これにより、現役世代からの後期高齢者支援金が急増することが見込まれています。このような状況の中、現役世代の負担上昇を可能な限り抑えるため、そして持続可能な全世代型社会保障制度を構築する観点から、後期高齢者の方々にも負担能力に応じた応分の負担をしていただくことが必要であると考えられています。今回の窓口負担割合の見直しは、こうした背景に基づき、後期高齢者の中でも比較的所得の高い方に2割の負担をお願いすることで、制度全体の持続可能性を高め、現役世代の負担を軽減することを目的としています。
「一定以上所得者」の具体的な定義と適用時期
新たに2割負担の対象となる「一定以上所得者」とは、具体的にどのような方々を指すのでしょうか。この定義は、高齢者の負担能力や生活状況を考慮した上で定められています。まず前提として、住民税課税所得が28万円以上であることが条件となります。ここでいう所得とは、収入そのものではなく、収入から各種控除を差し引いた後の金額を指します。
課税所得が28万円以上であることに加え、以下のいずれかの年収基準を満たす場合に「一定以上所得者」に該当します。 ・単身者の場合:年収200万円以上 ・同じ世帯に後期高齢者の方が複数いる場合(例えば夫婦):合計年収320万円以上
つまり、課税所得が28万円以上であっても、単身で年収200万円未満の方や、世帯に後期高齢者が複数いて合計年収320万円未満の場合は、「一定以上所得者」には該当せず、従来の1割負担が維持されます。この窓口負担割合の見直しは、2022年10月1日から施行されています。
窓口負担額の具体例と改正前後の比較
それでは、実際に医療機関を受診した場合の窓口負担額はどのように変わるのでしょうか。具体例を挙げて見てみましょう。
例えば、課税所得が28万円以上で、年収210万円の単身者を想定します。この方は「一定以上所得者」に該当します。月の医療費総額が8万円だったとします。
改正前(2022年9月30日まで)は、自己負担割合が1割でしたので、窓口での支払額は8万円 × 0.1 = 8,000円でした。
改正後(2022年10月1日以降)は、「一定以上所得者」として自己負担割合が2割となるため、単純計算では8万円 × 0.2 = 16,000円となります。
この例では、自己負担割合が1割から2割に上昇したことにより、月の自己負担額が8,000円から16,000円へと倍増し、8,000円の負担増となることがわかります。
新たな負担増に対する配慮措置
自己負担割合が1割から2割へと倍増することで、医療機関への受診を控えてしまうなど、必要な受診が抑制されることが懸念されます。このような急激な負担増による影響を緩和するため、配慮措置が設けられています。この配慮措置は、特に負担増の影響が大きい外来患者を対象としています。
具体的には、窓口負担割合が2割となる方について、施行後3年間(2022年10月1日から2025年9月30日まで)に限り、1ヶ月の外来医療における自己負担額の増加分を最大でも3,000円に抑えるというものです。これにより、急激な窓口負担の増加を緩和し、患者様が安心して医療を受けられるように配慮されています。ただし、この配慮措置は外来受診の場合に限定されており、入院医療にかかる自己負担には適用されませんので注意が必要です。
配慮措置を可能にする仕組み(高額療養費制度の活用)
配慮措置は、高額療養費制度を活用することで実現されます。高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、1ヶ月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分の金額が払い戻される制度です。この制度は、高齢者医療確保法だけでなく、健康保険法など他の医療保険制度にも共通して存在するものです。
配慮措置として、窓口負担が2割となる一定以上所得者の外来患者については、施行後3年間(2022年10月1日から2025年9月30日まで)における外来療養にかかる高額療養費算定基準額が特例的に設けられています。一般的な所得区分の方の場合、通常の外来療養の自己負担限度額は定められていますが、この配慮措置の対象となる方については、高額療養費制度の計算において、通常の限度額よりも低い金額が適用されることになります。これにより、結果として1ヶ月の自己負担額の増加が最大3,000円に抑えられる仕組みとなっています。
配慮措置による負担増の抑制効果の例
先ほどの例で、月の医療費総額が8万円、窓口負担割合が2割となる「一定以上所得者」である単身者の場合を改めて見てみましょう。配慮措置がなければ自己負担額は16,000円になるところでした。
配慮措置が適用された場合、高額療養費制度における自己負担限度額の計算に特例が適用されます。具体的には、施行後3年間の外来療養にかかる自己負担限度額の計算式は、6,000円 + (医療費総額 – 3万円)× 0.1 となります(ただし、上限額が定められています)。
この計算式に医療費総額8万円を当てはめると、 6,000円 + (80,000円 – 30,000円)× 0.1 = 6,000円 + 50,000円 × 0.1 = 6,000円 + 5,000円 = 11,000円
となります。つまり、配慮措置が適用されることで、この場合の窓口での自己負担額は11,000円となります。
改正前の自己負担額は8,000円でしたので、負担増は11,000円 – 8,000円 = 3,000円に抑えられていることがわかります。これは、配慮措置によって月の負担増が最大3,000円に抑えられるという内容と一致しています。このように、配慮措置は高額療養費制度の仕組みを利用して、急激な自己負担の増加を緩和しています。

まとめ:後期高齢者医療制度の改正ポイントと留意事項

今回の後期高齢者医療制度の改正の主なポイントは、以下の通りです。
- 自己負担割合に2割負担が導入されたこと: これまでの1割または3割に加え、「一定以上所得者」については2割負担が適用されるようになりました。
- 「一定以上所得者」の定義: 住民税課税所得が28万円以上であり、かつ単身者で年収200万円以上、または世帯に後期高齢者が複数いる場合は合計年収320万円以上の方が該当します。ただし、課税所得が28万円以上でも、これらの年収基準を満たさない場合は従来の1割負担となります。
- 配慮措置の適用: 施行後3年間(2022年10月1日~2025年9月30日)は、外来患者に限り、自己負担額の増加分が1ヶ月あたり最大3,000円に抑えられる措置が講じられています。
特に注意が必要なのは、配慮措置はあくまで外来受診に限定されるという点です。入院療養にはこの配慮措置は適用されず、2割負担の対象となる場合は、高額療養費制度の一般的な自己負担限度額に基づき負担額が計算されます。
今回の法改正は、後期高齢者医療制度を持続可能なものとし、全世代での支え合いを推進するための重要な見直しです。ご自身の所得状況や年収によって窓口負担割合が変わる可能性があるため、制度改正の内容をしっかりと理解しておくことが大切です。特に、新たに2割負担となる可能性がある方は、窓口負担額や配慮措置の適用について確認しておくことをお勧めします。