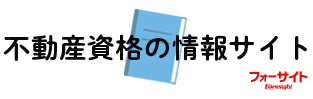ある程度の年齢になり、自分の将来を考えたときに、遺産相続という問題にぶつかる方もいるかと思います。一般の方を中心に考えれば、遺産としてもっとも大きなものは不動産ではないでしょうか。不動産をはじめ、自分の財産を親族などに贈与する場合、生きている間に贈与する生前贈与と、亡くなってから受け渡す相続があります。生前贈与と相続。何が違い、どちらがよりよい選択なのかについてまとめていきましょう。
目次
生前贈与と相続の違い
不動産にかかわらず、遺産となる財産を持っている方は、亡くなってから遺族に相続するか、生きているうちに誰かに自分の財産を贈与するかを選択することになります。遺産相続と生前贈与にはどのような差があるのでしょうか?
まず遺産相続に関しては、基本的に相続を受けられる相続人が法で定められています。これを法定相続人といい、法定相続人の順位によって遺産の相続は決められることになります。
しかし生前贈与の場合、この法定相続人という考え方はありません。財産の所有者が希望すれば、親族以外の第三者に贈与することも可能であり、だれにどの程度の財産を贈与するかを、自身の希望通りに決められるという違いがあります。
そして、遺産相続と生前贈与の最大の違いが税金に関する制度ということになります。続いてはそれぞれの税金に関して解説していきましょう。
生前贈与と相続における税金の違い
生前贈与と遺産相続では税金が大きく変わります。どちらが有利になるかは状況次第、相続する財産次第ということになりますが、不動産のように高額の財産の場合、相続のほうが税制面で有利になることがほとんどです。
生前贈与と遺産相続における税金の制度と、税率などについて解説していきましょう。
相続税
相続税を解説するには、まずは相続税額の算出順序を知ることが重要です。そこで順を追って算出手順をご紹介しましょう。
- 相続するすべての遺産の総額を出す
- 遺産総額から控除金額を差し引き課税遺産総額を算出する
- 課税遺産総額を法定相続人ごとに取得した場合の各相続人の課税相続金額を算出
- 各相続人ごとに課税相続金額に税率をかけ、相続税の総額を算出
- 相続税の総額を、相続人ごとの割合通りに按分する
- 各相続人ごとに税率控除を計算し相続税を収める
文字だけですと少々わかりづらくなりますので、細かく解説していきます。まず「課税遺産総額」の算出方法について。故人が遺した遺産から控除金額を差し引いた分が課税遺産総額となり、この金額に税率をかけることによって相続税は算出されます。課税遺産総額の計算式は以下の通りです。
課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額(3,000万円+遺産相続人の人数×600万円)
仮に遺産相続人が1名の場合、3,600万円までが、遺産相続人が5人の場合は、6,000万円まで控除金額になります。一般的な家庭の多くの場合は、遺産の大部分が控除される、もしくは全額が控除されると考えて間違いありません。
相続税には税率があり、この税率は相続する遺産の金額によって変わります。税率は以下の表のとおりになります。
| 法定遺産相続分の所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ナシ |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
では、実際に遺産相続が発生した場合の遺産相続金額の算出手順を確認していきましょう。遺産相続に関しては、配偶者控除や未成年控除などほかにも控除額があります。
故人の遺産総額が不動産を含め1億円、法定相続人が配偶者と子が2人のケースを想定します。まず課税遺産総額を計算しましょう。
1億円-(3,000万円+600万円×3)=5,200万円
この5,200万円を3人の遺産相続人に分けます。
配偶者…5,200万円×1/2=2,600万円
子(1人あたり)…5,200万円×1/4=1,300万円
続いて、それぞれの相続税額を、上の表の税率をもとに算出します。配偶者も子も、課税遺産総額は1,000万円超~3,000万円以下の範囲ですので、控除金額50万円、税率15%になります。
配偶者…2,600万円×15%-50万円=340万円
子(1人あたり)…1,300万円×15%-50万円=145万円
3人が納める相続税の総額は630万円になります。この630万円を各相続人の割合通りに分配すると、以下のようになります。
配偶者…630万円×50%=315万円
子(1人あたり)…630万円×25%=157.5万円
実際には葬儀費用は非課税であったり、生命保険の課税金額などで納税額は変わりますが、計算方法の流れは以上の通りになります。
暦年課税
生前分与を行う場合、納税方法は2種類あります。そのうちのひとつである暦年課税について解説しましょう。暦年課税とは、生前贈与があった年に贈与税として納める方法になります。暦年課税は贈与の相手が誰であろうとかかる税金になります。
暦年課税は年間110万円までは基礎控除となります。生前贈与の金額が110万円以下であれば非課税となります。暦年控除の税率と控除額に関しては以下の表の通りになります。
| 基礎控除後の課税金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ナシ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
では実際の課税金額を計算していきましょう。条件は上の場合と同様に、遺産総額1億円、相続人は配偶者と子が2人のケースです。配偶者に5,000万円、子にそれぞれ2,500万円ずつ配分したとします。
配偶者…(5,000万円-110万円)×55%-400万円=2,289.5万円
子(1人あたり)…(2,500万円-110万円)×50%-250万円=945万円
納税額の総額を計算すると、4,179.5万円となり、遺産の半分は税金として納付することになります。ちなみに、贈与する側が「父母」・「祖父母」の直系尊属であり、受け取る側が20歳以上の場合、特例贈与財産用として、やや税率が軽減されます。特例の場合の税率は以下の通りです。
| 基礎控除後の課税金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ナシ |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続時積算課税制度
相続時精算課税制度とは、利用できる方に条件はありますが、贈与税として納めた税金を、相続の際に相続税として精算できるという利点があります。また贈与の控除額が2,500万円と高額に設定されていますので、不動産の生前贈与など、高額な贈与の場合はこちらの制度を利用するのがおすすめです。
贈与税の税率は一律20%。計算式は以下の通りになります。
贈与総額-控除額(2,500万円)=課税贈与額
課税贈与額×20%=贈与税
こちらも上と同じ条件で計算してみましょう。
配偶者…(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円
子(1人あたり)…(2,500万円-2,500万円)×20%=0円
配偶者は500万円の贈与税の納付が必要となり、相続よりも高額の税金を支払うことになります。贈与する側が直系尊属で60歳以上、贈与を受ける子が20歳以上という条件を満たしていれば、子は贈与税の支払い義務はなくなりますが、贈与した方が亡くなった場合、相続税として157.5万円の納税義務が発生します。
最後に暦年課税と相続時積算課税の違いについて表にまとめておきます。
| 暦年課税 | 相続時積算課税 | |
|---|---|---|
| 贈与税 | (贈与額-110万円)×累進課税(10~55%) | (贈与額-2,500万円)×20% |
| 条件 | 誰でも可 | 贈与側:直系尊属かつ60歳以上授与側:直系尊属かつ20歳以上 |
| 相続税との関係 | 相続税とは切り離して計算(贈与から3年以内に相続が発生した場合は相続税に加算) | 相続時に精算(精算時の財産の価値は贈与時の時価) |
| メリット | ・年間110万円以内であれば非課税で贈与可能 ・親族以外にも贈与可能 ・暦年課税から相続時積算課税への変更が可能 |
・控除金額が大きいため不動産など高額財産の贈与に向いている |
| デメリット | ・高額の財産は高い税率がかかる | ・暦年課税への変更は不可 ・年齢など贈与の条件がある |
生前贈与のほうが節税になるケース
上記の例を見ていただければわかる通り、基本的に贈与税よりも相続税のほうが安くなります。つまり生前贈与は税制面で不利になるということです。しかし、特別なケースにおいては、生前贈与のほうが得になるケースはありますので確認しておきましょう。
贈与額が110万円を超えないケース
不動産では可能性は低いものの、贈与額が110万円を超えないのであれば相続税も贈与税も0円ということになります。そもそも相続税の控除額が3,000万円+αと高額なため、それ以上の遺産があり、その中で110万円いかの財産があれば生前贈与をしたほうが節税になるということになります。
相続時までに不動産価値が急騰する場合
続いてかなり特殊なケースになりますが、相続時精算課税を利用して節税となるケースがあります。これは、生前贈与の段階で価値の低かった不動産が、相続の時点で価値が跳ね上がっているというケースです。不動産、特に土地の価値は、周辺の環境に大きく影響を受けます。それまであまり価値がなかった土地でも、近くに駅ができる、高速道路のICができる、大きな大学のキャンパスや大企業の支社、工場ができるなどの特殊な条件がそろうと、驚くほど価値が跳ね上がることがあります。
仮に生前贈与時の価値が1,000万円だった土地が、相続時に1億円になっていたとしましょう。しかも、相続時精算課税を利用できる状況だったとします。この場合生前贈与であれば控除額以下ですので非課税での贈与が可能です。相続時も、贈与時の価値で相続税を計算しますので、ほかに大きな財産がなければ非課税となります。
しかし、相続時に1億円の土地を、仮に成人している子が1人で相続した場合、相続税は以下の計算になります。
(1億円-3,600万円)×30%-700万円=1,220万円
つまり1,220万円の節税になるということになります。もちろんこれは非常に特殊なケースですが、可能性として提示しておきます。
生前贈与の注意点
いろいろな条件を加味したうえで、それでも生前贈与を行う場合に注意したい点についてまとめておきます。財産の贈与、相続に関してはトラブルが発生しやすいので、トラブルを避けるためにも確認しておきましょう。
必ず契約書を作成する
生前贈与に関しては、税務上の処理さえきっちり行えば、契約者がなくても口約束でも十分に可能です。しかし、契約書が残っていないと、実際に相続となった場合に遺族間でもめ事に発展する可能性があるため、契約書はしっかりと残しておきましょう。
この契約書は、贈与する側とされる側のみで作成しただけでは、あまり効力がありません。費用は掛かっても弁護士や司法書士などに仲介してもらい、できれば公証役場で保管することをおすすめします。
遺留分侵害額請求について
生前贈与で贈与した財産に関しては、状況次第で遺留分侵害請求の対象になるケースがあります。遺留分侵害請求とは、遺産相続の権利を持つ法的相続人が、自身の遺産分配分が少ない場合に起こせる請求で、贈与を受けた人に遺産としての不足分を請求できるという権利です。
こういった訴訟が起きないように、法定相続人となる方には事前にきっちりと説明し、納得してもらう必要があります。
基本的には相続のほうが税金は安くなる
生前贈与の贈与税と、遺産相続の相続税について解説してきました。基本的には贈与税よりも相続税のほうが安くなるケースが多く、よほど特殊なケースを除けば、相続をするほうが節税対策にはなります。
しかしそれでも何らかの理由で生前贈与を望む場合は、必ず法の専門家である弁護士や司法書士などに相談しましょう。生前贈与以外に節税対策になる方法があるかもしれませんし、生前贈与をするにしても、のちに禍根を残さないような方法を提案してもらえるはずです。
生前贈与を考えている方は、あくまでも慎重に、そして専門家の意見をよく聞いて決断することをおすすめします。