令和7年度 第57回社会保険労務士試験の解答速報・試験講評
2025/08/19
8月24日(日)に実施されました、令和7年度 第57回社会保険労務士試験の解答速報・試験講評をこちらのページで公開しています。
自己採点機能も公開しておりますので、ぜひご活用ください。
また、二神講師による試験講評を試験当日にライブ配信も実施いたしました。
※アーカイブでご覧いただけます。
解答速報
8月24日(日)に実施されました、令和7年度 第57回社会保険労務士試験の解答速報を公開いたします。
選択式
問1 労働基準法及び労働安全衛生法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 6 | 4 | 7 |
問2 労働者災害補償保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 4 | 16 | 18 |
問3 雇用保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 8 | 10 | 3 |
問4 労務管理その他の労働に関する一般常識
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 6 | 12 | 9 |
問5 社会保険に関する一般常識
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 5 | 14 | 9 |
問6 健康保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 10 | 7 | 20 |
問7 厚生年金保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 16 | 19 | 11 |
問8 国民年金法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 14 | 7 | 4 |
択一式
労働基準法及び労働安全衛生法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| D | D | A | E | A |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| E | D | D | C | E |
労働者災害補償保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | E |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| E | B | C | D | E |
雇用保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| B | D | B | B | A |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| A | A | E | A | D |
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| A | B | E | D | B |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| E | E | D | A | D |
健康保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| E | B | C | C | D |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| E | D | E | B | B |
厚生年金保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| C | E | B | C | D |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| D | B | E | C | D |
国民年金法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| B | B | E | D | D |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| D | B | C | E | E |
試験講評
選択式試験について
8月24日に、令和7年度社会保険労務士試験が実施されました。受験された方、お疲れ様でした。
今年度の選択式試験については、全体的に見た場合、極端に難しいというものではありませんでしたが、科目によっては、平均点が低くなることが予想されます。
「労働基準法」は、最近の傾向どおり、判例の問題がありました。
問題文1は、「付加金の支払」からの問題で、基本的な内容でした。
問題文2は、判例問題で「東朋学園事件」からの出題です。判例自体は、多くの受験者がテキストなどで見たことのある内容です。毎年、頭を悩ませる労働基準法の判例問題ですが、テキストレベルからの内容だったので、少しハードルは低めと言えるかもしれません。
「労働安全衛生法」ですが、問題文3は、「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」という通達からの出題でした。「作業管理」が「作業環境管理」及び「健康管理」とともに、労働衛生の3管理の1つとして位置づけられていることを知らないと、選ぶのに苦労したかもしれません。問題文4は、「譲渡等の制限等」からの問題で、基本的な内容でした。労働基準法とあわせると、3点を確保することは難しくないので、基準点引き下げの可能性は低いでしょう。
「労災保険法」は、昨年度に比べると、難化しました。
問題文1は、「遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態」の問題で、多くの受験者がテキストなどで見たことのある内容ですが、対策が手薄になっていたため選ぶのに苦労した方がいたかもしれません。問題文2は、「長期家族介護者援護金」からの出題で、多くの受験生にとってなじみのない内容だったため、正答率はかなり低くなるでしょう。
問題文3は、判例からの問題でした。テキストに掲載されている可能性の高い判例で、D・Eいずれも、文脈判断での解答が可能でした。全体としてみると、受験生の対策が手薄となっているかもしれない箇所からの出題だったため、基準点引き下げの可能性は0ではありません。
「雇用保険法」です。
問題文1は、目的条文からの出題で、特に、Aは法改正点からの出題でした。Bは基本的な内容であるものの、選択肢を絞り切れなかった受験生もいたかもしれません。
問題文2は、「高年齢求職者給付金」についての問題で、基本的な内容でした。また、問題文3は、「日雇労働求職者給付金の特例」からの出題で、基本的な内容でした。いずれも基本的な内容だったため、基準点引き下げはないでしょう。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」ですが、
問題文1は、総務省の報道資料からの問題で、頻出の論点である労働力調査からの引用ではあったものの、ノーマークだったという受験生が多かったかと思います。Bは、昨今のコメ不足に関連し、農業における就業人口の高齢化を連想できれば、解答することが可能でした。
問題文2は、労働施策総合推進法からの出題で、基本的な内容でした。他の空欄の難易度が高いことから、ここは正解しておきたいところです。
問題文3は、判例問題で、企業施設を利用した組合活動についての問題でした。Dは問題文の中に空欄が6つもあったため、ヒントとなる箇所が多く、文脈判断によって正解しておきたいところです。Eは、選択肢を絞り切るのに苦労した受験生が多かったと考えられます。以上より、基準点が2点に下がる可能性があると言えます。
「社会保険に関する一般常識」ですが、
問題文1は、「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」からの問題でした。厚生労働白書でも取り上げられている内容なので、けっして解けない問題ではありません。
問題文2は、高齢者医療確保法からの出題で、「地方公共団体の責務」からの出題でした。「住民の」という文言から、正解にたどり着くことが可能でした。問題文3は介護保険法からの出題で、対策が手薄になっていた受験生も多かったと考えられます。問題文4は、確定給付企業年金法からの出題で、多くの受験生にとってなじみのない規定についての問題でした。問題文5は、厚生労働白書からの出題でしたが、ノーマークだった方が多かったと考えられますが、空欄の直前・直後から正答にたどり着けた受験生も一定数いると考えられます。以上より、可能性は低いものの、基準点が2点に下がるかもしれません。
「健康保険法」について、
問題文1は、「出産育児一時金」からの出題で、A・B・Cいずれも基本的な内容でした。問題文2は、「任意適用事業所の取消し」についての問題で、Dは基本的な内容で、Eも選択肢をよくみれば正解できました。油断をしてしまって、ミスをしてしまうということがあるかもしれませんが、できるだけ得点を稼いでおきたい科目といえます。そのため、基準点が2点に下がることはないでしょう。
「厚生年金保険法」ですが、
A・Bは「定時決定」に関して、Cは「調整期間における再評価率の改定」に関して、いずれも基本的な内容でした。D・Eの事例問題で正しい選択肢を選べなかったということもありそうですが、3点を確保することは難しくはないので、基準点の引下げの可能性は低いでしょう。
最後に「国民年金法」についてです。
問題文1は、国民年金保険料の沿革についての問題でした。受験歴が浅い方には、少し難しく感じられたかもしれませんが、A・B・Cのうち2つは正解しておきたいところです。また、問題文2の「学生納付特例に係る所得要件」について学習が手薄になっていて、正しい選択肢を選べなかったということもありそうです。とはいえ、3点を確保することは難しくはないので、基準点の引下げの可能性は低いでしょう。
全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったりということはありませんでした。
例年と比べて、受験者のレベルに大きな変化がないのであれば、トータルの基準点については、昨年度と同程度で、基準点は、24~26点ではないでしょうか。ただし、科目別の基準点の引下げの状況などにより、変わってくる可能性もあります。
択一式試験について
8月24日に行われた「令和7年度社会保険労務士試験」の択一式試験について講評します。
まず、問題冊子のページ数は65ページでした。平成10年度頃は50ページ前後、その後、平成10年代は50ページから60ページ、そして、平成20年代は60ページ以上が増え、ここ8年、60ページ以上が続いています。
今年度は昨年度より1ページ減ってはいたものの、かなりのボリュームであることに変わりはなく、時間配分で苦戦したという方も多かったのではないでしょうか。
それでは、各科目について見ていきます。
「労働基準法」は、
傾向どおり、通達や判例、コンメンタールの記載などからの出題がありました。細かな内容に関する問題もありましたが、基本的な内容や過去問で出題実績のある論点が多かったので、かなり正解することができたでしょう。そのため、できれば5問前後は正解しておきたいところです。
「労働安全衛生法」は、問9と問10の難度が非常に高かったことから、問8は正解しておきたいところです。「労働基準法」と「労働安全衛生法」を合わせた10問で考えた場合、確実に基準点を確保し、できれば6点以上は取っておきたいです。
「労災保険法」は、
昨年同様に事例や認定基準などの出題があったほか、労災保険法の特徴である、1つのポイントに視点を置く問題がありました。
その中で問6は、基本的な内容なので確実に正解しなければならない問題です。今年も通達からの細かな内容の出題があるなど、全体的に難しいレベルですが、昨年度よりは易化しているため、できれば4点以上取っておきたいところです。
「労働保険徴収法」は、
基本的な内容が中心でしたが、問9の事例問題の数字の処理であわてた等の理由で、正解肢を選べなかったものがあったかもしれません。そのため、全問正解とならなかったとしても、「労災保険法」とのトータルで6点以上は取っておきたいところです。
「雇用保険法」は、
特に、行政手引から出題されたものを中心に、判断に迷う出題がありました。全体として難しく感じた方も多かったのではないでしょうか。その中でも問3や問4など、比較的取り組みやすい問題もあり、最悪2点、できれば4点以上取っておきたいところです。
「労働保険徴収法」は、
問9がやや難しかったものの、3問中2問は正解しておきたいところです。「雇用保険法」とのトータルで4点は確保したうえで、できれば5点以上とりたいところではありますが、わずかながら、基準点が3点に引き下げられる可能性があります。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」について、
令和6年度は、労働経済が2問で、法令等が3問という出題構成となっていましたが、今年は、令和5年度と同様、労働経済が3問、法令等から2問、その内訳は、「労働契約法等」「社会保険労務士法」です。
労働経済から出題された問1から問3のいずれについても、初めて又は十数年ぶりに出題される調査に関する内容で、自信を持って正解肢を選ぶのは難しいものでした。ただし、関連する調査(「外国人雇用状況」の届出状況まとめ、「障害者雇用状況」の集計結果等)について学習していた方は、比較的取り組みやすかったと考えられます。
問4と問5は、極端に難しいというものではなく、正解しておきたい問題です。いずれも消去法で正解肢を絞り込める内容でした。これらの状況から、少なくも2点、できれば3点を確保したいところです。
「社会保険に関する一般常識」は、
問10が「社会保障制度に関する問題」、それ以外が法令に関する問題となっており、3問が単独の法律に関する選択肢で構成されていました。
論点が分かりづらい選択肢が多く、個数問題も含まれていましたが、できれば3問は正解したいところです。「労務管理その他の労働に関する一般常識」と合計して考えると、科目別の基準点である4点を確保したうえで、できれば5点を取りたいところです。
「健康保険法」は、
例年、通達や事務連絡からの出題が多い傾向にありますが、昨年同様、今年も、約7割が条文をもとにした出題となりました。テーマとしては、保険給付を軸に保険者や被保険者、費用の負担など、幅広く出題されています。5肢のうち2つまで絞ったものの、その2つで迷ってしまうような問題がいくつかありました。また、多くの受験生にとってなじみのない内容が正解肢として設定されている問題もありました。そのため、思ったほど正解することができていないということが考えられます。
したがって、大量得点は難しいでしょうが、5点以上は取っておきたいところです。
「厚生年金保険法」は、
基本的な事項からの出題が多く、比較的得点しやすかったといえます。ただ、昨年度に比べると、一見しただけでは正誤の判断がつかない選択肢が増えており、昨年度よりも難化しました。
問4や問5など、基本的な知識を問う問題で確実に得点し、全体として6点、7点を取っておきたいところです。
最後に「国民年金法」は、
昨年と同様、複雑な事例の出題はなかったものの、受験生にとってなじみのない内容からの出題もあり、昨年度よりも難化しました。
個数問題が2問、組み合わせ問題が2問あり、問題文を読むのに時間を要した受験生も多くいたと考えられますが、科目全体で見たとき、正解肢を見つけやすい問題が多かったと言えます。以上から、7点以上は取れたのではないでしょうか。
トータルの基準点については、問題のレベルから考えた場合、昨年度(44点)より1点さがって、43点前後ではないでしょうか。
※解答速報・試験講評に関するご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※この解答速報・試験講評の著作権は株式会社フォーサイトが有し、無断転載及び無断転用を禁じます。

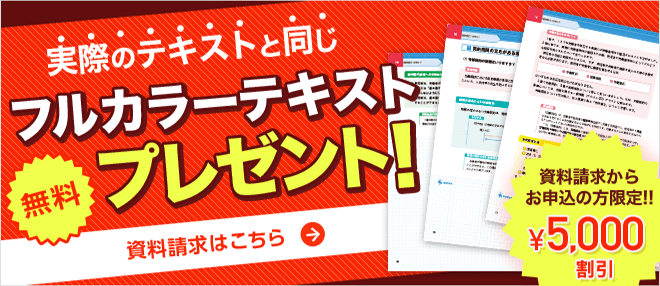

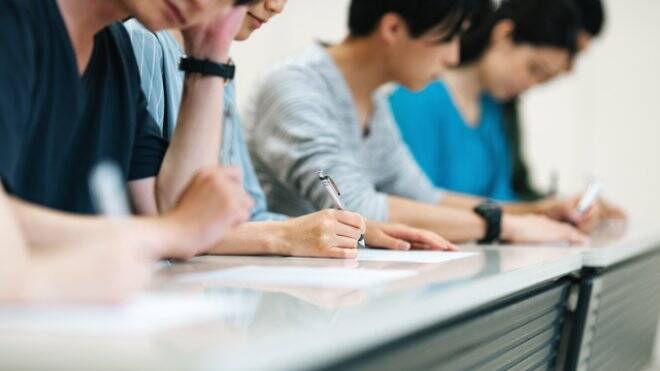


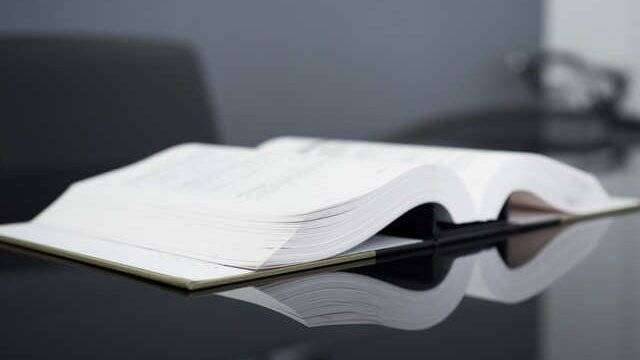








 ログイン
ログイン





