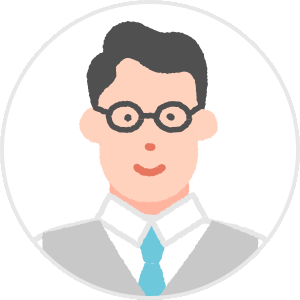
行政書士の勉強法を2年目からフォーサイトに変更しました
【行政書士】
2016年(平成28年度)合格
- 勉強期間
- 1年間
- 受験回数
- 3回目
- 職業
- 正社員(サラリーマン)
- 年代
- 40代
- 性別
- 男性
昨年は、力不足で結果が出ず、記述式、択一式ともに本番での感触の悪さ、実際に結果も出なかった事実に今後どのように勉強していくべきか不安に感じていました。
今年は自分と向き合い、不安材料を一つ一つ潰していくことで合格できたと思います。
まず、受験の動機ですが、契約審査、コンプライアンス、官庁対応等を会社員として経験する機会があり、体系的に実務で活かせる法律知識を習得し、使いこなせる実務家になりたいと思ったこと、
また、災害などの際に、行政書士が直後から罹災証明書発行の支援等で被災者の生活再建に直接貢献して喜ばれているニュースに触れ、スキルを活用して目に見える形で社会に貢献できる道があるのだと気付かされたことも大きな動機でした。
次に受講の理由についてです。
前年度も過去問や演習中心主義の重要性は認識していたつもりでした。
しかし、本番で記述式も想定テーマから外れると歯が立たず、択一式も判例の問題などで確信が持てなかったため、次に向け、過去問にどう取り組み、対処能力を養うか?演習中心とはいうものの、体系学習とどう折り合いをつけるか?について、具体的指針が明確ではありませんでした。
そこで、前年度試験直後の12月にフォーサイトの門を叩くことになりました。
魅力的だったのは、フルタイムの会社員にとってはありがたい通信制でありながら、過去問集を素材とした解説講座等があることで、演習中心主義であったことでした。
一方向の知識の講義だけではなく、実際の過去問の解説と対処法、勉強法や効果的な自己演習の方法、スケジューリングのノウハウ、さらには直前模擬試験に至るまでカバーされていることでした。
二、 勉強法の前に
勉強法の情報は巷に溢れていますが、自分が使えるかは実際にやってフィットするかどうかを実感と効果をもって見つけるしかありません。
勉強法の前に「自分を知る」ことも本年度の私の勝因の大きな要素であったかもしれませんので、少し触れたいと思います。
「自分を知る」には、敗因分析、思考のクセ、好き嫌いの傾向等を知ることが肝要かと思います。
私のように前年度に結果が出なかった場合、単に実力不足という抽象的な言葉で終わらせずに向き合うことが重要です。
実力不足とは、知識不足だったのか?記憶不足だったのか?いわゆる本番力不足だったのか?本番力はいかにして養成し、発揮できるか?本番の理想の状態とは何か?を問うことから始めました。
その過程で、私は私法より好きな公法の勉強に偏りがちとなる傾向、民法の図式をおろそかにしていたこと、文字より図式が好きで、白黒テキストよりカラーテキストが好きなことなども分かりました。
読む勉強のみではなくDVDやCD等で講義を聞く勉強もバランス良くしないと飽きやすく、ペースやモチベーションが落ちてしまう傾向も分かりました。
そうした自分の傾向を合格者と比べて嘆くよりは、事実として受け入れ、把握し、目標に対し力を発揮できる方向性を実感を深めながら見つけ、実践・継続していくことも合格者の勉強法を参考にすることと同様に重要なことではないかと思います。
三、 私の勉強法
敗因分析後の勉強の中核は、択一式は過去問を繰り返し解くこと、記述式を意識したテキスト読み、記述式予想問題の繰り返し解くことを主軸に据えました。
択一は福澤先生の過去問解説講義を聞いて独習でやると立ち止まってやる気を失ってしまいそうな問題や苦手な問題も講義のペースで一つ一つ淡々と取り組み、その後は出来るまで繰り返し解きました。
直近10年分ほどの過去問を体系別過去問と市販の肢別問題集を使って角度を変えて知識の正確性のチェックを継続しました。
記述式の過去問は直近10年分は全てやりきり、今年度は予想問題を模擬試験、市販本でやりきりました。
結果として私がやったもので的中問題はありませんでしたが、やりきったという精神的な自信は大きく、本番の記述式は52点、本番が最も出来がよかった結果に繋がりました。
以上と並行して演習で得た知識の位置付けをテキストで確認し、理解を深めました。
特にテキスト学習はなんとなく棒読みするのではなく、記述で出された場合、どう書くか?どうまとめるか?キーワードは何か?を意識して学習されると効果的だと思います。
フルタイムの会社員であるため、勉強は通勤の移動中をメインに、昼休みのテキストパラパラ読み、帰宅後に復習、週末はカフェや図書館で過去問学習という形で取り組みました。
試験本番の3ヶ月前から通勤時に混雑している時は、効率性を重視してグリーン車に乗ってテキスト読みを、超直前期は、体力も大事と自覚していたので、趣味の合氣道の稽古は週二回程度1週間前まで続け、直前2週間の週末は1日12時間ほど勉強して追い込みをかけました。
試験前の金曜日に会社を休み、自宅から試験会場まで遠かったリスク回避の目的、数日は家族からも離れて試験だけに集中する目的で、ホテル住まいにし、前日もホテル近くのスパの大浴場につかって適度に休息をとって本番を迎えました。
四、 最後に
精神論になってしまいますが、福澤先生もよくおっしゃっている「最後まで諦めない」ことの重要性を信じて文字どおり「最後まで諦めない」ことを決めてください。
私も直前の模擬試験の結果は芳しくなく、弱気の虫が囁き始めましたが、諦めない強い気持ちで踏みとどまることができた思います。
また、行政書士試験は一般知識を含めると大変範囲が広いので、特に直前1カ月においては、勉強対象をいかに絞るかだと思います。
もう一度、試験の配点を確認し、それを意識した勉強、具体的には最も配点の多い行政法、そして、次に多い民法の学習、決して低くない記述式おろそかにしないことに徹することにしました。
逆に、商法や一般知識の読解、政治史、時事以外の分野は費用対効果が低いと割り切るべきでしょう。
大変助かったのは、フォーサイトの模擬試験は基礎レベルと本番レベルと二種類あり、基礎レベルのミスは最重要課題として取り組むことができ、解説もシンプルで、解説さえ読めば正解の肢としてまとまっていることでした。
最終的には二回分の模試解説をミスしたもの、新判例・改正法を中心にした4ページほどの分量まで絞って本番のお守りの一つに持って行きました。
試験監督が試験開始前に「しまってください」というまで勉強を続け、「鉛筆をおいてください」と言われるまで力を出し切ることに尽きるのではないでしょうか?
今年の本番も現時点ですでに9ヶ月を切っていますので、あっという間です。
次は皆様の番です。是非頑張ってください。


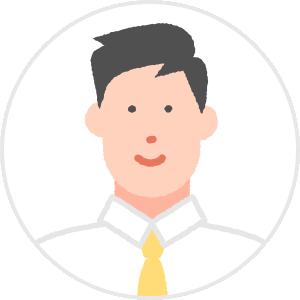
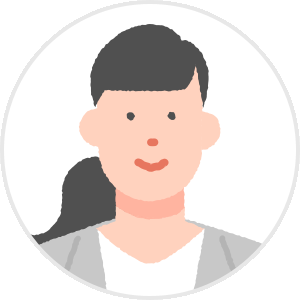
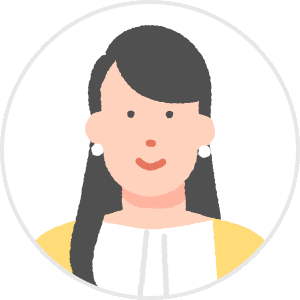
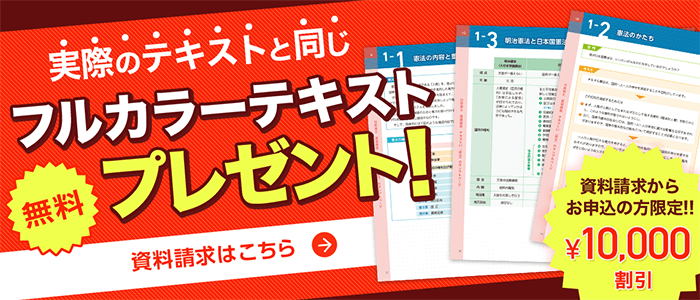













 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


