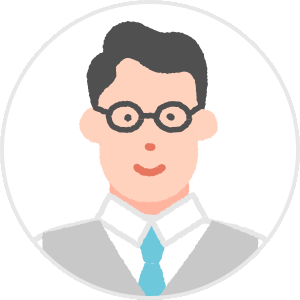
分かりやすいテキストや講義DVDがあったから行政書士に受かったんです
【行政書士】
2017年(平成29年度)合格
- 勉強期間
- 10ヶ月間
- 受験回数
- 初学者(1回目)
- 職業
- 正社員(サラリーマン)
- 年代
- 50代
- 性別
- 男性
漠然と「将来の転職時に有利かも?」とは考えましたが、「何も資格が無いのは寂しい」という気持ちのほうが強かったと言えます。
行政書士を選択したのは、約20年前に一度学習を開始して諦めたことがあったので、リベンジの意味もありました。
「思い立ったら吉日」というタイプなので、すぐさまネット検索。
最初から通信教育に決めていたので、複数の候補をピックアップ&資料請求して、最も結果が期待できそうな御社を利用することに決めたのが、昨年2月上旬。
早速「道場破り」で学習スケジュールを作成するものの、理解しないと先に進めないタイプなのですぐに遅れがちとなり、スケジュール遵守の目標は早々と放棄。(最終的には、約3ヶ月分ほど学習項目を残して本番を迎えることになってしまいました。)
主な学習パターンは以下のとおりです。
1.往復の通勤電車内でダウンロードした講義を視聴:約1時間
2.朝だけは、JRから地下鉄に乗り換えずに会社まで歩いて通勤し、その間に再度講義を聞く:約30分間
3.会社の休み時間には問題集など集中して学習:約30分間
4.帰宅後、食事を済ませてから:約1〜2時間
合計:3〜4時間(休日も大差なし)予定通りできない日もあったので、平均すると1週間あたり19時間前後だったと思います。
個人的には「民法」が苦手で、理解するまでに時間がかかりました。講師の講義を何度も一時停止して考え、紙に書きながら少しずつ進めていったときには、正直焦りました。
ただ、最後の2ヶ月を迎える頃には一気に理解度が向上したように感じられたので、結果的には良かったのかもしれません。
特別なノートは一切作らず、全てテキストに書き込みながら覚えました。場合によっては、過去問題集の解説をコピーしてテキストに貼り付けました。後は、過去問題を解きながら適宜テキストに戻って確認するだけです。
最初は、単語カードや確認テストをもっと使いこなす予定にしていましたが、過去問題集を3回繰り返す予定のところ、1.5回(初回は難易度Aのみ)しかできなかったので、ほとんど利用しなかったです。
気持ちに余裕がなくなっていたからだと思いますが、ひたすらテキストと過去問題集に集中しました。
模擬テストを受けることができたのは、良い経験でした。本番のレベル感が掴めたし、時間配分などの練習にも効果的です。ただ、その結果が思いの外良かったので、ちょっと気を抜いたかもしれません。
本番までの学習時間がやや不足したことに加え、本番ではケアレスミスが5問見つかり、自己採点ではギリギリ合格圏内でしたが、結果発表までは薄氷を踏む思いでした。
初めての試験で合格できたのは、的を絞った分かりやすいテキストや講義DVDのおかげだと思います。
特に、「道場破り」はスマートフォンで大活躍しました。お陰で、学習環境は大変良くなっており、スキマ時間の活用が容易になっています。今後、「道場破り」の機能が更に向上することを大いに期待しています。
現在、引き続いて「社労士」の講座を受講しています。
依然として開業志向ではないのですが、学ぶことが楽しくなってきたので、続けてトライすることにしました。
早期退職を目前に控えて環境が大きく変化するため、流石に集中して勉強することは難しくなるかもしれませんが、何とか初年度合格を目指して頑張ります。


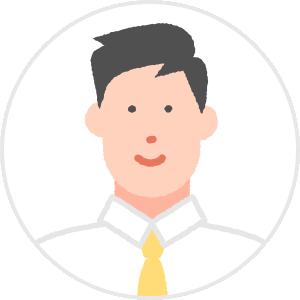
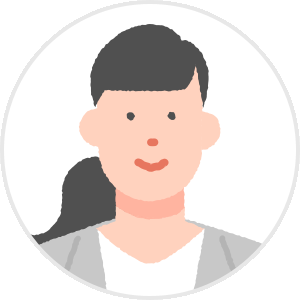
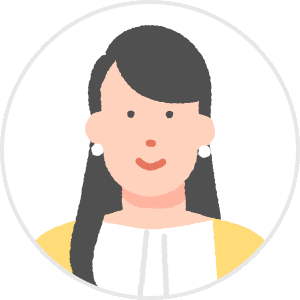
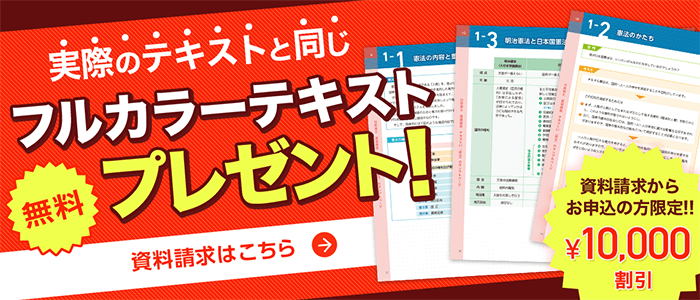













 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


