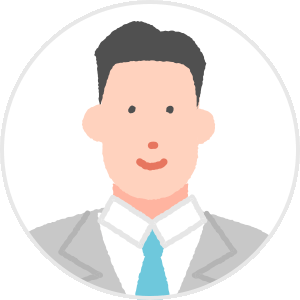
約10か月の学習期間で行政書士合格!自分と教材を信じて進むことが大切
【行政書士】
2018年(平成30年度)合格
- 勉強期間
- 9ヶ月間
- 受験回数
- 初学者(1回目)
- 職業
- 自営業・会社経営
- 年代
- 50代
- 性別
- 男性
■受験動機等
以前より法学の基礎科目である「憲法」「民法」や、仕事に関連する「行政法」を学びたいと考えていたところ、行政書士試験が、そのニーズに最も適合しているように感じ、2018年2月に受験を決めました。
対策講座は、かつて社労士を合格したときにお世話になったという験の良さもあり、フォーサイトさんを受講することとしました。
■学習の進め方①:2月~8月
福澤講師が「丁寧な1回転より、拙速な3回転」という趣旨のお話をされますが、基本的には、これに尽きます。
理解しているか否かということを気にすることなく、まずは講義動画を1回転しました。講義の内容は平易で、民法・行政法など、ほぼ初学者の私でも十分についていくことはできます。ただし、これに続けて過去問を解くものの、当然、あまり正解できません。でも、そんなことはまったく気にせず2回転目に入ります。ここからは1.5倍速動画で所要時間を短縮、さらに過去問の正答率も少し上がりますが、もちろん合格レベルには届きません。それでも、そんなことは気にせず3回転目へと前進します。繰り返しますが、この期間は、細部にこだわらず、腹をくくって、とにかく前進するのみです。
野球でいえば「素振りとノック」、相撲でいえば「四股・鉄砲とぶつかり稽古」ということになるでしょうか。最も大切な基本動作を、頭ではなく、身体に浸み込ませるイメージでこの期間の学習を進めました。
■学習の進め方②:9月
この時期に各受験校で「中間模試」が開催されます。私は、できるだけ規模の大きな模試で、会場受験できるところを利用しました。基本動作だけで野球が上手くなり、相撲が強くなるわけではないのと同じで、試験形式で正答するための実戦トレーニングを進める期間と位置付けました。規模と会場受験を重視したのは、試験当日の雰囲気、緊張感、心身の負担感等を、早めに体験したいと考えたからです。
模試の結果自体は、ほとんど気にしません。ここでは、問われていることを正確に理解できたか、正確な理解のもとに各選択肢を取捨したか等、必要な場合にはテキストに戻るだけでなく、各法条文にもあたりながら細かく復習することを重視しました。中間模試の復習後には、過去問を同様のやり方で細かく復習する時間に費やしました。
野球でいえば「シートバッティング」、相撲でいえば「関取衆との三番稽古」ということになるでしょうか。実戦をイメージしながら細部も意識するという学習期間でした。また、焦る気持ちがないわけではありませんが、完成させるのは11月11日の本試験です。ピーキングを誤らないように心がけました。
■学習の進め方③:10月~直前期
この時期は各受験校の「最終模試」があります。野球でいえば「オープン戦」、相撲でいえば「横審の稽古総見」といったところでしょうか。
中間模試と同様に、大きな規模の模試を会場受験しました。あくまでも模試ですので、結果に一喜一憂すべきではありませんが、一応の目標として上位20%以内にいられればいいなと考えていました。結果は上位25%くらいで目標には届いていませんが、例によって気にしません。むしろ復習を重視して、中間模試と同様に細かくやって時間もかけました。ただし、時間をかけすぎたこともあって、「直前対策講座」を十分に消化することができませんでした。
最終模試後の直前期に関しては、各年度の過去問を、本試験の時間に合わせて解答して試験当日のシミュレーションを繰り返し、最終調整としました。
■反省等
一般知識等の出題傾向が変化し、十分に得点できた実感がなくて、解答速報等も見る元気もありませんでしたが、おかげさまで運良く合格出来ました。終盤に若干の消化不良があったものの、中間模試:176点→最終模試:182点→本試験:190点という経緯で、概ね、当初に想定したとおりピーキングできたようです。
ただし、記述式に関しては、中間模試:22点→最終模試:22点→本試験:8点と、終始、低空飛行でした。特に、「今年の記述は易しかった」といわれる本試験での8点はひどいものです。上記の消化不良とともに、文章を書くこと自体、不得手ではないことから「択一式・多肢選択式が十分に対策できれば大丈夫だ」と過信していたかもしれません。記述式への対策に、もう少し時間を割くべきだったと思われます。
■これから受験される方へのメッセージ
約9カ月の学習期間は、振り返ればあっという間に過ぎてしまいましたが、学習を進めているときにはウンザリするほどの長期戦です。特に序盤から中盤にかけては、学習成果がなかなか感じられず、メンタルの維持が大変です。苦しいところですが、序盤から中盤の苦しみが「土」となって、終盤に「花」が咲き、ピークである本試験で「実り」が得られます。ご自身を信じて、また、ご自身が選んだ教材を信じて前進してください。


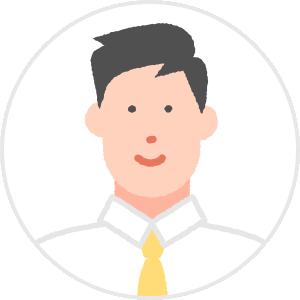
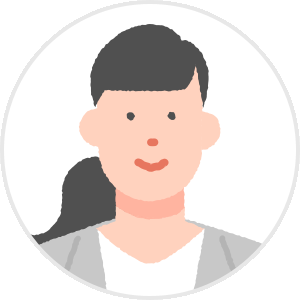
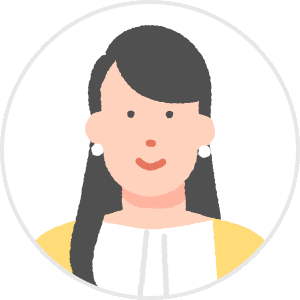
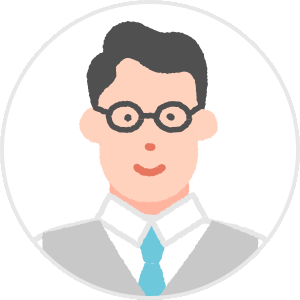
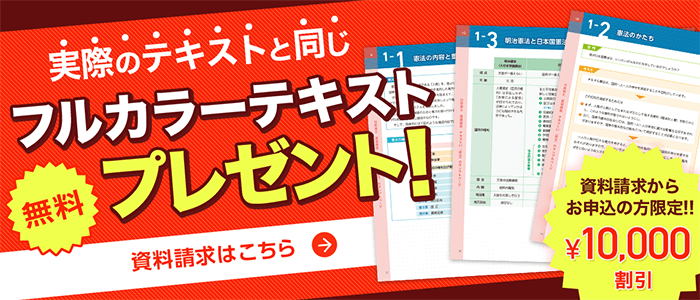













 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


