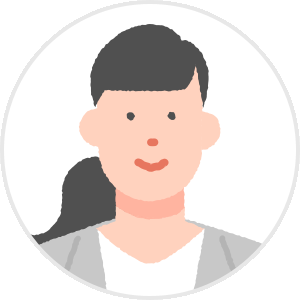
行政法、民法を優先して過去問演習。商法は講義の範囲に絞り、効率的に学習!
【行政書士】
2019年(平成31年度)合格
- 勉強期間
- 7ヶ月間
- 受験回数
- 初学者(1回目)
- 職業
- 正社員(サラリーマン)
- 年代
- 20代
- 性別
- 女性
道場破りで想定した通りには勉強が進められませんでした。
最初は熱心に勉強に取り組んだものの、徐々に中だるみになり、設定したスケジュールからずれていく様子をアプリで見てはモチベーションが下がっていきました。
そのため、焦る気持ちもありましたし、今の勉強に意味があるのだろうかと悩むこともありました。
私は法学部出身ではありましたが、法律の学習は卒業以来ほぼしておらず、初学者同然。過去問を解いてもなかなか正解せず、1週目はまるで読み物を読むかのよう…。そうなると、モチベーションはあまり上がりませんでした。
そんな時はなぜこの試験を受けるのか、という原点を考えるようにしました。そうすると、「今の自分を責めても仕方ない、10分でいいから勉強しよう」と前向きになれました。直前期、模試の結果があと一歩及ばずしんどい時も原点を考えると、このために頑張ろうと最後まで諦めずに底力を出せたと思います。
優先順位を大切に
そのような経緯もあり、集中して取り組める時は勉強に全集中できるように優先順位を常に考えて勉強を進めるようにして、苦手でとっつきにくい科目ほど序盤に手を出すようにしました。
行政書士試験では重要科目と言われている行政法、民法が苦手でしたので、過去問演習はこれらの科目を中心にしていました。
特に行政法は範囲が広いので、行政法の中でも重要度が高い、行政不服審査法、行政事件訴訟法を中心にとりかかり、次に地方自治法といったように重要度と苦手度合いから優先順位をつけていきました。
学習が間に合うのかどうかギリギリの状態だったので、商法会社法は軽くさらう程度で手を出すのを止めようと思っていましたが、模試の結果を見る限り完全に落とすのは惜しいと感じ、直前で方針を変えて最重要ポイントだけ詰め込みました。講義で必要と言われたところのみ突貫で勉強しましたが、本試験でもなんとか得点することができました。
何が足りないかを探してあがき続け、優先順位を基に効率的に学習を続けたからこそ、合格を手に入れられたと思います。


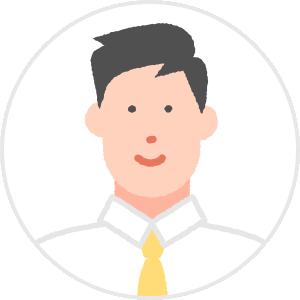
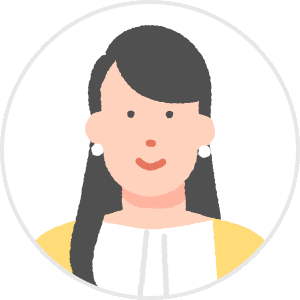
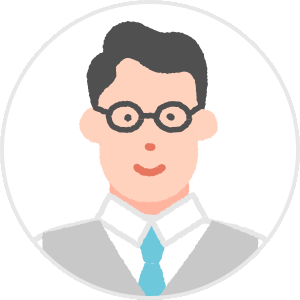
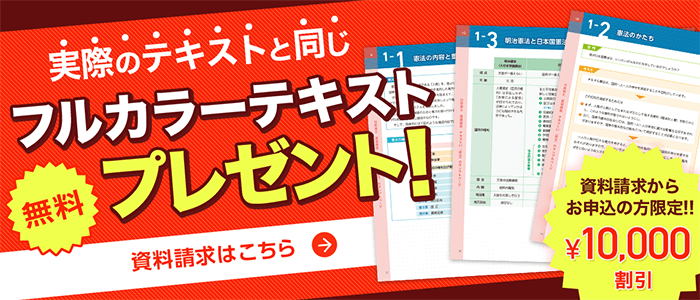













 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


