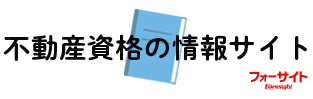「衣・食・住」は人が生きていくには欠かせない要素と言われています。そのうちの「住」を担うのが不動産業界であり、古くから衰退することは考えにくい業界といわれてきました。しかし、これからの日本は少子高齢化が進むこともあり、人口減少により影響を受ける業界は少なくないといわれています。では、不動産業界はどうなるのか?近年の動向から不動産業界の将来性を考えていきましょう。
目次
2020年現在不動産業界は活況
2020年現在、日本国内の不動産業界は好調といわれています。その大きな要因が都市部における活況です。日本全体の不動産の推移を計算する際、人口が集中する都市部の数値に大きな影響を受けるのは当然であり、都市部の数値が上がれば全国平均も上がっていきます。
では、2020年現在、特に都市部において不動産が好調な原因をいくつか挙げていきましょう。
オリンピック特需
不動産業界の景気判断に、もっとも大きな影響を与えたのが2020年に開催予定だった東京オリンピックの影響です。東京でオリンピックが開催されるのに合わせ、都心部では宿泊施設が多く開業し、それに合わせ地価も高騰していきました。
いかに示す数値は、東京都が発表した公示地価の推移です。2020年のオリンピック開催地が東京に決定したのが2013年9月。そこで2013年、2017年、2020年の、東京都の住宅用地の公示地価をまとめてみましょう。
| 年度 | 公示地価(/㎡) | 2013年との比較 |
|---|---|---|
| 2013年 | 337,200円 | – |
| 2017年 | 385,300円 | 48,100円(+14.2%) |
| 2020年 | 432,300円 | 95,100円(+28.2%) |
(参考:東京都財務局 東京都基準地価格)
この上昇がオリンピック特需であるのかを確認するためにもう少し細分化して数値を比較します。新国立競技場のある新宿区、オリンピック選手村がある中央区、東京23区でも人口の多い世田谷区、大田区の4つの区についても同じ数値を出してみましょう。
| 年度 | 新宿区 | 中央区 | 世田谷区 | 大田区 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 601,600円 | 857,000円 | 512,300円 | 444,700円 |
| 2017年 | 681,300円 +79,700円 +13.2% |
1,159,100円 +302,100円 +35.3% |
586,000円 +73,700円 +14.4% |
488,600円 +43,900円 +9.9% |
| 2020年 | 803,500円 +201,900円 +33.6% |
1,300,500円 +443,500円 +51.8% |
636,200円 +123,900円 +24.2% |
528,200円 +83,500円 +18.8% |
(参考:東京都財務局 東京都基準地価格)
いわゆる住宅地といわれる世田谷区、大田区も地価は上がり続けていますが、新規の施設が建設された新宿区や中央区は大きく公示地価が上がっていることがわかります。
消費税増税対策
もうひとつ大きな要因となっているのが、2019年10月にアップした消費税の影響です。消費税増税にあたり、増税前にマイホームを購入する動きに拍車がかかり、いわゆる駆け込み需要で一気に不動産業界がにぎわいました。
東京などの首都圏地域では特に中古マンションの販売が増加。これは消費増税前に駆け込みで購入したいものの、新築マンションはオリンピック特需もあり高額すぎたという点が挙げられています。
2025年大阪万博に向け大阪の地価高騰も
東京以外の地域でも、大阪府では2025年に万博の開催が決定。オリンピック同様世界中からの観光客、報道陣が大阪に押し寄せることが決まり、大阪府内では宿泊施設の絵kン節ラッシュが見込まれており、それに合わせ地価も高騰するものとみられています。
近い将来には業界縮小も
東京オリンピックに大阪万博と、都市部を中心に不動産業界も景気のいい話が飛び交いますが、この好調がいつまでも続くとは言われていないのが事実です。オリンピックや万博といった特需は、イベント開催終了後には落ち着くもの。むしろ高騰しきった地価がその後下落に向かうという見通しを出している機関もあります。
何より大きな問題といえるのが、日本の人口減少、および少子高齢化です。人口が減るということは当然ながら世帯数が減少するということ。その分マイホームの数が余ってしまうことが予想されています。
現実を見てもすでに地方及び地方都市では空き家問題が顕在化しています。日本の人口が減少するということは、こらから空き家問題の数も増加していくことになり、新規の建築件数も減少していくでしょう。
参考:なぜ空き家はここまで増える?空き家増加の問題を検証|空き家パス
都市部集中の傾向が顕著に
人口の減少、そして少子高齢化の影響が色濃く出るのは地方でしょう。人口が少なくなった地域では仕事も少なくなります。すると地方に住む若者は、仕事を求めて都市部を目指すことになります。
大阪や東京、札幌、名古屋、仙台、福岡といったその地方における最大都市に人口が集中し、周辺の地方部ではどんどん人口が減少します。しかも労働人口が減り高齢者が残るような状態が想定されますので、より状況は深刻です。
すでに人口の減少、公示地価の下落が進む地域もあり、こういった地域では不動産業界も縮小の傾向にあります。この縮小傾向がこれからどんどん顕在化するともいわれており、近い将来一気に縮小するのではとの予測をする機関もあるようです。
不動産業界にある明るい未来
オリンピック特需の終了や、長引く人口減少のあおりを受けて、将来的に縮小傾向といわれている不動産業界ですが、ただ縮小傾向を受け入れているだけではありません。多くの企業が近い将来に向けて、新たな動きを見せています。
そんな不動産業界における明るい未来の材料に関してまとめてみましょう。
海外不動産の開発
特に大手といわれる不動産業者は、不動産開発業者を中心に海外の不動産開発に注目しているようです。特に発展途上国と呼ばれるような東南アジアの国を中心に、大規模な不動産開発を行うことで、日本国内以外で業績を安定させようという傾向がみられます。
日本式の建設は、高い耐震性を誇り、少なからず地震や災害の可能性がある地域では注目を集めているようです。
2022年生産緑地の宅地化問題
日本国内に目を向けると、2022年問題に注目している企業が多いようです。これは1992年に制定された制度で、「生産緑地」として指定された土地が、2022年に30年の営農義務期間を終えるために起こるであろう問題です。
生産緑地に指定された土地は、宅地としては利用できない代わりに固定資産税や相続税の優遇措置を受けています。しかし生産緑地としての認定が外れる2022年以降は、この優遇
がなくなるため、多くの土地所有者が宅地転用し売却すると予想されています。
特に都市部に近い地域の生産緑地は、宅地として開発されることが予想されますので、不動産業界としては注目に値するタイミングといえるでしょう。
生活様式の変化による新たな都市開発
少子高齢化が進むことを逆手に取る企業も増えているようです。少子高齢化、核家族化が進むということは、これまでとは異なる住宅事情になるということです。加えて2020年は世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が問題になりました。
この影響でテレワークなど、自宅で仕事をする方が増え、感染拡大が落ち着いても引き続きテレワークが基本となる方も増えると予想されています。自宅で仕事をするとなれば、仕事用の部屋が必要となるため、こういった点でも住宅事情は変わってくるでしょう。
こういった動きに合わせ、新しい生活様式にあった開発も進んでいます。マンション開発においても、少々狭くても仕事用のスペースが確保できる物件が増えたり、そもそもテレワークを前提として増加するであろう地方移住に合わせた都市開発などが計画されているようです。
少子高齢化、働き方改革をきっかけに新しい生活様式に適した開発も注目を集めています。
将来性の見極めが重要になる
不動産業界の今後の動向に関しては、極めて不透明な中にあるということがいえるでしょう。少なくとも2020年秋現在のような好調さがいつまでも続くということはなさそうです。特に少子高齢化、人口減少という大きな問題を中心に考えれば、不動産業界も都市部と地方部で二極化が進むでしょう。
しかし、海外における不動産開発や、新たな生活様式に即した都市開発など、多くの企業が生き残りをかけさまざまな新規事業に取り組んでいます。
これから不動産業界へ就職、もしくは転職を考えているという方は、その企業や業種における将来的なビジョンや新規事業などにも注目し、将来性を自分なりに分析したうえで企業を探すのが重要となるでしょう。