令和5年度 第55回社会保険労務士試験の解答速報・試験講評
2023/08/27
8月27日(日)に実施されました、令和5年度 第55回社会保険労務士試験の解答速報・試験講評をこちらのページで公開しています。
自己採点機能も公開いたしますので、ぜひご活用ください。
また、二神講師による選択式試験についての試験講評をライブで配信いたしました。 ※アーカイブでご覧いただけます。
解答速報
8月27日(日)に実施されました、令和5年度 第55回社会保険労務士試験の解答速報を公開いたします。
選択式
問1 労働基準法及び労働安全衛生法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 20 | 7 | 15 |
問2 労働者災害補償保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 2 | 10 | 14 |
問3 雇用保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 16 | 19 | 3 |
問4 労務管理その他の労働に関する一般常識
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 3 | 20 | 12 |
問5 社会保険に関する一般常識
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 18 | 13 | 2 |
問6 健康保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 12 | 17 | 3 |
問7 厚生年金保険法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 12 | 2 | 5 |
問8 国民年金法
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 20 | 17 | 2 |
択一式
労働基準法及び労働安全衛生法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| E | E | A | B | A |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| C | C | E | D | A |
労働者災害補償保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| E | C | E | B | D |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| E | E | E | D | C |
雇用保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| E | A | B | C | C |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| D | A | C | A | E |
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| C | B | A | E | D |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| C | D | D | E | B |
健康保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | C |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| C | D | D | A | B |
厚生年金保険法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| A | A | E | D | B |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| A | C | D | D | B |
国民年金法
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
|---|---|---|---|---|
| D | C | C | A | B |
| 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| C | A | C | D | C |
試験講評
選択式試験について
8月27日に、令和5年度社会保険労務士試験が実施されました。受験された方、お疲れ様でした。
今年度の選択式試験については、全体的に見た場合、極端に難しいというものではありませんでした。
「労働基準法」は、最近の傾向どおり、判例の問題がありました。BとCは、見たことがない文章であったとしても、文脈と選択肢から正しい選択肢を選ぶことはできなくはないレベルです。Aは基本的な内容なので、正しい選択肢を選ぶことはそれほど難しくはなかったと思われます。
「労働安全衛生法」は、Dは平成7年度に記述式で出題された箇所で、DとEいずれも基本的な内容でしたので、正しい選択肢を選ぶことは容易であったでしょう。これらから、基準点の引下げの可能性は低いといえます。
「労災保険法」のAからCは「休業補償給付」に関する問題で、基本的な内容でした。
問題文2は「社会復帰促進等事業」に関する問題で、やはり基本的な内容といえます。そのため、すべて正解することは難しくないので、基準点の引下げはないでしょう。
「雇用保険法」は、傾向どおり数字に関する空欄が複数出題されました。
AとBは技能習得手当に関する問題で、Aについては平成13年度の選択式で出題された箇所です。
いずれにしても正しい選択肢を選ぶのは難しくなかったでしょう。
CとDは「日雇労働求職者給付金」に関する問題で、いずれも基本的な内容です。
Eは「受給期間の延長」に関する問題で、事例として出題しています。そのため、正しい選択肢を選ぶのが難しかったといえます。ただ、全体として見れば、3点を確保することは難しくはないので、基準点の引下げはないでしょう。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、問題文1は判例からの出題でした。
文脈と選択肢から正しい選択肢を選べなくはないですが、選択肢が長く、紛らわしいものだったため、正しいものを選べなかった受験者が少なからずいると思われます。
問題文2は「労働者派遣法」に関する問題で、基本的な内容でした。
問題文3は「最低賃金制度」に関する問題で、Eは基本的な内容でした。Dはやや難しいといえますが、選択肢から正解を導き出すのは、それほど難しくはないでしょう。このような状況ですので、問題文1の得点状況によっては基準点が下がるかもしれません。
「社会保険に関する一般常識」はAからⅮは法令からの出題で、基本的な内容なので正解することは容易といえます。
Eは厚生労働白書からの出題で、知っていたかどうかであって、もし知らなかったとしても、AからⅮを正解することができていれば、できなくとも構わない問題(捨て問)です。
そのため、基準点の引下げの可能性は低いといえます。
「健康保険法」は、例年どおり数字を含んだ空欄が複数ありました。
数字といっても、基本的なものでしたから、確実に正解しなければいけないレベルです。
ただ、Cの高額療養費算定基準額は覚えていなかったという受験者がある程度いたと思われます。
AとDは数字ではないもので、いずれも基本的な内容です。そのため、3点以上確保することは容易で、基準点の引下げはないでしょう。
「厚生年金保険法」は、CとDは事例問題で、じっくり考える必要がある問題でした。
そのため、正解できなかった受験者が少なからずいると思われます。
その他はいずれも基本的な内容でした。そのようなものだと油断をしてしまい、うっかりミスをしてしまうということがあるかもしれません。
そのため、可能性は低いですが、基準点が2点に下がるかもしれません。
「国民年金法」は問題文1は「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」に関する問題で、AとBは平成23年度の選択式で出題されたときと全く同じ空欄でした。 その他の内容も含め、基本的な内容ですが、平成23年度の選択式では基準点の引下げが行われています。知識が曖昧で正しい選択肢を選べないという受験者がかなりいた場合、基本的な内容(3点を確保することは難しくはない)とはいえ、基準点の引下げがあるかもしれません。
全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったりということはなく、やや得点しやすかったといえる程度ですが、取りこぼしをしてしまいそうなものがあることから、受験者のレベルに大きな変化がないのであれば、トータルの基準点については、昨年度と同程度か、少し下がり、基準点は、25~27点ではないでしょうか。
ただ、科目別の基準点の引下げの状況などにより、変わってくる可能性もあります。
択一式試験について
8月27日に行われた「令和5年度社会保険労務士試験」の択一式試験について講評します。
まず、問題冊子のページ数は60ページでした。平成10年度頃は50ページ前後、その後、平成10年代は50ページから60ページ、そして、平成20年代は60ページ以上が増え、ここ6年、60ページ以上が続いています。 今年度は昨年度より減っているとはいえ、このページ数だと、かなりのボリュームで、時間配分で苦戦したという方もいたかと思います。
それでは、各科目について見ていきます。
「労働基準法」は、傾向どおり、通達や判例、コンメンタールの記載などからの出題がありましたが、極端に難しいとは感じなかったのではないでしょうか。また、知らない内容のものがあったと思いますが、それに惑わされなければ、答えとなる肢は基本的な内容や過去問で出題実績のある論点だったので、かなり正解することができたでしょう。そのため、できれば5問前後は正解しておきたいところです。
「労働安全衛生法」は、問9は難しい問題でしたが、問8と問10はそれほど難しくはなく、いずれも正解したいところです。「労働基準法」と「労働安全衛生法」を合わせた10問で考えた場合、いずれもそれほど難しくはないことから、確実に基準点を確保し、できれば7点以上は取っておきたいです。
「労災保険法」は、昨年同様に事例や認定基準などの出題が多かったほか、労災保険法の特徴である、1つのポイントに視点を置く問題がありました。
その中で問2は、基本的な内容なので確実に正解しなければならない問題です。その他はどちらかというと難しいレベルですが、正解できなくはない問題もありました。最悪2点、できれば3点以上取っておきたいところです。
「労働保険徴収法」は、基本的な内容が中心でしたが、正誤の判断が難しい肢が含まれていたので、正解肢を選べなかったものがあったかもしれません。そのため、全問正解とならなかったとしても、「労災保険法」とのトータルで5点以上は取っておきたいところです。
「雇用保険法」は、細かい内容もありますが、全体としては難しくはなく、基本的な知識で正解を導き出せる問題が多くありました。そのためできるだけ得点をしたい科目といえ、5点以上は取っておきたいところです。
「労働保険徴収法」は、3問とも難しくはないので、3問すべてを正解することができたかもしれません。「雇用保険法」とのトータルで最低7点以上は取っておきたいところです。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、一昨年度までの出題状況は、労働経済が2問で、法令等が3問、その内訳は、「労働契約法等」「労働関係法規」「社会保険労務士法」でしたが、令和4年度は「労働契約法等」の出題がなく、労働経済が3問で、令和5年度も同様の出題構成となっていました。
労働経済のうち問1と問2は、過去に出題されたことがあるので、対策をしていた受験者もいたかと思われますが、内容的に正解肢を選ぶのは難しかったでしょう。問4の「労働関係法規」は極端に難しいというものではなかったので、正解しておきたい問題です。問5は2肢までは絞り込める内容でした。これらの状況から、少なくも1点、できれば2点を確保したいところです。
「社会保険に関する一般常識」は、すべて法令に関する問題で、昨年度は法令が混在した問題が3問ありましたが、令和5年度は5問とも単独の法律で構成されたものでした。内容としては、全体的に難しくはありません。ですので、少なくとも3問は正解したいところです。1問か、2問しか正解することができないと、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の状況によって、合計で、科目別の基準点である4点を確保できない可能性があります。
「健康保険法」は、全体として見た場合、レベルは普通です。通達や事務連絡の内容がかなり出題されますが、近年の傾向どおり、通達や事務連絡からの出題がいくつもありました。見たこともないものがあったかもしれませんが、そのようなものばかりではなく、出題実績があるものや基本事項が多々出題されています。また、正解肢は簡単だったため、わからない肢があっても正解肢は選べたというものがあったでしょう。そのため、大量得点も可能で、7問以上は正解しておきたいところです。
「厚生年金保険法」は、主に基本的な事項からの出題で、比較的簡単な問題が多かったです。そのため、大量得点が望め、できれば8点以上確保したいところで、満点という受験者も少なからずいるのではないでしょうか。
「国民年金法」は、複雑な事例など具体的な内容の問題が出ることがよくありますが、令和5年度試験では、複雑な事例の出題がありませんでした。全体的に基本的な知識で答えを導き出せるものが多くありました。正誤の判断がしにくい肢がありましたが、消去法などで正解肢を導き出すことが可能でした。全体として取組みやすい問題が多かったことから、6点、7点は取れたのではないでしょうか。
トータルの基準点については、問題のレベルから考えた場合、昨年度(44点)と同程度の44点前後ではないでしょうか。
※解答速報・試験講評に関するご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※この解答速報・試験講評の著作権は株式会社フォーサイトが有し、無断転載及び無断転用を禁じます。


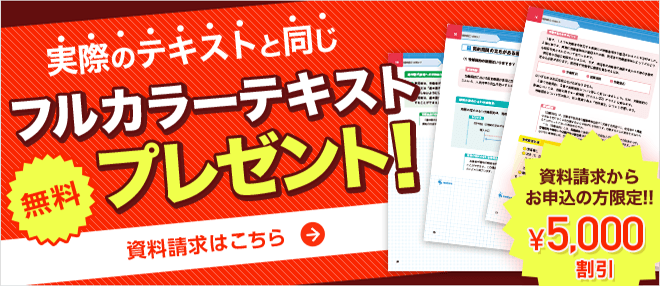

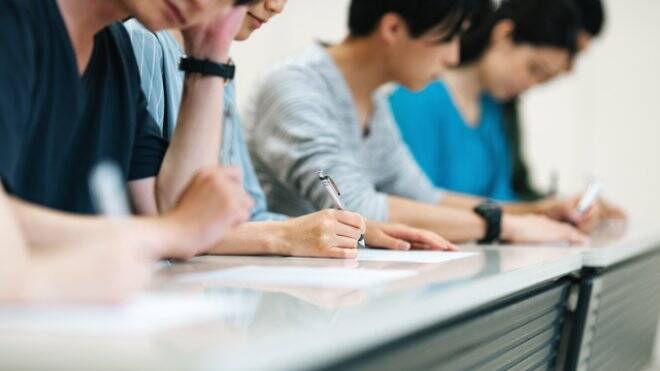


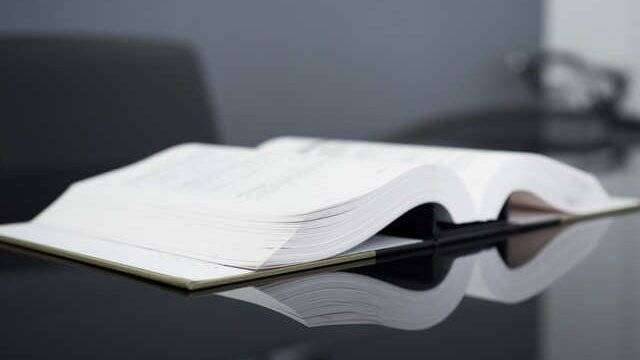










 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


