固定資産圧縮損とは
更新日:2020年2月25日

固定資産圧縮損という勘定科目を理解する前に、圧縮記帳という仕組みの存在を理解する必要があります。
圧縮記帳という言葉になじみがない、あるいは初めて聞いたという方は、まずは下記圧縮記帳に関するページをご確認ください。
以上を踏まえ、固定資産圧縮損の計上後について、時系列に追っていきます。そうすることで、固定資産圧縮損について、よりスッキリとご理解いただけることでしょう。
固定資産圧縮損を計上する効果の具体例
圧縮記帳のページで、固定資産圧縮損は「補助金に課税されないため」との記載がありました。
国庫補助金の効果をきちんと発揮させるための固定資産圧縮損について、もう少し詳しく確認することにしましょう。テキストの数値を、もう少しシンプルにしたものを使用します。
【設例】
X1.4/1 当社は国から国庫補助金1,000円を現金で受け取った。また、国庫補助金の対象になっている備品5,000円を現金で購入した。
X2.2/31 決算日。定額法(残高価値ゼロ、耐用年数10年)、間接法により減価償却を行った。
各年度の税引前当期利益の25%に法人税等が課税される。また、各期とも国庫補助金受贈益以外の収益として1,000円が計上されるものとする。
圧縮損を計上する効果~補助金の効果を最大限に!~
X1に固定資産圧縮損を計上した場合としなかった場合についての比較をします。
ここで、「補助金の効果を最大限にする」ということは「国庫補助金への課税がなされない」ことを意味するとお考えください。
| 固定資産圧縮損を計上した場合 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 備品 固定資産 圧縮損 |
1,000 5,000 1,000 |
国庫補助金受増益 現金 備品 |
1,000 5,000 1,000 |
| 減価償却費 | 400 | 減価償却累計額 | 400 |
| 損益計算書への影響 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | 収益 | ||
| 固定資産 圧縮損 減価償却費 当期純利益 |
1,000 400 600 |
その他収益 国庫補助金受増益 |
1,000 1,000 |
| 固定資産圧縮損を計上しなかった場合 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 備品 |
1,000 5,000 |
国庫補助金受増益 現金 |
1,000 5,000 |
| 減価償却費 | 500 | 減価償却累計額 | 500 |
| 損益計算書への影響 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | 収益 | ||
| 減価償却費 当期純利益 |
500 1,500 |
その他収益 国庫補助金受増益 |
1,000 1,000 |
圧縮記帳のページにもありましたように、国庫補助金受増益と固定試算圧縮損プラスマイナスゼロになり、国庫補助金受増益については、実質的に課税されていないことがわかります。
一方で、圧縮記帳をしなかった場合は当期純利益の中に国庫補助金受増益が含まれ、せっかく出した補助金に課税され、補助金の効果が打ち消されているというわけです。
圧縮損を計上することによる課税の繰り延べとは?
さて、次に、第1期の法人税等をご覧ください。当期純利益の25%ですから、次のように計算できます。
| X1年の法人税等 | |
|---|---|
| 固定資産圧縮損を計上した場合 | 固定資産圧縮損を計上しなかった場合 |
| 600×25%=150 | 1500×25%=375 |
このように、固定資産圧縮損を計上した場合、X1年については法人税等の支払額が減少しています。
では、次に、「課税の繰り延べ」という点について、時間を追って観察していきましょう。
「繰り延べている」ということは、圧縮記帳をすると、その時点では支払わないとしても、将来的にはどこかで支払っていることを意味します。
先ほどの設例のX2年以降について見てみましょう。
その前に、まずは、X1年終了時点での貸借対照表(資産)の状況を確認しておきます。
| 固定資産圧縮損を計上した場合 | 固定資産圧縮損を計上しなかった場合 | ||
|---|---|---|---|
| 備品 備品減価償却 累計額 |
4,000 400 |
備品 備品減価償却 累計額 |
5,000 500 |
備品の帳簿価額が異なることから、この違いは当然、X2年以降の減価償却費の計算にも影響を及ぼします。
| X2年以降の当期純利益への影響 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産圧縮損を計上した場合 | |||||||
| 費用 | 収益 | ||||||
| 減価償却費 当期純利益 |
400 600 |
その他収益 | 1,000 | ||||
| X2年以降の法人税等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×25%=150 | |||||||
| X2年以降の当期純利益への影響 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産圧縮損を計上しなかった場合 | |||||||
| 費用 | 収益 | ||||||
| 減価償却費 当期純利益 |
500 500 |
その他収益 | 1,000 | ||||
| X2年以降の法人税等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×25%=125 | |||||||
X2年以降の「法人税等」の金額に着目すると、「固定資産圧縮損を計上した場合」のほうが多く支払っています。
それでは、この備品の償却期間(10年間)を通してみた場合、支払っている法人税等の金額はいったいどのようになっているのでしょうか?
| 法人税等の支払金額 | |
|---|---|
| 固定資産圧縮損を計上した場合 | 固定資産圧縮損を計上しなかった場合 |
| X1年:600×25%=150 X2年以降:150×9=1350 10年間合計=150+1350=1500 |
X1年:500×25%=375 X2年以降:125×9=1125 10年間合計=375+1125=1500 |
以上のように、支払っている税金は同じになります。あくまでも課税の繰り延べであるという点がご確認いただけたのではないでしょうか。
つまり、固定資産圧縮損を計上した場合どのような形で将来的に支払うことになるかというと、次の流れです。
第2期目以降、減価償却費という費用が減る
→収益が大きくなる
→その結果として課税される金額が大きくなる
→支払う法人税等が多くなる
→償却期間を通算すると固定資産圧縮損を計上しなかった場合と同じになる
以上のように、固定資産圧縮損を計上する場合としなかった場合を比較することで、損益計算書や貸借対照表への影響が、よりはっきりと読み取れ、「補助金への課税回避」「課税の繰り延べ」といったメリットを持つことがご確認いただけたのではないでしょうか。
無料体験学習








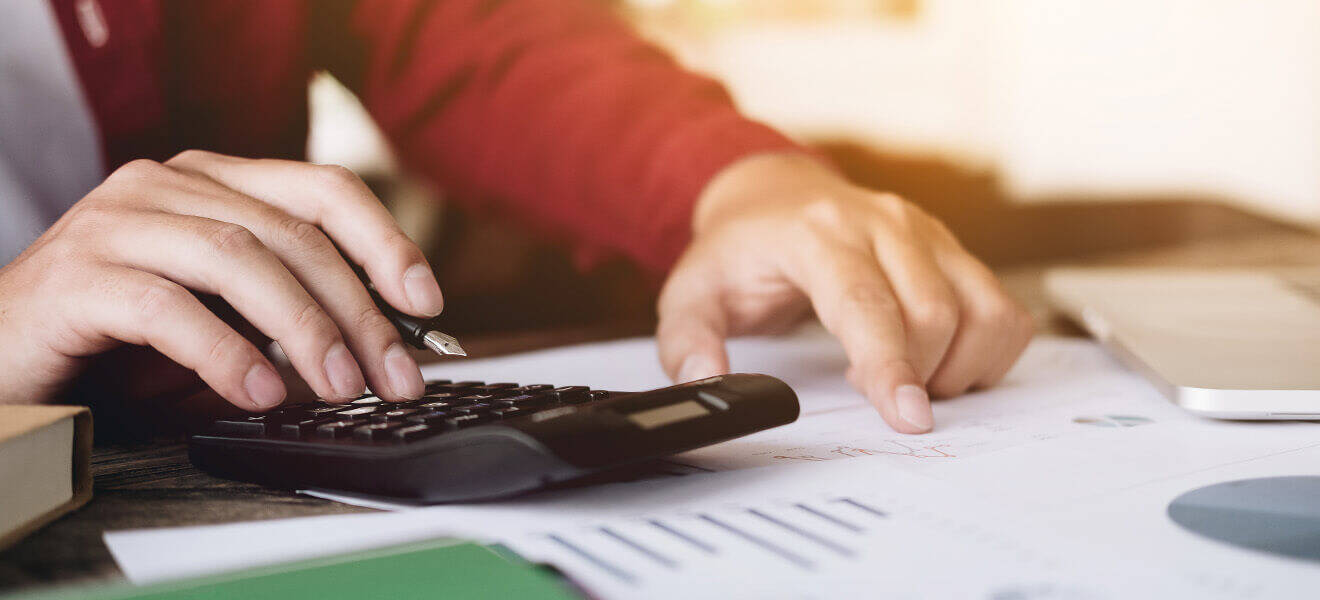

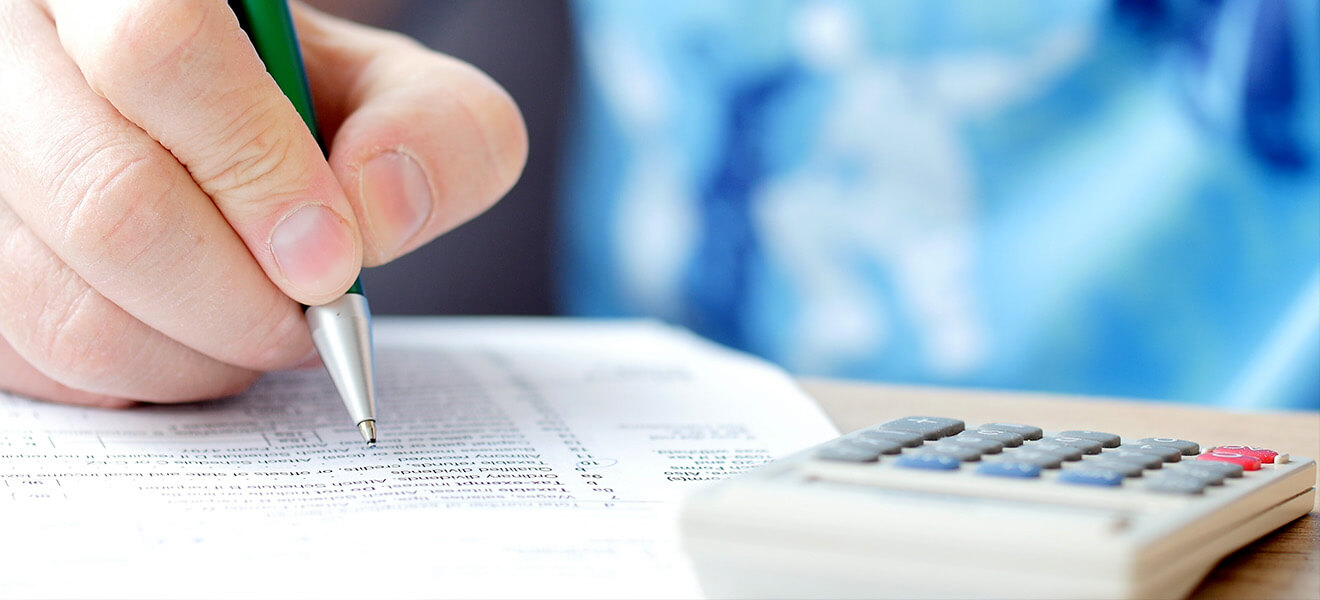






 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


