中小企業診断士に合格するために必要な勉強時間はどのくらい?
更新日:2023年5月19日
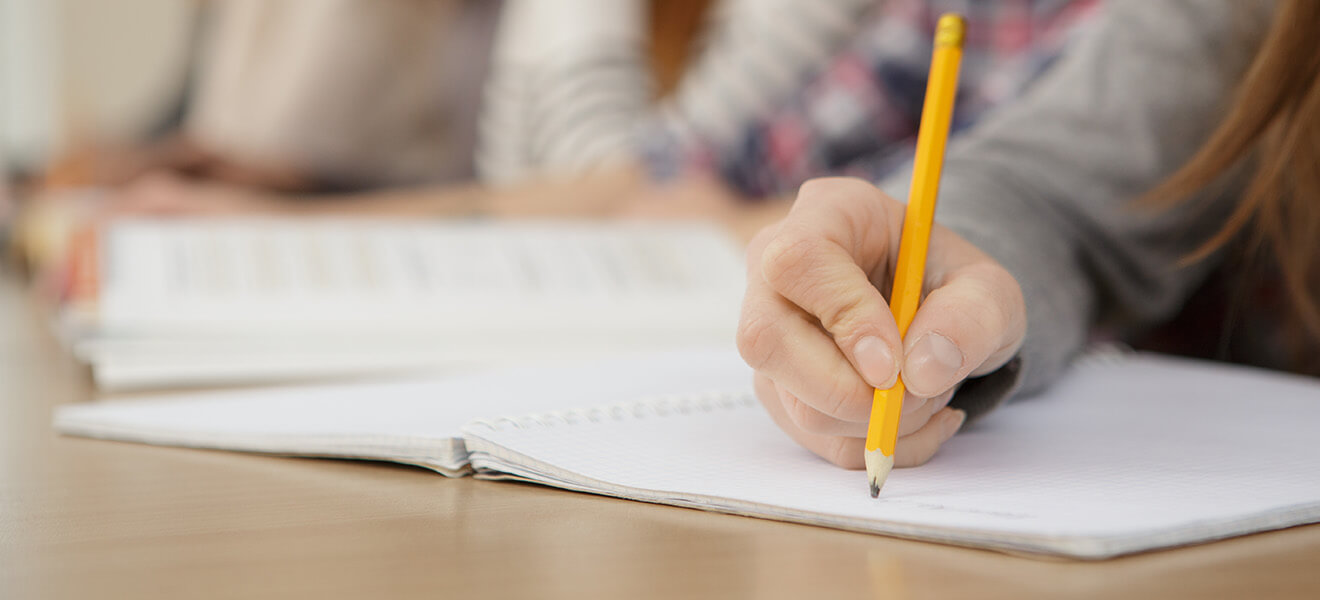
日本版MBAとも呼ばれ、多くの方が取得を目指すのが中小企業診断士資格です。
この中小企業診断士試験は難易度が高い試験としても知られており、多くの勉強時間が必要な資格試験となっています。
この記事では中小企業診断士試験合格に必要な勉強時間や勉強期間、さらに科目別の勉強時間の目安などを細かく解説。これから中小企業診断士を目指す方の参考になる情報を集めました。
中小企業診断士試験合格のために必要な勉強時間
中小企業診断士試験は難関試験としても知られています。試験は一次試験と二次試験で行われ、当然ですが一次試験・二次試験ともに合格して初めて資格を取得することができます。
ちなみに過去10年間で、一次試験・二次試験を一度にパスした合格率はおよそ7.7%。10人に1人も合格できない難関試験となっています。
そんな中小企業診断士試験ですが、独学で合格したという方はいます。独学でも合格は不可能ではありませんが、決して簡単でもありません。
初学者の方が独学で中小企業診断士試験に合格するために、必要と言われている勉強時間に関して紹介していきましょう。
一次試験合格に必要な勉強時間
一次試験に合格するために必要とされている勉強時間は800~1,000時間。一次試験は出題範囲が非常に広く、経済学から法知識、経営理論などさまざまな知識が必要なため、勉強時間も長くなります。
必要な勉強時間に大きな開きがあるのは個人差が大きいため。あらかじめある程度の基礎知識がある方、ほかの資格を取得するために似たような分野の勉強をしたことがある方などは比較的800時間に近い勉強時間で合格できるでしょう。
反対に特に出題範囲の勉強をしたことがないという方が挑戦すれば1,000時間を超える勉強時間が必要になるかもしれません。
いずれにせよ十分な勉強時間を確保しないと合格は難しいというのが事実です。
二次試験合格に必要な勉強時間
中小企業診断士試験の二次試験では事例問題が出題されます。その事例問題の対策として必要な勉強時間は200~400時間と言われています。
事例問題というのは、一次試験で勉強した範囲の知識を総動員して答えを導き出す必要があり、勉強時間も十分確保する必要があります。
一次試験の対策時間と比較するとかなり短く二次試験対策は比較的容易に見えるかもしれませんがそれは勘違い。
二次試験の問題に正確に解答するためには、一次試験の知識を暗記するだけではなく、実際に応用できなければいけません。つまり一次試験の勉強時間は、ある程度二次試験対策の勉強も含まれていると考えられます。
そのうえで事例問題に慣れるために200~400時間という勉強時間が必要になりますので、相当しっかり勉強する必要があるということになります。
合格に必要な勉強時間を確保するための勉強期間
中小企業診断士試験に挑戦するためには、合計で最大1,400時間の勉強時間が必要になります。この1,400時間という勉強時間を確保するためにはどのくらいの勉強期間が必要になるかを計算していきましょう。
勉強期間別 毎日確保すべき勉強時間
まずは1,400時間の勉強時間を確保するために必要な勉強期間の目安を表で紹介しましょう。
| 勉強期間 | 毎日の勉強時間(合計1,400時間) |
|---|---|
| 6ヶ月 | 平日:各7時間/土日:各10時間 |
| 12ヶ月 | 平日:各2時間/土日:各8時間 |
| 15ヶ月 | 平日:各2時間/土日:各6時間 |
| 18ヶ月 | 平日:各2時間/土日:各4時間 |
| 24ヶ月 | 平日:各1時間/土日:各4時間 |
現実的には1年以上の勉強期間が必要
現実的に考えれば必要な勉強期間は1年以上。1年だとしても平日に2時間、土日に8時間を確保する必要があります。祝日や有給休暇などを考慮に入れればなんとかクリアできそうなのがこの1年間という勉強期間です。
しかし、毎日の生活を送っている以上、すべての休日を勉強だけに充てるのもあまり現実的とは言えません。家族と過ごす時間や恋人と過ごす時間、さらに体調不良や仕事の都合など、いろいろな理由である程度休日は潰れるという方がほとんどかと思います。
そう考えると必要な勉強期間は1年半以上というのが現実的ということになります。
中小企業診断士試験で多くの勉強時間が必要な理由
中小企業診断士試験に挑戦するには多くの勉強時間、長い勉強期間が必要になります。
ここまで勉強時間が必要となる理由について改めて整理しておきましょう。
一次試験の科目数が多い
中小企業診断士試験の一次試験では7科目の試験科目があります。7科目と聞けば、ほかの資格試験でも同じ程度の科目が出題される試験はあり、そこまで多くないと感じるかもしれません。
問題はこの7科目が、分野として多岐にわたるという点です。一般的に資格試験というものは、ある分野における専門知識がしっかり身についているかどうかが試されます。そのため試験科目が多いといっても、各科目ともに特定の専門分野から出題されることが多く、各科目の勉強にはある程度共通点があったりします。
しかし中小企業診断士試験では、経済学や経営理論、さらに法務の知識や中小企業政策の問題など、共通点のないまったく違う分野の問題が出題されます。それぞれの分野に関する専門知識が必要となるため、一般的な資格試験よりもより広い分野の知識が必要とされます。
一次試験には科目別足切り点が設定されている
中小企業診断士試験の一次試験対策に多くの勉強時間が必要となる理由として、科目別に足切り点が設定されているという点も挙げられます。
一次試験で出題される7科目はそれぞれ100点満点で採点されます。その合格基準点は総得点が420点以上かつ、科目別で40点未満の科目がないことです。
つまり苦手科目でも40点以上取らないと合格はできません。全ての科目で40点以上取り、かつ合計で60%以上の正答率があって初めて合格となります。
全ての科目を平均的に学び、苦手科目がないことが条件となるため、多くの勉強時間が必要ということになります。
記述式の二次試験の難易度が高い
二次試験は事例問題に解答していきます。出題されるのは4題。こちらも一次試験と同様で、各問100点満点で採点され、合計240点以上かつ40点未満の問題がないことが合格基準となります。
二次試験は一次試験とは違い記述式で行われ、出題に対し500~800文字程度の論述で回答する形になります。
二次試験で問われるのは、一次試験で身に着けた知識をしっかり実務で活用できるかどうかの応用力。一次試験で勉強した範囲を、単に暗記するのではなくその内容をしっかり理解しているかどうかが試されるうえ、短い文章で的確に説明することが求められます。
単に知識を問われるだけではなく、論理的思考力も試されるため対策にはある程度の勉強時間が必要ということになります。
科目別 必要な勉強時間の目安
中小企業診断士試験合格のために必要な勉強時間に関して、さらに細かく考えていきたいと思います。ここからは一次試験、二次試験の各科目に必要とされる勉強時間に関して紹介していきたいと思います。
一次試験の科目別勉強時間の目安
| 試験科目 | 必要な勉強時間の目安 |
|---|---|
| 財務・会計 | 190時間 |
| 企業経営理論 | 160時間 |
| 運営管理 | 150時間 |
| 経済学・経済政策 | 150時間 |
| 経営情報システム | 140時間 |
| 経営法務 | 140時間 |
| 中小企業経営・政策 | 70時間 |
上の表が一次試験の科目別の勉強時間。あくまでも目安として捉えていただければと思います。特徴的な点は、財務会計にある程度力を入れる必要があるという点。また、中小企業経営・政策の科目は多少短めでもいいという点でしょう。
財務・会計の科目に多く時間が必要なのは、企業の現状を把握するためにその財務状況を正しく把握することが重要であるというのはもちろん、専門用語が多く、さらに数学的な知識も求められるからでしょう。
そのほかの科目に関してはやはり平均的に学んでいくのがいいようです。とにかく苦手科目を作らないことが合格への近道ですので、全体を平均的に進めていけるように工夫しましょう。
二次試験の科目別勉強時間の目安
二次試験の事例問題は、出題ごとにテーマが決まっています。
- 事例Ⅰ…「組織(人事含む)」
- 事例Ⅱ…「マーケティング・流通」
- 事例Ⅲ…「生産・技術」
- 事例Ⅳ…「財務会計」
それぞれの問題に必要な勉強時間は以下の通りです。
| 試験科目 | 必要な勉強時間の目安 |
|---|---|
| 事例Ⅰ~Ⅲ | 200時間 |
| 事例Ⅳ | 200時間 |
事例Ⅰ~Ⅲまでに関しては3題で200時間、事例Ⅳは1題で200時間ほどの勉強時間が必要とされています。
事例Ⅰ~Ⅲに関しては、一次試験で学んだ知識を応用することで対応できますので、一次試験対策がしっかり終わっていればそこまで多くの勉強時間は必要ありません。
問題は事例Ⅳの問題。この問題は論述式の解答に加え、財務会計に関する計算問題が出題されます。この計算問題が厄介な分、多くの勉強時間が必要となります。
一次試験で学んだ財務・会計の分野の知識を基に、それを実際に計算式に起こして解答を導き出すのは、ある程度演習問題を重ねて慣れていくしかありません。過去問などで何度も繰り返し解答するようにしましょう。
中小企業診断士試験に短期間で合格するためには?
中小企業診断士試験には、多くの勉強時間が必要であり、当然ですが長い勉強期間が必要となります。
ただしこの勉強期間が長くなるというのは、試験対策としてはあまりおすすめできません。勉強期間が長期間となるとどうしても勉強に対するモチベーションが下がりやすくなります。モチベーションが下がった状態で勉強をしても効率は上がらず、さらに勉強期間が長くなるという悪循環に陥りかねません。
そのためにも勉強期間はできるだけ短くするのがベスト。そのためにできることを紹介していきましょう。
試験の傾向をつかみ適切な勉強スケジュールを立てる
勉強期間が長期化することで避けたいのがモチベーションの低下です。そこで毎日の勉強の中で達成感を感じながら勉強をするのがおすすめとなります。
勉強が終わったわけでもないのに達成感を感じるにはどうすればいいか。勉強スケジュールをしっかりと立てるというのがひとつの解決法になります。
毎日の勉強スケジュールを考え、そのスケジュールを日々クリアすることで、毎日の勉強に達成感を感じることができ、持ちーベーションをキープすることができます。
勉強スケジュールを立てるのは、まず試験の全体像の把握が重要。勉強を本格的に始める前に参考書などを最後まで通しで読みましょう。理解しにくい部分があっても強引に読み進めてもOKです。
全体を通して読むことで重要なワード、分野、項目といったものが見えてきます。そうした重要ポイントを意識してざっくりとした月単位のスケジュールを組みましょう。月単位のスケジュールができたら今度は週単位のスケジュール、そして毎日のスケジュールと順番に組んでいきましょう。
スケジュールを組むときに意識するのは、決して無理なスケジュールを組まないこと。勉強スケジュールを立てるのは、そのスケジュールを実行することで達成感を感じながら学び続けるためです。
自分がクリアできる目標をしっかりと設定し、目標をクリアしながら勉強を続けていけるようにしましょう。
ちょっとしたスキマ時間も勉強時間に活用する
勉強期間を短くするには、勉強効率を上げるか、日々より多くの勉強時間を確保するしか方法はありません。独学で勉強効率を高めるには限界がありますので、強く意識したいのは勉強時間の確保です。
とはいえ睡眠時間を無理に削って勉強時間を増やしても長続きはしません。もちろん日常の仕事や家事に影響ができるような方法もおすすめできません。
おすすめしたいのが毎日のスキマ時間を活用すること。毎日の通勤電車の中や、洗濯機を回している時間など、ふとしたスキマ時間を勉強時間に変えていくことで、日々の勉強時間を増やすことができます。
1日15分でも勉強時間を確保できれば年間で65時間の勉強時間を確保できます。スキマ時間の有効活用を意識するのがおすすめです。
短期間で合格を目指すのであればフォーサイトがおすすめ
中小企業診断士に短期間の勉強期間で合格を目指すというのであれば、独学にこだわるのはおすすめできません。おすすめしたいのは通信講座フォーサイトの中小企業診断士講座です。
中小企業診断士を目指すと考えた場合、考え得る勉強方法は3つ。独学か、通信講座受講か、予備校通学です。その中で通信講座をおすすめするには理由があります。
まず独学以上に効率的に学べるということ。通信講座でも専門講師の講義を受けることができますので、独学と比較すれば勉強効率は大きくアップします。専門講師の講義を受けられるという点では予備校通学も同じですが、予備校と通信講座では大きな違いがあります。
予備校の講義を受けるには、通学可能圏内に予備校が存在する必要があります。都市部などであればある程度の距離に予備校があるかと思いますが、地方部在住の方はそうはいきません。
効率的に学ぶために、片道1時間かけて予備校に通うのは、正直効率的ではありません。通学で往復2時間かかるのであれば、予備校に通わず自宅にいれば2時間の勉強時間が確保できるということになります。
自宅で、通学時間なしで予備校と同等の専門講師の講義を受講できる通信講座はより効率的な学び方といえるでしょう。
しかし通信講座の中で中小企業診断士講座を開講している講座は多数あります。その中でフォーサイトをおすすめするには理由があります。
独学では1,000~1,400時間かかるといわれる勉強時間ですが、フォーサイトの講座を受講すれば、600~900時間まで短縮することができます。
なぜそこまで短縮できるのか?その理由を紹介していきましょう。
合格点主義で効率的に学べる
フォーサイトではオリジナルテキストを用意しています。このオリジナルテキストは、中小企業診断士試験で100点を取ることを目的としていません。あくまでも目指すべきは合格点。徹底した合格点主義で、余計な項目は勉強せず、合格に向かって一直線で学べるように考えられています。
また授業カリキュラムもこのテキストをベースに考えられており、中小企業診断士試験に精通したスタッフや専門講師が、もっとも効率的に学べる順序を考えてカリキュラムを構成しています。
合格点主義で最短で合格を目指せる。それがフォーサイトの中小企業診断士講座ということになります。
eラーニング教材が充実でスキマ時間も有効活用
フォーサイトをおすすめするもうひとつの理由がeラーニング教材の充実です。eラーニングとは、スマホやタブレットを利用して、時間と場所を選ばず行う勉強法のこと。そのために活用できるデジタル教材が豊富にそろっているのがフォーサイトです。
eラーニング教材にはデジタルテキストはもちろん、講義動画もあります。講義動画はスキマ時間に学ぶことを意識した短時間の構成で、15分程度で視聴できるようになっています。また、スマホの小さな画面でも文字が読みやすいようにデザインされており、通勤電車の中などでも気軽に勉強が可能です。
さらに講義動画の音声のみのデータや演習問題なども搭載されていますので、ちょっとした時間に自分が好みの方法で学べるのが大きなメリット。このeラーニング教材を上手に活用すれば、より短期間での合格が目指せるでしょう。
まとめ
中小企業診断士試験に独学で合格しようとした場合、必要とされる勉強時間は1,000~1,400時間。フルタイムで働く方の場合、最低でも1年半ほどの勉強期間がないと合格は難しいという計算になります。
中小企業診断士試験は出題科目数が多く、さらにそれぞれ学ぶ分野も変わるということもあり、なかなか対策が難しい試験です。さらに二次試験では身に着けた知識を応用する力や論理的思考力も試されるため、独学で目指すのは簡単ではありません。
より短い勉強期間で取得を目指すのであれば、独学にこだわらず通信講座を利用するのがおすすめです。通信講座の中では、合格点主義のオリジナルテキストや、充実のeラーニング教材を提供しているフォーサイトがおすすめ。
気になる方はまず資料請求から考えてみるといいでしょう。



















 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


