FP2級試験「資産設計提案業務」の実技対策は?過去問の解き方は?
更新日:2019年3月11日

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)で実技試験を受ける場合、受験科目は「資産設計提案業務」のみです。FP2級の「資産設計提案業務」について、その特徴、過去問の紹介や解き方について解説していきます。
「資産設計提案業務」は、FPの試験範囲である6分野すべてから出題されます。
この記事では、過去問解説として、「リスク管理」で頻出の生命保険、「タックスプランニング」で頻出の所得税に関する問題をそれぞれ取り上げます。
FP2級実技 資産設計提案業務の試験について
FP2級の本試験は、学科試験と実技試験があります。学科試験は日本FP協会と一般社団法人金融財政事情研究会(きんざい)で共通ですが、学科試験はそれぞれ異なるものを実施しています。
日本FP協会の資産設計提案業務は、6分野から幅広く出題される実技試験です。きんざいには中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務という、それぞれの分野に特化した実技試験があり、これらの分野に進もうと決めている場合は、きんざいで実技試験を受けると良いでしょう。まだ特に分野を決めていない場合は日本FP協会の資産設計提案業務、またはきんざいの個人資産相談業務を選ぶことになります。実際には、FP2級受験者の多くが資産設計提案業務または個人資産相談業務を選択します。
FP2級実技試験受験者の内訳
直近のFP2級実技試験の受験者推移を見てみると、次のようになっています。
資産設計提案業務または個人資産相談業務と、それ以下では桁が1つ違うことがわかります。
| 試験機関 | 試験科目 | 2023年5月 | 2023年9月 | 2024年1月 |
|---|---|---|---|---|
| 日本FP協会 | 資産設計提案業務 | 22,167 | 20,892 | 24,632 |
| きんざい | 個人資産相談業務 | 9,827 | 9,065 | 10,036 |
| きんざい | 中小事業主資産相談業務 | - | 1,005 | 1,116 |
| きんざい | 生保顧客資産相談業務 | 9,112 | 8,352 | 8,225 |
| きんざい | 損保顧客資産相談業務 | - | 268 | - |
(いずれも日本FP協会およびきんざいHPより)
資産設計提案業務は人気なの?
上の表でFP2級実技試験の受験者数を見ると、資産設計提案業務よりも個人資産相談業務のほうが若干受験数は多いです。一方、AFP取得を考える方にとっては、資産設計提案業務が人気です。
資産設計提案業務の試験対策
資産設計提案業務は受験者が多いため、書店などで多くの教材が出回っています。パラパラとめくって、使いやすそうなものを選ぶと良いでしょう。通信教育も豊富です。AFP取得を目指している場合は、AFP認定研修に認定されている通信教育を選びましょう。
試験対策としては、問題演習や過去問、模擬試験などでアウトプット力をつけていきます。問題を解きながら、間違えたところは適宜、テキストに戻って復習します。6分野すべてをまんべんなく学ぶようにしましょう。
資産設計提案業務の配点は?
日本FP協会の2級実技試験である資産設計提案業務の大いなる謎が、「配点はどうなっているのか?」という点です。配点がわからないと過去問の採点をするときに困るので、知りたいところですが配点は公開されていません。
公開はされていませんがある程度の推測はできます。問題数は40問で100点満点なので、単純に100を40で割ると2.5となります。1問2.5点というのはやや考えにくい数字ですので、一律同じ配点ではなく、どこかで配点の多寡があると推測できます。〇×式の問題、穴埋め問題など、1問につき複数回答が出る場合は、配点も多くなるのだろうと推測されます。その点を考慮しつつ、試験対策するようにしましょう。
問題集の選び方

問題集は、解答力をつけるために、なくてはならないものです。選ぶポイントは、テキストと同じ出版社から出ているか、ということです。
テキストと同じ出版社から出ている問題集を使うメリットは、内容が連動しているところです。例えば、テキストではファイナンシャルプランニング、次にリスク管理、それから金融資産…と、順番に内容を説明しています。その際、暗記すべき重要なトピックはここ、捨てていいトピックはここ、というように、それぞれ定義しながら進みます。問題集もそれに合わせて構成されているので、勉強しやすいです。
問題集は買いすぎない
問題集は、1種類に絞ることをおすすめします。特に初めてFP2級を受験する場合、不安な気持ちから、できるだけ多くの問題集を解きたくなってしまうものです。いろいろな問題を解くと、それだけ安心できるからです。
しかし、出版元の異なる複数の問題集を解いていると、それぞれで言っていること、推していることが違うので、混乱を招いてしまうおそれがあります。また、それぞれの問題集は他の問題集の内容を関知しないので、当然、内容の重複も出てきます。勉強に余計なロスを招いてしまいますので、問題集はテキストと同じ出版社のものを1冊(1セット)だけ購入し、それを繰り返し解くようにしましょう。
過去問を問題集として使う
問題集には、「予想問題」「演習問題」のような形で、出版社オリジナルの問題が収録されているものと、過去問を引用しながら解説を加えていくものの2種類があります。
予想問題を解いて、慣れてから過去問を活用した問題集に移行する、というのも1つの方法ですが、最初から後者の問題集を使って勉強したほうが、手っ取り早いです。
過去問式問題集は分野ごとにまとめられている
過去問を活用した問題集は、「2018年9月試験問題」「2018年5月試験問題」のように、過去に使われたそのままの形で掲載されているのではありません。分野ごとに分けて過去問がまとめられています。例えば不動産の過去問を解きたい場合、「不動産」のページを開けば、過去に出題された不動産の問題が掲載されています。
テキストと連動している過去問式問題集なら、テキストの順番に合わせて問題集が構成されているので、間違えたところを復習するときにも便利です。
ノートを活用しよう
過去問式問題集について、資産設計提案業務の実技は記述式ですが、選択式の問題がほとんどです。四択を一択に絞り込んでいく力をつけるために活用したいのがノートです。
問題を解くとき、選択肢1つ1つのどこが誤りなのか、どこを直せば正解になるのかという理由を書き込みながら解くようにしましょう。
答え合わせのときには、ただ合っているかどうかだけではなく、解答についている解説を読んで、自分の考えた理由と合っているかどうかも見比べましょう。解説を読んでもわからなければ、テキストに戻って復習します。この繰り返しにより、解答力が身についてきます。
なお、解説が貧弱な問題集だと、この作業ができません。正誤の理由までしっかり解説している問題集を選びましょう。
過去問を解くときは復習を忘れずに
資産設計提案業務は6分野すべてから出題されます。それだけたくさんの問題をこなさなければならないわけですが、順番に勉強していると、最初に勉強した分野の内容を忘れてしまいがちなため要注意です。適宜、復習しながら進めていくようにしましょう。
復習というと気が進まない方は多いと思います。前に勉強したことをもう一度繰り返すのはつまらないし、それよりも新しいことを学んだほうが、利益が大きい気がします。しかし、復習は避けて通れません。なぜなら人間は、覚えたことを忘れていってしまう生き物だからです。新しいことを覚えると、古いことを忘れてしまうようにできています。試験日までに6分野すべてを覚えておかなければならないのですから、忘れるわけにはいきません。
「進んだら復習」を習慣づけよう
おすすめの復習法は、毎日の勉強に、新しいことの学習と復習をセットで組み込んでしまうことです。項目1を1日目に勉強したら、2日目には項目2の勉強をするとともに、項目1の復習をします。3日目には、項目3の勉強をすると共に、項目2の復習をし、さらに項目1にもざっと目を通します。4日目には項目4を勉強するとともに、項目1~3をざっと復習しておく。このようにすれば、新規学習と復習をルーチン化できます。
毎日復習するのが大変であれば、1つのカテゴリ終了を節目として復習するのも良いでしょう。たとえば、金融資産運用なら、「債権」のカテゴリを何日か解いていき、終了して次の「株式」に行ったらその前の「債権」の復習をする。「投資信託」に行ったら「債権」「株式」をざっと復習するのです。
無理なく続けられる方法で、継続的に復習するようにしましょう。
資産設計提案業務の過去問を見てみよう

資産設計提案業務で、実際にどのような問題が出ているのかを見てみましょう。過去に出題された問題で問題集を作成する、過去問式問題集の一部として解説していきます。
FP2級の試験範囲の1つ「リスク管理」において、生命保険は頻出です。「タックスプランニング」では、各所得金額の計算、所得税の申告や納付、所得控除など所得税関連の問題が頻出です。
リスク管理の問題 生命保険
|
近藤雅之さんが平成26年度中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合、雅之さんの平成26年度分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の更新は行われていないものとする。 <資料> 【参考:所得税の生命保険料控除額の速算表】 <平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額>
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
<平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額>
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
|
(平成27年5月出題)
解答編
答えは3番です。表を見るときのポイントは、これらの契約が新契約か、それとも旧契約なのかというところです。
終身保険の保険料は、一般の生命保険料控除が適用されます。個人年金保険(税制適格特約付)は個人年金保険料控除が適用されます。
一般の生命保険料控除の額
契約日が平成23年3月31日なので、旧契約に該当します。年間支払保険料は13万5,000円ですから、一般の生命保険料控除は5万円です。
個人年金保険料控除
契約日が平成25年11月1日なので、新契約に該当します。年間支払保険料は12万円ですから、個人年金保険料控除の額は4万円です。
これらを足した、5万円+4万円=9万円が生命保険料控除の金額です。
タックスプランニングの問題(1) 事業所得
|
目黒さんは個人で美容院を営む自営業者(青色申告者)である。平成29年分の目黒さんの美容院の財務データが下記<資料>のとおりである場合、目黒さんの平成29年分の所得税における事業所得の金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 <資料>
※青色事業専従者給与は目黒さんの妻に対して支払われたものであり、この金額は、(3)の必要経費には含まれない。 <計算式> |
(平成30年1月出題)
解答編
選択式ではないので、自分で計算し、答えを求める問題です。
事業所得の金額について、問題文に与えられた計算式を用いて算出します。売上金額1,128万円-売上原価169万円-必要経費448万円-青色事業専従者給与240万円-青色申告特別控除65万円=206万円
206万円が、事業所得の金額となります。
タックスプランニングの問題(2) 退職所得
|
退職所得(特定役員退職手当等に係るものを除く)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、退職は障害者になったことに起因するものではないものとする。
|
(平成28年5月出題)
解答編
選択式の問題になります。絞り込みのポイントは、下記の赤字部分の数字を記憶しているかどうかです。
答えは4番です。順番に見ていきましょう。
- 勤続年数20年以下で退職した場合の退職所得控除の額は、「40万円×勤続年数(最低80万円)」で計算します。したがって、問題無し。ちなみに、勤続年数20年超で退職した場合は、「800万円+70万円(勤続年数-20年)」で計算します。
- 退職所得控除の額を計算する際の勤続年数に1年未満の端数があるときには、端数が1日でも1年に切り上げて計算します。したがって、問題無し。
- 退職所得の金額は、退職一時金の額から退職所得控除の額を控除した残額の2分の1に相当する額となります。したがって問題無し。
- 退職一時金を受け取る際、「退職所得の需給に関する申告書」をその退職一時金の支払い者(勤務先の会社)に他提出していれば、勤続年数に応じた退職所得控除を受けることができ、確定申告は不要となります。したがって、これが誤っています。ただし、確定申告はしても構いません。申告書を提出していない場合は、所得税については、その退職金の支払い金額につき20%の税率により、源泉徴収されます。
まとめ
資産設計提案業務は幅広い分野から出題されますが、出やすい問題がある程度決まっているので、勉強範囲をできるだけスリム化していくことが大切です。ただ内容を絞ったとしても、6分野もあるので、覚えるべきことは多いです。定期的・継続的に復習して、一度覚えたことを忘れてしまわないようにしましょう。
電卓で解く問題が出題されるので、計算に慣れておくことも大切です。














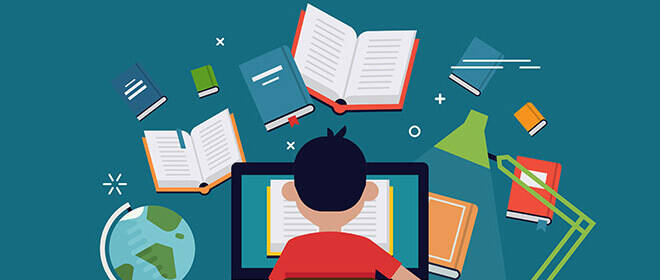


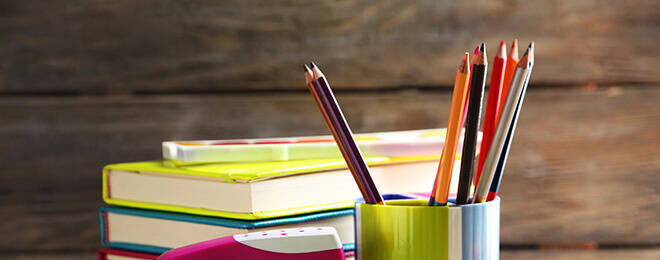




 ログイン
ログイン


 0120-966-883
0120-966-883


