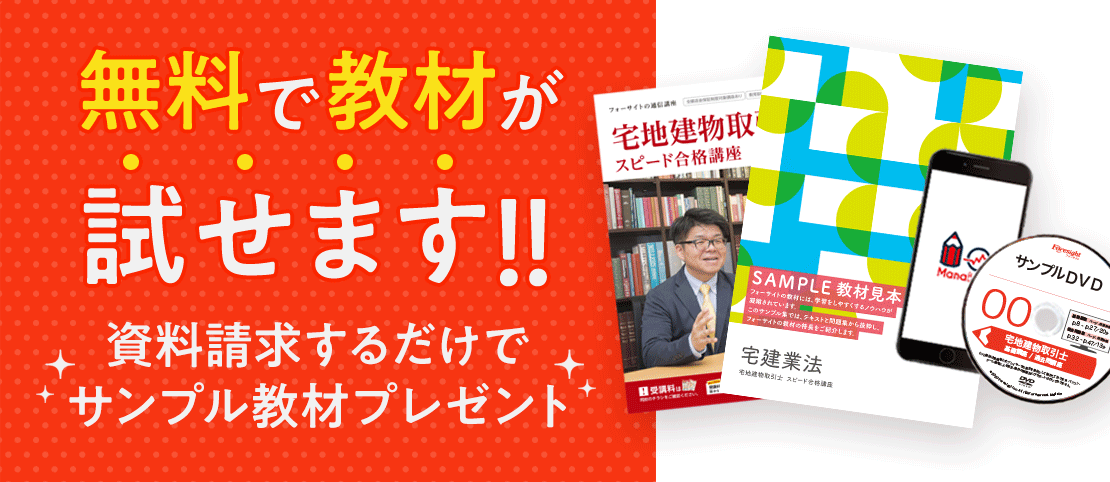中卒の方の中には、社会に出るまではどうしても学歴というものが気になってしまう方も多いかと思います。しかし、実際社会に出てしまえば、中卒や大卒といった学歴などは大して意味を持ちません。それ以上に重要なのが実務経験や、実務で残した結果となります。
とはいえ、中卒という学歴が気になっている方もいらっしゃるでしょう。そこで中卒の方にこそおすすめしたい人気資格を厳選して紹介していきたいと思います。
その資格の難易度や、どんな分野で活躍できるのかなど、資格の特徴や情報も紹介していきますので、参考にしていただければと思います。
中卒の方が資格を取得するメリット
中卒の方の中には、自身の学歴にコンプレックスを持っている方もいらっしゃるかと思います。しかし、実際に社会に出てみれば分かりますが、仕事をするうえで中卒や大卒といった学歴は何も意味を持ちません。
中卒の方でも仕事ができる方はたくさんいますし、東大卒で仕事ができない方もたくさんいます。実際の仕事と学歴にはなんの関係もありません。
ちなみに田中角栄氏(第64代内閣総理大臣)、松下幸之助氏(パナソニック創業者)、本田宗一郎氏(本田技研工業創業者)は皆中卒かそれ以下の学歴しかありません。もちろんこういった方は時代背景や、個人の資質が違ったという部分もありますが、学歴では中卒ということになります。
就職や転職の際、自分の仕事の能力を証明するのは中卒や大卒といった学歴ではありません。職歴や実務経験、そして所有している資格です。
とはいえ、良い学校を出た人の方がより良い就職先に就いていると思われるかもしれませんが、新卒者採用の場合、就職希望者の誰にも職歴はありません。職歴以外でその人を判断するには、学歴が占めるウエイトがどうしても大きくなってしまいます。
少なからずとも職歴がある方であれば中卒や大卒といった学歴よりも実務経験や資格の方が重要視されますので、ここはしっかり理解しておきましょう。
中卒の方が目指すべき2つの資格の種類
日本国内を見ても資格には多くの種類がありますが、これらの資格はいくつかの種類に分けることができます。
国が認可している国家資格、民間業者が認定している民間資格、国家資格と民間資格の中間に位置する公的資格の3つです。
中卒に方に特におすすめしたい資格は国家資格と民間資格。その理由を紹介しておきましょう。
国家資格
まずは国家資格です。その名の通り、国が認可している資格であり、目指すだけの価値がある資格ということになります。国が認めた資格こそ、中卒の方が目指すべき資格と言っても過言ではありません。
国が認可する資格は、本当にその資格がないと実務上困るから認可している資格です。つまりどの資格も無くてはならない資格であり、実用性の高い資格が多いという特徴があります。
また、国家資格は価値が高い資格が多いというだけではなく、その価値が落ちにくいというのも特徴。時代に合わせて資格の増減はありますが、その資格が持っている価値が落ちるということはまずありません。
どの業種でも長く活躍できるのが国家資格の特徴。中卒の方にこそおすすめしたい理由がこの部分となります。
民間資格
数多くある民間資格の中にも、実務で活用でき、しかも人気の高い資格があります。民間資格で多いのは受験資格なしで受験できる資格が多いという点。受験資格がないということは当然中卒の方でも挑戦可能ということ。
資格を認定している民間団体にとっても、その資格をより多くの方に取得してもらい、存在価値を高めたいという思いがあります。そのため民間資格は比較的受験資格なしの資格が多く、誰でも挑戦できる資格が目立ちます。
学歴や職歴に関係なく取得できる、より実用的な民間資格は中卒の方にもおすすめの資格となります。
中卒の方におすすめしたい人気資格11選
では、数ある資格の中で、特に中卒の方におすすめしたい資格を11種紹介していきましょう。
ここで紹介する資格は、中卒の方でも受験可能で、かつ人気の高い資格ばかりです。まずは表にまとめてみましょう。
| 資格名称 | 資格の種類 | 受験資格 | 上位資格 | 必要な勉強時間 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地建物取引士 | 国家資格 | ナシ | ナシ | 300~500時間 |
| 行政書士 | 国家資格 | ナシ | ナシ | 1,000時間 |
| 日商簿記【2級】 | 民間資格 | ナシ | アリ | 400~500時間 |
| ファイナンシャル・ プランニング技能士【2級】 | 国家資格 | アリ | アリ | 300時間 |
| 基本情報技術者 | 国家資格 | ナシ | アリ | 150~200時間 |
| 保育士 | 国家資格 | アリ | ナシ | 300時間 |
| 診療報酬請求事務能力認定試験 | 民間資格 | ナシ | ナシ | 400~500時間 |
| 調理師 | 国家資格 | アリ | ナシ | 400時間 |
| MOS【一般レベル】 | 民間資格 | ナシ | アリ | 50~80時間 |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 国家資格 | ナシ | ナシ | 250時間 |
| 総合旅行業務取扱管理者 | 国家資格 | ナシ | ナシ | 400時間 |
| インテリアコーディネーター | 民間資格 | ナシ | ナシ | 300~350時間 |
必要な勉強時間は、独学で勉強をした場合の勉強時間です。
なかには受験資格が必要な資格もありますが、この受験資格は中卒の方でもクリアできるものですのでご安心ください。
ここからはそれぞれの資格を中卒の方におすすめする理由などを中心にまとめていきます。
宅地建物取引士

| 正式名称 | 宅地建物取引士 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2024年度) | 241,436人 |
| 合格者数(2024年度) | 44,992人 |
| 合格率(2024年度) | 18.6% |
不動産取引の現場で、重要事項説明を行うという独占業務を持つ宅地建物取引士。一般的には宅建士と呼ばれている資格で、受験資格なしで挑戦できる資格の中では非常に人気の高い資格となります。
宅建士資格は主に不動産業界で活躍する資格です。特に不動産取引が多い仲介業や売買業、賃貸業などの業界で重宝されます。
さらに不動産に関する法知識なども身につきますので、金融業界など不動産業界以外でも活躍できる資格です。金融業界などは、資格なしの場合、学歴が重視されやすい業界。中卒の方がこういった業界を目指すのであれば、ぜひ取得しておきたい資格といえるでしょう。
不動産業界の営業職は、歩合制を導入している企業が多く、結果が収入に直結するケースが多々あります。中卒の方でもやる気次第で高給取りを目指せる、非常におすすめの資格となります。
行政書士
官公署などに提出する書類の作成や、その書類の提出代行という独占業務を持つ行政書士。行政書士をおすすめするポイントは、独立開業が可能な資格であるという点です。
独立開業ができるということは、面倒な就職や転職といった活動の必要がないということ。つまり中卒の方でも資格取得で、理想の働き方が実現できる資格ということになります。その分取得難易度は高くなりますが、それだけ価値のある資格ということもできます。
また、行政書士資格を取得しているということは、豊富な法知識を持っていることの証明にもなり、就職や転職の際にも好印象を与えることになるでしょう。これは中卒という学歴を大きく超えるインパクトとなりますので、一般企業への就職を目指す中卒の方にもおすすめとなります。
日商簿記
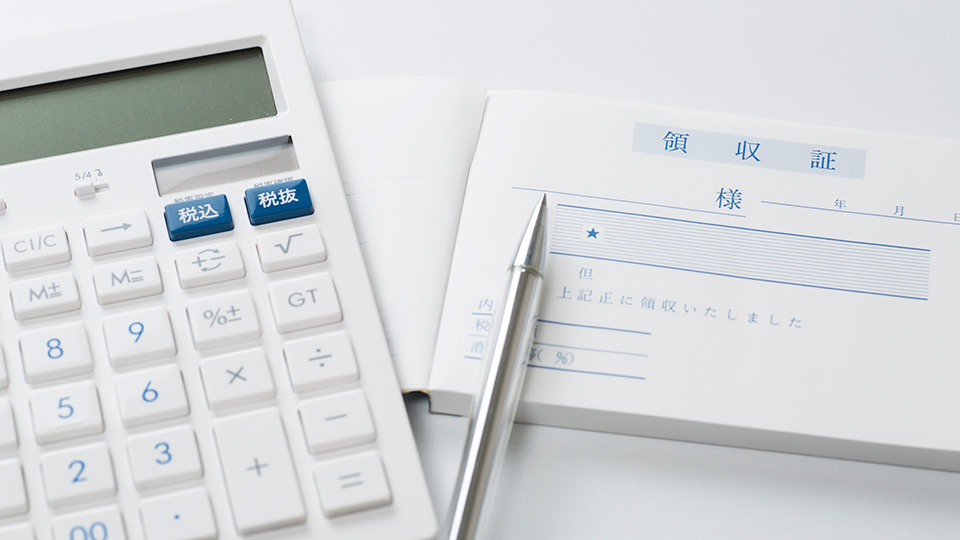
| 正式名称 | 日商簿記検定 |
|---|---|
| 資格種類 | 公的資格 |
| 受験者数(2025年2月) | 簿記2級:7,118人 簿記3級:21,026人 |
| 合格者数(2025年2月) | 簿記2級:1,486人 簿記3級:6,041人 |
| 合格率(2025年2月) | 簿記2級:20.9% 簿記3級:28.7% |
企業の経理部門の方にとっては取得必須とも言える資格。民間資格でありながら、非常に人気の高い資格であり、この資格を取得して活躍している中卒の方も多数います。
日商簿記には1~3級がありますが、実務上役立つという点では2級以上の取得がおすすめ。受験資格なしでいきなり2級から受験できますので、狙う場合はいきなり2級を狙ってもいいでしょう。
日商簿記をおすすめするポイントは、すべての業種で活躍できるという点。どんな業種でも経理部門がない会社は存在しません。どんな業種でも活躍できるため、中卒の方でも就職活動、転職活動の際、より多くの候補の中から勤め先を探せるというメリットがあります。
ファイナンシャル・プランニング技能士

| 正式名称 | ファイナンシャル・プランニング技能士 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2025年1月) | FP2級 学科試験:21,678人 実技試験:19,135人 |
| 合格者数(2025年1月) | FP2級 学科試験:9,634人 実技試験:9,342人 |
| 合格率(2025年1月) | FP2級 学科試験:44.4% 実技試験:48.8% |
顧客の資産運用やライフプランニングに関してアドバイスできる資格。一般的には「FP資格」とも呼ばれています。
金融業界やハウスメーカー、さらにコンサルティング業界などで活躍する資格で、中卒など学歴に関係なく受験者の多い人気資格でもあります。
FP資格には1~3級があり、実務で役立つのは2級以上。FP2級には受験資格がありますが、実務経験もしくはFP3級取得などでクリアできますので、興味がある方はFP業務で実務経験を積んでから挑戦するというのも一つの方法です。
実務経験がないという方は、FP3級を取得してからFP2級を取得するという方法もあります。2つの資格を取るのは大変と思われがちですが、3級の勉強は2級の勉強にも生かせますので、そこまで大変ではないかと思います。
FP資格さえ持っていれば、保険の営業やハウスメーカーの顧客担当など、中卒の方でも活躍の場が一気に広がるでしょう。
基本情報技術者

| 正式名称 | 基本情報技術者試験(FE) |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2024年度) | 133,732人 |
| 合格者数(2024年度) | 54,501人 |
| 合格率(2024年度) | 40.8% |
ITエンジニアの登竜門的な資格。情報処理技術者試験という国家資格の中に1つの区分になります。こちらも受験に学歴は関係なく、中卒の方でも挑戦できる資格です。
情報処理技術者試験の入門編的な資格というとITパスポートという資格が思い浮かびますが、ITパスポートはITを利活用する全ての社会人向けの資格。もちろん中卒の方がITパスポートの資格を目指すのもいいですが、問われるのはそこまで専門的な知識とはなりません。
その点基本情報技術者試験は、すべての社会人ではなく、IT系で働く方、特にITエンジニアの方を対象とした資格。問われる知識はより専門性が高く、試験としての難易度も随分変わります。
中卒の方でITエンジニアを目指す方には、基本情報技術者をスタートに、さらに上級の区分の資格を目指すというのがおすすめ。IT系への就職を目指している方は、まずは就職前に基本情報技術者を取得しておき、後は仕事をしながら自分に合った上級資格を目指すといいでしょう。
保育士

| 正式名称 | 保育士 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験申請者数(2022年度) | 79,378人 |
| 合格者数(2022年度) | 23,758人 |
| 合格率(2022年度) | 29.93% |
保育士試験には受験資格が必要で、大卒などの学歴が必要となります。しかし、受験資格の中には実務経験の項目もあり、中卒でも児童福祉施設などで一定期間の実務経験があれば受験可能となっています。
保育士資格をおすすめするのはなんといっても求人の多さ。特に全国の都市部において保育士は不足しており、常に多くの求人情報があります。
また、人材不足に関しては国も動いており、近年補助金なども強化されており、今後より職場環境や収入面もアップすると見られています。
保育士試験に挑戦するには、受験資格以上に実技試験が問題かもしれません。読み聞かせや音楽、絵画といった実技試験をクリアしないと合格できないのがネックとなるかもしれません。
こうした実技試験に関しては、学歴が大して意味を持ちません。中卒の方でもしっかり準備をすれば十分にクリアできる科目となっています。
とはいえ実技試験は独学では対応が難しいのがポイント。独学で対策しても、それで正しいのかどうかを自分自身で判断するのがなかなか難しくなります。
もし独学での対策に自信がないという方は、通信講座など実技試験対策講座も開講しているところを頼りにしましょう。
診療報酬請求事務能力認定試験

| 正式名称 | 診療報酬請求事務能力認定試験 |
|---|---|
| 資格種類 | 民間資格 |
| 受験者数(2023年度) | 2,446人 |
| 合格者数(2023年度) | 905人 |
| 合格率(2023年度) | 37.0% |
病院や歯科医院の受付業務などで、診療費に関して計算することができるようになるのが診療報酬請求事務能力認定試験です。病院などの受付業務に関しては、資格なしでも就職は可能です。しかし、この資格を取得していることでより就職しやすくなったり、より好条件で就職しやすくなるでしょう。
この資格をおすすめするポイントは求人の多さ。病院や歯科医院の数は非常に多く、コンビニエンスストアよりも数が多いとも言われています。その数だけ受付の数があるわけですから、当然求人も多くなります。
資格の取得には医療に関する専門用語や、薬品に関する専門用語など、あまり普段の生活では触れることのない単語を多く覚える必要があります。そのため資格取得にはある程度時間が必要となりますが、それだけメリットがある資格であることも間違いありません。
特に出産や育児を経験し、改めて働き始めるという中卒の女性の方などは、この資格を持っているといろいろな働き方ができますのでおすすめとなります。
調理師

| 受験資格 | 学歴 中卒以上 実務経験 2年以上 |
|---|---|
| 受験料 | 6,100~6,400円 |
| 試験会場 | 原則都道府県ごと |
| 出題方式 | マークシート式 全60問 |
| 合格基準点 | 60%以上 |
| 試験免除規定 | 厚生労働大臣が指定した調理師養成施設を卒業した者は無試験 |
中卒の方に特に人気が高い資格ともいえる調理師資格。
調理師試験は毎年1回。試験の実施は原則都道府県ごとの開催となっています。受験には資格が必要ですが、学歴は中卒以上、実務経験が2年以上となっていますので、中卒の方も受験可能な資格となっています。
また、厚労省指定の専門学校の課程を修了することで、無試験で調理師免許が手に入ります。
調理師はご存じの通り活躍の場が広い資格。学歴とは関係なく、自身の腕のみで生きていくことができるようになる資格でもあり、おすすめの資格となります。
MOS(マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト)

| 資格の種類 | 【一般レベル】 Microsoft Office Word 365&2019 Microsoft Office Excel 365&2019 Microsoft Office PowerPoint 365&2019 Microsoft Office Outlook 365&2019 【上級レベル】 Microsoft Office Word 365&2019 Microsoft Office Excel 365&2019 Microsoft Office Access 365&2019 |
|---|---|
| 受験料(税込) | 一般レベル】 10,780円 【上級レベル】 12,980円 |
| 試験日程 | 全国一斉 毎月1回開催 随時受験もアリ |
| 合格率 | 非公開 |
MOSとはマイクロソフト・オフィス・スペシャリストの頭文字。ビジネスの場で利用することが多いオフィスソフトの習熟度を図る民間資格となります。
どんな会社でも、ワードやエクセルなどのオフィスソフトは必ず利用しているといっても過言ではありません。そんなソフトを確実に扱えることを証明できるのは、就職や転職の際にも大きなアピールポイントとなるでしょう。エントリーシートにおいて、採用担当者が中卒や大卒といった学歴以上に興味を示す資格と言ってもいいかもしれません。
合格率に関しては公開されていませんが、一般レベルで約80%、上級レベルで約60%と言われています。
そこまで難易度の高い試験ではありませんので、しっかり準備して挑戦するようにしましょう。
旅行業務取扱管理者

| 正式名称 | 旅行業務取扱管理者 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2024年度) | 国内:10,141人 総合:4,680人 |
| 合格者数(2024年度) | 国内:3,181人 総合:1,320人 |
| 合格率(2024年度) | 国内:31.4% 総合:28.2% |
旅行業務取扱管理者の資格は、旅行商品を取り扱う旅行代理店などには設置義務がある資格です。主に国内旅行業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者に分けられ、国内は国内旅行を扱い、総合は海外旅行も含めてすべての旅行を取り扱えるようになります。
旅行業務取扱管理者をおすすめするポイントはなんといっても設置義務です。旅行代理店には必ずこの資格を持った方を設置する必要があり、そのため旅行代理店では新入社員などに資格の取得を義務付けているケースもあります。
旅行業界への就職を目指している中卒の方は、就職活動前にこの資格を取得してしまいましょう。採用側としても、採用してから資格を取らせるより、すでに資格を持っている方の方が採用しやすいのは間違いありません。
この資格を取得するために身に着ける知識は、設置義務のある旅行代理店はもちろんですが、旅行に関するすべての業界で活用できる知識です。なんとなくでも旅行関係の職を探している中卒の方には特におすすめしたい資格となります。
インテリアコーディネーター

| 正式名称 | インテリアコーディネーター |
|---|---|
| 資格種類 | 民間資格 |
| 受験者数(2022年度) | 8,943人 |
| 合格者数(2022年度) | 2,193人 |
| 合格率(2022年度) | 24.5% |
部屋やオフィスの内装やインテリアに関して、顧客の希望を聞きその希望を実現できるように提案することを業務とするインテリアコーディネーター。その能力やスキルを証明するのがインテリアコーディネーター資格です。
インテリアコーディネーターに必要なのは豊富な商品知識や建造物に関する知識、そして自分のセンスということになります。どれも学校の勉強では習わないことばかりですので、中卒の方が活躍しやすい職種とも言えるでしょう。
学歴がまったく必要ない職場ということでもあり、そこで活躍するには資格の有無が重要になります。
インテリアコーディネーターの仕事自体は、資格がなくてもできる仕事ではありますが、資格がある方が顧客から信頼されやすいというメリットがあります。仕事柄顧客とのコミュニケーションが重要になる仕事になりますので、顧客から信頼されるのは重要。
そのためにも資格取得がおすすめとなります。
資格取得を目指す中卒者へのQ&A
資格を取得するかどうか悩んでいる中卒の方が、疑問に持つであろう部分を、Q&A方式で答えていきたいと思います。
Q.高卒認定資格の取得は必要?
高卒認定資格の取得は原則不要
高校卒業程度の学力を証明する資格として知られる高卒認定資格。中卒の方の中には、資格取得前にまずは高卒認定を取得すべきではと考えている方もいらっしゃるかと思います。
しかしこの記事の最初に説明した通り、実務能力と中卒や大卒といった学歴は無関係です。高卒認定は仕事をするための資格ではなく、あくまでも大学を受験するための資格。仕事には関係ない資格といえます。
高卒認定を取得するために勉強時間を使うのであれば、その時間をより有用な資格取得に充てる方がよほど効率的といえるでしょう。
もちろん資格取得と並行して、将来的に大学受験を考えている中卒の方は、高卒認定を目指すのがおすすめとなります。
学歴がなくても稼げる仕事のおすすめは?中卒女性や資格無しでも転職するコツは?|Up Survive
Q.資格取得と実務経験はどちらが重要?
重要なのは実務経験
実務経験と資格を比較すれば、やはり実務経験の方が重要視される傾向にあります。資格はないけど実務経験がある方と、実務経験はないけど資格はあるという方が採用試験に来たら、高確率で実務経験のある方が採用されるでしょう。
とはいえ、資格の取得に意味がないということではありません。実務経験が積めるかどうかは、その実務に就けるかどうかが重要。その実務に就くためには、特に中卒の方は資格がある方が有利になります。
もうひとつ仮の話になりますが。両者ともに実務経験がない場合、資格を持たない方よりも、資格を持っている方の方が優先されるのも事実です。
資格を取得して実務につく、その実務経験を活かしてよりよい条件を目指すというのが中卒の方にとって理想のキャリアアップ法。自分が進みたい道を見定めて、その道で活躍できる資格をしっかり取得するのがおすすめです。
Q.資格を取得すれば就職できる?
必ず就職できるわけではありません
就職や転職のために資格取得をおすすめしていますが、資格を取得すれば必ず就職できるかと聞かれればそんなことはありません。これは中卒だからということではなく、学歴とは無関係で、必ず就職できるなどと言うことはありません。
ただし、資格を取得することで就職しやすくなるというのも事実ですし、資格があることで申し込める仕事が増えるのも事実です。資格の取得が無駄になることはまずありませんのでご安心ください。
資格を取得せず、限られた求人からある程度の職に就くよりも、しっかり資格を取得してから、自分が望む仕事に就く方がより働きがいがあるのは間違いないでしょう。また、資格を取得することで、将来の仕事の仕方が変わることもあります。
資格を取得する場合は、将来を見据えて取得するのがおすすめとなります。
参考:マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本|ゆいてろぐ
まとめ
実際社会に出て働き始めてしまえば、中卒も大卒も関係ありません。重要なのは学歴ではなくどれだけ仕事ができるかですので、中卒であることを気にする必要はありません。
ただし、社会に出るタイミングでは、どうしても学歴を見られてしまう部分はあります。採用担当者としても、実務経験がない新人を比較するには、どうしても履歴書にある文字が頼りになってしまうからです。
そこでおすすめしたいのが資格の取得。採用担当者としても現実的には学歴よりも仕事ができるかどうかを知りたいところ。そう考えると資格の有無は大きなポイントとなります。
資格を取得することで、中卒の方でも希望する職種や業種への就職や転職が叶う可能性が高くなります。その職に就いてしまえばあとは実務で存在感を見せればいいだけ。ここは学歴とは無関係です。
中卒の方こそ資格で自身が持つスキルや知識をしっかりアピールし、自分が希望する道を進めるようにしましょう。