行政書士による成年後見業務とは?
更新日:2019年11月26日

「成年後見制度」とは、2000年にスタートした制度で、成人しているものの、知的能力や精神的判断能力が不十分であり、自力で法律行為等を行うことができない人のために、第三者が法律行為等を代理して行うといった法制度のことです。
成年後見制度を必要とする方は、知的障害者や精神障害者、認知症のお年寄りが挙げられます。
これらの成年後見を必要とする方々を成年被後見人、代理する人のことを成年後見人といいます。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」があり、前者は、現在は判断能力が十分であるものの、将来判断能力が不十分となったときに備えて準備するもので、後者はすでに判断能力が不十分な方々を支援するものです。
行政書士による成年後見業務とは?
行政書士が行う成年後見業務の具体例としては主に以下のようなものが挙げられます。
- 成年後見制度を利用するにあたっての必要書類の収集
- 任意後見契約書作成の相談にのること
- 成年後見人に就任すること
行政書士は、成年後見を考えている依頼者の方の相談にのることはもちろん、自身が、成年後見人になることも可能です。
成年後見人となった場合の仕事の具体例
次に、行政書士を含め、成年後見人となった場合の具体的な仕事について紹介します。
後見人となった場合にする仕事としては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 収入と支出の管理
- 不動産や預貯金等の財産管理
- 金融機関との取引き
- 相続に関する手続き
- 保険契約の締結、変更、解除および保険金の受領
- 通帳、印鑑、各種カード等の保管
- 住居に関する契約の締結および費用の支払い
- 医療契約の締結および費用の支払い
- 介護契約その他福祉サービスの契約締結および費用の支払い
- 施設の契約の締結および費用の支払い
成年後見人の申立て手続きの流れについて
ところで、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
たとえ親族であっても、被後見人の判断能力が低下しているからといって、何ら手続きすることなく、当然に後見人となれるわけではありません。
必要書類の準備
まずは必要書類を準備します。具体的な書類については以下のとおりです。
ここで必要な書類の収集や作成に関して前述のとおり行政書士は依頼者に対してアドバイスをすることができます。
- 成年後見申立書
- 後見人等候補者身上書
- 親族関係図
- 本人の財産目録
- 本人の収支予定表
- 診断書
- 本人の戸籍謄本
- 本人および後見人等候補者の住民票又は戸籍附票
- 本人について成年後見等の登記がなされていないことの証明書
- 本人の健康状態がわかる資料
- 不動産や預貯金、株式、生命保険、負債、収入や支出等の財産関係資料
家庭裁判所へ申立書の提出
申立書ができたら、必要書類を添付し、本人の住民票上の居住地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市町村長、検察官です。
申立て費用は約1万円です。
多くの家庭裁判所が事前予約制であるため、電話等で日時を予約しておきましょう。
また、提出時に申立人および後見人等候補者との面接も行われます。
面接の所要時間は約1~2時間です。
家庭裁判所による鑑定・調査
家庭裁判所の審理が進み、成年後見人の選任が必要であると判断された場合、「後見開始の審判」がなされて、審判書が申立人や成年後見人、本人へ郵送で届きます。
申立ての際に、後見人候補者として親族を指定したとしても、必ずしもそのとおりに選任されるというわけではないため、注意が必要です。
後見登記の完了
家庭裁判所より審判があると、法務局にて登記がされます。
選任された成年後見人が財産管理を始める際、金融機関での手続き等で必要になるため、原本を取得しておいた方が良いでしょう。
行政書士が成年後見人となった場合に期待できること
行政書士が成年後見人となった場合には、街の身近な法律家であり、権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家として、被後見人の心に寄り添い、細かい部分まで対応していくことができるとともに、成年後見業務に付随した遺言書の作成等相続業務にも対応していくことで、被後見人の生活のトータルサポートをしていくことができます。
少子高齢社会を迎えている日本において専門的な知識を持った行政書士が後見人として選任される需要はますます高まり、様々な事情を抱える依頼者の力になることができるのではないでしょうか。
また、知的障害者や精神障害者、認知症高齢者等社会的弱者を保護する成年後見制度へ積極的に携わることで、福祉国家社会に貢献していくことができます。
行政書士の成年後見業務の報酬の相場は?
成年後見業務の報酬については、任意後見契約書の作成を始めとする各種書類の作成は約5万円程度が相場だと言われています。
成年後見人に就任した場合には、個々の事案により家庭裁判所が審判で決定します。
基本報酬と付加報酬というものがあり、基本報酬は約5万円程度が相場であると言われています。
付加報酬は、特別な財産管理行為を行った場合、例えば有料老人ホームと入居契約を行ったり、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加したりした場合に、基本報酬に上乗せをして家庭裁判所に報酬付与の申立てを行います。
複雑な遺産分割協議等の場合には、100万円以上の報酬になることもあるようです。
行政書士の成年後見制度に関する研修もある!
最近では、成年後見制度を支援する団体が多く存在しており、その中には行政書士の方々によって構成されている団体もあります。
「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」は、2010年に日本行政書士会連合会により行政書士を正会員として設立された団体です。
ここでは、入会者を対象に成年後見制度に関する研修や業務に関する相談等を行っています。
また、会員の指導や監督を徹底しており、会員が成年後見業務を積極的にかつスムーズに行えるようサポートしています。
まとめ
成年後見制度は、社会的弱者を保護する制度として大切な制度です。
行政書士は、成年後見制度に関する相談にのり、アドバイスを行うとともに、成年後見人として被後見人の生活のサポートをすることもできます。
責任は非常に重い業務ではありますが、近年、専門職後見人を養成する支援団体も増えており、行政書士においては文中でも紹介したとおり、「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」というところがあります。
随時研修等を行っているため、安心して受任することができるでしょう。
平成25年の司法統計では、後見、補佐、補助の申立ては4万件を超えており、年々増加傾向にあります。
そのことからもわかるように、これからさらに成年後見業務の需要は増えていくと思われます。
行政書士の成年後見業務は、重要な業務のひとつです。
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















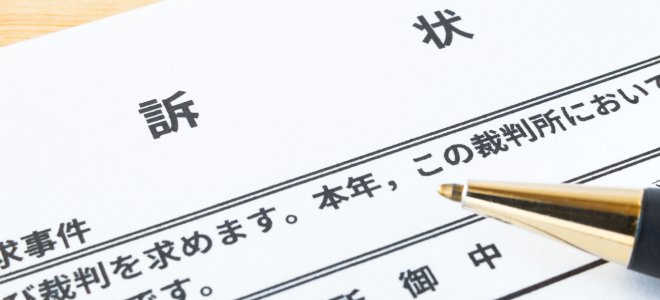


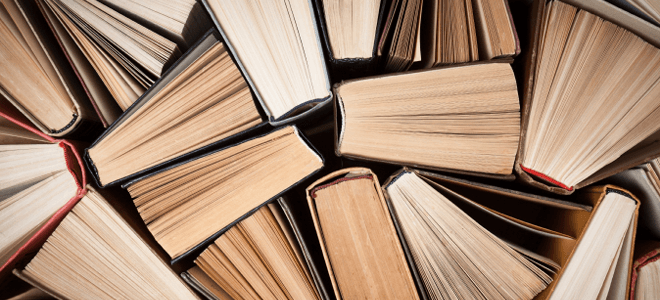



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


