行政書士試験「民法」のおすすめの勉強法!
更新日:2019年3月19日
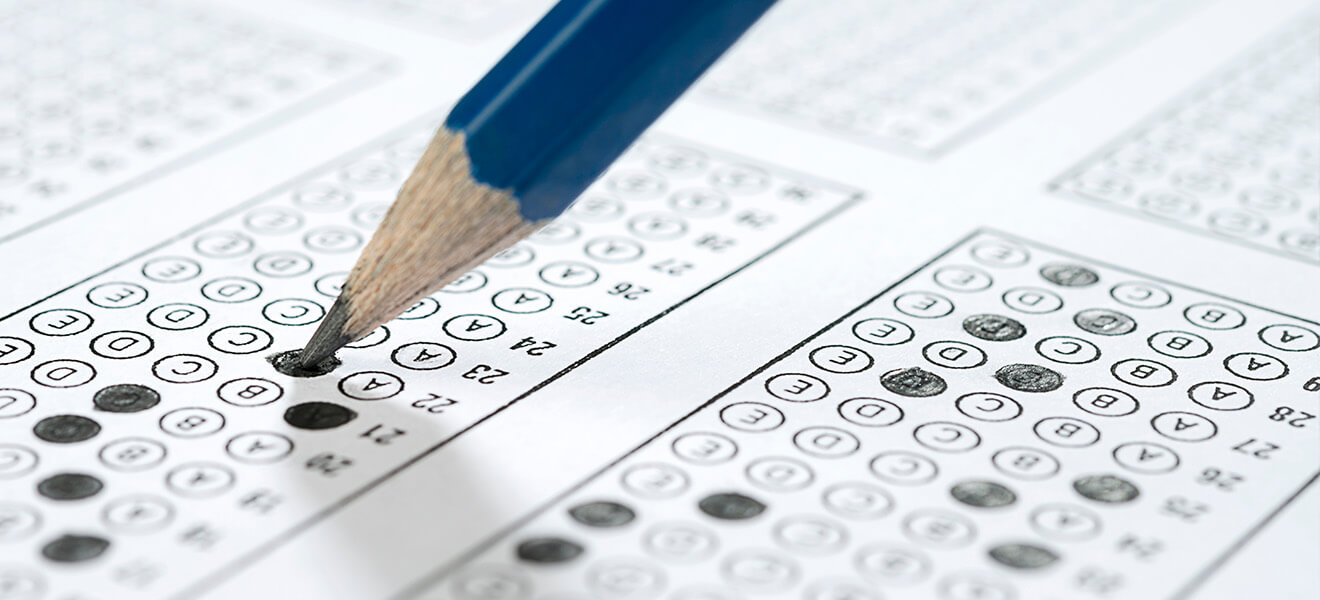
- 民法はしっかりと条文を理解し、問題文の事例に当てはめができるようになるように意識することが大切です。
- 記述で点を取るコツは、もし答えがわからなくてもとにかくキーワードを繋いで「何か書く」ということです。
- 長文の問題文は、関係図を書いてから答えを考えるようにするのがコツです。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
民法の勉強方法
民法は、行政書士の試験科目の中でも難しい科目です。条文が細かく、初めて法律系資格の勉強をする人にとっては複雑に感じるでしょう。しかし、条文が細かいということは、それだけ解釈が入る余地が小さいということでもあります。そのため、憲法に比べると民法の勉強は判例ではなく条文の理解と当てはめが中心になります。
まずはしっかりと条文を理解すること、それから問題文の事例に当てはめができるようになること。その2点を意識して勉強を進めましょう。
民法とは、どんな科目?
問題演習が重要
民法の出題数……5肢択一:9問、記述式:2問
配点………………76点
重要度……………☆☆☆☆
難易度……………☆☆☆☆
民法は、私人(しじん)間の権利義務を調整する法律です。憲法が法律や行政、司法を縛る規律であるのと比べると、非常に細かい規定まで置かれています。そのため、憲法から民法へと勉強を進めていくと、急に難しくなったように感じると思います。
しかし、私人(しじん)間の権利義務を調整する法律だということを念頭に置いて勉強すれば、納得できる部分も多いでしょう。
自分の生活に当てはめて考えてみると身近に感じられると思います。
「何のための法律か」
「なぜこの法律が必要か」
という点は、どの科目を勉強するときにも必要な視点ですが、民法は特にそこを意識して勉強すると良いでしょう。
民法の問題
過去問で出題傾向をつかむ
“共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。”
※平成29年度 民法の問題本文より
これは平成29年度の民法の問題本文です。
このように、民法の問題は本文で状況設定がされ、そこに条文を当てはめて考えさせる問題が多いです。
そのため、問題文の状況設定を理解できていないと肢も判断できません。問題文を読んで、ある程度どのような条文知識が必要かを判断し、それから肢の判断という流れになります。
民法の効果的な勉強方法

国語力と問題演習が大事
前述の通り、民法は私人(しじん)間の権利義務を調整する法律なので、問題文の登場人物が重要です。誰が誰に対して権利行使をするのか、または誰と誰がどのような関係で登場するのか。その点を把握しておかなければ、肢の判断を間違えてしまうことがあります。
最近の問題の傾向では問題文も肢も3~4行の長文問題が多いので、それをしっかり読み解く国語力が大事です。苦手意識がある人は、登場人物とその関係を図にしながら問題を解いていくと分かりやすいと思います。
次に、条文を問題文の状況に当てはめて正解の肢を選ばなくてはならないため、条文そのものの理解も必要です。条文をただ暗記しただけでは理解したとは言えないので、問題演習を通じて「そういうことなのか」という気づきを積み重ねていきましょう。
条文の理解
条文の理解とは、その条文がどんな権利義務を調整しているかがわかる、ということです。条文そのものの意味がわかる、ということでもあります。
例えば、“代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。(民法99条)”は、代理人がした行為が本人に効力を及ぼすことを定めています。
例えば、Aさんの代理人Bさんが、Aさんのために買い物をしたら、Aさんはその支払いをする義務を負います。
代理とは、「他人の行為によって、自分に何か影響がある」ということになります。
これが、条文の理解です。
条文の当てはめ
前述の代理について、条文を問題文に当てはめてみましょう。
- Bさんは甲会社でAさんの代理人として契約を結んだ
- BさんはAさんに無断でAさん名義の銀行口座からお金をおろした
- BさんはAさんの代理人であることを隠して、Cさんと契約を結んだ
など、各肢に条文を当てはめます。条文には、「その権限内において」「本人のためにすることを示して」とあるので、各肢の状況はそれらに当てはまるかどうかを判断していきます。
これが条文のあてはめです。条文そのものの意味内容を聞いてくるのではなく、肢に条文を当てはめて考えさせるので、難易度は低くありません。
行政書士民法を実際に解いてみよう
判断のポイントをつかむ
“共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。”
※平成29年度 民法の問題本文より
という問題本文のポイントは、
- 連帯保証債務
- 弁済期間は1年
- 負担部分は2分の1ずつ
です。
肢の1について、実際に解いてみましょう。
【肢1】
“本件貸金債務につき、融資を受けるに際してAが要素の錯誤に陥っており、錯誤に基づく無効を主張してこれが認められた場合であっても、これによってBが債務を免れることはない。”※平成29年度 民法の問題本文より
これは連帯債務の相対効を聞いているのである、ということがわかれば簡単な問題ですが、連帯保証債務だということを問題本文で押さえていないと間違えてしまいます。
つまり、連帯保証債務に関する条文を適用するということがわかって、さらに相対効が原則の場面なのか、例外の場面なのかを肢に当てはめて判断する必要があります。
行政書士民法の記述式対策

考え方を整理整頓する
記述式とは、40字程度で解答を記述する問題です。全部で3問出題され、そのうち2問が民法からの出題です。配点は2問で40点にもなります。
記述で点を取るコツは、もし答えがわからなくてもとにかくキーワードを繋いで「何か書く」ということです。公表はされていませんが、記述には部分点があるので何か書いておけば部分点が取れる可能性が高いです。
次に、民法の記述については問題文に登場する人物等の関係性を図解して、整理整頓してから答えを考えることです。
考えながら、書きながら、とするのではなく、いったん考えを整理してから解答をまとめる作業にかかるのがコツです。
長文の問題文攻略法
民法の問題は、長文であることが多いです。読解力が無いと、読んでいるうちに登場人物の関係性が分からなくなったり、前提条件を見落としたりします。
そうならないためにも、図を書きながら整理整頓して考えましょう。
特に、登場人物が3者以上になった場合は図解して整理整頓しておかなければ、何度も問題文を読み直す羽目になります。時間がもったいないですし、解答を作る方に頭が使えません。
- 誰が
- 誰に
- いつ
- なにを
- どのように
ということを意識して、関係図を書いてから答えを考えるようにするのがコツです。
40字にまとめるテクニック
記述は、勉強が足りない人は字が余り、よく勉強している人は足りなくなる傾向があります。いずれにしても、まずは「聞かれていることだけに答える」ことを意識しましょう。
例えば、「Aはどのような法律に基づいてどのような主張をするべきか」という問題に対し、問われていることに最低限で答えると、
『Aは、( )という法律に基づいて、( )と主張すべきである。』
と、いうようになります。
ここに例外の場合分けも加えるかどうかは余った字数によりますが、例外まで考えて場合分けをすると大抵文字数が足りなくなります。
文字数が足りないほど書ける人は良く勉強している人なので、つい書き足したくなると思いますが、40字前後に収まらないときは、「聞かれていること以外にも答えていないか?」と自問してみましょう。
まとめ
民法は、行政書士実務にも直結する法律なので、難しいながらも勉強する楽しさがあると思います。
何を意識して勉強するかによっても、勉強の効果は変わってきます。このページでお伝えしたことを意識しながら、民法の勉強を進めてもらいたいと思います。
行政書士最短合格なら通信講座がベスト
行政書士試験という難関を最短で乗り越えるためには、通信講座がおすすめです!通信講座を推奨する理由を以下にまとめます。
➀通信講座なら自分のペースで効率的な学習ができる
時間や場所を選ばず、空き時間を学習に充てることができます。これは通勤や通学の途中、または家事の合間や仕事の昼休みなど、日常のスキマ時間にも柔軟に勉強時間に変えることが可能です。忙しくても、自分の生活リズムに合わせて自由に学習を進められます。
②費用を抑えられる
通学講座の場合、授業料に加え、通学するための交通費もかかります。一方、通信講座なら受講料も比較的リーズナブルで、交通費もかかりません。
③学習サポートが充実
独学で市販の教材を使って勉強する際には、自分で疑問点を解決しなければなりません。しかし、通信講座では質問対応をはじめとする充実した学習サポートが受けられます。不明な点を放置せず、安心して学習を進めることが可能です。
1分で完了!
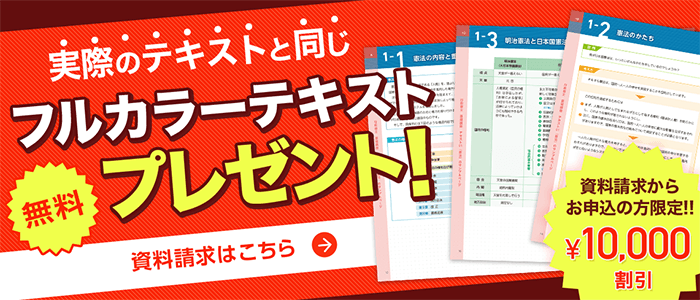
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















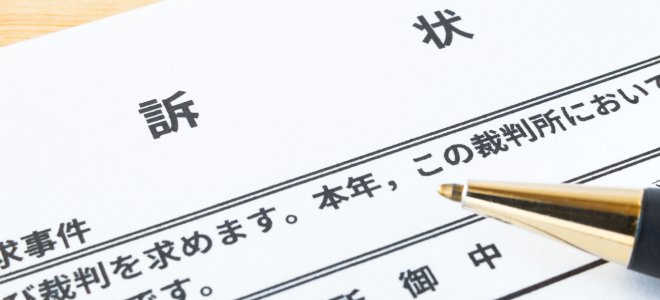


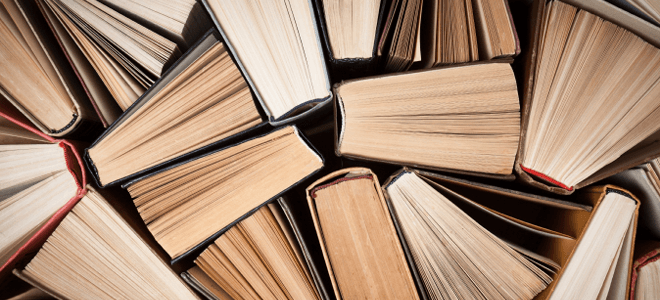



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


