行政書士と風営法の関係とは?風俗営業許可申請業務ってどんなもの?
更新日:2019年12月20日

行政書士の主な業務に、許認可申請に関する書類の作成や代理があります。
この許認可申請には、例えば飲食店の営業許可申請や建設許可申請などがありますが、他にも風俗営業許可申請というのもあります。
風俗営業許可申請には風営法に基づく細かいルールがあり、許認可申請のプロフェッショナルである行政書士に依頼する方が増えています。
行政書士と風営法の関係とは?
では、行政書士が取り扱う風営法に関する業務とはどのようなものでしょうか。行政書士と風営法の関係についてみていきます。
風営法とは?
「風営法」という法律があるのはご存知でしょうか。
あまり聞きなれない法律かと思いますが、「風営法」とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。
昭和23年7月10日に制定され、これまで30回以上の改正を繰り返しています。
風俗営業に関する営業が少年の健全な育成に悪影響を及ぼさないようにするためのルールを規定し、公安委員会が指導監督を行うということを目的としており、その目的のために営業区域や営業時間、年少者の営業所への立ち入り規制等の制限を設けています。
「風俗営業」とは、具体的にキャバクラ、スナック、パチンコ店、ゲームセンター、ラブホテルやアダルトショップの他、深夜に酒類を提供するバーや居酒屋のことも言います。
風営法第2条では、次の6種類のお店を営業する場合に、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で風俗営業の許可を受けなければならないことが規定されています。
1号営業
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
例:クラブ、キャバクラ等
特定遊興飲食店営業
客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
例:ナイトクラブ、ディスコ等
2号営業
客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの
例:喫茶店、バー等
3号営業
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
例:喫茶店、バー等
4号営業
客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
例:麻雀店、パチンコ店等
5号営業
スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業
例:ゲームセンター、ダーツバー等
行政書士が取り扱う風俗営業許可申請業務とは?
風俗営業に許可が必要ということはおわかりになったかと思いますが、では、具体的に行政書士が取り扱う風俗営業許可申請業務とはどのようなものでしょうか。
まず、許可申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権限を疎明する書類
- 営業所の平面図
- 営業所の半径100mの周囲の略図
- 住民票の写し
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 身分証明書
- 法務局の証明書
- 業務を誠実に行う旨の誓約書
また、法人許可申請の場合には、
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票の写し
- 役員に係る身分証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の誓約書
等も必要になります。
個人、法人ともに、このような必要書類の収集や作成をするにあたって、行政書士は主に次のような業務を行うことができます。
①現地調査
申請場所から半径100m以内にある建物の調査をして、申請場所で許可が取得できるか否かを判断します。
↓
②店舗の測量
店舗の形状や構造、防音設備の状況を確認することや、店舗の寸法を測量して、平面図や面積計算表、証明・音響設備図面等を作成します。
↓
③各種書類取得
住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書等を代理して取得します。
↓
④申請書類の作成
依頼者の方からの情報をもとに法令に照らし、風俗営業許可申請書等を作成します。
↓
⑤申請同行
風俗営業許可申請時に、同行することができます。
書類不備があった場合には、その場で訂正も可能です。
また、申請時に公安委員会の担当者と面接がありますが、想定される質問についてアドバイスをします。
申請から1~2週間で許可か不許可の結果が出ます。
↓
⑥検査立会い
申請書が受理された後、風俗浄化協会によって申請図面のとおりの構造や設備であるかの確認等、店舗の調査がありますが、その検査に立ち会うことができます。
風俗浄化協会からの質問にも依頼者に代わって答えることができます。
行政書士による風俗営業許可申請業務の注意点は?
風俗営業許可申請手続きにおいては、
①人的基準
②場所的基準
③営業時間に関する基準
④建設設備等に関する基準
を満たさなければ許可がもらえないため、注意が必要です。
①人的基準
風営法4条第1項により、風俗営業許可を受けようとする方が以下のいずれかに該当するときには、営業許可を受けることができないとされています。
(1)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2)1年以上の懲役もしくは禁錮の刑(無許可風俗営業など一定の罪については1年未満の懲役もしくは罰金の刑)に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
(4)アルコール、麻薬、大麻、あへん、または覚せい剤の中毒者
(5)風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(取消しを受けた会社の役員であった者や、取消しの前に脱法的に廃業した者等を含む。)
(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
②場所的基準
風俗営業許可が出る地域というのは限られているという点には特に注意が必要です。
営業可能な場所は基本的には繁華街であり、住居地域、住居専用地域であったり、一定の距離内に保護対象施設があったりする場合には申請却下されてしまうため、事前の調査は必須だと思います。
また、都道府県によっても異なる細かなルールがありますので、ホームページや電話等で確認しておくことも大切です。
保護対象施設は、主に以下のとおりです。
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等)
- 図書館
- 児童福祉施設
- 病院(歯科医院を含む医療施設で病床が20以上であるもの)
- 診療所(歯科医院を含む医療施設で病床が19以下であるもの)
また、保護対象施設の有無というのは、審査の時点で判断されるため、許可申請の時点で保護対象施設が存在していなかったとしても、審査の時点で保護対象施設が存在していれば、不許可になる場合があります。
さらに、保護対象施設には、「将来保護対象施設が設置される予定のある土地」というのも含まれます。
そのため、審査の時点で保護対象施設が存在していなくても、将来保護対象施設が設置されることが決定されていると、不許可となる場合があるため、注意が必要です。
③営業時間に関する基準
風俗営業については、風営法第13条第1項により営業時間は午前0時を超えてはいけないとされています。
ただし、都道府県の条例により、午前1時まで営業できる地域も定められているため、しっかりと確認することが必要です。
また、2016年の改正により、条例でさらに営業時間を延長できることが認められており、申請場所の地域の情報を抑えておくことが大切です。
④建物設備等の基準
風俗営業許可申請においては、営業する店舗の建物設備等の基準も細かく定められています。
(1)客室が2室以上ある場合は、1室の面積が16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)であること
(2)店舗の外側から客室が見えないようになっていること
(3)客室内に見通しを妨げる物(仕切り、つい立て、カーテン等)がないこと
(4)善良の風俗を害するおそれのある写真、ポスター、装飾等がないこと
(5)客室出入口(店舗自体の出入口は除く。)に施錠の設備がないこと
(6)店内の照度が5ルクスを超えていること
(7)ダンスのための構造や設備がないこと
(8)騒音の数値が、55デシベル未満であること
風俗営業許可申請業務はどのくらい稼げる?専門行政書士も多い?
風俗営業許可申請業務の費用の相場は、どのくらいでしょうか。1号~5号営業のいずれの許可申請をするかによっても変わりますが、およそ1件30万円前後と言われています。
風俗浄化協会による検査の立ち会いや質疑応答代理には、別途費用を加算している行政書士事務所も多く、1件でも高い報酬が見込めるため、風俗営業許可申請業務を専門とすると、かなり稼ぐことができる業務であると言えます。
夜のお店の営業に関する業務ということで、細かいルールも多く、手続きも大変であり、素人ではなかなか難しいため、許認可申請の作成・代理の専門家である行政書士の需要は増えてくるかと思います。
また、風俗営業許可申請手続き後、店舗の構造や設備を変更する場合には、公安委員会に届け出て変更承認を受けなければならないため、その際の手続きの代理やアドバイス、変更届出に必要な書類の作成等も行うことができます。
依頼者の方がリピーターとなれば、継続的に依頼が来る可能性もある業務です。そのため、数名の顧客を抱えることで、コンスタントに収入を得ることができるのではないかと思います。
風営法改正について
2016年6月23日に風営法が改正されました。ここでは、主な改正点について紹介していきます。
①客にダンスさせる営業に関して規制の範囲や内容の見直し
改正前は、「ダンス教室」や「ダンスホール」も風営法の規制対象となっていましたが、改正後は、飲食を伴わず、客にダンスをさせる営業に関しては規制から除外となりました。この部分が今回の改正で一番大きなポイントだったようです。
②「特定遊興飲食店営業」を新たな許可業種として分類
客席の照明が10ルクス以下であれば風俗営業ですが、10ルクスを超える場合には、深夜営業と酒類提供の両方を行っている場合には「特定遊興飲食店営業」として風営法の対象となり、深夜営業か酒類提供のいずれか一方だけであれば「飲食店営業」として、風営法とは別の法律で管理されることになりました。
③良好な風俗環境を保全するための規制整備
風俗営業または特定遊興飲食店営業を営む者の義務として「店舗周辺における客の迷惑行為の防止措置」と「苦情処理に関する帳簿の備付け」が規定されました。
また、警察署長や特定遊興飲食店営業等の営業所の管理者、地域住民等により構成される風俗環境保全協議会が設置されました。
④風俗営業時間の緩和
改正前は、営業時間が最長午前1時でしたが、改正後は、条例により営業時間を延長することが可能になりました。
また、クラブ営業のうち、店内の照明が明るく、酒類を提供しなければ「飲食店」とみなされて24時間営業が可能となります。
⑤ゲームセンターへの18歳未満の立入制限についての見直し
改正前は、18歳未満の22時以降の滞在や、16歳未満は保護者が同伴していても18時以降の入店は禁止されていましたが、改正後は、16歳未満は保護者が同伴していれば22時までの滞在が可能となりました。
まとめ
行政書士と風営法の関係についてご理解いただけましたでしょうか、風俗営業許可申請業務においては、手続きが複雑で店舗の計測や図面作成など、技術も必要になります。
図面作成は手書きも可能ですが、最近ではパソコンを使って作成する行政書士の方も多いようですので、そういったパソコンによる図面作成の知識を習得することも大切になってきます。
細かい作業が好きな方や、パソコンが得意で、パソコン知識を活かしたいと思っている方には、特に、この風俗営業許可申請業務を専門とする行政書士がおススメかと思います。
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















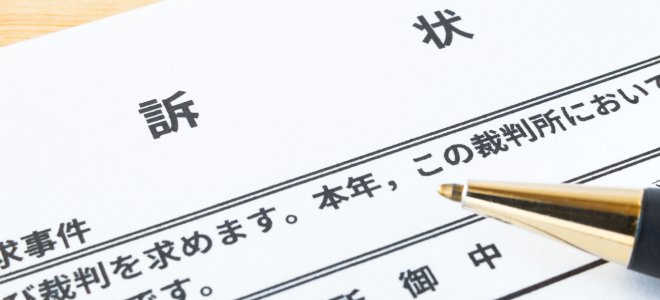


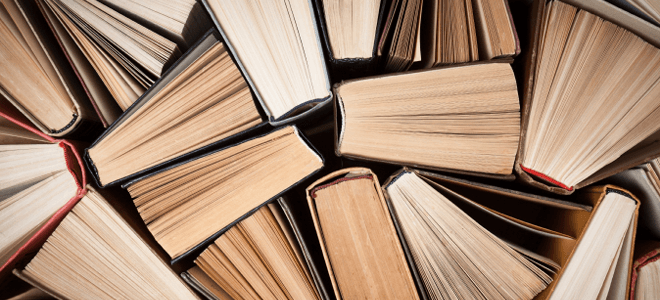



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


