行政書士試験における「おすすめテキスト」の選び方と使い方!
更新日:2019年3月18日

資格試験に合格するためには、テキスト選びが重要になります。
テキストは、自分自身で使いやすいようにカスタマイズすることで、最強の勉強ツールになります。最終的に目指すのは、全ての情報を集約した1冊としてのテキストです。それさえあれば、ノートも参考書も不要、というくらいにテキストに全てを集約させます。
得意不得意は人によって差があるため、テキストもその人に合わせて使いやすい形に変えていきましょう。また、テキストを綺麗に使うのではなく、どんどん書き込み、付箋を付け、自分だけの1冊を仕上げてください。
- テキストは長期間使い続けるため、「なんとなく」や、価格で選ばない。
- テキスト選びのポイントは、コンパクトであること、2色刷りであること、最新版であることの3つ。
- テキストは綺麗に使わず、書き込みをする。抵抗がある場合は付箋などを活用する。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
おすすめテキストの3つのポイント

「なんとなく」で選ばない!
テキストは、一度選んだら半年~1年以上は使い続けるものです。そのため、「なんとなく」や、価格で選んではいけません。
途中で「このテキスト使いにくいかも」と気付き、新しくテキストを探して変えるのにも時間がかかってしまうので、最初から使いやすいテキストを慎重に選びましょう。
選び方のポイントは、
- コンパクトであること
- 2色刷りであること
- 最新版であること
上記3つです。
後は個人の好みに合わせて選びましょう。例えば、移動時間が多い人なら持ち歩きを考慮し薄いテキストを、さらに科目ごとに分かれているものが使いやすいでしょう。
主に自宅で勉強される人なら、分厚い総合版のテキストの方が、1冊で管理がしやすくなります。このように、自分の勉強環境や生活に合わせて考えることも必要です。
1.コンパクトであること
テキストを選ぶ上での1つ目のポイントは、コンパクトであることです。具体的には余計なことを極力排除してある内容のテキストを指します。
よく、行政書士試験の対策に司法書士試験のテキストや、司法試験の短答のテキストを使用するという人がいますが、(特に民法にその傾向がみられています)そういう人に限って1度で合格出来ていないように見受けられます。
なぜなら、行政書士試験で出る部分に絞った勉強ができていないからです。大まかに勉強し、その中で何かは出るだろうというような臨み方ではなく、合格のために「出るところだけ勉強する・繰り返す」ということが資格勉強では大切です。
また、「出るところだけ勉強する」ことをサポートしてくれるのは、コンパクトなテキストです。分厚いテキストと比べると厚みの違いに不安を感じるかもしれませんが、内容を絞りこんで繰り返し勉強する方が、合格に近付くことができます。
2.二色刷りであること
2つ目のポイントが、2色刷り以上であることです。2色刷りとは、重要部分を赤字で示し、かつマーキングされているようなテキストのことを指します。
学校の教科書は黒一色で、自分で赤線を引き蛍光ペンでマーカーすることで、重要単語を目立たせることをしてきました。テキストももちろんそのようなカスタマイズはしていくものの、黒一色は無意識に難しく感じ、勉強がストレスになってしまうこともありますので、避けましょう。
また、テキストで望ましいのはフルカラーですが、印刷費がかさむことからなかなか見かけません。フルカラーの場合、黒一色に比べて脳に印象として残りやすく、あとで思い出すときに色がヒントになることもあります。
3.最新版であること
3つ目のポイントは、最新版であることです。これはおすすめポイントというよりは、必須のポイントです。
なぜ、最新版でなければならないのかというと、行政書士試験の科目は法改正が多くみられます。法改正により、同じ問題でもそれまでと答えが真逆になることもあります。そのため、古いテキストを使用していたら気づかずに間違えてしまう恐れがあります。
また、法改正部分は本試験で出題されることが多く、受験生にとっては押さえておきたいポイントです。古いテキストでは、対応しきれずチャンスを逃してしまうこともあります。したがって、安いからという理由で、古いテキストを購入するのではなく、テキストは常に最新のものを選ぶようにして下さい。
合格に近付くテキストの使い方

綺麗なテキストはいらない
テキストを使用して勉強をする際、書き込みをするのが苦手という方は意外と多いのではないでしょうか。勉強を始めてすぐの段階でした書き込みは、後から読み返すと必要がないように思えてしまうこともあります。
しかし、書き込みをしていくことでテキストに情報が集約され、最も使い勝手の良い参考書になります。そのため、綺麗なテキストにこだわらず、どんどん書き込みしていくことをおすすめします。
どうしてもと尻込みしてしまう人は、鉛筆で書き込めば後から消すこともできます。また、消せるボールペンであれば色が豊富なので、自分なりにルールを作って書き込みをすることもできます。
もしくは、付せんを使用するという方法もあります。付せんは目立つため、大きめの付箋に書き込んだ上でテキストに貼り、理解出来たら剥がすという方法もあります。どのような方法であれ「情報をテキストに集約させる」ということを意識して実行してみてください。
書き込みが重要
自分だけのテキストを作成していく上で重要なことは書き込むことです。その時々の気付き、疑問を書き込むことによってそれらと向き合うことができます。
あとで考えようと思ってそのまま忘れてしまったりすることも多いので、小さな疑問はメモ帳やノートに書いておきましょう。そこから、より重要な疑問や解決した内容をテキストに転記しておきます。
自分の書き込みがあることで、テキストが印象に残りやすくなるという効果もあります。中身を整理するために、疑問点は青、重要事項は赤、キーワードは緑というように自分でルールを決めた色で書き込みしていくと、使いやすい参考書としても役立つようになります。
1冊にまとめる
最終的な目標は、「試験会場に持ち込むのはテキスト1冊だけ」という状態にすることです。勉強の初期には、科目ごとのノートを作ることは効率的ですが、それらを持っていったとしても、試験前の限られた時間の中ですべてを確認する時間はありません。
テキスト1冊にまとめておけば、自分の書き込みだけでなくテキストの内容も合わせて確認できます。仕上げ段階の勉強でも、この1冊と過去問があれば勉強できるので、非常にシンプルです。
前述の通り、自分のメモとテキストの内容を一度にまとめて確認できるので、効率良く勉強できるでしょう。そのため、限られた勉強時間の中でいかに効率良く勉強できるかを頭に入れ、まとめていくことが重要です。
過去問とテキストをクロスさせて使う
<行政書士試験過去問の攻略法>のページでも記述しましたが、過去問とテキストを使って力を付けることができる勉強方法があります。その方法とは、解説を読む前にテキストの該当箇所を自分で探し、正解かどうかを判断するというものです。
肢ごとに行えば、1問解くのにも相当な時間がかかります。しかしながら、自分で根拠を探しながら答え合わせをすることで、正解にたどり着くプロセスを思考することができます。
また、テキストを読んで、過去問の答えがすぐ理解できる場合もあれば、解釈が必要なこともあります。解説を読むと理解したような気になり、考えることをやめてしまうこともあります。そのため、自分で苦労して探し出し、しっかりと記憶に残し、それをもとに考えるという方法も身につけましょう。
なお、この作業をするときに、ヒントとなるのが書き込みです。過去問から気づいたことも新たに書き込んでいきましょう。そのように過去問とテキストは常にペアで使うことをおすすめします。
フォーサイトの行政書士通信講座の特徴
高合格率が魅力のフォーサイト提供の行政書士通信講座について、その特色を解説します。
➀4ヶ月での合格例も!
通常、行政書士試験の合格には12ヶ月の準備が一般的ですが、フォーサイトの講座では4ヶ月での合格者も出ています。フォーサイトは合格に必要なポイントに絞った教材作成により、短期合格を現実のものにしています。
合格できなかった場合でも心配無用です!受講料は全額戻ってきます。
②満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト
試験に必要な情報量、重要情報のカラー分け、理解を深めるイラストが豊富に含まれており、それが高い合格率につながっています!
③講師歴20年以上の実力派講師陣!
フォーサイトの行政書士講座は、福澤繁樹講師・五十嵐康光講師・北川えり子講師、の3名が担当しています。
経験豊かな専任講師が、カリキュラムに合わせた講義や教材の執筆を行っています。
④通信講座でありながら、ライブ配信の授業が受けられる「eライブスタディ」
周期的に実施されるライブ配信講義のことです。
一般的に通信講座は独学が基本ですが、このシステムを利用することで、授業のペースを保ちやすくなり、学習進度の遅れを防ぐことができます。
行政書士通信講座を体感するなら資料請求しよう!
通信講座に手を出したことがない方や、一度挑戦して挫折した経験のある方々にとって、もう一度通信講座に挑戦することは大きな不安につながるかもしれません。
その不安を解消する第一歩として、無料の資料請求から始めてみるのが良いでしょう。
資料請求をすることで、次のような体験が可能になります。
➀サンプルテキストや問題集を閲覧することで、実際の教材の内容を直接確かめることができます。
これにより、教材がどの程度理解しやすく、勉強に適しているかを自分自身で体感することが可能です。
②無料でeラーニングを試してみることができます。
この機会を利用して、スマートフォン一台があれば、時間や場所を選ばずに学習できる便利さを実感してみてください。
③行政書士試験に最短で合格するためのノウハウ書がブレゼントされます。
1分で完了!
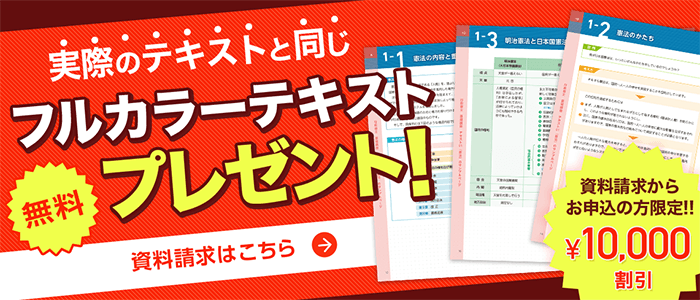
まとめ
テキストは読むだけではなく、カスタマイズして使い倒すことが重要です。単に綺麗なまま使用するのではなく、字が汚くても、他人に読めなくても構わないので、自分だけにわかるオリジナルテキストにしていきましょう。
また、最初からメモの余白が多めのテキストを選ぶのも良いと思います。長い付き合いになるテキストだからこそ、最強のツールに仕上げていくことが大切なのです。
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















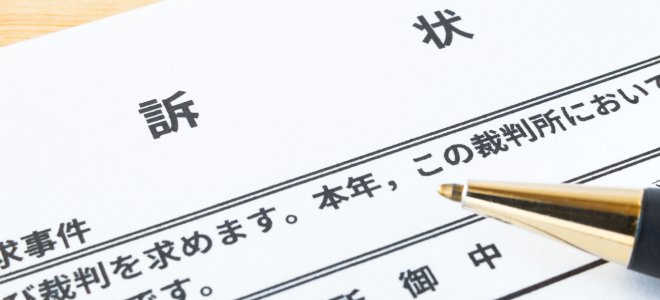


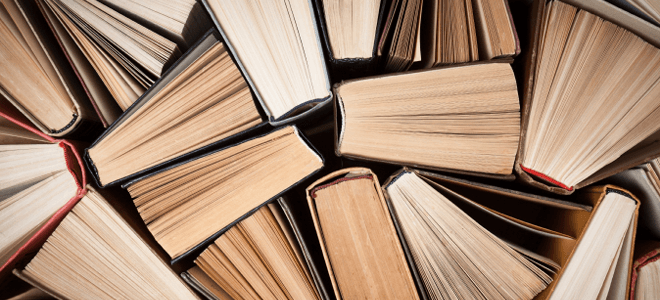



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


