取消訴訟における事情判決の法理とは?
更新日:2021年7月6日

- 「事情判決」とは、行政庁の処分や裁決は違法であるものの、これを取り消すと公共の利益に著しい損害が生じるおそれがある場合に、様々な事情を考慮した上で、裁判所が請求棄却判決を出すことができるというものです。
- 事情判決は、行政訴訟においては、違法な処分を前提として新たに確立された法律関係を尊重すべき場合があることから存在していると考えられています。
- 行政不服審査法にも「事情裁決」という名前で、事情判決と類似する制度が存在しています。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
事情判決とは
「事情判決」とは、行政庁の処分や裁決は違法であるものの、これを取り消すと公共の利益に著しい損害が生じるおそれがある場合に、様々な事情を考慮した上で、裁判所が請求棄却判決を出すことができるというものです。
つまり、原告の主張に理由があって、本来は請求認容判決を出すべきところ、認容判決を出すと公共の利益に大きな影響を及ぼす場合には、請求棄却判決を出すということです。
ただし、事情判決を出す場合には、判決の主文で、行政庁の処分又は裁決が違法であることを宣言しなければなりません。
また、訴訟費用は、弁護士費用を除いて、被告である行政庁が負担します。
事情判決の条文は、行政事件訴訟法第31条にあります。
そして、事情判決は、行政事件訴訟のうち、取消訴訟、民衆訴訟、機関訴訟で認められています。
事情判決があった場合、原告側は、当然上訴可能ですが、被告側も、判決の既判力により、処分が違法であると宣言された部分を訂正しなければ後の訴訟に影響が出る場合があるということから上訴が可能と考えられています。
【行政事件訴訟法】
(特別の事情による請求の棄却)
第31条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。2項 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
事情判決の存在理由
事情判決は、行政訴訟においては、違法な処分を前提として新たに確立された法律関係を尊重すべき場合があることから存在していると考えられています。
日本では、三審制を採用していることもあり、裁判期間が長期に渡る場合があります。
取消訴訟には、たとえ違法な処分であっても権限ある機関によって適法に取り消されるまでは有効として扱われる「公定力」があるため、取消訴訟が長期に渡る場合、処分取消しの確定判決が出される間に、その違法な処分を前提として他の行為が行われたり、大規模な公共事業が完成したり、利害関係人が増えて原状回復が困難となったりする可能性もあります。
そうなると、違法な処分を取り消すことよりも新たに確立された法律関係を尊重しなければ余計に社会が混乱してしまうと考えられます。
そのような取消訴訟の性質から、事情判決が存在しています。
事情判決について、学説には、①肯定説、②否定説、③制限適用説があり、通説は③制限適用説です。
事情判決の類似制度
行政不服審査法にも「事情裁決」という名前で、事情判決と類似する制度が存在しています。
事情裁決とは、違法又は不当な処分を取り消すことによって、公共の利益を害すると考えられる場合、審査庁は、審査請求又は再審査請求を棄却することができるというものです。
この場合、裁決の主文で処分が違法又は不当であることを宣言しなければなりません。
唯一異なる点としては、事情裁決においては、不当な処分も対象となるというところです。
【行政不服審査法】
第45条3項 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
事情判決の法理とは?
「事情判決の法理」とは、次に紹介する「議員定数不均衡違憲訴訟」の判例において使われた表現です。
公職選挙法では、第219条において、行政事件訴訟法第31条の事情判決を準用しないことが規定されているため、選挙訴訟で事情判決を出すことはできません。
ただ、公職選挙法における一票の格差に関する選挙訴訟を違憲とすると、全ての選挙区において選挙が無効となることになり、公共の利益に多大な損害を及ぼす可能性があるため、事情判決の法理により選挙は違憲であるものの、選挙そのものは無効とはならないとされています。
【公職選挙法】
第219条 この章(第二百十条第一項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法・・・第三十一条の規定は、準用せず、・・・
事情判決の法理に関する判例「議員定数不均衡違憲訴訟」(最大判昭和51年4月14日)
|
【事案】 昭和47年12月に行われた衆議院議員選挙で、千葉県の選挙人Xが、衆議院議員選挙当時、各選挙区の議員1人あたりの有権者数の最大値と最小値に4.99対1という格差があり、この格差は、平等選挙で制度上許容される範囲をはるかに超えるものであるから、選挙区別の議員定数を定めた公職選挙法の各規定は、憲法第14条1項の法の下の平等に違反して無効であるという理由で、選挙の無効判決を求めました。 |
|
【争点】 ①4.99対1の格差を生じ、約8年間是正がなされなかった議員定数配分規定は憲法に違反するか? ②違憲の場合には、定数配分規定全体が違憲となるか? ③違憲の場合には、選挙も無効となるか? |
【理由および結論】 ①選挙制度の具体的決定は国会の裁量に委ねられているものの、人口数と定数との比例の平等は最も重要かつ基本的な基準である。 そして、投票価値の不平等が、国会で考慮する諸般の要素を斟酌しても、一般的に合理性を持つとは到底考えられない程度に達しており、かつ、人口の変動の状態を考慮して合理的期間内に是正が行われない場合には、違憲となる。 これをあてはめると、約5対1の程度に達した投票価値の不平等は、一般的に合理性を持つとは考えられない程度に達しており、かつ、昭和39年の改正後本件選挙まで、約8年間に渡り改正がなされなかったといえるため、議員定数配分規定は違憲である。 ②選挙区割および議員定数の配分は、相互に有機的に関連し、一体不可分と考えられるため、違憲の部分のみならず、選挙全体が違法とされる。 ③本件選挙を違憲無効とすると、明らかに憲法の所期しない結果を生ずる。 そして、高次の法的見地に立つとき、行政事件訴訟法第31条1項の事情判決の条項から、一般的な基本原則を読み取ることができるため、本件は事情判決の法理に照らして違法ではあるものの、選挙は無効とはならない。 |
まとめ
「事情判決」とは、行政庁の処分や裁決は違法であるものの、これを取り消すと公共の利益に著しい損害が生じるおそれがある場合に、様々な事情を考慮した上で、裁判所が請求棄却判決を出すことができるというものです。
事情判決では、主文に処分や裁決が違法である旨を宣言しなければならず、原告側、被告側ともに上訴が可能と考えられています。
行政不服審査法にも「事情裁決」という同様の制度が存在します。
通説では、事情判決を制限的に適用すべきと考えられています(制限適用説)。
選挙訴訟においては、公職選挙法により事情判決そのものを行うことはできないものの、判例において、一票の格差に関する違憲訴訟に関しては、「事情判決の法理」によって、選挙自体は無効としないという判断がなされました。
行政書士最短合格なら通信講座がベスト
難関である行政書士試験に、最短で合格するためにベストの学習法は、ズバリ、通信講座です!
その理由は、下記のとおりです。
➀忙しくても、自分に合ったスピードで学べる
通信講座は、場所や時間に限定されず、いつでもどこでも勉強可能です。移動中だけでなく、家事の合間や仕事の休憩時間にも学習を進めることができます。どんなに忙しくても、自身の生活パターンに合わせて勉強を続けられます。
②経済的にお得です。
通学講座には、授業料とは別に交通費が加わりますが、通信講座では受講料が割安に設定されており、交通費も不要です。
③学習に対するサポートが充実しています。
市販のテキストで自習する際には、疑問点を自分で調べる必要がありますが、通信講座では質問対応や学習アドバイスなど、豊富なサポートが用意されています。そうした支援のおかげで、分からない点を残さずにしっかりと学習を進めることができます。
フォーサイトの行政書士通信講座の特徴
ここでは、高合格率で知られるフォーサイトの行政書士通信講座の主な特徴をご紹介します。
①たった4か月で合格!!
行政書士試験の合格までには、一般的に12か月程度の学習期間が必要と言われています。しかしフォーサイトの行政書士講座なら、4か月で合格されている方もいます。満点主義ではなく、合格点主義で教材を制作しているフォーサイトだから、短期合格が可能なのです。
②不合格だったら、受講料全額返金!!
万一、不合格でも安心!!受講料が全額返金されます。
③満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト
試験に必要な情報量、重要情報のカラー分け、理解を深めるイラストが豊富に含まれており、それが高い合格率につながっています!
④講師経験20年以上のベテラン講師陣
福澤繁樹先生、五十嵐康光先生、北川えり子先生が指導を担当しているフォーサイトの行政書士講座では、彼らの豊富な経験と専門知識を活かし、カリキュラムに基づいた授業と教材の作成が行われています。
⑤通信講座なのにライブ配信講義! eライブスタディ
「eライブスタディ」とは、定期的に行われるライブ配信講義です。通学講座と異なり、通信講座は自分ひとりだけで学習を進めるので、学習のペースが遅れがちになります。eライブスタディに参加すれば、定期的に講義があるので、きちんと学習のペースを守ることができます。
1分で完了!
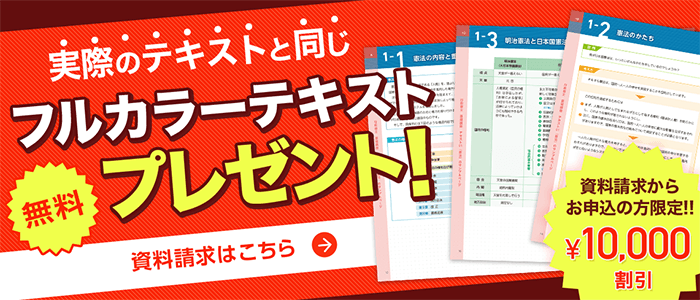
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















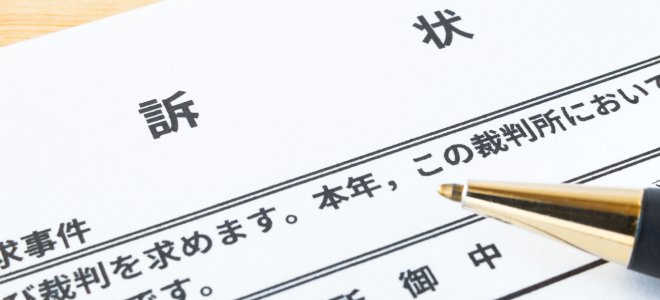


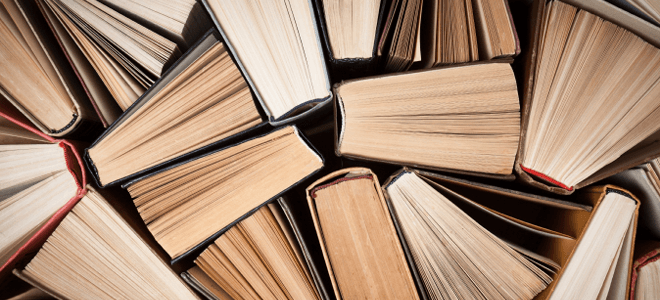



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


