行政書士会への登録費用とは?
更新日:2019年3月6日

入会だけで約30万円!
行政書士になるには、必ず行政書士会に登録しなければなりません。
そして、登録には費用がかかります。
費用はだいたい30万円程度かかり、費用の支払は一括のみで分割払いはできません。
入会にかかる費用は、登録料、入会金、月会費の前払い、バッジなどの代金です。
それぞれについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
- 登録手数料と入会金を合わせて登録料と呼ばれます。
- どの単位会に属するかは、どこに事務所を置くかによって決まります。
- 金額は単位会によって異なりますが、行政書士として出来る仕事に変わりはありません。
- 行政書士会に登録されるには、登録料などを支払ったうえで審査を受ける必要があります。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
行政書士会の登録料
登録料が安い県、高い県がある
登録手数料と入会金を合わせて登録料と呼ばれます。
都道府県の行政書士会(単位会と言います)に支払う費用で、単位会によって金額が異なります。
以下は、東京都行政書士会の例です。
| 登録手数料 | 25,000円 |
|---|---|
| 入会金 | 225,000円 |
登録料は事前に指定口座に振り込みします。一括払いです。
なお、どの単位会に属するかは、どこに事務所を置くかによって決まります。東京都内に事務所があれば、自宅は神奈川県でも東京都行政書士会に所属する事になります。
入会金
入会金は、単位会によって異なります。
東京都行政書士会の場合、200,000円です。
東京都が最も高額になりそうな気がしますが、実は神奈川県行政書士会の方が高額で250,000円となっています。
神奈川県のほか、大阪府なども250,000円です。
逆に、安いところだと山形県は100,000円です。
このように、金額は単位会によって異なるのですが、行政書士として出来る仕事に変わりはありません。また、東京都で登録しているために、他府県の仕事をすることができない、ということもありません。
その他
登録・入会料のほかにも費用がかかります。
- 登録免許税 30,000円
- 月会費前払い分(3カ月) 21,000円(東京都行政書士会の場合)※月会費は毎月7,000円で、以降3カ月ごとにまとめて払います。
- バッジ3,000円~ (メッキ製だと3,000円くらい、純銀製だと1万円くらい)
- 名刺 4,000円くらい
- 領収書、事件簿など帳票類 数百円
- 職印(行政書士の印鑑) 5,000円くらい~
このように細かい費用が積みかさなって、最終的に合計30万円ほどになります。
日業連の登録・入会手続きについて

入会手続き完了までは1カ月ほどかかる
行政書士会に登録されるには、登録料などを支払ったうえで審査を受ける必要があります。
この審査には、だいだい1カ月前後かかります。
登録手続きの流れは次の通りです。
- 書類提出・書類精査
- 現地調査(事務所の調査)※現地調査が無いこともある
- 単位会で1、2が終わった後、日本行政書士連合会(日業連)で審査
- 登録完了
欠格事由と言って、行政書士になれない理由が無いかなどを調査されます。「現地調査」というものがありますが、これは事務所の調査です。事務所としての実態があるかを現地に来て確認されます。現地調査の代わりに事務所の写真を提出する事もあります。
いずれにしても、事務所の実態がないと登録されません。
書類提出は予約制で、1日に数名しか受付されません。そのため、合格発表後は予約が殺到しがちです。
予約、審査に時間がかかることを考えた開業スケジュールにしないと、仕事ができないまま2、3カ月も事務所家賃を払い続けることになるので注意が必要です。
必要な書類
登録・入会手続きにはかなりの量の書類を用意しなければなりません。
中には今まで聞いたこともないような書類もあります。
主な提出書類(試験合格のケース)
- 合格証書原本
- 戸籍抄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 事務所の使用権限を証する書面(賃貸借契約書など)
- 事務所の写真、他
戸籍や住民票はなじみがあると思いますが、「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」は、どんなものか知らない人も多いでしょう。
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人にでないことを証明する書類で、法務局の本局で取得します。
身分証明書は、破産者でないことを証明する書類で、本籍地の市区町村役場で取得します。
書類の不足や間違いがあると審査が長引くので、事前に確認してしっかりと用意する必要があります。
事務所について

自宅を事務所にすることもできる
行政書士登録をするには、必ず事務所が必要です。事務所は、自宅と兼用でもかまいませんが、応接スペースと事務スペースが確保されていることが必要です。
また、長期にわたって使用できることが求められるので、賃貸借契約の期間が1年未満だと事務所として認められません。
シェアオフィスなどでは、ある程度独立した応接スペースと事務スペースが無いと事務所にできないので、注意が必要です。
自宅兼事務所にする場合は、賃貸人に許可をもらう必要があります。(賃貸の場合)
表札や郵便受けに行政書士事務所の表示をする必要があります。
事務所の表示が無いと、行政書士会からの郵便物が届かない事があります。
なお、広さや場所に制限はありません。
毎月の会費について

入会金だけでなく、毎月の会費もある
所属する単位会には、月会費を払います。月会費の金額は単位会ごとに異なります。東京都行政書士会は月7,000円(行政書士会6,000円、政治連盟1,000円)です。3カ月ごとにまとめて21,000円を引き落としか振込みで支払います。
支払の時期になると、単位会から通知が来ます。振込みで支払っている事務所には納付書が届きます。行政書士でいる限り、月会費は払い続けなければなりません。仮に、行政書士を廃業するときは、きちんと廃業の手続きをしないといつまでも会費を払い続けなくてはならなくなります。
会費を払わないとどうなる?
毎月の会費を支払うのは義務なのですが、中には払わない人もいます。また、手続きをせずに廃業して、それ以降の会費を払わなくなる人もいます。会費を払わないと、どんなペナルティがあるのでしょうか。
まずは納付するよう再三の通知が行われますが、それでも納付しない場合は、会員の資格の停止、廃業勧告と進んで行きます。
会員の資格の停止
会員の資格とは、研修などに参加できる資格のことです。この資格が停止されても行政書士として仕事をすることは可能です。
廃業の勧告
行政書士をやめなさい、という指示です。5年以上など長期滞納者に対してこの勧告がされます。滞納している会費を全額納付すれば、勧告が解除されます。
他に、会費滞納者への取り立てを行う委員会もあります。払わなくても何とかなるものではありません。
「支部会費(年会費)」とは?

都道府県より小さな単位が「支部」
行政書士は、その全員が日本行政書士連合会に所属しています。その上で、単位会といって、各都道府県の行政書士会にも所属します。さらに、「支部」という小さな単位の行政書士会にも所属します。
つまり、全部で3つの組織に所属する事になります。自分の事務所がある地域の支部に、強制的に所属させられます。自分で支部を選んだり、断ったりすることはできません。
その支部に支払うのが支部会費です。だいたい年間1万円前後ですが、支部によって金額は異なります。
支部とは?
支部とは、小さな単位の行政書士会のことです。例えば、東京都には33の支部があります。23区にはそれぞれ区ごとの支部があり、市レベルになると会員数が少ない市はいくつか集まって一つの支部を作っています。
自分の事務所がある地域の支部に所属する事になります。東京都行政書士会に比べて、支部はより地域密着の活動を行います。例えば、区役所などでの無料相談会です。また、支部会員に向けた研修会なども行ないます。新入会員にとっては、身近な所に相談できる場所や先輩ができて心強いでしょう。
行政と連携した仕事は、個人では働きかけが難しいですが、支部としてまとまることによって話が通りやすくなることもあります。
支部会費は支部ごとに年会費が異なる
支部会費は、支部ごとに金額が決められます。高い支部と安い支部だと、倍くらいの開きもあります。6,000円~10,000円(年会費)くらいが主流です。人数の多い支部だとその分事務手数料などもかかるので、支部会費が高くなる傾向があります。また、研修や福利厚生などに積極的な支部も、会費が高くなります。
行政書士会に払う月会費とは別に払うものですが、支部会費は年会費なのでそれほど負担は重くありません。
支部会費を払わないと、研修に参加できない、支部から仕事の紹介を受けられないなどのペナルティが発生することもあります。
融資を利用する
手軽に利用できる創業融資
ここまで、登録から月会費までの費用をまとめてきました。意外とまとまった額の費用がかかります。そこで、融資を利用することも検討してみましょう。
創業(開業)時に利用しやすいのが、日本政策金融公庫の創業融資です。まだ何の実績が無くても融資を受けることが可能です。金利も2%台~と低く、返済期間も最大5年まで伸ばせるので利用しやすい融資です。
融資の事業計画書作成は行政書士業務でもあります。一度自分の事として経験しておいて損はありません。融資については、担当者と相談しながら書類を作ったり検討したりできるので、返しきれないほどの借金を抱えることはないでしょう。安心して相談してみてほしいと思います。
ただし、まったく貯蓄が無いのは融資の審査に置いてマイナスなので、登録を考え始めたらコツコツ貯蓄を始めましょう。
行政書士最短合格なら通信講座がベスト
難易度が高い行政書士試験を手早くクリアするためには、通信講座を利用するのが最適です。この選択が一番良いと言われる理由があります。
➀通信講座なら自己のペースで効率的に学習できる
時間や場所を選ばず、利用可能な瞬間を学習に充てることができます。これは通勤や通学の途中、または家事や昼休みなど、日常の隙間時間にも柔軟に勉強できることを意味します。忙しくても、生活リズムに合わせて自由に学習を進められます。
②経済的にお得です。
対面式の講座には、授業料とは別に交通費が加わりますが、通信講座では受講料が割安に設定されており、移動のための費用も不要です。
③サポート体制が充実している
市販のテキストを購入し独学で勉強するとき、疑問点を自力で調べなければいけません。これに対して、通信講座なら、質問対応など、学習中のサポート体制が充実しています。不明点をそのまま放置することなく、安心して勉強に取り組むことができます。
フォーサイトの行政書士通信講座の特徴
ここで、高い合格率を誇るフォーサイトの行政書士通信講座の特徴を述べてみます。
➀わずか4ヶ月での合格実績あり!
通常、行政書士試験の合格には約12ヶ月の準備期間が見込まれますが、フォーサイトのコースを受講すれば、4ヶ月で合格することが可能です。この短期間での成功は、フォーサイトが合格点を目指した教材作りに注力しているからこそ実現できます。
②不合格だったら、受講料全額返金!!
万一、不合格でも安心!!受講料が全額返金されます。
③満足度驚異の90%以上 こだわりのフルカラーテキスト!
フォーサイトのフルカラーテキストは、試験に出るだけのボリューム・重要度毎の配色・理解を助ける豊富なイラストで、高い合格率を実現しています!
④講師歴20年以上の実力派講師陣!
フォーサイトの行政書士講座は、福澤繁樹講師・五十嵐康光講師・北川えり子講師、の3名が担当しています。経験豊かな専任講師が、カリキュラムに合わせた講義や教材の執筆を行っています。
⑤通信講座でありながら、ライブ配信の授業が受けられる「eライブスタディ」
周期的に実施されるライブ配信講義のことです。一般的に通信講座は独学が基本ですが、このシステムを利用することで、授業のペースを保ちやすくなり、学習進度の遅れを防ぐことができます。
行政書士通信講座を体感するなら資料請求しよう!
もし通信講座が初めて、または以前挑戦したけれど挫折したという方がいれば、新しく通信講座を始めるのに不安を感じることでしょう。そのような不安を少しでも和らげるため、まず資料請求をしてみることをお勧めします。資料請求は無料で行えます。
資料請求をすることで、次のような体験が可能になります。
➀サンプルテキストや問題集に目を通すことで、実際に使われている教材を手に取り、どれほどわかりやすく、学習しやすいかを実感できます。
②無料でeラーニングを体験できます。
これにより、スマホさえあれば、いつでも、どこでも学習できることが体験できます。
③行政書士試験を最短でクリアするためのコツをまとめたノウハウ本が、プレゼントとしてもらえます。
1分で完了!
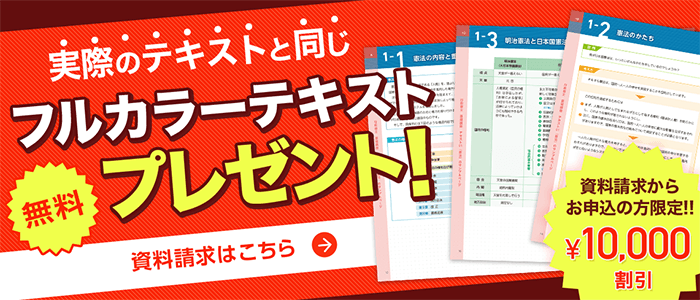
まとめ
行政書士になるには、意外とお金がかかることがお分かりいただけたかと思います。融資も利用できるので、事業計画と合わせて検討してみるのが良いでしょう。行政書士になると、この先にも融資を受ける機会があります。
会社員だと、お金を借りる機会がほとんどないと思いますが、事業主と借金は切っても切れないものなので、適正な範囲で利用していきましょう。
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ

















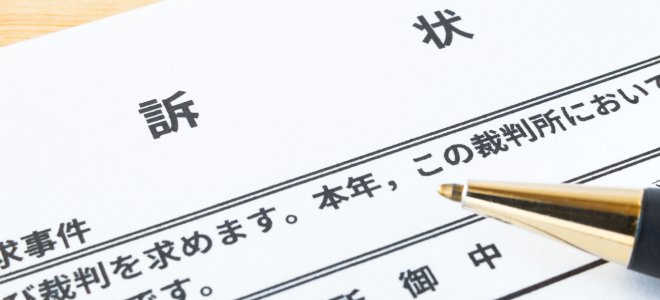


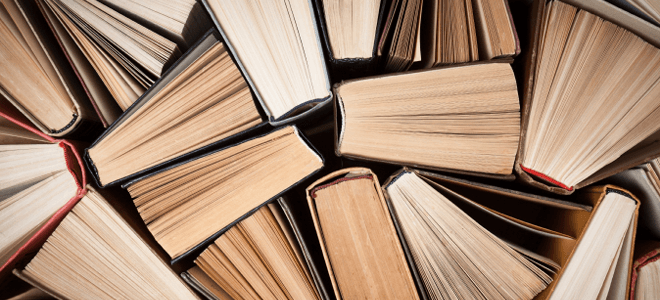



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


