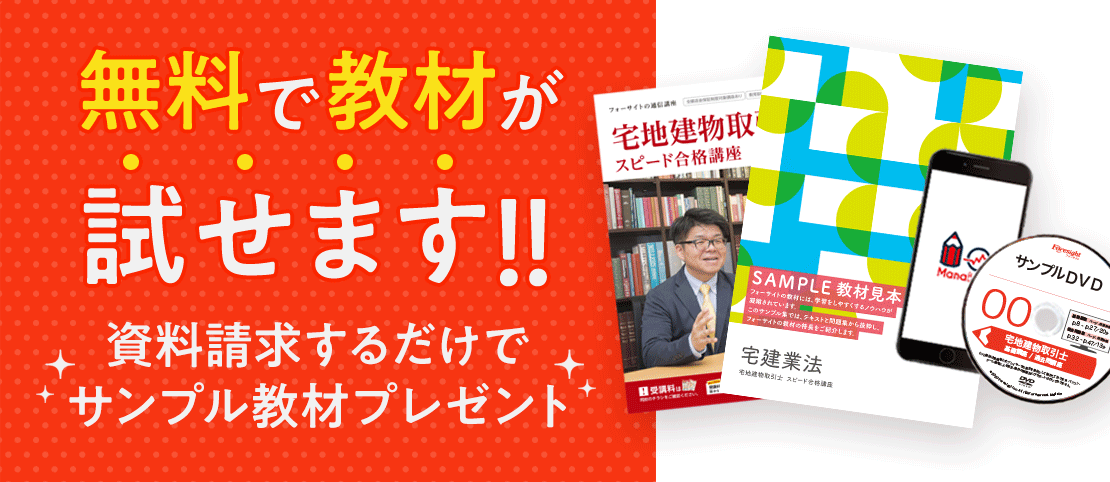資格を取得するにはいろいろなきっかけがあるかと思います。就職や転職はもちろん、現状の社内での自身の評価アップや、資格手当を目指すというのも理由でしょう。
これから資格取得を目指す場合、重要になるのが「いつ取れるのか?」という点。つまり、どの程度勉強時間を確保すれば取得できるのかを知ることです。
そこでこの記事では、人気の資格、注目の資格24個の取得に必要となる勉強時間をランキング形式で紹介。
さらに各資格の特徴や、受験勉強のポイントを紹介していきたいと思います。
【人気24資格】資格取得に必要な勉強時間ランキング
資格試験の難易度を表す数値にはいろいろなものがあります。その資格試験の合格率から推測する方法もありますし、その合格率から偏差値として表記する方法もあります。
しかしこれらの表現方法では、実際にどのくらい難しいのか想像がしにくいというのも事実。そこでこの記事では、シンプルに「どのくらい勉強すれば合格できるのか?」という勉強時間に着目して難易度を紹介していきたいと思います。
もちろん勉強時間には個人差があります。極端な例を出せば、すでに弁護士の資格を持っている方と、法律知識がほぼないという方が、同じ資格試験に挑む場合、同じ勉強時間ということはほぼありません。
ここで紹介する勉強時間は、その資格の勉強に関する知識がほぼない方が、独学で挑んだ場合に必要な勉強時間の目安というもの。あくまでも参考資料としてご活用いただければと思います。
まずは何より人気の資格・注目の資格24個の合格に必要な勉強時間をランキング形式で紹介していきましょう。
| Rank | 資格 | 勉強時間 |
|---|---|---|
| 1 | 司法書士 | 約3,000時間 |
| 2 | 中小企業診断士 | 約1,000~1,400時間 |
| 3 | 行政書士 | 約1,000時間 |
| 4 | 社会保険労務士 | 約800~1,000時間 |
| 5 | マンション管理士 | 約600時間 |
| 6 | 裁判所事務官(一般職・大卒程度) | 約500~1,000時間 |
| 7 | 公務員採用試験(一般職・教養試験) | 約500時間 |
| 8 | 管理業務主任者 | 約500時間 |
| 9 | 通関士 | 約400~500時間 |
| 10 | 診療報酬請求事務能力認定 | 約400~500時間 |
| 11 | 総合旅行業務取扱管理者 | 約400時間 |
| 12 | 宅地建物取引士 | 約300~500時間 |
| 13 | インテリアコーディネーター | 約300~350時間 |
| 14 | 保育士 | 300時間+α |
| 15 | ファイナンシャル・プランニング技能士2級 | 約300時間 |
| 16 | 日商簿記2級 | 約250~350時間 |
| 17 | 国内旅行業務取扱管理者 | 約250時間 |
| 18 | 基本情報技術者(情報処理技術者試験) | 約150~200時間 |
| 19 | 日商簿記3級 | 約120~150時間 |
| 20 | ITパスポート(情報処理技術者試験) | 約100時間 |
| 21 | 証券外務員一種 | 約80~100時間 |
| 22 | 証券外務員二種 | 約50~80時間 |
| 23 | 危険物取扱者【乙種4類】 | 約40~60時間 |
| 24 | 年金アドバイザー3級 | 約30時間 |
こちらが各資格取得に必要な勉強時間のおおよその目安です。
では、これらの勉強時間を確保するのに、どの程度の勉強期間が必要かを考えていきましょう。
勉強時間の目安
資格取得を目指す方が、毎日の生活の中でどの程度勉強時間を確保できるかを簡単に計算していきたいと思います。
ここでは一般的な社会人の方(平日出勤・土日祝日休み)、さらに一人暮らしの方の1日の生活スケジュールを想定していきます。
★1日の生活スケジュール
・7:00 起床
・8:00 出勤
・18:00 終業
・19:00 帰宅
・24:00 就寝
通勤時間は片道1時間。平均して1日1時間程度の残業を想定します。
この生活リズムを崩さず勉強時間を確保するとなると、帰宅してから就寝するまでの5時間が対象となるでしょう。とはいえこの5時間がそのまま勉強時間というわけではありません。
この5時間で夕食を摂り、洗濯や簡単な掃除、入浴などの時間も確保しなければいけません。そう考えると1日に確保できる勉強時間はMAXでも3時間。無理なく計算するのであれば2時間といったところでしょう。
ここまでは平日の勉強時間です。土日祝日など仕事が休みの日はさらに勉強時間の確保が可能です。とはいえ、一人暮らしであることを考えれば、週末にまとめて洗濯をする、掃除をする、買い物に出かけるという時間も必要です。これらの事情も鑑みると、休みの日は5時間勉強時間が確保できれば上出来ではないでしょうか。
非常に単純な計算ですが、この計算で行けば1週間で確保できる勉強時間は20時間が無理のない線でしょう。
このペースで勉強した場合、1ヶ月、1年で確保できる勉強時間も併せて計算してみましょう。
| 1週間 | 20時間 |
| 1ヶ月 | 90時間 |
| 1年間 | 1,135時間 |
1ヶ月は20日出勤、10日休日で計算、1年間は230日出勤、135日休日で計算しました。1年間の休日数の内訳は、土日=104日、祝日16日、有給休暇10日、お盆+年末年始の休暇=5日の計算です。
この数字だけを見ると、ほとんどの資格は1年間の勉強で取得できると思われるかもしれませんが、これは最大で確保できる勉強時間。残業時間も考慮していませんし、冠婚葬祭や家族との時間、友人や恋人と過ごす時間に趣味の時間も一切加味していません。
1年間誰とも遊ばず、残業も一切断り、趣味の時間もまったく取らないというのはまず難しいところでしょう。上で紹介した勉強時間を基準に、ほかにどの程度時間を割くかは個々のライフスタイルに合わせて考えるといいでしょう。
あくまでも個人的な印象ですが、上記の勉強時間の7割達成できれば、かなり勉強時間を確保しているという感覚かと思います。
ここでは一人暮らしの社会人としての勉強時間を計算しましたが、専業主婦の方、実家暮らしの方、ご家族のいらっしゃる方、子育て中の方も、まずは自分の毎日の生活に必要な時間を書き出し、そのうえで1日何時間勉強時間が確保できるかを計算してみましょう。
その計算ができれば、資格取得までに必要な勉強期間もおのずと計算できるでしょう。
ちなみに資格取得の勉強は、できるだけ毎日行うのがポイント。1日2時間勉強し、翌日は勉強しないというスケジュールよりも、1日1時間45分勉強し、翌日15分だけでも勉強時間を確保するのであれば、巧者の方が勉強効率は圧倒的に高くなります。
上手にスキマ時間を見つけて勉強スケジュールを立てましょう。
人気24資格の概要と勉強時間
各資格の取得に必要な勉強時間が、自分にとってどのくらいの期間勉強する必要があるかをイメージできたかと思います。
ここからは上で紹介した人気の資格・注目の資格の概要や試験内容、そのような方におすすめかなど、それぞれの資格を簡単に紹介していきたいと思います。
何か資格が欲しいけど、度の資格を目指すのが良いか分からないという方や、自分が目指そうと思っている資格の詳細を知りたいという方は、気になる資格の内容をチェックしてみましょう。
また、上記の24の資格の中で、同じ種類の資格や、似た系統の資格に関しては、まとめて紹介していきますので、その中で違いを知り、自分が目指すべき資格を見定めましょう。
資格取得に必要な勉強時間が短い順に紹介していきます。
年金アドバイザー3級
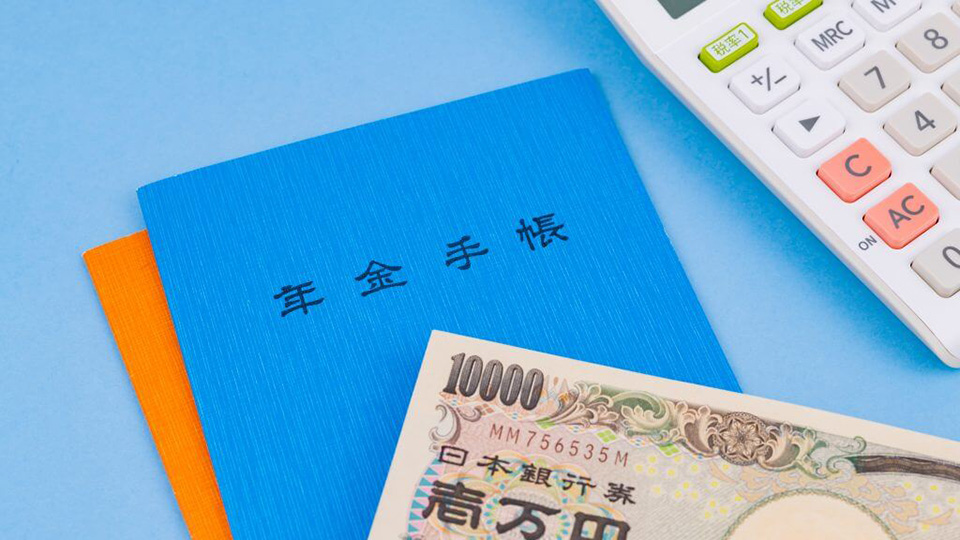
| 正式名称 | 年金アドバイザー3級 |
|---|---|
| 資格種類 | 民間資格 |
| 受験者数(2024年10月) | 1,940人 |
| 合格者数(2024年10月) | 714人 |
| 合格率(2024年10月) | 36.80% |
「年金アドバイザー」とは、「銀行業務検定協会」が認定する民間資格です。各種年金に関する知識を証明する資格であり、2~4級まで設定されています。
4級は各種年金に関する基礎知識が問われ、3級になると各種年金の知識を用い、顧客などの年金相談に載ることができるレベルが求められます。最上級の2級になると、金融機関などにおける社内研修の講師ができるレベルの知識が必要です。
もっとも人気が高いのがこの3級で、銀行や保険会社など、金融機関に勤務する、窓口業務担当者や渉外業務担当者の多くが取得する資格となります。
| 年金アドバイザー3級試験 ~民間資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約30時間 |
| 試験日 | 年2回(例年3月と10月)+CBT方式 |
| 受験資格 | ナシ |
| 2022年3月度試験 受験者数 | 4,157名 |
| 2022年3月度試験 合格者数 | 1,325名 |
| 2022年3月度試験 合格率 | 31.87% |
必要な勉強時間は約30時間。年金に関する基礎的な知識がない方でも、速ければ1週間程度、余裕を持って考えても1ヶ月の準備期間があれば取得可能な資格となります。
試験は筆記試験の開催が年に2回。さらに近年はCBT方式の試験も導入しており、随時受験が可能です。
この後の資格でも何度か出てくるので、ここで「CBT方式」について簡単に説明しておきます。
CBT方式とは、コンピューターを使用した受験方式。つまりパソコンで受験することができるテストです。CBT方式の試験は多くの場合試験日、時間が設定されたおらず、受験者の希望する日時に自由に受験ができるという特徴があります。
試験会場はパソコン教室など試験ごとに指定されていますが、全国多くの地域に試験会場が設置されており、受験しやすいのも特徴の一つ。さらに試験によっては受験が終わった瞬間に合否が確認できるなどの特徴も持っています。
CBT方式にはこのようにメリットが数多くありますが、最大のメリットはやはり自分の都合に合わせた日時に受験できること。受験できるだけの用意ができたら即受験できますので、最高の状態で受験が可能な受験方式となっています。
出題される内容
年金アドバイザー3級の試験で問われるのはやはり各種年金、保険に関する知識です。とはいえ、3級の試験であれば問われるのは基礎的な知識。さらにその基礎的な知識を、実際に顧客相談などに活かせる実践力が試されます。
まずは各種年金や保険に関する基本的な部分を、単純に暗記するだけではなく、内容をしっかりと理解したうえで身に着けるようにしましょう。
どのような方におすすめの資格か?
年金アドバイザー3級は、顧客の年金相談に対応することができるだけの知識を持っていることを証明する資格ですので、銀行や郵便局、農協などで窓口業務や渉外業務に従事している方はぜひ持っておきたい資格といえます。
また、こうした業種への就職を目指す学生の方、転職を目指す方は、就職活動前にぜひ取得しておきたい資格となります。
また、年金に関する基礎的な知識がしっかり身に付きますので、将来的にファイナンシャルプランナー(以下FP)や社会保険労務士(以下社労士)の資格を目指しているという方が、まず取得する資格としても知られています。
FPや社労士の試験には年金に関する問題も多く出題されるため、年金アドバイザー3級の勉強をし、資格を取得することでFP試験や社労士試験への準備となり、さらに業務上や就職活動で有利になるケースがあるからです。
危険物取扱者【乙種4類】
危険物取扱者の資格は、発火や爆発といった危険性のある物質を取り扱うことができる資格であり、国家資格となります。
資格は取り扱える危険物によって特別会員資格があり6つの種類に分類されており、さらにできる業務によって「甲種」、「乙種」、「丙種」に分けられています。
まずは6つある危険物の分類を確認しておきましょう。
| 類 | 代表的な危険物 |
|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 (塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウム、次亜塩素酸ナトリウムなど) |
| 第2類 | 可燃性固体 (硫黄、赤リン、マグネシウムなど) |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 (ナトリウム、リチウム、黄リンなど) |
| 第4類 | 引火性液体 (ガソリン、灯油、軽油、エタノールなど) |
| 第5類 | 自己反応性物質 (ニトログリセリン、トリニトロトルエン、アジ化ナトリウムなど) |
| 第6類 | 酸化性液体 (過酸化水素、硝酸など) |
続いて甲種・乙種・丙種の違いもまとめておきます。
| 甲種 | 全ての危険物の取り扱いができる。また、危険物取扱者の資格を持たない者が取り扱う際の立ち合いができる。 |
| 乙種 | 上記の6種類の危険物ごとに資格が存在。指定された危険物に関しては取り扱い及び立ち合いが可能。 |
| 丙種 | 可燃性固体 上記6種類のうち【第4類】にふくまれる一部の危険物のみ取り扱いが可能。立ち合いは不可。 |
つまりここで紹介する「乙種4類」とは、「ガソリンや灯油、経由などの引火性液体を取り扱うことができ、また危険物取扱者の資格を持たない者が、引火性液体を取り扱う際に立ち会うことができる」という資格になります。
| 危険物取扱者【乙種4類】試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約40~60時間 |
| 試験日 | 都道府県ごとに異なる |
| 受験資格 | ナシ |
| 2022年4~5月 受験者数 | 11,722名 |
| 2022年4~5月 合格者数 | 5,140名 |
| 2022年4~5月 合格率 | 43.85% |
危険物取扱者の試験は、都道府県ごとに実施されており、都道府県によって試験の実施日も回数も違います。
乙種4類の資格は受験者数がもっとも多い資格のため、どの都道府県でも毎年数多くの試験日が設定されています。ちなみにもっとも試験実施回数が多い東京都では、週に1度のペースで試験が行われており、年に50回ほど受験のチャンスがあります。
危険物取扱者【乙種4類】の資格取得に必要な勉強期間は、早い方で2週間程度、一般的には1ヶ月ほどあれば十分取得を目指せる資格となっています。
出題される内容
危険物を取り扱うことができる資格ですので、求められる知識は当然その危険物に関する基礎的な化学知識。さらに対応する危険物に対する火災予防の方法や消火の方法、そして危険物に関する法令などが中心となります。
どのような方におすすめの資格か?
取り扱える危険物の種類から見てもわかる通り、もっとも多いのはガソリンスタンド勤務というケース。いわゆる従業員の入りガソリンスタンドでも持っていれば大きなメリットになります。
さらにセルフのガソリンスタンドとなると、働くには必須の資格となります。セルフのガソリンスタンドは、運転者が自分で給油をする、つまり危険物であるガソリンや経由を取り扱いますので、そこには必ず危険物取扱者乙種4類の資格を持つ従業員がいる必要があります。
また、タンクローリーなど、ガソリンや灯油、経由を運搬する業務にも必須の資格。ドライバーが資格を持っていない場合は、危険物取扱者乙種4類の資格を持った者が同乗する必要があり、ここでも活躍する資格となります。
証券外務員一種・二種

| 正式名称 | 一種外務員資格試験・二種外務員資格試験 |
|---|---|
| 資格種類 | 公的資格 |
| 受験者数(2023年度) | 一種:5,886人 二種:3,833人 |
| 合格者数(2022年度) | 一種:4,199人 二種:2,516人 |
| 合格率(2022年度) | 一種:71.3% 二種:65.6% |
証券外務員資格とは、日本証券業協会が認定する公的資格。証券外務員資格には、「正会員資格」と「特別会員資格」があり、さらにそれぞれ「一種」と「二種」があります。
特別会員資格とは、銀行や保険会社など、「日本証券業協会」に特別会員として加盟している企業に勤務している方のみが受験できる資格。それ以外の方が受験できるのは「正会員資格」となります。
証券外務員資格は、金融商品の販売を行うための資格であり、証券会社はもちろん、銀行や信用金庫、さらに保険会社で働く方が持つべき資格。「一種」と「二種」は取り扱える金融商品に違いがあるため区別されています。
| 証券外務員【一種】試験 ~公的資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約80~100時間 |
| 試験日 | 随時 ※CBT方式 |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年度 受験者数 | 4,690名 |
| 2021年度 合格者数 | 3,365名 |
| 2021年度 合格率 | 71.75% |
| 証券外務員【二種】試験 ~公的資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約50~80時間 |
| 試験日 | 随時 ※CBT方式 |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年度 受験者数 | 2,846名 |
| 2021年度 合格者数 | 2,006名 |
| 2021年度 合格率 | 70.48% |
ここで紹介しているのは正会員資格の試験に関してです。
証券外務員資格もCBT方式が導入されており、基本的には受験者の好きな日時と場所を指定して受験することが可能。
資格取得に必要な勉強時間から計算すると、二種は早い方であれば勉強開始から2週間程度で、遅くとも1ヶ月あれば十分に合格を目指せる資格となります。
一種はやや難易度が上がり、早い方でも3週間程度、一般的には1ヶ月半ほど勉強期間が必要な資格となります。
出題される内容
証券外務員の資格は、金融商品を販売することができる資格ですので、当然ながら各種金融商品に関する基礎知識が必要になります。また、金融商品取引に関する法令や、実際に販売する場合の業務に関する知識も出題されます。
さらに直接金融商品とは関係ないように見えますが、実際に金融商品を販売する以上必要である知識として、企業の財務諸表を読み取る力や株式市場における基礎的な知識も問われます。
【一種】と【二種】の違いは取り扱える金融商品の種類であり、【一種】に関してはすべてんも金融商品の取り扱いが可能、【二種】は信用取引や先物取引といった金融商品が取り扱えない資格となっています。
どのような方におすすめの資格か?
まず銀行や信用金庫、また証券会社は保険会社など、金融商品を販売する業種の方は取得必須といってもいいでしょう。特に営業職や窓口業務、さらに渉外業務に従事する方は持っていないと仕事になりません。
もちろんこういった職種への就職を目指している方や、転職を考えている方も、先に取得しておくことで就職活動が有利になる可能性があります。
ITパスポート・基本情報技術者
ITパスポートと基本情報技術者の試験はどちらも「情報処理技術者試験」の区分のひとつとなります。
| 情報処理技術者試験 区分一覧 | ||
|---|---|---|
| レベル | 試験 | 対象者 |
| 1 | ITパスポート試験 | ITを利活用する者 |
| 2 | 情報セキュリティマネジメント試験 | |
| 2 | 基本情報技術者試験 | 情報処理技術者 |
| 3 | 応用情報技術者試験 | |
| 4 | ITストラテジスト試験 | 高度情報処理技術者 |
| 4 | システムアーキテクト試験 | |
| 4 | プロジェクトマネージャ試験 | |
| 4 | ネットワークスペシャリスト試験 | |
| 4 | データベーススペシャリスト試験 | |
| 4 | エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | |
| 4 | ITサービスマネージャ試験 | |
| 4 | システム監査技術者試験 | |
ITパスポートと基本情報技術者試験の違いは主に対象となる方でしょう。
ITパスポートはITを利活用する者が対象ですので、すべての社会人が対象。ITを利用して業務を行う以上、知っておくべき基礎的な知識が問われる試験です。
基本情報技術者は受験対象が「情報処理技術者」ですので、一般の社会人というよりIT業界で働く方を対象としている試験といえます。
| 基本情報技術者試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約150~200時間 |
| 試験日 | 随時 ※CBT方式 |
| 受験資格 | ナシ |
| 令和3年度 受験者数 | 85,428名 |
| 令和3年度 合格者数 | 34,734名 |
| 令和3年度 合格率 | 52.68% |
| 基本情報技術者試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約100時間 |
| 試験日 | 随時 ※CBT方式 |
| 受験資格 | ナシ |
| 令和3年度 受験者数 | 211,145名 |
| 令和3年度 合格者数 | 111,241名 |
| 令和3年度 合格率 | 52.68% |
どちらもITの知識を問う試験らしくCBT方式を採用。この点では非常に挑戦しやすい試験といえるでしょう。
ITパスポート取得に必要な勉強期間は、早い方で1ヶ月程度、一般的には2ヶ月ほど時間を確保しておくのがおすすめです。
基本情報技術者試験はもう少し難易度が高く、必要な勉強期間は1ヶ月半~2ヶ月半程度。
どちらの試験もITに関する専門用語が多く、全く知識がない状態から勉強を始める場合は、もう少し余裕を持って勉強期間を用意しておくといいかもしれません。
出題される内容
ITパスポートも基本情報技術者も基本的に出題される科目は同じです。
・ストラテジ系(経営全般)
・マネジメント系(IT管理)
・テクノロジ系(IT技術)
出題はこの3科目から。ITパスポートと基本情報技術者の違いは、ITパスポートはすべての試験範囲に置行ける基礎知識が問われ、基本情報技術者試験では特にテクノロジ系を中心に知識を問われることになります。
どのような方におすすめの資格か?
最初に受験対象として触れたとおり、ITパスポートは全ての社会人が持っているべきレベルの資格。そのため業種や職種を問わず、さまざまな方が受験する資格です。
特にこれから就職活動を行う学生の方に人気の資格であり、就職活動の際、すでにITに関する基本的な知識を持っていることがアピールできます。
一方情報処理技術者試験は、特にIT関連企業で働く方が多く取得している資格です。実際にIT関連の業務を行う方にとって情報処理技術者の資格を持っているのは、メリットが多く、IT企業への就職、転職を考えている方はぜひ取得しておきたい資格といえます。ITパスポート検定通信講座
日商簿記2級・3級
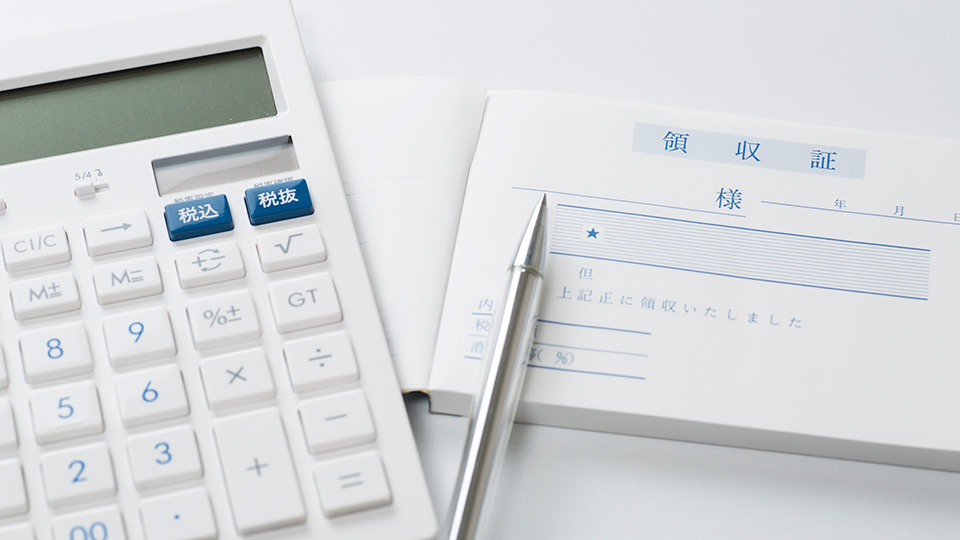
| 正式名称 | 日商簿記検定 |
|---|---|
| 資格種類 | 公的資格 |
| 受験者数(2025年2月) | 簿記2級:7,118人 簿記3級:21,026人 |
| 合格者数(2025年2月) | 簿記2級:1,486人 簿記3級:6,041人 |
| 合格率(2025年2月) | 簿記2級:20.9% 簿記3級:28.7% |
簿記に関する資格はいろいろな資格がありますが、中でももっとも人気があるのが商工会議所が認定する「日商簿記」でしょう。
日商簿記には1~3級と初級があり、特に人気が高いのが日商簿記2級と3級です。まずは各級の違いを簡単に紹介しておきましょう。
| 1級 | 大卒程度の商業簿記・工業簿記・原価計算・会計学が身についている。 大企業の経理担当者として業務にあたることができる |
| 2級 | 商業簿記に加えて工業簿記が身についている。 中小企業の経理担当者として業務にあたることができる |
| 3級 | 商業簿記が身についている。 零細企業の経理担当者として業務にあたることができる |
| 初級 | 簿記の基本用語や複式簿記の基本的な仕組みを理解している |
日本国内の企業のほとんどが中小企業であることを考えると、求められるのは2級か3級です。
2級も3級も受験資格不要の資格ですので、いきなり2級を受験しても何も問題はありませんが、簿記の知識がなくいきなり2級は難しいと感じる方は、まず3級の資格を取得し、その後2級の資格に挑戦するという方法もあります。
| 日商簿記2級試験 ~公的資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約250~350時間 |
| 試験日 | 筆記 年3回(2月・6月・11月) CBT方式 随時 |
| 受験資格 | ナシ |
| 2022年6月度試験 受験者数 | 13,118名 |
| 2022年6月度試験 合格者数 | 3,524名 |
| 2022年6月度試験 合格率 | 26.86% |
| 日商簿記3級試験 ~公的資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約120~150時間 |
| 試験日 | 筆記 年3回(2月・6月・11月) CBT方式 随時 |
| 受験資格 | ナシ |
| 2022年6月度試験 受験者数 | 36,654名 |
| 2022年6月度試験 合格者数 | 16,770名 |
| 2022年6月度試験 合格率 | 45.75% |
| 日商簿記2級+3級連続受験 | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約400~500時間 |
日商簿記の試験は年に3回筆記試験が行われているほか、CBT方式での受験も可能です。基本はどこかの試験日に合わせて勉強をすすめ、試験日までに準備が間に合わなければその後CBT方式で受験するなど、受験の選択肢が多く挑戦しやすい資格となっています。
日商簿記3級取得に必要な勉強期間は1ヶ月半~2ヶ月程度。余裕を持って準備するのであれば3ヶ月程度準備期間があれば十分でしょう。
2級は工業簿記が入りますので、もう少し勉強期間が必要です。必要な勉強期間は3~4ヶ月程度。余裕を持って準備するのであれば半年ほど準備期間を用意してもいいかもしれません。
3級と2級を連続して受験する場合は最初から半年程度は勉強期間を用意しておきましょう。あまり自信がないという場合は半年以上あってもいいかもしれません。
出題される内容
級ごとの違いを見てもわかる通り、出題科目の違いは、2級は商業簿記と工業簿記、3級は商業簿記に関する知識が問われます。
日商簿記の試験は、電卓の持ち込みはOKですが、ある程度数学的な知識が必要となります。数学の勉強が苦手だという方は、多めに勉強期間を取り、何度も問題集などにチャレンジして問題に慣れるようにしましょう。
どのような方におすすめの資格か?
3級は小規模企業、零細企業の経理担当者向けの資格であり、3級の資格だけでは収入アップや転職で有利になることはあまりありません。ただし一部大学の入学で有利になったりというケースがあります。
2級を取得しておけば、中規模企業の経理担当者として従事できますので、転職で有利になったり、現在の職場での待遇が良くなり収入アップにつながったりします。
また、2級の資格を持つと、企業の財務諸表を読む力も身に付きますので、経理の仕事だけではなく、営業職などでも活用できる資格となります。
旅行業務取扱管理者【国内・総合】

| 正式名称 | 旅行業務取扱管理者 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2024年度) | 国内:10,141人 総合:4,680人 |
| 合格者数(2024年度) | 国内:3,181人 総合:1,320人 |
| 合格率(2024年度) | 国内:31.4% 総合:28.2% |
いわゆる旅行代理店など、顧客に旅行商品を販売する販売所には、設置が義務付けられているのが旅行業務取扱管理者の資格を持った方です。
旅行業務取扱管理者の資格は2種類あり、ひとつは【国内】、もうひとつは【総合】という名称がついています。
この2つの違いは読んで字のごとく、【国内】は国内旅行飲みを取り扱える資格、【総合】は海外旅行も含めてすべての旅行商品を取り扱うことができます。
厳密に言えば旅行業務取扱管理者の資格にはもうひとつ【地域限定】という名称の資格があり、この資格は勤務する地域の周辺の旅行に関する知識が問われる試験となっています。
ただし【地域限定】はあまり汎用性のない資格でもあり、ここでは紹介はせず、全国的に汎用性の高い【国内】と【総合】に関して紹介していきます。
| 国内旅行業務取扱管理者試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約250時間 |
| 試験日 | 年1回(9月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年度試験 受験者数 | 9,910名 |
| 2021年度試験 合格者数 | 4,055名 |
| 2021年度試験 合格率 | 40.92% |
| 総合旅行業務取扱管理者試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約400時間 |
| 試験日 | 年1回(10月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年度試験 受験者数 | 2,819名 |
| 2021年度試験 合格者数 | 175名 |
| 2021年度試験 合格率 | 6.21% |
どちらの資格も試験は年に1度。旅行業務取扱管理者の取得を目指す方は、試験日に合わせて勉強を進める必要があり、ある程度計画的に勉強をしていく必要があります。
国内旅行業務取扱者資格を取得するのに必要な勉強期間は単純計算で約3ヶ月。ただし、勉強期間が長くなるほど、勉強に対するモチベーションの維持や、集中力の維持は難しく、その点も考慮すると5~6ヶ月は必要と考えておいた方がいいかもしれません。
総合旅行業務取扱管理者試験はさらに試験範囲が広くなり、単純計算でも5ヶ月近い勉強時間が必要です。余裕を持って準備するのであれば、6~7ヶ月の勉強期間を用意しましょう。
出題される内容
2つの資格で共通して出題されるのが、旅行業法に関する法知識や、旅行業約款や運送約款、宿泊約款などの知識が問われます。また、国内旅行の実務(JRやフェリー、飛行機などの運賃計算や、国内の観光地理など)に関する出題があります
総合旅行業務取扱管理者試験では上記各科目に加えて海外旅行実務の問題も出題されます。
海外旅行実務では、運賃計算や観光地理などに加え、英語力や出入国に関する法令知識も求められ、なかなか取得難易度の高い資格となっています。
どのような方におすすめの資格か?
旅行業務取扱管理者の資格は、旅行業界でこそ活かされる資格です。そのため受験者の多くは旅行業界で働く方、もしくは旅行業界で働くことを目指している方となります。
資格としては非常に狭い範囲で活用できる資格ですので、こういった方向けの資格といってもいいでしょう。
特に旅行業界への転職を考えている方は、転職活動の前に旅行業務取扱管理者資格の取得がおすすめ。上記の通り旅行商品を販売する場所には設置が義務付けられていますので、資格の有無で採用されるかどうかが決まるケースもあります。
ファイナンシャル・プランニング技能士2級

| 正式名称 | ファイナンシャル・プランニング技能士 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2025年1月) | FP2級 学科試験:21,678人 実技試験:19,135人 |
| 合格者数(2025年1月) | FP2級 学科試験:9,634人 実技試験:9,342人 |
| 合格率(2025年1月) | FP2級 学科試験:44.4% 実技試験:48.8% |
世間一般にはFPと呼ばれる資格ですが、正式名称はファイナンシャル・プランニング技能士という名称になります。
FPという資格には、いわゆる「この資格を持っていなければできない業務」という独占業務はありません。FPとしてどれだけの知識が身についているかを証明する資格であり、3級より2級、2級よりも1級のほうが、より知識を持っているということになります。
もっとも人気のあるのが2級。この2級は専門知識ごとに5つに分類されており、それぞれ試験内容が変わります。また、分類ごとに試験を主催する団体も変わる珍しい資格ですので、まずはそのあたりを確認しておきましょう。
| 分類 | 筆記試験実施団体 | 実技試験実施団体 | |
|---|---|---|---|
| FP2級 | 資産設計提案業務 | 日本FP協会 金融財政事情研究会 | 日本FP協会 |
| 個人資産相談業務 | 金融財政事情研究会 | ||
| 中小事業主資産相談業務 | |||
| 生保顧客資産相談業務 | |||
| 損保顧客資産相談業務 |
試験は筆記試験と実技試験で行われ、筆記試験では必要とされる知識が身についているかどうかを、実技試験では実例を元に、身に着けた知識をしっかりと活用できるかの応用力が問われます。
| 総合旅行業務取扱管理者試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約300時間 |
| 試験日 | 年3回(1・5・9月) |
| 受験資格 | アリ |
| 2022年5月試験 受験者数 | 27,678名 |
| 2022年5月試験 合格者数 | 13,617名 |
| 2022年5月試験 合格率 | 49.20% |
※日本FP協会主催試験・筆記試験の結果
FP2級の資格を取得するのに必要とされる勉強時間は約300時間。勉強期間で考えると、3~6ヶ月程度と考えられます。
受験資格
FP2級の試験を受験するには受験資格が必要です。主な条件は4つ。
・FP3級の取得
・FP業務に2年以上従事した実務経験
・日本FP協会の認定するAFP認定講習を受講・修了した者
・厚生労働省認定の金融渉外技能審査3級取得
すでに今従事している仕事がFP関連の仕事であれば問題のない条件ですが、そうではない場合、他の刺客を取得するか講習を受講する必要があります。
勉強期間もさらに必要となりますので、どの条件を満たすのか、しっかりと健闘して準備しましょう。
おすすめはFP3級の取得。FP3級の試験勉強は、FP2級の試験勉強に繋がる部分が多く、3級取得のために学んだことは、2級受験の時に無駄になりません。
FP3級に合格したら、間を置かずに、3旧受験のために勉強した記憶が鮮明なうちに2級試験に挑戦するのが、勉強期間を短くするコツとなりますので覚えておきましょう。
出題される内容
FP2級試験では筆記試験と実技試験が行われます。筆記試験で出題される項目は以下の6項目です。
・ライフプランニングと資金計画
・リスク管理
・金融資産運用
・タックスプランニング
・不動産
・相続・事業承継
不動産関連の知識や金融商品に関する知識、さらに資産運用や相続に関する法令知識など、出題範囲が幅広いのが特徴。すべての項目を網羅するだけでも、ある程度勉強時間が必要な資格となります。
さらにFP2級試験では実技試験を実施。実技試験では実際の例をもとに、記述式で解答する問題が出題されます。
つまり上で紹介した6項目の知識を情報として暗記するだけではなく状況に応じて活用できる応用力が求められるということに。
実技試験対策もしっかり準備しておく必要があるでしょう。
どのような方におすすめの資格か?
FP2級には5つの分類があり、分類ごとにおすすめの職種が変わります。生命保険を取り扱う会社に勤務している方には当然「生保顧客資産相談業務」が最適ですし、企業の持つ資産運用にアドバイスを行うコンサルタント業務などを考えている方には「中小事業主資産相談業務」がおすすめです。
ほかにも証券会社や金融機関など、顧客のライフプランや資産運用に関わる業種の方にお勧めの資格となります。
また、すでに行政書士や司法書士などの資格を持っている方が、さらに業務の範囲を広げるために取得するケースも少なくない資格となっています。
保育士

| 正式名称 | 保育士 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験申請者数(2022年度) | 79,378人 |
| 合格者数(2022年度) | 23,758人 |
| 合格率(2022年度) | 29.93% |
保育園や時児童福祉施設などで働く際、持っているとより有利な条件で働けるようになるのが「保育士」の資格です。
日本国内では少子高齢化の影響もあり、将来性に疑問符がつく資格のように思えるかもしれませんが、そのせいもあり2022年現在保育士は不足しているのが現状です。
少子高齢化といっても子供がいなくなる社会は考えられません。つまり保育士という仕事は将来的にも決してなくならない仕事ということ。今のうちに取得しておくことで、将来的に仕事の選択肢が増える可能性もある資格でありおすすめの資格となります。
| 保育士試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約300時間+α |
| 試験日 | 年2回 前期 筆記 4月・実技 7月 前期 筆記 10月・実技 12月 |
| 受験資格 | アリ |
| 2021年度試験 受験者数 | 83,175名 |
| 2021年度試験 合格者数 | 16,600名 |
| 2021年度試験 合格率 | 19.96% |
保育士の資格取得に必要な勉強期間は3ヶ月以上。上限を詳しく設定できないのは「+α」が理由ですが、この「+α」に関しては後に細かく解説していきます。
受験資格
保育士資格を受験するには、大学卒業、もしくは大学にて一定の単位を取得しているという条件をクリアする必要があります。
学歴面で条件をクリアできない方は、児童福祉施設で一定期間仕事を経験するという実務経験が必要であり、学歴の条件を満たしていない他業種の方が、いきなりチャレンジできる資格ではありません。
+αがある理由
保育士試験は筆記試験の他に、実技試験があります。勉強時間に「+α」があるのはこの実技試験が大きな理由です。
実技試験の受験科目は以下の3つ。
・音楽表現
・実技表現
・言語表現
このうち2科目を選択し合格しなければいけません。「音楽表現」が楽器を弾きながら歌を指導する科目、「実技試験」は写生など絵を描き、さらに絵の描き方を指導する能力、「言語表現」は物語の読み聞かせの能力が問われます。
この実技試験の対策に必要な時間は個人差が大きく、またどのように学ぶのかなどにもいろいろな方法があるため、参考例としても勉強時間が提示できない部分があります。
3科目のうち1つであればある程度想像できるかもしれませんが、2つとなるとなかなか難しいもの。保育士資格を目指す方は、どの2科目を選択し、その対策にどの程度時間が必要かを自分で計算する必要があります。
そこに筆記試験対策で必要な勉強時間をプラスして、必要な勉強期間を考えましょう。
出題される内容
保育士試験で出題されるのは、保育の心理学や子どもの食と栄養など、非常に幅広い範囲の科目が出題され、試験は2日にわたって行われます。
資格を取得し相対するのがまだ幼いお子さんということもあり、どのようなお子さんでも指導、保育、観察などができるよう、試験範囲が幅広いだけではなく、その出題難易度も高くなっています。
どのような方におすすめの資格か?
もちろん保育園や児童福祉施設などで働いている方、またはこうした職場への就職・転職を考えている方におすすめです。
ちなみに保育園も児童福祉施設も、働くために保育士の資格が必須というわけではありません。無資格でも仕事には従事できますが、保育士資格を取得している方が就職先を見つけやすい、または収入アップに繋がるという効果が期待できます。
インテリアコーディネーター

| 正式名称 | インテリアコーディネーター |
|---|---|
| 資格種類 | 民間資格 |
| 受験者数(2022年度) | 8,943人 |
| 合格者数(2022年度) | 2,193人 |
| 合格率(2022年度) | 24.5% |
顧客の住む住環境を快適に整える、もしくは快適に過ごせる空間を提案する業務で力を発揮するのがインテリアコーディネーターの資格です。
部屋の大きさや周囲の環境、建物の構造などを考慮し、顧客が求める住空間を実現するために提案する業務がインテリアコーディネーターの業務であり、その業務で必要とされる知識が身についているかどうかを証明するのがインテリアコーディネーターの資格となります。
| インテリアコーディネーター試験 ~民間資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約300~350時間 |
| 試験日 | 年1回 一次試験 10月 二次試験 12月 |
| 受験資格 | 一次試験 ナシ 二次試験 アリ |
| 2021年度試験 受験者数 | 9,640名 |
| 2021年度試験 合格者数 | 2,334名 |
| 2021年度試験 合格率 | 24.21% |
インテリアコーディネーター資格を取得するために必要な勉強期間は3~6ヶ月程度。後に出題される内容の項でも触れますが、学ぶ分野が幅広く、専門用語も多い試験となりますので、簡単に取得できる資格ではないという印象です。
受験資格
インテリアコーディネーター試験は一次試験と二次試験に分かれており、一次試験に関しては受験資格ナシ。だれでも挑戦できる資格となっています。
二次試験は一次試験に合格していることが受験条件となり、一次試験合格の有効期限は3年間となっています。つまり、一次試験に一度合格してしまえば、そこから3年間は二次試験のみの受験で合格を目指せるということ。
もちろん一発で一次試験・二次試験に合格するのが理想ですが、それが難しい場合はまず一次試験を突破できるように準備するのもいいでしょう。
出題される内容
一次試験ではインテリアコーディネータとして持っておくべき知識が身についているかどうかが問われる筆記試験。インテリア商品の基礎知識や、インテリア計画に関する基礎的な知識が問われます。
二次試験では、身につけた知識を、実際の現場で活用できるかを問われる実務的なテスト。論文やプレゼンの試験が行われますので、一次試験対策で身につけた知識は、単なる暗記ではなくしっかりと内容まで理解している必要があります。
上記の通り、出題範囲が幅広く、また専門的な知識が必要なため、専門用語が多く出てくる分野となりますので、未経験の方はしっかりと準備期間を用意する必要があります。
どのような方におすすめの資格か?
インテリアコーディネーターとして独立して仕事をされている方もいますが、多くの方は内装工事関連会社や、ハウスメーカーなどに勤務しています。
こうした業界で働く方は、インテリアコーディネーターの資格を取得することで待遇が良くなったり収入が上がるケースもあります。また、このような業界を目指すという方は、転職活動の前に資格を取得しておくと、有利な条件で就職先を見つけることができるでしょう。
宅地建物取引士

| 正式名称 | 宅地建物取引士 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2024年度) | 241,436人 |
| 合格者数(2024年度) | 44,992人 |
| 合格率(2024年度) | 18.6% |
不動産取引の現場に必須の存在となるのが宅地建物取引士(以下・宅建士)です。宅建士は国家資格であり、不動産取引の場で「重要事項説明を行う」という独占業務を持つ資格です。
| 宅地建物取引士試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約300~500時間 |
| 試験日 | 年1回(10月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年度試験 受験者数 | 209,749名 |
| 2021年度試験 合格者数 | 37,579名 |
| 2021年度試験 合格率 | 17.92% |
宅建士の資格取得に必要な勉強期間は4~9ヶ月程度。試験が年に一度ですので、1年間かけてしっかりと準備をするという方も多い資格です。
出題される内容
不動産に関する知識が問われる資格であり、土地の地質に関する知識や、建物の権利に関する知識、また土地や建物に関する法令問題が多く出題されます。
土地や建物に関する知識は専門用語が多く、大学の建築学科などで学んでいない限り、あまり日常生活で耳にしない単語も多く出てくる分野となります。
また法令問題も、法律に関する勉強をしたことがない方にとってはかなり難解なもの。受験資格ナシで挑戦できる資格ではありますが、勉強するのがかなり難しい資格試験とも言えるでしょう。
どのような方におすすめの資格か?
宅建士資格を目指す方の多くは、不動産業界、特に不動産売買業、不動産賃貸業、不動産仲介業で働く方々です。さらにこういった業界で営業職に就いている方の受験が多く、不動産業界を目指すのであればぜひ取得しておきたい資格となります。
不動産業界の営業職は、歩合制を導入している企業が多く、業務成績次第では一気に収入が跳ね上がるケースも。もちろんその分厳しい業界でもあり、離職率も高い業界ですので、常に求人が多く出ている業界でもあります。
高収入を目指したいという方は、この宅建士の資格を取得し、不動産業界への転職を考えるのも一つの方法です。
診療報酬請求事務能力認定
病院など医療事務の仕事に必須ともいえるのが診療報酬請求事務能力認定の資格です。医療にかかった費用などを計算できるようになる資格であり、人気の高い資格となります。
診療報酬請求事務能力認定試験は「医科」と「歯科」に分かれており、受験者はどちらかを選択して受験することになります。
| 診療報酬請求事務能力認定試験 ~民間資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約400時間 |
| 試験日 | 年2回(7・12月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年12月試験 受験者数 | 4,989名 |
| 2021年12月試験 合格者数 | 1,961名 |
| 2021年12月試験 合格率 | 39.31% |
診療報酬請求事務認定資格を取得するには、4~7ヶ月ほどの勉強期間が必要になります。試験は年に2度行われますので、勉強の進行度合いに合わせてどちらで受験するか決めるといいでしょう。
出題される内容
診療報酬を計算することができるようになる資格だけに、試験で問われるのは医療用語や薬学の知識、さらに診療ごとの点数計算など、専門的な分野となります。
また医療費を請求するということで、各種保険制度や介護保険制度に関する基礎知識も必要となります。医科と歯科では出題内容が変わるため、医科か歯科か、自身の仕事に合わせて受験時に選択しましょう。
学ぶ分野は専門用語も多く、なかなか頭に入りにくい分野です。勉強にはそれだけ期間が必要となりますので、しっかりと準備期間を用意しましょう。
どのような方におすすめの資格か?
診療報酬請求事務能力認定資格が活かせるのは医療事務の分野。医療機関で働く方にお勧めの資格となります。
また、半年程度の勉強期間で取得可能ということで、出産・育児のためにお仕事を辞めていた方が、育児が落ち着き改めて仕事を探す場合などにもおすすめの資格。比較的取得しやすい資格ですが、非常に有用な資格といえます。
通関士
日本は多くの物を輸入し、輸出することで経済が成り立っている国です。そんな日本で必要不可欠となる資格が「通関士」の資格です。
海外から日本国内に入ってくる輸入品も、日本から海外に出荷される輸出品も、必ず税関を通過する必要があります。この通関手続きを行うことができるのが、この通関士という資格になります。
| 通関士試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約400~500時間 |
| 試験日 | 年1回(10月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年試験 受験者数 | 6,961名 |
| 2021年試験 合格者数 | 1,097名 |
| 2021年試験 合格率 | 15.76% |
通関士の資格を取得するには5~9ヶ月ほどの勉強期間が必要になります。試験は毎年10月に行われますので、どんなに遅くとも5月には勉強を始めたいところ。それ以降に勉強を始める場合は、翌年の試験に挑むつもりで計画を立てるといいでしょう。
出題される内容
通関士は輸出入する物品の税関通過に関する手続きを代行する仕事ですので、専門分野の知識が必要となります。
通関業法や税関法などの法律問題が中心となりますが、通関書類の作成や手続きなど実務に関する問題も出題されます。
法律知識を中心に実際の通期案手続きの流れをしっかりと把握しておく必要があります。
どのような方におすすめの資格か?
通常輸出入品を税関通過させる場合、通関を専門に扱う通関業者に業務を依頼します。つまり通関士の資格を目指す方の多くは、こういった通関業者で働いている、もしくは働きたいと考えているということになります。
通関業者として業務を請け負う場合、通関士の資格を持っている人物を設置する義務があります。設置する通関士は従業員である必要はなく、通関手続きを行うという契約を結んでいれば、フリーの通関士を登録することも可能です。
通関士の仕事は、荷物の中身をしっかり把握することができれば、自宅でもできる仕事。通期案のための書類を作成するのが主な仕事となりますので、働き方が叫ばれる2022年現在、またはこれ以降は、テレワークでの業務が増える可能性もあります。
自宅で働きたい方などにもおすすめの資格といえるかもしれません。
管理業務主任者・マンション管理士
管理業務主任者とマンション管理士は、別の資格ではあるものの、その業務上出題される範囲が非常に近い資格となります。
管理業務主任者とは、マンションなど集合住宅の管理業務を行う場合に求められる資格。いうなれば、マンションの管理人サイド、管理会社サイドの人物が取得する資格です。
一方マンション管理士は、マンションの管理組合の活動をサポート、チェックなどができる資格。こちらは管理業務主任者とは反対に、集合住宅の住民サイドで活躍する資格となります。
| 管理業務主任者試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約500時間 |
| 試験日 | 年1回(12月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年試験 受験者数 | 16,538名 |
| 2021年試験 合格者数 | 3,203名 |
| 2021年試験 合格率 | 19.37% |
| マンション管理士試験 ~国家資格~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約600時間 |
| 試験日 | 年1回(11月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年試験 受験者数 | 12,520名 |
| 2021年試験 合格者数 | 1,238名 |
| 2021年試験 合格率 | 9.89% |
| 管理業務主任者+マンション管理士連続受験 | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約800~900時間 |
管理業務主任者の資格取得には、半年~9ヶ月程度、マンション管理士の資格取得には7~10ヶ月程度の勉強期間が必要です。
両方同時に資格取得を目指す場合は、9ヶ月~1年間ほど勉強期間を確保しておくといいでしょう。
出題される内容
出題される内容は共通する部分が多く、マンション管理に関する基礎知識や建物の構造に関する知識、さらに大規模修繕に関する知識が求められます。
マンション管理士試験の方が法律に関する出題が多く、必要時間が稍多いのはこのあたりが理由です。
建築などについて学んだことがない方にとっては、理解するのが難しい専門知識もありますので、慌てずじっくり勉強していくようにしましょう。
どのような方におすすめの資格か?
この2つの資格を目指すのは、不動産業界、特に不動産管理業界で働く方が目指す資格といえます。
管理業務主任者の資格は管理業者としては必要な資格ということは分かりやすいところですが、マンション管理士の資格は管理会社とは対立することもある資格。なぜ管理業界の方が取得を目指すのでしょう。
不動産管理会社は、集合住宅などの管理を請け負うことを業務としています。その際、一方的に管理するだけではなく、マンション管理士も配置し、マンションの住民たちが作る管理組合の活動もサポートできますという形を持っていた方が、業務を請け負いやすくなります。
また、実際にマンションで暮らしているという方は、ご自宅の管理組合の活動でマンション管理士の資格が生きるというケースもあるようです。
公務員採用試験【一般職・教養試験】

| 正式名称 | 公務員 一般職試験(大卒程度) |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2023年度) | 26,319人 |
| 合格者数(2023年度) | 8,269人 |
| 合格率(2023年度) | -% |
国家公務員、地方公務員として働く場合には、公務員採用試験に合格する必要があります。公務員採用試験は資格試験ではなく、いわゆる「採用試験」となりますが、出題範囲や毎年の傾向がハッキリしている試験ですので、事前に対策が可能です。
ここでは、国家公務員試験、大卒程度・一般職で出題される教養試験に関して紹介していきます。
| 公務員採用試験【一般職・教養試験】 ~採用試験~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約500時間 |
| 試験日 | 年1回 大卒 一次試験 6月 |
| 受験資格 | アリ |
| 2021年一次試験 受験者数 | 20,718名 |
| 2021年一次試験 合格者数 | 11,056名 |
| 2021年一次試験 合格率 | 53.36% |
公務員採用試験に必要な勉強期間は半年~9ヶ月ほどの勉強期間が必要です。学生の方で、1日の勉強時間を多く確保できる方の場合、半年もかからずに対策も可能でしょう。
ただし社会人として働きながら、国家公務員に転職を目指すという方は、仕事をしながらしっかりと対策すべき時間を確保しましょう。
公務員採用試験には年齢による受験制限があります。国家公務員の一般職の場合は30歳未満です。タイムリミットのある試験ですので、転職を考えている方は早めに準備に取り掛かりましょう。
出題される内容
公務員採用試験の教養問題は、専門的な知識ではなく一般教養を中心とした問題が出題されます。文章理解や判断推理など、聞いただけではどのような問題が出題されるか想像しにくい問題が多いのがポイント。
過去問などを活用し、出題傾向とどのように解答すべきかをしっかりと理解していきましょう。
公務員採用試験が難しいというポイント
公務員試験はほかの資格試験とはやや趣旨の違う試験です。もちろん公務員試験は採用試験ですので、趣旨が違うのは当然でしょう。
一般的に公務員採用試験が難しいと言われるのは、合格の基準が「相対評価」になるからです。採用試験ですから、試験の前に採用枠が決まっています。そして受験者の中から成績上位の者から合格していくという方式。
そのため受験者のレベルが高い年や、採用枠が少ない年は試験レベルが跳ね上がるという特性があります。
ちなみに試験には相対評価と絶対評価があります。採用試験や入学試験は事前に募集人数が決まっており、合格ラインが決まっていない試験。こういった試験はどのくらい勉強すれば合格できるか事前に想定できないため対策が難しくなります。
絶対評価の試験とは、事前に合格ラインが決まっており、その合格ラインを越えた方はすべて合格できるという試験。こういった試験は事前にどのレベルまで知識を身に着ければいいのかがハッキリしていますので、対策がしやすいといえます。
対策が難しい部分で、公務員採用試験は難しいとされているわけです。
裁判所事務官

| 正式名称 | 裁判所事務官 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2023年度) | 4,743人 |
| 合格者数(2023年度) | 2,351人 |
| 合格率(2023年度) | 3.6% |
裁判所事務官も、裁判所で働く国家公務員になるための採用試験となります。裁判所事務官の試験は通常の国家公務員試験とは別で行われ、出題される内容にも違いがあります。
そのあたりも紹介していきましょう。
| 裁判所事務官試験 ~採用試験~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約500~1,000時間 |
| 試験日 | 年1回(5月) |
| 受験資格 | アリ |
| 2021年一次試験 受験者数 | 7,802名 |
| 2021年一次試験 合格者数 | 3,274名 |
| 2021年一次試験 合格率 | 41.96% |
裁判所事務官の試験対策に必要な勉強期間は半年~1年以上となります。
裁判所事務官の試験を受けるためには受験資格があります。公務員採用試験と同様に年齢による制限もありますし、学歴による制限もあります。ご自身の学齢、年齢に合った試験に挑戦しましょう。
出題される内容
裁判所事務官の採用試験は、憲法と民法が必須科目。さらに刑法か経済原論から1科目選択し、合計3科目で受験することになります。
一般的な資格試験でも法律分野の出題がある試験は多いのですが、資格試験の場合、その資格に必要な法律の知識のみが問われますが、裁判所で働く以上、法律全般に関しての知識が問われます。
対策には多くの時間が必要となりますので、しっかりと勉強時間を確保しましょう。
裁判所事務官試験が難しいというポイント
裁判所事務官試験も公務員試験と同様に採用試験ですので、採用枠の問題もありますし、相対評価の試験となりますので、そもそも難しい試験となります。
さらに出題される内容が憲法・民法・刑法など幅広い知識が問われる問題となるため、非常に合格率が低く対策が難しい試験です。
社会保険労務士
数ある士業の中でも、珍しく企業に勤務しながら資格を活用した活動が認められているのが社会保険労務士の資格。そのため取得を目指す方も多く、人気の衰えない資格となります。
企業の労務管理や各種年金制度、保険制度の相談の受付や指導を行うことができる資格となります。
| 社会保険労務士試験 ~国家試験~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約800~1,000時間 |
| 試験日 | 年1回(8月) |
| 受験資格 | アリ |
| 2021年 受験者数 | 37,306名 |
| 2021年 合格者数 | 2,937名 |
| 2021年 合格率 | 7.87% |
社会保険労務士の資格取得には、1年間ほどの勉強期間を確保する必要があります。
受験資格はいろいろとあるため詳細は省きますが、主なところでは大卒の学歴が必要といったところになります。
出題される内容
労務管理を行う資格ということで、労働基準法など労働に関する法令に関してはしっかりとした知識が求められます。さらに各種保険や年金制度に関する専門知識も必要です。
さらに一般常識問題も出題されるため、専門的な科目だけ勉強していればいいというわけでもないところが難しい試験と言われるポイントかもしれません。
どのような方におすすめの資格か?
企業に勤務しながら活用できる資格ということもあり、業種を限定せず多くの業種の方が挑戦する資格です。特に総務部や人事部で働く方が多く、もちろんそれ以外の部署の方も取得を目指す資格となります。
また、行政書士や司法書士、さらにFPなどの資格を持っている方が、業務の幅を広げるために取得を目指すケースも多く、毎年多くの受験者が集まる試験となっています。
行政書士
官公署などに提出する書類の作成代理を請け負うことが主な業務となる行政書士。この行政書士試験も非常に人気の高い資格となります。
行政書士試験が人気である理由の一つとして、受験資格がないということが挙げられます。たとえ学歴がなくても、特定の実務経験がなくても、誰でも挑戦できる資格となっています。
| 行政書士試験 ~国家試験~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約1,000時間 |
| 試験日 | 年1回(11月) |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年 受験者数 | 47,870名 |
| 2021年 合格者数 | 5,353名 |
| 2021年 合格率 | 11.18% |
行政書士資格を取得するのに必要な勉強時間は、一般的には1年間かそれ以上。しっかりと準備をしたうえで挑戦すべき試験となっています。
出題される内容
行政書士試験で出題されるのは、基礎法学や行政法など法律の問題が中心となります。しかも出題される範囲が広く、対策には多くの時間がかかるでしょう。
さらに政治経済や文章理解といった一般教養問題も出題され、そべての科目において平均的に知識を高める必要があります。
どのような方におすすめの資格か?
行政書士の資格を活かして仕事をするためには、行政書士法人に就職するか、自ら独立開業をする必要があります。そのため独立開業を目指す方の受験が多く、受験者のレベルが高い試験とも言えます。
また、すぐに独立開業という計画は無くても、将来的に独立を考えているという方の受験も多い資格。資格は一度取得すれば、更新の必要がない資格となりますので、将来のことを考えて受験する方も多いようです。
中小企業診断士

| 正式名称 | 中小企業診断士 |
|---|---|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 受験者数(2023年) | 1次試験:18,621人 2次試験:8,241人 |
| 合格者数(2023年) | 1次試験:5,521人 2次試験:1,555人 |
| 合格率(2023年) | 1次試験:29.6% 2次試験:18.9% |
中小企業の経営診断や、経営方針の助言が行える資格として近年人気が高まっているのが中小企業診断士です。
試験は一次試験と二次試験(筆記+口述)に分かれており、全ての試験に一度の挑戦で合格するのは非常に難しい難関資格としても知られています。
| 中小企業診断士試験 ~国家試験~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約1,000~1,400時間 |
| 試験日 | 年1回 一次試験 8月 二次試験(筆記) 10月 二次試験(口述) 1月 |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年一次試験 受験者数 | 16,057名 |
| 2021年一次試験 合格者数 | 5,839名 |
| 2021年一次試験 合格率 | 36.36% |
| 2021年二次試験 受験者数 | 8,757名 |
| 2021年二次試験 合格者数 | 1,600名 |
| 2021年二次試験 合格率 | 18.27% |
中小企業診断士資格を取得するには、少なくとも1年以上、余裕を持った計画を立てるのであれば2年ほど勉強期間が必要となります。
勉強期間が長くなるため、特に独学で挑戦する場合はモチベーションの管理が大きなポイントとなるでしょう。
出題される内容
企業経営の診断や助言を行う資格ですので、必要とされる知識は経済正確や経営理論といった専門分野の知識となります。さらに企業法務など法令問題も出題されるため、法律に関する知識もしっかり身につける必要があります。
二次試験は記述式と口述式となりますので、得た知識を自分の言葉として活用できるレベルまで高めるようにしましょう。
どのような方におすすめの資格か?
中小企業診断士の資格が活躍する職種となると、やはりコンサルティング業務などが中心でしょう。
ただし、中小企業診断士は、自分の能力を確認するため、自己啓発のために受験する方も多く、職種や業種を問わずに取得を目指す方が多い資格でもあります。
中小企業診断士として独立開業をする方は多くはありませんが一部いらっしゃいます。こうした独立を目指す方の場合、社会保険労務士や行政書士など、ほかの資格も合わせて取得し業務を行っているケースが多いようです。
司法書士
数ある資格試験の中でも難関試験として知られているのが司法書士試験。司法書士は登記の代理を行ったり、裁判に代理で出席することもできる資格であり、その試験の難易度はかなり高くなります。
| 司法書士試験 ~国家試験~ | |
|---|---|
| 必要な勉強時間(独学) | 約3,000時間 |
| 試験日 | 年1回 筆記試験 7月 口述試験 10月 |
| 受験資格 | ナシ |
| 2021年 受験者数 | 11,925名 |
| 2021年 合格者数 | 613名 |
| 2021年 合格率 | 5.14% |
司法書士の資格を取得するには、少なくとも3年間ほどは勉強期間を確保する必要があるでしょう。合格率は例年10%を切っており、簡単に取得できる資格ではないというのは間違いありません。
これだけの難関試験でありながら、受験資格はなく誰でも挑戦できる資格でもあります。
資格取得の勉強に自信がある方は、しいっかりと準備期間を確保し、挑戦してみてはいかがでしょう。
出題される内容
司法書士試験で出題されるのは法律に関する問題です。憲法や民法はもちろん、不動産登記法や民事訴訟法など、非常に幅広い法知識が求められます。
また、求められるのは単純に法律を暗記すればいいというわけではなく、しっかりとその内容を把握しておくのもポイント。ほかの資格試験と比較しても、より専門的な知識を求められる試験となっています。
どのような方におすすめの資格か?
司法書士の資格を取得するには長い勉強時間が必要です。そこまでして取得する以上、やはり独立開業を目指す方におすすめの資格となるでしょう。
勉強時間を短縮する方法
いろいろな資格の取得に必要な勉強時間を紹介してきました。しかし、資格取得に必要な勉強時間は短いに越したことはありません。
勉強時間を短くするには、勉強効率を高める必要があります。独学と同じスタイルの勉強方法で勉強効率を高めることを考えれば、通信講座の受講がおすすめとなります。
勉強の効率を高めるには通信講座がおすすめ
勉強効率を上げる方法として通信講座をおすすめしましたが、資格取得の講座を開講している予備校に通うという方法もあります。
ただし予備校通学にはデメリットもあります。
まずは何より近所に予備校がないケース。資格取得の予備校は、都市部など人口の多い地域に集中しています。そのため地方部ではそもそも通学するという選択肢がとれません。
また、通学範囲に予備校があったとしても、予備校に通学する時間が必要になります。仮に往復1時間となれば、勉強に充てられる時間のうち、1日1時間は通学時間となってしまい、非効率的になります。
その点通信講座は独学同様自宅での学習が可能で、通学時間の無駄がありません。もちろん日本全国どこにいても受講可能であることメリットといえます。
では、独学と比較して通信講座は、どのような点で勉強効率を高めることができるのかを確認しておきましょう。
専門用語が多い資格の勉強は特におすすめ
通信講座ではその資格を取得するために必要な独自のテキストがあります。また、そのテキストに沿って、資格試験の専門家である講師の授業も受けることが可能です。
そのため特に大きな効果が期待できるのが「専門用語や専門知識が多く必要となる試験」です。
法律関係の勉強や、医療用語、不動産用語など、普段の生活ではあまり使わない用語が多く出てくる勉強は、独学でテキストを読んでいるだけよりも、その用語をしっかりと理解している専門家の話を聞く方が頭に入りやすいもの。
参考までに、専門用語の多い資格試験の勉強時間を、独学のケースと通信講座「フォーサイト」の受講生とで比較してみましょう。
| 資格 | 独学の勉強時間 | フォーサイト受講生の勉強時間 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引士 | 約300~500時間 | 約200時間 |
| 診療報酬請求事務能力認定 | 約400~500時間 | 約200~240時間 |
| 管理業務主任者 | 約500時間 | 約300時間 |
| 行政書士 | 約1,000時間 | 約500~600時間 |
資格もよりますが最大勉強時間が半減というケースも見受けられるほど勉強効率が高まります。これが通信講座をおすすめする大きな理由となります。
まとめ
資格取得を目指す場合は、まずその資格を取得するのにどの程度の勉強時間が必要かを知ることは重要です。そのうえで自分のライフスタイルを考え、毎日どの程度の時間を資格の勉強に当てられるかを考えましょう。
この2つがハッキリすれば、資格取得までに必要な勉強期間がイメージできます。あとはその中でしっかりと勉強計画を立て、その計画を遂行すれば合格に近づけるということになります。
ただし、独学で目指すのはある程度デメリットがあるもの。まずは想定以上に勉強効率が上がることがないということ。そのため勉強期間は長くなり、どうしてもモチベーションの管理が難しくなることになります。
資格の取得は取得することがゴールではありません。これが学校の入学試験や採用試験とは違う部分。資格の取得はあくまでもスタート地点であり、資格取得後どのようにその資格を活かすかが大きなポイント。そのためにも資格取得までの時間は短いに越したことはありません。
勉強時間を短縮するには勉強効率を上げるしかありません。そのためにおすすめしたいのが通信講座。
日本全国どこにいても受講でき、自宅で好きな時間に勉強できるというメリットもある通信講座は、資格取得に大きな力になるでしょう。