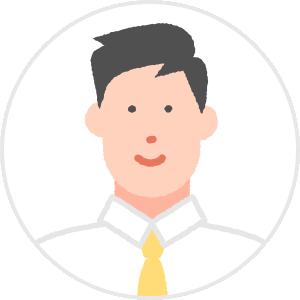
宅建の受験で、民法に手を伸ばしたのはやっと8月と遅かった!
【宅地建物取引士】
- 職業
- 自営業・会社経営
- 年代
- 30代
- 性別
- 男性
本格的に学習を開始したのは5月末から。1日の勉強時間は1-2時間くらいだったと思います。8月は集中できたので5時間くらいはやっていたかも。
まずは、民法には手を付けないと決め、宅建業法のDVDをテキストを見ながら視聴。はっきり言って全然理解できませんでした。理解できないので集中力も持続せず、なんとなく見終わったという感じでした。
その後に、テキストを見ながら重要そうな箇所をノートに写していく作業。口に出してブツブツいいながら、書いていくとなんとなく数字などは覚えていきました(あくまでなんとなくです)。
余談ですが、筆まめができて痛くなったのでノートは途中から執らなくなり、パソコンで打つようになりました。それも運悪くパソコンが故障しデータが消えたので辞めました。
そうしてとりあえず、宅建業法のテキストを1周し終わり、1問1答に取り掛かりました(私の場合、ipadの1問1答アプリでやっていました)。
それを1日300問ほどやっていたら2週間くらいでだいたいの知識はいつのまにか頭に入りました。同じように法令上の制限、その他の法令も取り組みました。
この時点で7月中旬くらいだったと思います。まだ、民法や過去問題集には手を付けていません。そこからもっぱら勉強は1問1答ばかり。テキストも見ることは少なくなりました。
8月に入り勉強できる時間が増えたので、真剣に過去問に取り組むようになります。
まずは過去問(民法以外)を1周。この時は30%くらいしか正解できていなかったと思います。そこで2週目はテキストを見ながらやりました。テキストに載っていない細かい知識はその都度テキストに書き込み、平行してややこしい数字(以上、以下、未満、より上)は表を作り書き出しました。
このように自分の苦手な箇所は自分で対策案を練り、覚えるようにしました。例えば私の場合は、重要事項の説明事項、契約書の記載事項、税金等です。やはり自分で作ると覚えるものです。
8月下旬になり、民法に取り掛かることにしました。DVDでも触れられてましたが、民法に時間をとるより他を確実にということだったので。
ただ、民法は予想以上に難しく、問題に文句ばかり言いながら勉強していました。自分の理解しやすい分野を確実に覚えることに集中しました。登記と抵当権はすぐに捨てました。
実際、書店で買った模試の予想問題集などをやりましたが、9月になっても民法の正解率は3割ほどでした。正直、民法はやる気にならなかったです。9月までは民法以外を徹底的に勉強し、10月に入り民法に割く時間を増やしていきました。
民法もDVDを2回くらい見るとなんとなく理解できるようになり、そうなると勉強していても頭に入るようになりました。事実、本番では民法も7割ほど正解できました。
私個人の勉強法としましては、テキストを読むより問題をやりながら覚えるという方が合っているのでテキストは1,2回くらいしか読んでいません。正解するよりも間違った問題の方が覚えるようです。
あとは、間違っても解答を見ない、質問をしないというのも心がけました。自分で答を探すのも勉強です。解答に納得できなければ納得できるまでテキストなりネットなりで調べて理解するようにしました。
私は他の人よりも真面目には勉強していないと思います。結構サボっていましたから。そういう意味でも通信講座は自分に合っていました。
自分が理解できていたら多少は心にゆとりを持った方が良いと思います。焦ってばかりでは疲れるだけですし、体調にも影響してくると思います。
最後に、なによりサボり気味で勉強嫌いな私が無事合格できたのもフォーサイトさんの優れたテキスト、DVD講座のおかげだと思っています。他の参考書などでしたら途中で嫌になっていたでしょう。
カラフルで見やすい、イラストが入っている、知識を詰め込みすぎない、などの工夫は予想以上に取り組みやすかったです。
本当にありがとうございました。


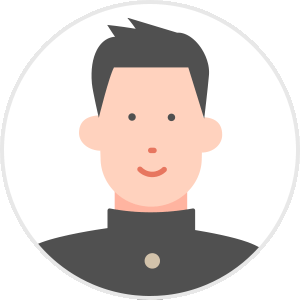
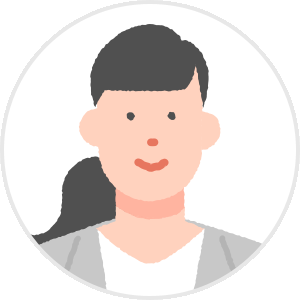
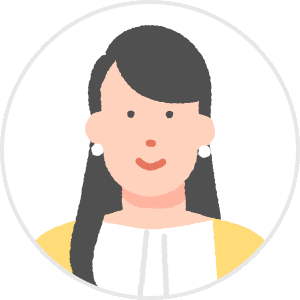
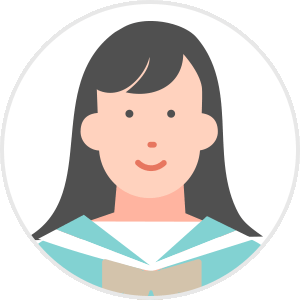
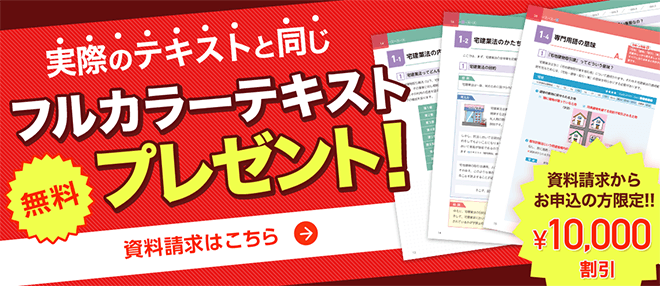
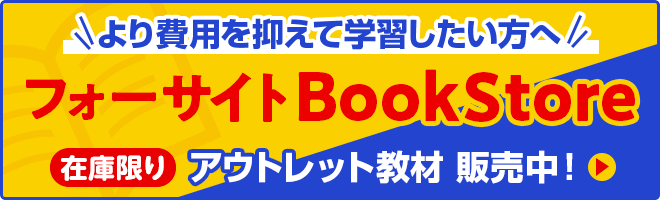
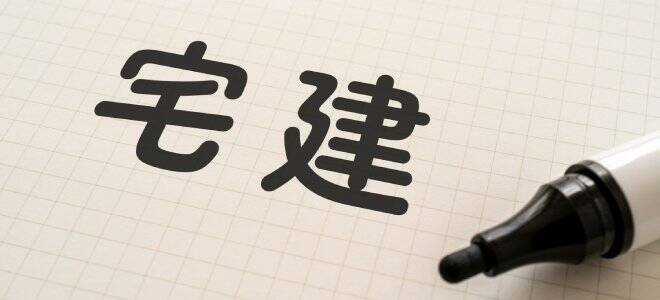












 ログイン
ログイン




 0120-966-883
0120-966-883


