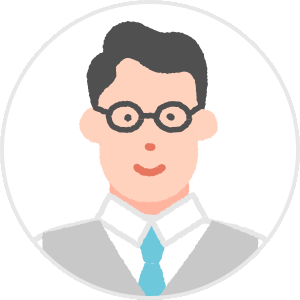
宅建も行政書士も一発合格できました。直前の改正情報と統計のテキストは大助かり!
【宅地建物取引士】
2018年(平成30年度)合格
- 勉強期間
- 9ヶ月間
- 受験回数
- 初学者(1回目)
- 職業
- 無職
- 年代
- 50代
- 性別
- 男性
30年近く勤めていた放送メディアの会社を早めに退職し、メディアの仕事では学べなかった分野の勉強をしたいと思い、選んだのが法律でした。去年、フォーサイトの行政書士講座を受講し、そのすばらしい内容のおかげで、半年ほどの学習でギリギリ、一発合格できました。その後、司法書士試験の勉強と共に始めたのが、宅建試験への挑戦でした。私の場合、行政書士合格後も民法の勉強は続けていたので、権利関係についてはあまり特別に勉強しなくて済みました。
■実は捨てられるジャンルがほとんどない
4月にフォーサイトの宅建業法を軽く勉強し、「結構、簡単だ」と思いました。そこで数ヶ月は、司法書士の勉強をしていたのですが、6月あたり、法令上の制限に進み、過去問に取りかかると、法令上の制限はまったく太刀打ちできません。テキストの理解が足りないのかと思いましたが、そうでもない。
そこで、フォーサイト流で、これらの分野をどの程度「捨てられるのか?」を考えてみました。
宅建業分野で確実に勉強し(20点中17点)、得意の権利関係でも結果を出せた(14点中11点)として、34点中28点です。去年までですと、合格ラインには、まだあと5点以上も必要です。
本当に簡単な資格試験なら、重要な2科目で高得点をとれれば、合格ラインは超えるはずではないでしょうか。
しかし、私のシミュレーションでは、それをしても、法令上の制限とその他の法令の16点で、5点以上を取らないといけません。
数字だけだと簡単そうですが、この分野は法令の数も非常に多く、しかもそれぞれが宅建業法に比べて格段に理解が難しく、ちょっとの勉強で確実に得点できるものではない、ということが分かってきました。
運を天に任せて、「捨てる」という手もありますが、それをしたら「運が悪ければ合格できない」という可能性がどんどん増していきます。
いまの宅建試験では、絶対に合格できるレベルまで持っていけるには、捨てることのできるジャンルがほとんどない、というのが現実だ、と思います。ちょっと頑張れば合格できるわけではない、意外とシビアな試験だと思いました。
■法令上の制限でめげる
宅建試験合格の肝は、実は権利関係と法令上の制限だと思います。宅建業法は、簡単に理解できるし、過去問を繰り返し解けば、点はとれます。逆に、ほとんど落とさないぐらいまでにしないと合格できません。
そして権利関係は民法ですから、難しいのですが、これも全体に占める割合が多いですから、14点中10点はなんとかとらないと、合格ラインの勝負に持ち込めないでしょう。
そしてそのうえで、本当の合否の勝負は、法令上の制限とその他の法令にかかってきます。
法令上の制限はきつかった!
まず建築基準法は、複雑で理解が大変です。建築基準法のすべての過去問を理解するために、結局、私は建築基準法の構造体系を理解し、細かい数字や規制の意味も自分で勉強せざるをえませんでした。
そしてそれと同時に苦しかったのは、国土利用計画法、農地法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土地区画整理法というこの6つの法律が、お互いに関わっていて、どこでどう関連し、どこでどう関連しないのかという全体像がネットや別の書籍をあたっても書いてなかったことです。
なにしろ、混同しやすいものばかりなのです。都市計画法の開発許可と宅地造成等規制法。都市計画法のツールである土地区画事業と土地区画整理法との関係などなど、同じような印象のものが多すぎるのです。これらをしっかり頭に入れるには、そのひとつひとつの法律の目的と、具体的に自分が土地を手に入れて造成して、家を建て、販売するというストーリーで、どうこれらが関わってくるのかを理解しなければなりませんでした。そうして初めて、それぞれがしっかり分類、認識できました。
■直前の改正情報と統計のテキストは大助かり
「ひとつの法律を丁寧に勉強して、ようやく70%の確率で1点ゲットの実力」という作業を繰り返し、合格確実ラインへ1点1点を積み上げるという作業を繰り返す中、助かったのが最後のテキストです。
このうすっぺらのテキストは、直前1週間にきちんと学ぶだけで、3点ぐらいがほぼ100%の確率で手に入れられるようになる魔法のテキストでした。これは1点の重みがあるこの試験では、非常に貴重です。
宅建業法については、全体の得点の土台固めを怠らないため、2週間前からもう一度6巡目の過去問を行いました。それまで捨てジャンルをなるべく作らず(所得税法あたりなどは、あまりにも学習に時間がかかるので放棄しました)着実に全分野を丁寧に理解していたおかげで、結果は45点でした。5問しか間違えなかったというのは自慢ではありますが、一方で、もし手を抜くジャンルをいくつか増やしていたり、過去問の捨て問を学習しないでいたら、たぶん37点前後で、1点に泣いて不合格、ということもありえたと思います。
宅建士試験は、問題のレベルは浅くとも、ものすごい種類の法令を、確実に理解する必要がある試験です。
行政書士の方が難しいかもしれませんが、その難しさの種類は異なります。ほとんど満点に近い実力を持っていないと確実に合格できない宅建士試験は、それはそれでなかなか大変な試験です。でも、内容は仕事ばかりでなく、どれも日常生活の役に立つことばかりだと思います。
心よりみなさまのご健闘をお祈り致します。


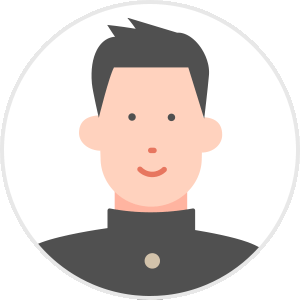
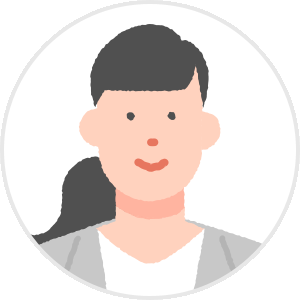
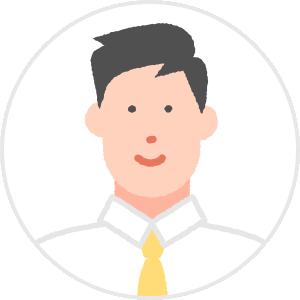
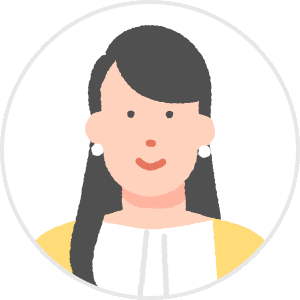
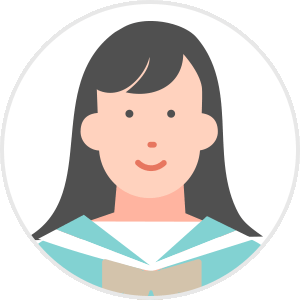
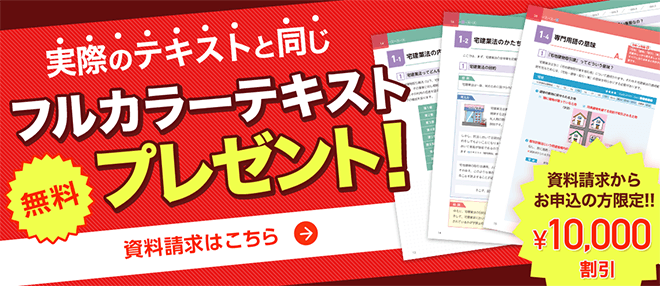
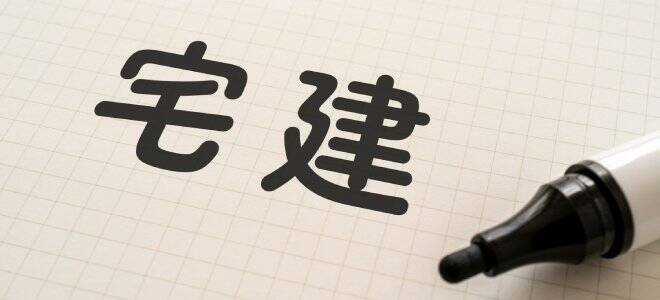










 ログイン
ログイン




 0120-966-883
0120-966-883


