行政書士試験は独学でも突破できるか?
更新日:2022年3月7日

国家資格であり、幅広い法律知識が問われる行政書士試験。この試験に合格するための勉強法には、予備校への通学や通信講座の受講があります。では予備校に通うことなく、通信講座などを利用する独学でも合格を目指せるのでしょうか?行政書士試験に合格するために必要な勉強時間や効果的な勉強方法をご紹介しましょう。
- 行政書士試験は毎年1度、例年11月に実施されます。近年ではおよそ4~5万人が受験し、およそ1割程度となる4~5,000人が合格しています。
- 行政書士試験の出題科目には「法令科目」と「一般知識」があり、それぞれ合格基準点が定められています。
- 法律知識がない方が行政書士試験に1年間で合格するためには、1,000時間程度の勉強時間を確保する必要があります。
- スキマ時間を勉強時間として活用することは、効率的な学習方法を実現するために非常に重要なポイントとなります。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
行政書士試験の試験科目
行政書士試験は毎年1度、例年11月に実施されます。受験者数は年度ごとに変化しますが、近年ではおよそ4~5万人が受験し、およそ1割程度となる4~5,000人が合格しています。
合格率は10%前後と決して高くなく、しっかりと準備をしておかないと簡単には合格できない試験といえるでしょう。しかもこの行政書士試験の独学で挑むとなるとさらに難易度は高くなります。
独学で勉強を進める場合の大きな問題は、テキスト選び、勉強計画、モチベーションの維持など多数あります。
独学をする方にとってテキストは、試験合格まで頼りにする唯一の味方。どのテキストを選ぶかで合格率は大きく変わります。勉強計画はすでに行政書士試験にチャレンジしている方なら想像できるかもしれませんが、初めて挑戦する方は、何をどの程度勉強すべきか判断するのが難しくなります。
モチベーション維持に関してはさらに難しくなります。同じ目標にチャレンジする仲間がいない環境では、なかなか勉強に対して前向きな気持ちを維持するのは難しいでしょう。
では、行政書士試験に合格するには、どんな準備をすればいいのか、勉強の方法などの目安などを紹介しますが、まずは行政書士試験の受験科目を確認しておきましょう。
法令科目
行政書士試験の出題科目は大きく分けて2種類。そのうちのひとつが「法令科目」です。行政書士試験は法令科目が出題の中心であり、多くの法律知識を身に付ける必要があります。
| 受験科目 | 五肢択一式 | 多肢選択式 | 記述式 | 科目合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 配点 | 出題数 | 配点 | 出題数 | 配点 | 出題数 | 配点 | |
| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 2問 | 8点 | ||||
| 憲法 | 5問 | 20点 | 1問 | 8点 | 6問 | 28点 | ||
| 行政法 | 19問 | 76点 | 2問 | 16点 | 1問 | 20点 | 22問 | 112点 |
| 民法 | 9問 | 36点 | 2問 | 40点 | 11問 | 76点 | ||
| 商法・会社法 | 5問 | 20点 | 5問 | 20点 | ||||
| 合計 | 40問 | 160点 | 3問 | 24点 | 3問 | 60点 | 46問 | 244点 |
行政書士試験全体の合計点数は300点満点であり、その80%以上が法令問題ということになります。さらに詳しく科目別の配点を見ると、民法と行政法で188点と試験全体の半分以上の配点を占めています。
法令問題の対策という点では、民法と行政法が中心となるでしょう。
ちなみに行政書士試験には合格基準点が定められており、法令科目は244点満点で122点以上が基準点となっています。
一般知識
行政書士試験では、法令科目以外にも一般知識を問う問題も出題されます。一般知識の問題は3つの科目から出題されますので、配点等を確認しておきましょう。
| 受験科目 | 五肢択一式 | |
|---|---|---|
| 出題数 | 配点 | |
| 政治・経済・社会 | 7問 | 28点 |
| 情報通信・個人情報保護 | 4問 | 16点 |
| 文章理解 | 3問 | 12点 |
| 一般知識合計 | 14問 | 56点 |
一般知識の問題は合計で14問。中心となるのは「政治・経済・社会」ということになります。一般知識にも合格基準点があり、56点満点で24点の獲得が必要となっています。
法令科目の合格基準点は122点、一般知識の合格基準点は24点ですが、合計300点満点の合格基準点は180点です。少なくとも6割以上得点できるように準備することが重要です。
勉強する割合は?
各科目の配点を確認したところで、行政書士試験対策において、どのような割合で勉強をするべきか、その割合を考えてみましょう。
配点の上でも当然ながら法令科目の勉強が中心となるのは間違いありません。全体の8割ほどが法令問題であり、ここで得点を延ばせないと、合格するのは難しくなります。
法令科目の中では特に民法と行政法に注目。この2科目で全体の6割に当たる188点が割り振られており、ここで得点を伸ばせないと合格は難しくなります。
行政書士試験の対策は、行政書士が身に付けておくべき法律知識を身に付けるのが最大の課題です。民法と行政法を中心に、しっかりと法律知識を身に付けるような学習計画を立てましょう。
配点の上ではさほど大きくない一般知識問題ですが、無対策で挑むのはおすすめできません。一般知識科目にも合格基準点があり、ここを落としているようでは話になりません。
また多くの受験生が法令科目を中心に対策をしてきますので、ライバルに大きな差をつけるとすればこの一般知識問題ということになります。
一般知識問題は3科目に分かれています。「政治・経済・社会」の問題に関しては、中学・高校で習った政経の基本を身に付け、さらに時事問題をインプットしておけばさほど難しいものではありません。
毎日テレビのニュースや新聞を購読していれば、概ね対策はできるでしょう。ちなみにニュースはネットニュースよりもテレビのニュースがおすすめ。ネットニュースはどうしても自身が興味のある項目に偏りがちで、広く浅く情報を入手するのには向きません。テレビのニュース番組を毎日視聴する癖をつけると、広く浅く時事問題に関する知識を得ることができます。
「文章理解」の問題は、文章の穴埋めや並べ替えが中心に出題されます。実際に過去問を見ると分かりますが、じっくり時間をかければさほど難しい問題ではありません。ある程度過去問に挑戦しておけばある程度対策済みと考えて問題ないでしょう。
むしろほかの問題を素早く解けるようにし、文章理解の解答時間をより多く確保することを目標にしましょう。
一番対策が必要なのが「情報通信・個人情報保護」の問題。ここは法律理解にもかかわる部分ですし、専門用語も多く出題されるポイントです。情報通信に関する最新の専門用語を理解し、個人情報保護に関する法令にも精通しておく必要があります。
特にこの分野に関しては、近年法改正が繰り返されていますので、最新の法に対応できるように準備しておきましょう。
勉強時間を確保する方法
法律知識がない社会人の方が、行政書士試験に1年間という短期間で合格するためには、1,000時間程度の勉強時間を確保する必要があります。
単純に考えれば、1年間は365日間ですから、1日3時間程度の勉強時間を確保することになります。では、実際に社会人の方が1日3時間の勉強時間を確保できるかどうかを考えてみましょう。
社会人は勉強時間の確保が課題
1年間で1,000時間を確保するには、1日あたり3時間の勉強時間が必要になります。しかし実際に社会に出て働いている方に、仕事以外に3時間の勉強時間を確保できるかと問えば、多くの方が「難しい」と答えるでしょう。
朝起きて仕事に行き、帰宅して寝るまでの間に、3時間の余暇がある方はそう多くありません。実際にどの程度の暮らしが必要になるかを考えていきたいと思います。
実際の生活から想定
一般的なサラリーマンの方の毎日の生活を想定してみましょう。毎日9時~17時までのお仕事をしている方を想定してみましょう。
9時出社であれば朝起きるのは7時ごろ。8時に家を出て9時に出社と考えます。仕事の終わりは17時ですが、毎日定時で帰宅できるという方は稀かと思いますので、18時まで仕事と考えてみましょう。すると帰宅時間は19時ということになります。
毎日0時に就寝と考えると、自由にできるのは19~24時の5時間。この5時間の間に食事をして入浴すると考えると、それだけで2時間は必要でしょう。そう考えると、毎日無駄なく過ごしてギリギリ確保できる勉強時間が3時間です。
単純に毎日3時間は難しいとすると、仕事のない休日に集中的に勉強する形が考えられます。一般的なサラリーマンの年間休日数を考えてみます。1年間は約52週間ですから、まず土日で104日の休みがあります。
さらに祝日が年に15日程度あり、年末年始・お盆などの休暇が6日ほどあるとしましょう。ここに年間の有給休暇が20日間あれば、年間休日は合計145日。出勤日数は220日となります。
出勤日に1日1時間、休日に1日5時間勉強時間を確保すれば、合計945時間の勉強時間を確保できます。休日をしかり勉強に使えば、計算上は1年間で1,000時間の勉強時間確保は可能です。
ただし、この通りに生活するということは、休日はすべて勉強に充てることになり、帰省や旅行、恋人とのデートや家族サービスの時間はほぼありません。また、出勤日の帰りに飲みに行くということも難しくなります。
この生活を1年間続けるというのはなかなか難しいのではないでしょうか。
もちろん資格取得という目標のためではありますが、もう少し現実味のある、より効率的な学習方法を探すのが行政書士試験合格への最短距離かと思われます。
効率的な学習方法
社会人の方にとって、1年間で1,000時間の勉強時間を確保するのはなかなか難しいのが事実です。それでも短期合格を目指す、しかも独学で短期合格を目指すという場合は、時間をより有効活用する必要があります。
そんな時間の有効な利用方法や、より短時間で実力が付く学習方法などを考えてみましょう。
スキマ時間を有効に生かす
時間の確保が難しい方にとって、使い方が重要になるのがスキマ時間です。通勤をしている方であれば往復の通勤時間や昼食後のちょっとした休憩時間などがスキマ時間にあたります。
ご自宅で家事などを行う専業主婦(もしくは主夫)の方にとっては、例えば洗濯機の洗濯を待つ時間などもスキマ時間といえるでしょう。こうしたスキマ時間をうまく勉強時間として活用すると、確保できる勉強時間は大幅に増えます。
例えば上記のサラリーマンの1日を思い出してみましょう。上記の1日の予定では、通勤時間を片道1時間と想定しました。1日往復で2時間という計算ですが、この中で1時間でも勉強時間に充てることができれば、1年間の勉強時間はそれだけで+220時間ということになります。
こうなるとたまに仕事帰りに飲みに行くこともできますし、休日にデートをすることも可能でしょう。家族がいる方であれば、年末年始の帰省や、家族サービスの時間も確保できるでしょう。
スキマ時間を勉強時間として活用することは、行政書士資格など難関資格取得を目指す場合非常に重要なポイントとなります。
短時間でも効果的な勉強を行う
この記事では1年間に1,000時間の勉強時間を確保することを前提に検討していますが、この1,000時間をより短縮することを考えることも重要です。
勉強時間を短縮するということは、それだけ効率的に勉強ができる環境を整えるということです。効率的な勉強を実現するには、独学で自身が選んだテキスト頼りでは難しくなります。
そう考えると通信講座を利用した独学が現実的な方法で、しかもより効率的な学習ができる通信講座を選ぶことが重要なポイントとなります。
通信講座を勉強効率で選ぶ場合、注目すべきポイントがいくつかあります。ひとつはテキストの分かりやすさや見やすさです。テキストを一目見ただけで、ある程度理解ができれば勉強時間は短縮できます。
講義動画の見やすさも重要です。勉強は講義動画を中心に行うことになりますので、この動画が見やすい、聞きやすいことは重要です。反対に見づらい動画ではモチベーションの維持も難しいでしょう。
さらに講師陣の質も注目ポイントです。通信講座においてテキストの制作や勉強スケジュールの立案には、講師陣の意見が反映されています。講師陣の質が高ければ、それだけ勉強時間は短縮できるはずです。
最後にスキマ時間の活用ができるかどうか。この点にも注目して通信講座を選びましょう。
行政書士最短合格なら通信講座がおすすめ
行政書士試験という難関をクリアする秘訣は、通信講座にあります!通信講座がなぜ良いのか、はっきりとした理由があります。
➀自分のペースで学習を進めることができるいつでも、どこでも、時間を最大限に活用することができます。これは移動時間や家事の合間、仕事の昼休憩など、日々のスキマ時間を勉強時間に変えられることを意味します。忙しくても、スケジュールに合わせて学習のペースを調整できます。
②学習費用の節約が可能通学講座に比べて、通信講座は授業料がリーズナブルで交通費もかからないため、学習にかかる費用を大きく削減できます。
③万全のサポート体制独学では解決が困難な疑問も、通信講座を利用すれば、質問や不明点の解消に向けて手厚い支援が受けられます。これにより、学びながら疑問点を解消し、よりスムーズに学習を進めることができます。
フォーサイトの行政書士通信講座の特徴
ここでは、高合格率で知られるフォーサイトの行政書士通信講座の主な特徴をご紹介します。
➀わずか4ヶ月での合格実績あり!通常、行政書士試験の合格には約12ヶ月の準備期間が見込まれますが、フォーサイトのコースを受講すれば、4ヶ月で合格することが可能です。この短期間での成功は、フォーサイトが合格点を目指した教材作りに注力しているからこそ実現できます。
②合格できなかった場合でも心配無用です!受講料は全額戻ってきます。
③満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト試験に必要な情報量、重要情報のカラー分け、理解を深めるイラストが豊富に含まれており、それが高い合格率につながっています!
④フォーサイトの行政書士講座は、講師歴20年以上を誇る福澤繁樹先生、五十嵐康光先生、北川えり子先生の実力派の講師陣によって運営これら経験豊富な教師たちが、講座のカリキュラムに沿った質の高い授業や教材を提供しています。
⑤通信講座でありながら、ライブ配信の授業が受けられる「eライブスタディ」周期的に実施されるライブ配信講義のことです。一般的に通信講座は独学が基本ですが、このシステムを利用することで、授業のペースを保ちやすくなり、学習進度の遅れを防ぐことができます。
行政書士通信講座を体感するならまずは資料請求から!
通信講座を利用したことがない方や、以前試したものの断念したことがある方々にとって、再度通信講座に挑戦するというのは不安につながるかもしれません。そんな不安を解消するためにも、まずは無料の資料請求からスタートすることをおすすめします。
資料を請求すると、以下のような体験ができます。
➀サンプルテキストや問題集を通じて、教材の質を自分の目で確認できます。直接教材に触れることで、教材がどの程度理解しやすく、自分に合っているかを確かめることができます。
②無料でeラーニングが体験できます。これにより、スマートフォンがあれば、場所を選ばず学習を続けることが可能です。
③行政書士試験合格に向けたテクニックを凝縮したノウハウ書をプレゼントいたします。1分で完了!
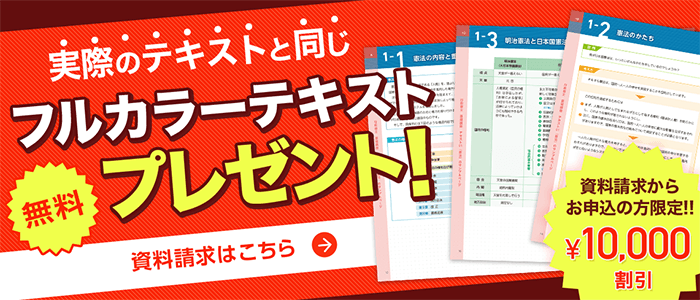
まとめ
行政書士試験は、法令科目を中心に、一般知識も問われる試験になります。例年の合格率は10%前後と非常に低く、短期間で合格しようというのは不可能ではありませんが、かなり厳しいという難易度です。
さらにこの行政書士試験に独学で合格するということを考えると、より時間が必要であり、短期間での合格難易度はさらに高くなります。
独学で行政書士試験を目指すのであれば、通信講座を利用し、効率的に勉強するのがおすすめ。過去の合格実績が高い通信講座であれば、より信頼度は高まります。
それでも特に社会人の方が、仕事をしながら1年間などの短期間で行政書士試験に合格するのはかなり難しいといえます。そこで有効活用したいのがeラーニングです。
eラーニングはスマホやタブレットを利用し、場所を選ばずにできる学習方法。通信講座を選ぶ場合は、このeラーニングがしっかりした講座を選ぶのがおすすめです。
特におすすめしたいのが、eラーニングシステム「ManaBun」を提供しているフォーサイト。フォーサイトのManaBunであれば、通勤電車の中や昼食後のコーヒータイムなどでも気軽にeラーニングが可能。こういったスキマ時間を有効に活用することで、効率的に勉強を進めることが可能です。
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















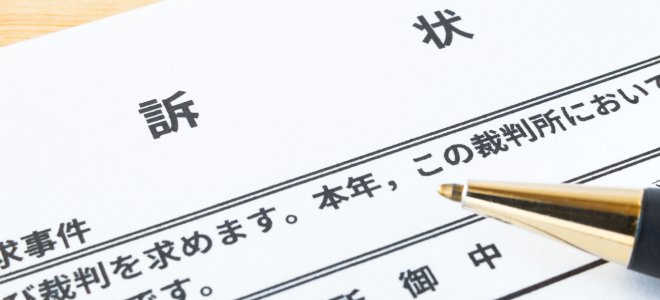


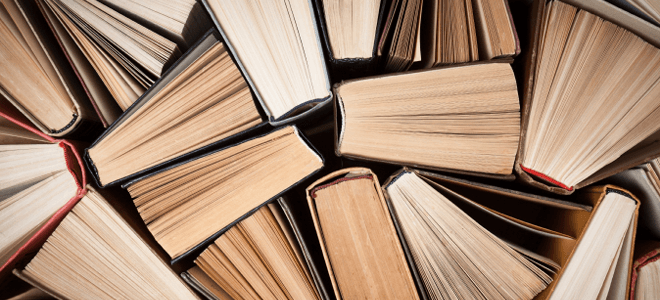



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


